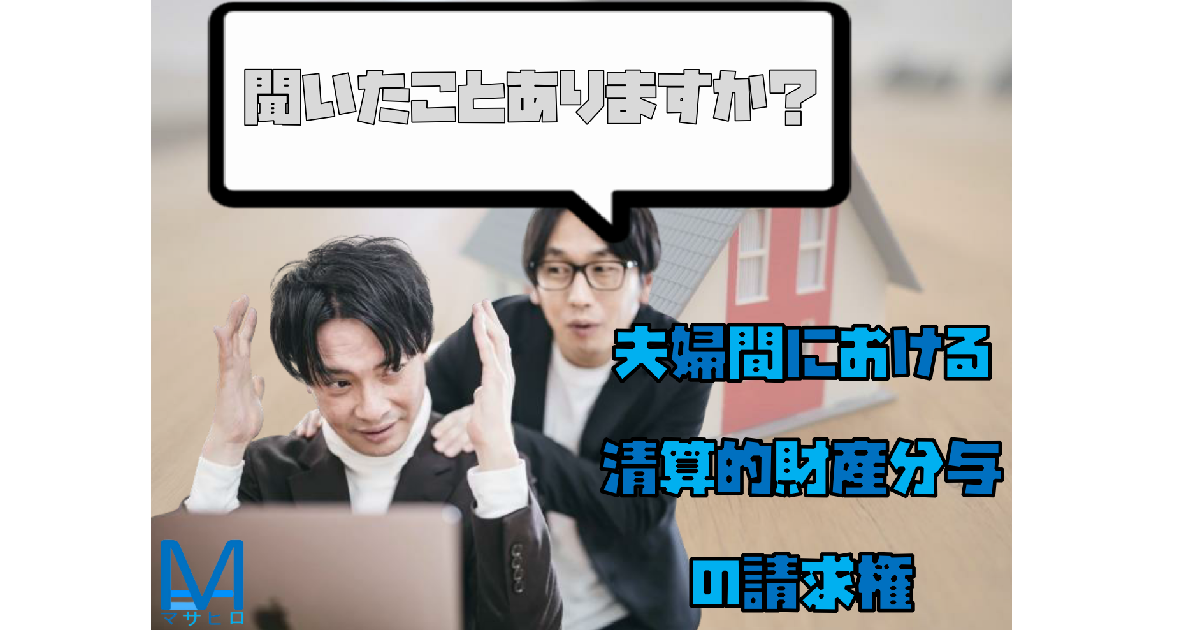家事案件と言えば、離婚や親権争いを思い浮かべることが一般的ですが、実は一括りに家事案件と言っても、婚姻の無効や婚姻関係存在の確認(甲類事件)、婚姻の取り消しや離婚(乙類事件)、婚姻の無効・婚姻の取り消し・離婚・婚姻関係の消滅による損害賠償請求(丙類事件)、失踪宣告や人身保護請求手続(丁類事件)、夫婦同居や子の引き渡しの訴え(戊類事件)といったカテゴリーに細かく分類することができます。
一見刑事事件や民事事件より単純であったように見える家事案件ですが、実は多くのうんちくが見え隠れており、腹をくくって専門家に相談してみたら、目からウロコ!って感想を抱く方も少なくないでしょう。次は、離婚について、台湾で知っておいたほうが良い基礎知識をシェアさせていただきます。
目次
そもそも、相手方とは婚姻関係が存在していますか?
2008年5月23日までは、改正前民法の適用となり、「公開の結婚式」及び「2人以上の証人」との二つの要件を満たしたら結婚成立となります。一方、2008年5月23日以降の結婚は、改正後民法の適用対象となり、2人以上の証人によって署名がなされた書面による証明のほか、双方の当事者が戸籍事務所にて結婚登記を行う手続きも必要とされています。(民法第982条)
こういった要件が欠如した場合は、法律上では「婚姻関係が不適合」との扱いとなり、婚姻無効の訴えや婚姻無効の確認を目的とする訴えを提起することができます。
離婚がしたいけど、どうすれば...
協議離婚
当事者双方合意のうえ、2人以上の証人によって署名がなされる離婚協議書を作成し、当事者双方が戸籍事務所に対して離婚届けを提出すれば成立します。(民法第1050条)
裁判離婚
当事者双方が離婚について合意に達することができず、いずれかの一方に所定の事由があったと認められた場合は、他方は訴状を作成し、証拠書類を添えて管轄権を有する裁判所に提出することで、離婚の訴えを提起することができます。(民法第1052条)
離婚案件は、プロセス的には強制調停が要求されます。つまり、離婚の訴えが提起されてから裁判所によっり起訴がなされ、裁判の手続きに入る前に、一旦裁判所主導の調停が導入されます。調停が成立しなければ裁判が行われる形となります。
離婚案件の調停は、原則として内容が非公開とされており、裁判所による調停が成立し、又は当事者双方が和解に達した時点で、婚姻関係の消滅を意味します。調停又は和解の結果を書き記した調停調書は裁判所によって作成され、当事者個別に当該調書を管轄の戸籍事務所へ持っていけば、独身と記載された戸籍謄本と身分証明書を入手可能となります。
「いずれかの一方に所定の事由があったと認められた場合」における「所定の事由」には、以下のものがあります。(民法第1052条)
裁判離婚の請求事由
- 重婚したとき
- 配偶者以外の者との合意性交があったとき
- 夫婦いずれか一方が他方に行った、同居に耐えないほどの虐待があったとき
- 夫婦いずれか一方が他方の直系親族、若しくは夫婦いずれか一方の直系親族が他方に行った、共同生活に耐えないほどの虐待があったとき
- 夫婦いずれか一方が悪意を以って他方を遺棄し、その状態が継続しているとき
- 夫婦いずれか一方が他方を殺害することを意図したとき
- 不治の悪疾があるとき
- 重大不治の精神病があるとき
- 生死不明が3年以上経過したとき
- 故意による犯罪で6ヶ月以上の懲役に処され、確定したとき
前項以外の重大な事由があって婚姻を維持しがたいときは、夫婦いずれかの一方は、離婚を請求することができます。但しその事由が夫婦の一方により責めを負うべきときは、他方のみが離婚を請求することができます。
上記言及のあった離婚事由は、それぞれ個別の訴えを成立させる効果を有するものとなります。説得力を上げようと、なるべく多くの事由を一部の訴状にまとめるケースはたまに見かけますが、事実無根な事由をいくら訴状に書いても、より有利な判決結果を呼び寄せるところか、裁判官の心証を悪くするばかりなので、裁判所に提出した証拠書類で証明可能な事由を一つずつ、丁寧に書いて、本当に複数の事由が同時に存在のであれば、それぞれを結びつける形で訴状にしっかりと書けたらよいと思われます。
裁判離婚の事例
事例その1
「夫婦いずれか一方が他方に行った、同居に耐えないほどの虐待があったとき」を離婚の事由とした場合には、事実関係をもとに、一方が受けた虐待がどの程度のものかを評価し、当事者の教育水準、社会的地位その他の事情を総合的に考慮のうえ、婚姻関係の継続が困難であるかどうかを判断する必要があります。虐待の程度が通常の夫婦間で耐えられ得る範囲を超え、人格・尊厳と人身の安全への侵害があったと認められた場合は、「同居に耐えないほどの虐待」の事実があったと考えられます。(司法院大法官会議釈字第372号解釈)虐待の種類は、大きく次2つのカテゴリーに分けることができます。
●身体的虐待
些細なことで、夫婦の一方が他方に一時的又は繰り返し暴力を振るったとき、当該暴力行為は原則として「同居に耐えないほどの虐待」とされますが、当事者の教育水準、社会的地位その他の事情をもとに、客観的な視点で判断する必要があります。(最高裁判所32上1906判例)受けた傷害の程度次第で、一回限りの暴力行為も身体的虐待と判断されるケースが存在しています。
●精神的虐待
例えば、夫婦の一方が他方に対して、事実無根の姦通行為を指摘したりするという、他方への侮辱、恐喝、貶める発言や行動その他重大な侮辱行為があったと認められたとき、「同居に耐えないほどの虐待」と判断されます。ただし、当該他方に明らかに不当な行為があって、一方がそれによって一時的に過剰な行為を働いた場合においては、「同居に耐えないほどの虐待」に該当しないと考えられます。(最高裁判所32上4554判例)
身体的又は精神的虐待を問わず、虐待をされた一方は、家庭内暴力防止法に基づき人身保護命令を申請することができます。
事例その2
夫婦は原則として、互いに対して「同居の義務」を負っていますが、正当な理由があって同居できない場合はこの限りではありません。正当な理由がなく、かつ「悪意の遺棄」であると認められた場合は、「夫婦いずれか一方が悪意を以って他方を遺棄し、その状態が継続しているとき」の事由が成立する形となります。ただし、留学、やむを得ない旅行、会社から命じられた出向、服役、DVを避けるための別居等は、通常「悪意の遺棄」とは認められません。
また、悪意の遺棄の成立には、同居義務の不履行という客観的事実が存在し、なおかつ同居義務の履行を拒否する意思表示がなされたかとの2点が判断基準となっています。例えば、夫と喧嘩した妻は実家に戻って長い時間が経っていたにもかかわらず、夫からは一切の連絡がなかったため、同居義務の履行を拒否する意思表示がなされたとは認めがたいと考えられます。(最高裁民事判例49台上1251号)
一方、夫婦いずれかの一方には、生活費の支払い義務を負う必要があったとき、正当な理由を有していないにもかかわらず、当該一方が生活費の支払いを拒否し、それによって他方が生活を維持できなくなった場合には、「悪意の遺棄」とみなされます。つまり、遺棄というのは、同居及び扶養義務の不履行、若しくはそのうちのどれかを履行しないことを意味します。(最高裁民事判決22上9220号)
事例その3
その他の離婚事由、「前項以外の重大な事由があって婚姻を維持しがたいときは、夫婦いずれかの一方は、離婚を請求することができます」については、夫婦の共同生活が維持できなくなる具体的な事情を考慮し、客観的に見て、当該事情が果たして夫婦が一緒に生活するうえでの無視できない妨げとなり、当事者双方がそれによって婚姻関係の維持を諦めせざるを得ないとの影響があったかを判断する必要があります。つまり、離婚裁判を起こした一方の主張のみで判断するではなく、その他同様な立場にあった夫婦では、そのような原因で確実に婚姻関係を維持できなくなるかをもとに判断がなされます。(最高裁87年度台上字第2495号等)
離婚裁判を起こしたいけど、いくらかかる?
離婚裁判を起こそうとする固定費については、第一審の裁判所手数料は3,000台湾ドルとなります。第一審の判決を不服として、控訴の提起(第二審)、及びその後上告の提起(第三審)を行った場合には、それぞれ4,500台湾ドルの裁判所手数料が発生します。
離婚裁判を起こした際に、原告が主張した離婚事由に理由があったと認められたとき、未成熟子の親権その他もろもろ権利義務の行使方法についても定めてもらおうと、裁判所に対して付帯請求を行うことができます。その場合、追加で行った付帯請求には別途裁判所手数料はかかりません。
一方、離婚による財産分与や慰謝料の請求は、別途裁判所手数料がかかり、請求総額をもとに手数料を算出し支払う形となります。
離婚裁判の当事者双方は、全ての請求について和解又は調停が成立した場合には、支払済み裁判所手数料の2/3の額の還付請求を行うことができます。
離婚をしようとするときは、相手方に対してはどういった請求ができますか?
台湾の法律上では、離婚裁判を起こした際に、その他請求を同時に提出したり、変更したり、追加したり、又は反訴を起こしたりすることができます。よく同時にされる請求は例えば以下のようなものがあります。
その他請求可能な権利
- 清算的財産分与の請求(民法第1030-1条)
- 特有財産の返還請求(民法第1058条)
- 婚姻費用の給付請求(民法第1003の1条)
夫婦いずれかの一方が他方に立て替えた家庭内の生活費も、他方が得た不当利得として返還請求できます。
要留意なのは、こちらの請求対象は、あくまでも婚姻関係が消滅する前で発生した生活費となる点です。 - 扶養的財産分与の請求(民法第1057条)
- 養育費(民法第1116の1条)
父母が未成熟子に対しての扶養義務は、婚姻の取り消しがなされ、又は離婚によって影響されることはありません。 - 離婚判決が出されたことによる損害賠償の請求(民法第1056条)
例えば、同居に耐えないほどの虐待を受けたら、医療費や精神的慰謝料を請求可能であり、「配偶者以外の者との合意性交」があったと主張しようとする場合には、精神的苦痛による損害賠償金を請求することができます。 - 離婚事由に理由があったと認められたとき、未成熟子の親権について、裁判所に定めてもらうことの請求ができます。(民法第1055条)
ちなみに、上記の請求は、最初に起こした離婚裁判のみならず、控訴審又は上告審での口頭弁論が終結する前であれば、何時でも追加したり、反訴を起こしたりすることができます。この点をしっかり押さえて、戦略を組んでいくことが大変お勧めです。
離婚協議書に何を書いたらよいでしょうか?
実務上、結構細かい条件についての合意内容がずらりと書かれる離婚協議書もあったりしまして、第三者から読んだら気が遠くなるぐらい、すごく充実した内容となっているレアケースもたまにありますが、通常は、下記6つのポイントさえ記載したら概ね大丈夫かと思われます。
離婚協議書に要記載な点
- 夫婦双方が離婚について合意すること
- 子供の親権はどちらの親が取ること
- 未成年の子との面会交流の頻度、場所、及び方法
- 未成熟子への養育費の負担方法
- 清算的財産分与の方法
- 戸籍事務所に対しての離婚届けの提出時期
要記載事項が何となく理解していても、全体的な構成が今一つイメージできないようでしたら、台湾の地方自治体が用意する離婚協議書の雛形がご参考いただけます。(ダウンロードはこちら)ただ、雛形の内容はごく簡単なものしか書かれていなくて、そのような内容のみでは、納得のいく離婚条件が作れないと考えていらっしゃるカップルも少なくないでしょう。その際、是非気軽にマサヒロへご相談いただけたら幸いです。
どういった状況があったら、離婚裁判の提起がNGとなるんでしょうか?
NGケースその1
民法第1052条に定めのあった十の事由のいずれかも該当しないものの、どうしても離婚したいなぁと思って、同条第2項の「その他重大な事由があって婚姻関係を維持しがたい」を理由に、離婚裁判を起こそうとする場合には、婚姻関係の維持が困難であるそもそもの原因が、実際原告にあったとその後の裁判手続きで判明したら、その時点で勝機が消え失せていきます。
★NGポイント:原告の有責性が被告より大きい!
NGケースその2
配偶者の人が第三者と重婚したり、又は第三者との合意性交があったりすることで、離婚裁判を起こそうとする場合には、もし原告が配偶者の人が行った当該行為に対して、事前に了承したり、事後になって許したり、又は当該行為を知り得て6ヶ月が過ぎて若しくは起きてから2年を超過したら、裁判所から離婚の訴えが退けられてしまいます。
★NGポイント:時効問題を全く気付いていない!
NGケースその3
自分を殺害しようとする意図が認められる、若しくは故意による犯罪で6ヶ月以上の懲役に処され、確定したときといった事由をもって、配偶者の人に対して離婚裁判を起こそうとする場合には、当該意図又は事実を知り得て1年超となったり、 当該意図又は事実があったと認められた日から5年経過してしまったら、訴えが無効とされてしまいます。
★NGポイント:時効問題を全く気付いていない!
NGケースその4
自ら起こした離婚裁判が裁判所から退けられたら、原告は当該裁判の訴えを合併したり、変更したり、追加したり、反訴を提起したりすることで、同じ婚姻関係について別途裁判を起こしてはならないとされています。ただし、2点の例外があります。一つ目は、裁判所がとある見解についての釈明がなされていないことで原告がそれを主張しそこなった場合、二つ目は裁判所によって釈明がなされたものの、原告に帰さない事由によって主張できなかった場合ではその限りではないとされています。(家事事件法第57条)
★NGポイント:最初から主張がまとまらず、事後になって主張をいじって再チャレンジしても受け付けれない!
NGケースその5
配偶者の一方が審理中で亡くなったら、裁判が即終結とみなされます。
★NGポイント:離婚裁判が長丁場なので、しっかりと健康管理をしなければ最後までたどり着かない!
夫婦の共同債務が離婚時ではどのように扱ったらいい?
共同債務の計算基準日については、次のように、二つのタイミングが存在しています。(民法第1030条の4)
離婚による清算的財産分与を行おうとする場合には、まず婚姻関係が開始してから夫婦それぞれが取得した財産から、以下三つの項目を差し引いた額を算出し、計算結果がプラスであったら、手持ち財産の少ない一方は他方に対して、前述の計算で求められた額の半分を請求する形となります。もし前述の計算結果がマイナスであったら、請求権がありません。
清算的財産分与における減算項目
- 婚姻関係継続中で発生した債務
- 夫婦いずれかの一方が相続その他無償の方法で取得した財産
- 慰謝料
分与可能な財産、具体的に例えばどういったもの?
財産の種類によって、清算的財産分与の範囲が異なります。以下いくつかの例を取り上げます。
清算的財産分与の考え方
- 不動産
原則として、不動産の登記申請が婚姻関係継続中になされていたら、分与対象とされます。 - 動産
結婚後に取得した車、預貯金、株、投資信託、宝飾類、積立型の保険等が分与対象。 - 結婚前に購入した株、投資信託
提訴日(裁判離婚の場合)の市場価格が結婚時の市場価格を上回ったら、上回った分が分与対象。 - 預貯金の利息
結婚前の預貯金が婚姻関係継続中で発生した利息が分与対象。(民法第1017条第2項) - 婚姻関係継続中の債務の返済に充てた結婚前の財産
夫婦いずれかの一方が結婚前の預貯金をもって、結婚後で組んだ住宅ローンの返済等に充てた場合には、返済分が婚姻関係継続中の債務としてカウントされます。 - 結婚前の債務の返済に充てられた婚姻関係継続中で得た財産
夫婦いずれかの一方が婚姻関係継続中で稼いだ収入をもって、結婚前の債務の返済に充てた場合には、当該収入が分与対象とされます。
要留意なのは、清算的分与財産の請求権は、それを知り得てから2年以内、若しくは婚姻関係が消滅してから5年以内に行わないと、時効となってしまう点です。裁判離婚のケースでは、判決が確定されてから2年以内に行使しないと、前述の請求権が時効となります。しっかりと覚えておきましょう!
早速アクションを取りましょう!
今まで一緒に見てきた情報が結構膨大であり、必要な内容をしっかりと身に着け、有効な戦略を組んで実施していくことは相当難しいと思料しています。にもかかわらず、こちらの文章をご覧いただいている読者は、おそらく類似事件に悩まされ、若しくは知人のほうでこういった問題を抱えていらっしゃるなので、すぐにでも何等かのアクションを取らないと、近い将来不利益を被る可能性が非常に高いと考えるようでしたら、是非気軽にマサヒロへのご相談を試みてください。トップシークレットとしてご相談事項を取り扱わせていただき、当事者視点でアドバイスさせていただきます。
早速アクションを取りましょう!ご自分の幸せは、ご自分の手でしか掴めないのです!
Attention!
※こちらの文章は2021年9月3日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。