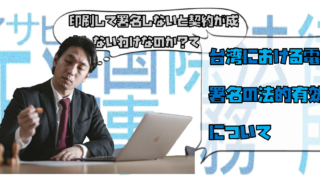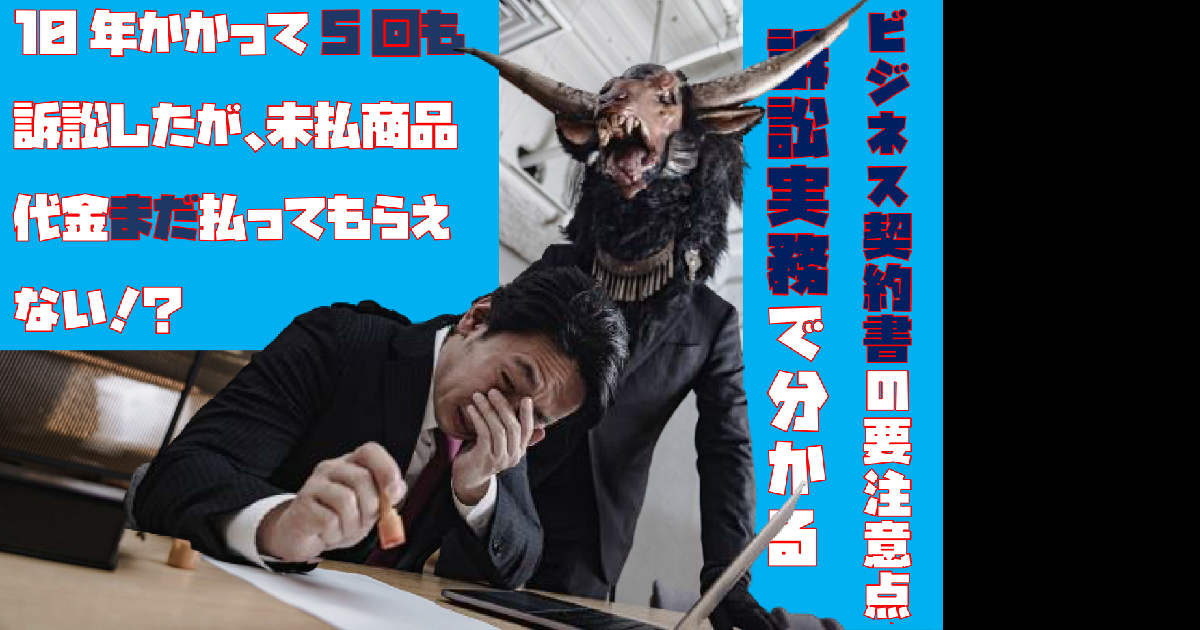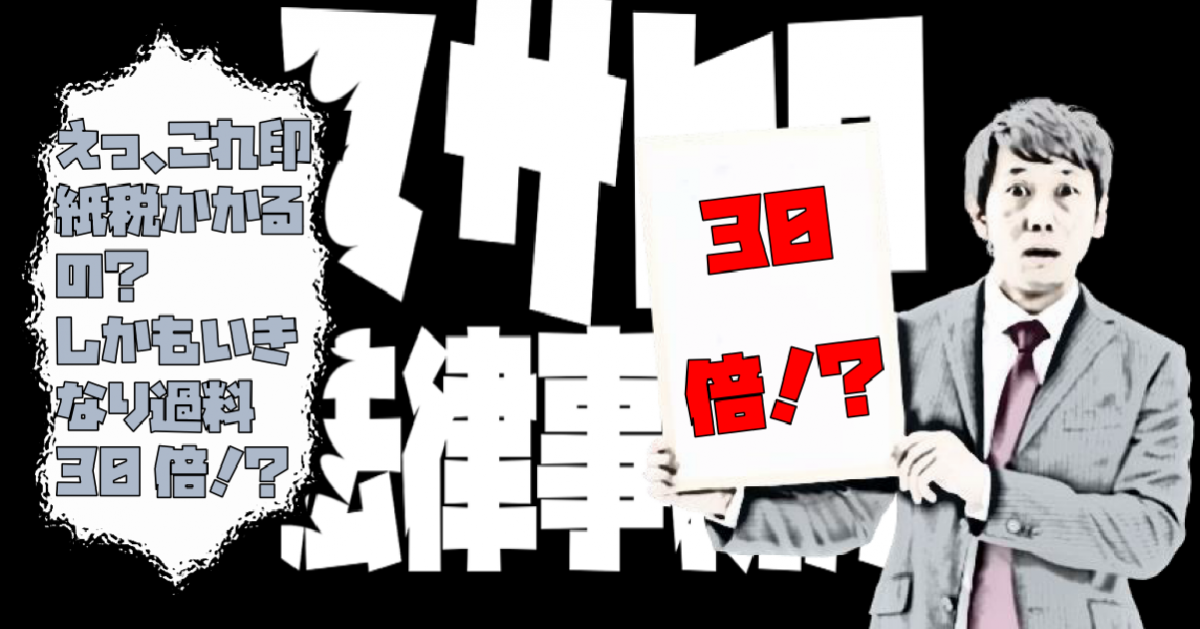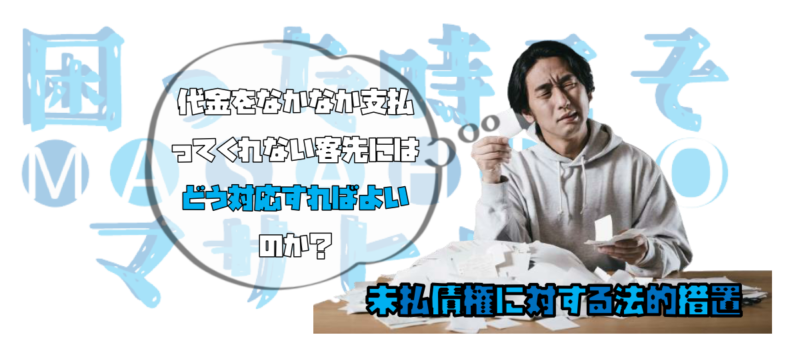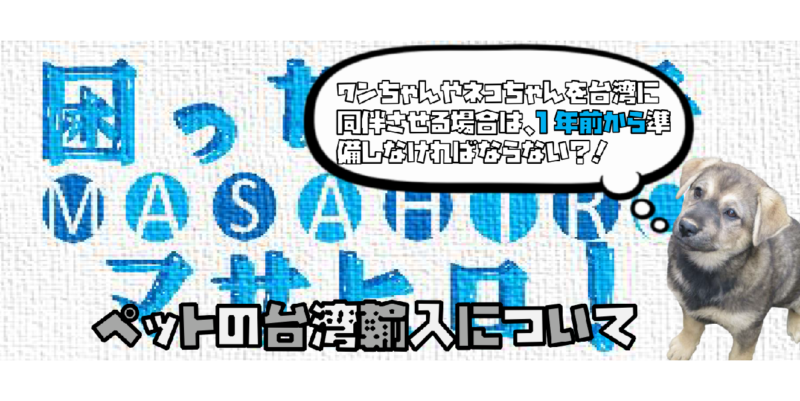【印刷して署名しないと契約が成立しないわけなのか?】台湾における電子署名の法的有効性について
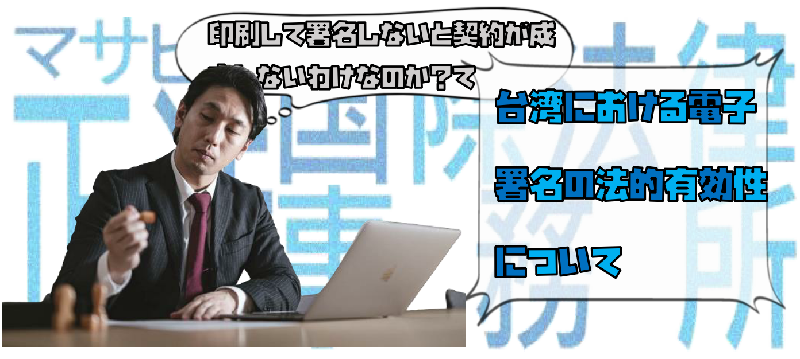
商品棚から缶コーヒーをとって、レジで代金を支払えば取引が完了します。カレー屋でシェフ特製好み焼きを注文し、台湾PAYでスキャンすれば、「お好み焼き売買契約」が成立します。
商品の売買は、不動産の担保設定や身元保証などとは違い、明示か黙示を問わず、とある事項に対して合意に至れば、契約関係が成立し(民法第153条)、何かしらの書面をわざわざ作ってそれに調印するプロセスは必ずしも必要ではありません。にもかかわらず、ビジネスの世界では契約書の応酬が普通に行われています。何故なら、取引にまつわるトラブルが多すぎて、契約書にそれらを防げる条件を細かく書かないと、後々になったらリスクが大きいからです。
弁当一個を買うレベルじゃない取引なら、契約書の作成は避けられないようだが、少なくとも締結の手間をできるだけカットしたい、と考えたりもします。それに答える形で、契約書の締結手続をネットで完結可能な電子署名が登場します。

電子署名で契約すると、事後になって、その契約書が無効と判断される可能性はないのか?
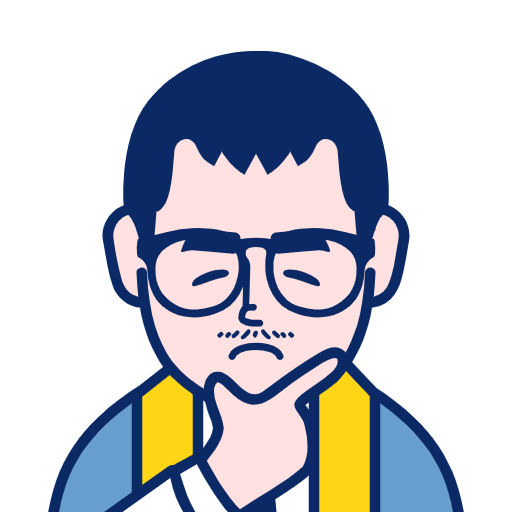
電子署名だと、偽造しやすいのではないか?

そもそも、何をもって電子署名と言えるのか?
以上のような疑問点を一掃する形で、台湾における電子署名の法的有効性について解説させていただきます。
いわゆる電子署名とは?
契約書のやり取りにおいてよく見かけるのは、個人名、社名の印影又は署名の画像の背景を透明にして、それを契約書の電子データに貼り付ける形で、契約書そのものを郵送する代わりに締約する方法です。当該背景が透明にされた印影又は署名の画像データを電子署名と認識する方が少なからずいるようだが、厳密的には、それが100%正しいとは言えません。
台湾の法律では、以下3つの特徴を有すれば、電子署名に該当するとされます。
- 電子文書に依存し、かつそれと関連性がある。
- 電子文書に署名する者の正体を識別、確認できる。
- 電子文書の真偽を証明できる。
もし背景が透明にされた印影又は署名の画像データは、押印又は署名した本人ではなく、会社内でいろんな人に使いまわされているのであれば、それが法律的に有効な電子署名とは言えず、それによって調印された契約書は、その後法的拘束力の有無について争われやすくなってしまいます。
従って、契約書になされた電子署名が法的に有効であることを確保するためには、署名者にきちんと本人確認を行うのと、電子文書としての契約書を適宜保管し、何時でも完全な状態で内容を確認できるようにしなければなりません。
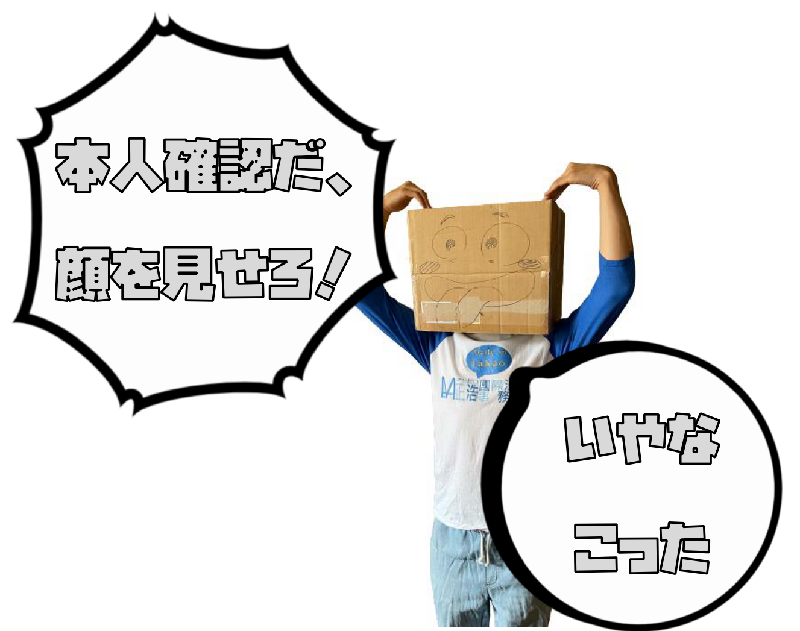
電子署名が使えない場合とは
電子署名法によると、電子署名で契約するためには、他方の契約当事者の同意を得る必要があるとされます(電子署名法第9条)。つまり、契約当事者が全員電子署名の使用を承諾しなければ、通常のやり方で締約する必要があります。
何故電子署名を使うのに、他方の当事者から同意を得なければならないかというと、デジタル端末を使い慣れしていない従来型の中小企業がまだまだ多いその他IT力の格差問題を考慮し、電子署名の使用に抵抗感を覚える者に、無理やりやらせるわけにはいかない、という政府の意向が法律に反映されたからです。こういった格差を、これからどうやって埋めていくかは、台湾におけるペーパーレス化の進展に大きな影響が与えられるでしょう。
一方、契約当事者の他方から同意が得られたにもかかわらず、電子署名が使えない場合はほかにもあります。それが、民法に定めた要式契約です。
要式契約というのは、契約を成立させるのに一定の方式が必要となる契約をいいます。例えば遺言書(民法第1189条)、動産譲渡担保(民法第899-1条)不動産の取得や移転(民法第758条)などがその典型例です。こういった作成方法が予め法律によって定められた契約は、たとえ当事者の双方が合意して電子署名で調印したとしても、法律上無効と認定されてしまうので、留意が必要です。
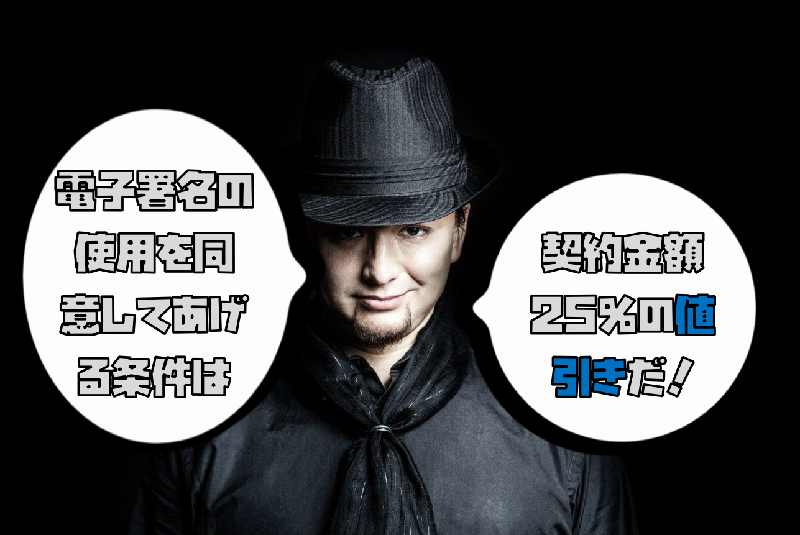
考えが及ばない、準拠法!

今回客先と締結しようとするのは、要式契約に該当しない取引基本契約書で、電子署名を使用することも先方の了解を得ており、なおかつ電子メールのやり取りも客先の代表者と直接行ってきたので、全ての法的要件が揃ったと思って、早速電子署名で契約したものの、出荷寸前になって急に客先と連絡がつかなくなり、裁判所に損害賠償請求を申し立てたら、契約が最初から成立していなかったため、客先に賠償の義務はないとの判決が下された。
法律に則って遵守すべきルールを悉くクリアしたのに、何故?と考えたりするかもしれません。理由は、準拠法の設定にあります。
今まで紹介してきた内容は、台湾国内で正しく電子署名を使うために必要とされる条件です。それらを守っておけば、台湾において問題なく電子署名を活用できます。一方、取引先が国外企業の場合、取引契約書に「準拠法」についての条項が大体盛り込まれており、当該条項を利用すれば、たとえ双方のビジネス行為が100%台湾国内で完結する予定であるにもかかわらず、台湾法の適用を排除し、とある外国の法律を根拠にすることが可能です。
当該外国の法律は電子署名をどのように扱うか、そもそも電子署名を認めるかを把握しないままで、台湾の考え方に則って電子署名で契約を締結してしまうと、その後契約が無効と判断されるリスクが発生してきます。そのため、取引先との契約書に記載された準拠法の内容を見極めたうえ、電子署名を合法的に運用可能かを検討する必要があります。
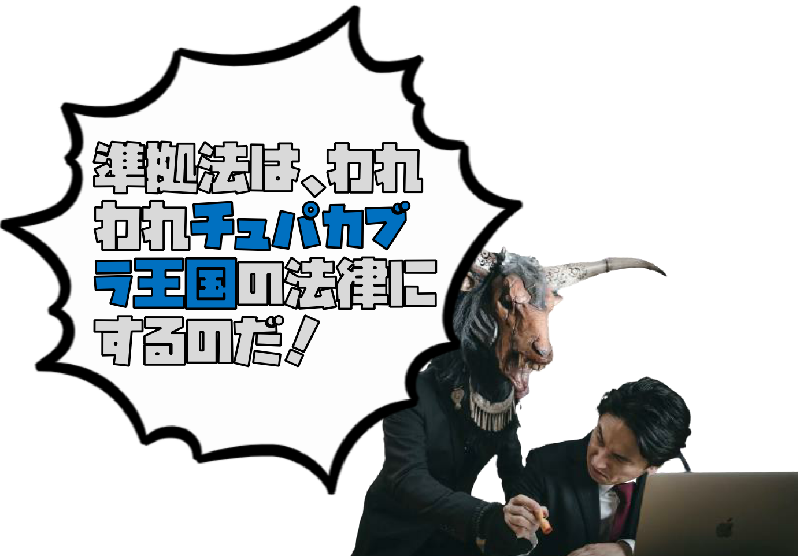
電子署名で契約すれば、印紙税はかからない?!
締約する際に電子署名を使えば、「紙」を「印」刷しないので、「印紙」税を払う必要はない、との節税効果を一大メリットとして電子署名の使用を促す説をたまに聞きます。
台湾の印紙税法によると、台湾国内で売買契約書などの課税文書を作成したら、印紙税を納付しなければならないとされます(印紙税法第1条)。そのため、海外で締約した場合を除き、たとえ締約行為がオンラインで行われたとしても、印紙税の納付が義務付けられるわけです。例えば、台湾の政府機関から案件の依頼を受ける際の契約書は、電子署名で締結することは可能だが、契約が成立した後、所定の税率に則って印紙税を納付必要とされています(台財税字第10404573930号通達)。
ですので、「電子署名=印紙税かからない」というのは都市伝説に過ぎません。
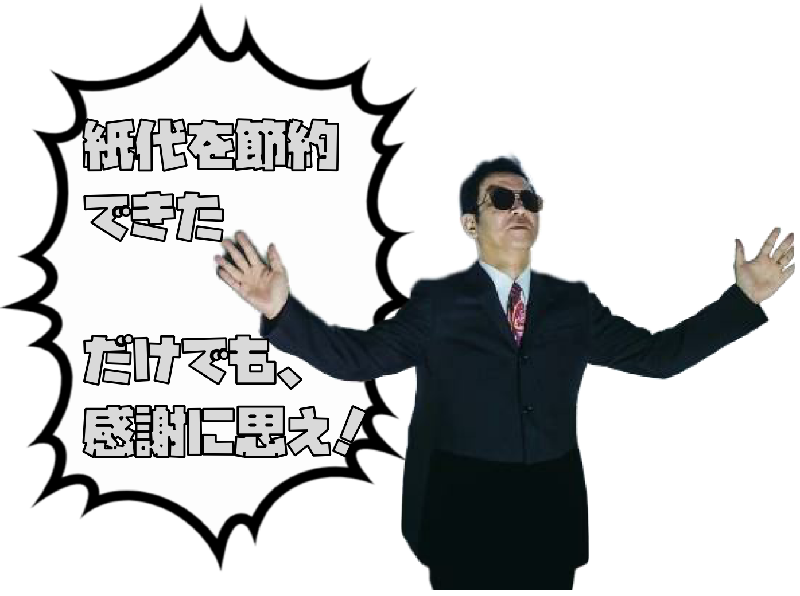
デジタル署名と電子署名の違いは?
オンラインで署名を作成する方法に、電子署名のほか、デジタル署名というのもあるが、両者を混同し間違って使ったりする場合が散見されます。実際、デジタル署名は電子署名とは異なる署名方法ではなく、電子署名の一種として位置づけられています。
台湾の電子署名法において、デジタル署名は以下のように定義されています。
電子文書ファイルを数学的なアルゴリズムその他方法で、長さが一定のデジタルデータに変換し、署名者の秘密鍵で暗号化して電子署名を生成し、公開鍵で検証できるもの。
上記の定義はややこしくて、その分野の専門家でなければ理解に苦しむかもしれません。要するに、デジタル署名に仕上げるためには、所定のデジタル方法で対象となる電子署名に加工を施す必要があり、それによって、通常の電子署名と比べたら、より高度な機密性、安全性が期待できる、というわけです。
ただし、上記の定義に当てはまっても、完全に合法的なデジタル署名とは言えません。以下2つの要件を同時にクリアできてはじめて、法律に認められるデジタル署名となります。
- 正式に許可された証明書機関が発行するデジタル証明書を使用すること。
- デジタル証明書が有効であり、かつ許可された範囲内で使用されること。
上記の制限により、会社内で自社用のデジタル署名をゼロから生成することはちょっと考えられなくて、その他企業が開発するデジタル署名サービスを利用することが一般的です。
他人のサービスを利用することとなると、使用料を支払わなければならないが、将来において電子署名の真偽問題で取引先とひと悶着するよりましである、と考える会社も少なくありません。

今週の学び
SDGsを推進するための取組として、ペーパーレス化の実施はメリット大です。電子帳簿を設置したり、電子統一発票を導入したりすれば、税務上で優遇が受けられることや、会社の変更登記をオンラインで行ったら政府手数料が300NTD減額されるなど、会社が自主的にペーパーレス化に取り組むよう、政府はいくつかの優遇策を設ける形で後押ししようとする努力が見て取れます。にもかかわらず、ビジネスの世界においては、紙依存の傾向が依然として根強く、紙を触らないと怖くて署名できないと考えたりする人はまだまだ多いようです。電子署名が普及するまでには、まだかなりの時間を要するでしょう。