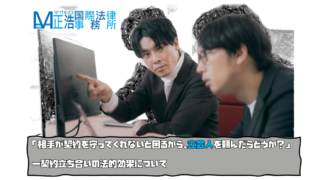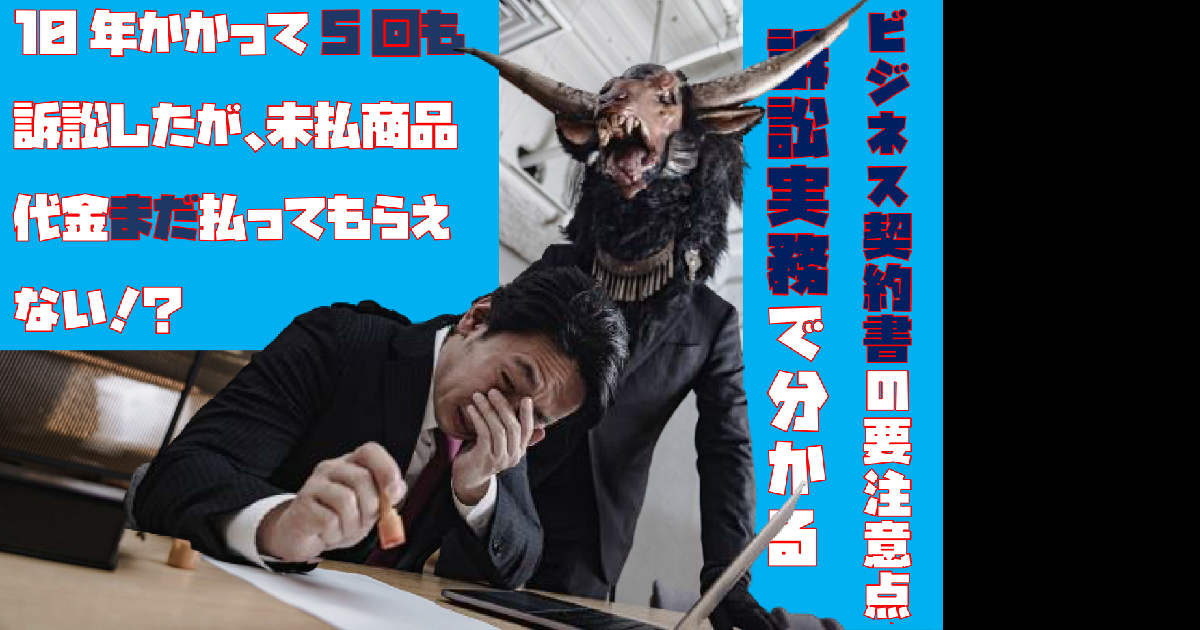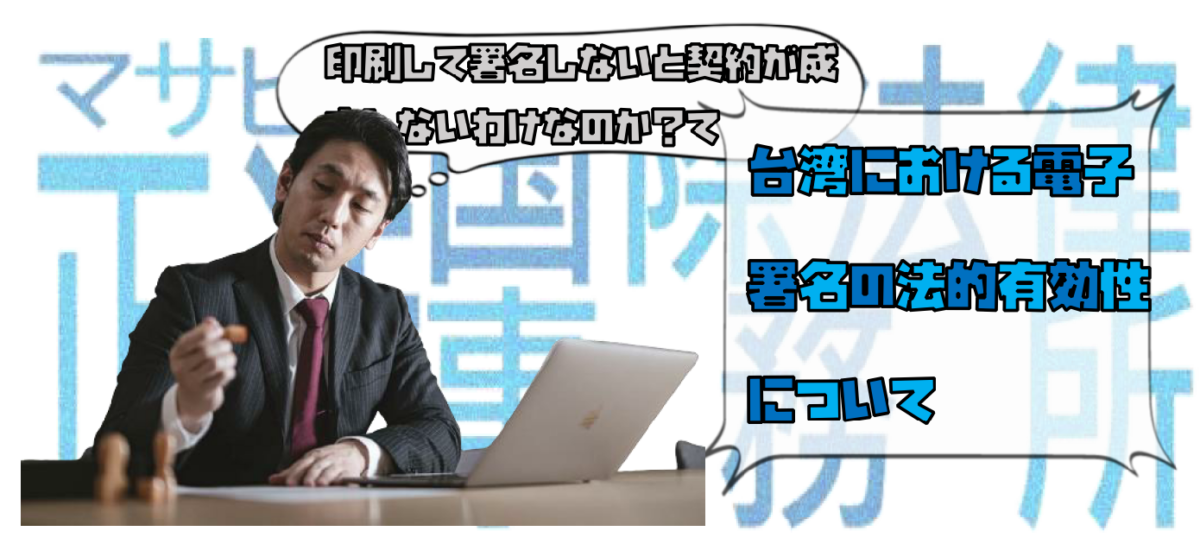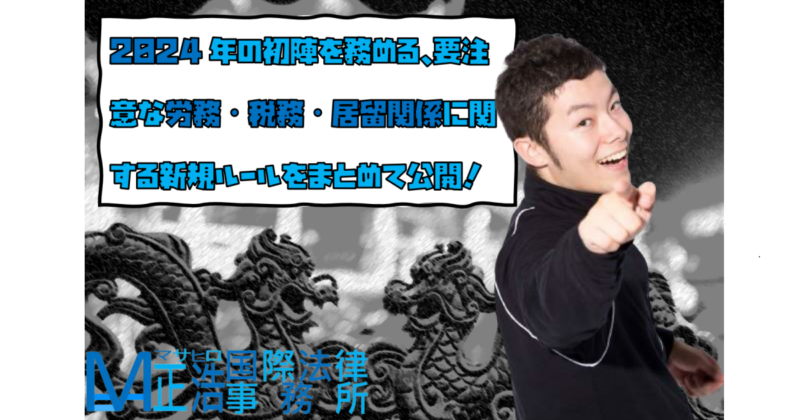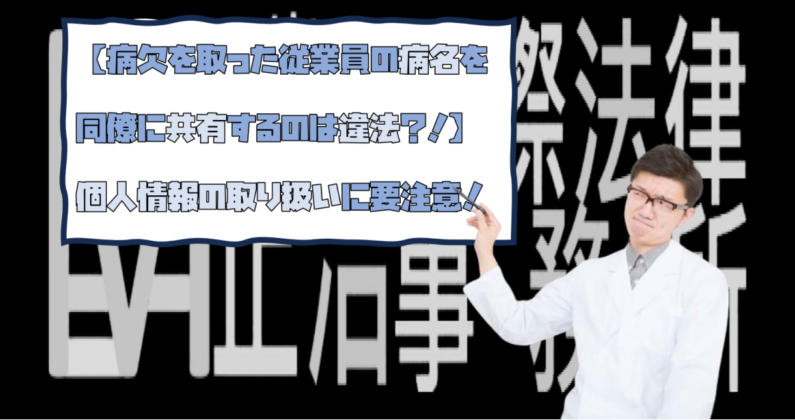「相手が契約を守ってくれないと困るから、立会人を頼んだらどうか?」―契約立ち合いの法的効果について
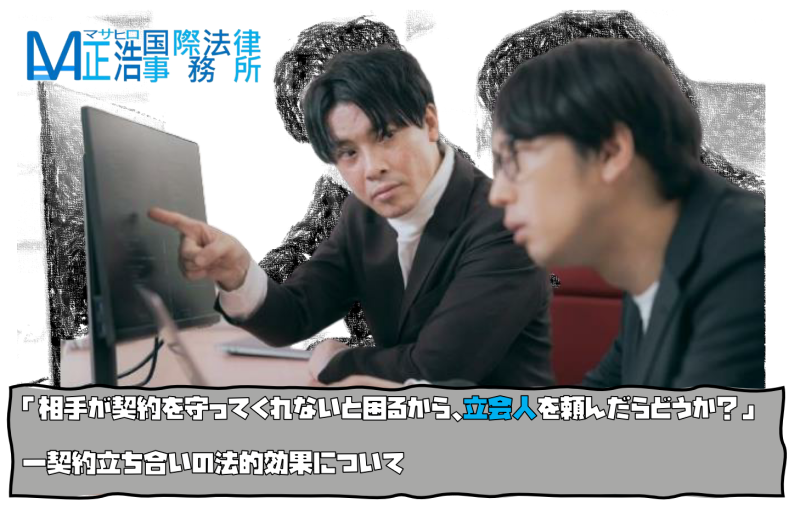
契約を結ぶことは、何もビジネスの世界に限られた話しではなく、他人から部屋や金銭を借りたり、ウェブサイトからソフトをダウンロードしたり、デパートでバイトしたりするなども契約を交わす必要があるかもしれないから、「契約する行為」はまさに日常的に行われています。
契約書にびっしりと書き込まれた活字を最初から最後まで読んで、内容をしっかり理解したうえ、署名欄にサインするのはむしろ少数派で、多くの場合、契約書を提示された一方は、社名または氏名及び金額などの情報さえ間違わなければ、10分もかからないうちに記名したりしています。そのため、「私がサインした契約書にその条項はないはず」、「この表現にはいろんな解釈ができるから、買い手にこんな義務があるとは知らなかった」など、成約した後において、程度の違いこそあれ、契約にまつわるトラブルが常に起きています。
契約にまつわるトラブルは、契約双方が互いに誠意をもって協議して解決できれば、それに越したことはないが、双方がどうしても一歩を譲らない状態に発展してしまうと、お金のかかる仲裁か、時間がかかる訴訟で紛争を解決するしかありません。

では、保険を掛ける意味で、契約の調印時に立会人を立てると、違約問題で契約当事者双方の関係がバチバチにならずに済むのか?
契約するとき、立会人はどういった役割を発揮するのか、弁護士を立会人として同席させたら何かメリットあるのかを含め、「契約立ち合い」の意味及び効果について以下解説します!
契約立ち合いの必要性と効果
台湾において、結婚や遺言書の代筆など立会人を立てないと成立しないレアケースを除けば、契約を交わすこと自体は、原則として第三者による立ち合いは必要とされません。契約当事者双方が契約書に自らサインしたり、口頭で約束したり(諾成契約)すれば契約が成立するので、立会人がなくても契約の法的効力は何ら影響を受けません。
では、わざわざ立会人を立てて、契約時に同席させるメリットは何かというと、「契約した事実の信憑性」が高まるほかありません。
立会人は基本的に契約当事者双方のどちら側にも属しない、客観性を有する第三者であり、このような人が現場に居合わせて、契約時の様子、調印に至るまでの一部始終を身をもって見聞きするわけなので、当事者がいつ、どこで調印したのか、取り交わされた契約書のタイトルは何なのか、何ページあるか、といった当事者間でしか知らない細かい情報が証明できるようになります。
契約の真正性が保たれるとはいうものの、立会人がいるから、契約当事者の一方が違約しない、もしくは当事者双方がその後特定の条項に関する解釈でもめたりしないというわけではないため、「立会人を立てると、相手が契約を守ってくれないリスクがなくなる」的な効果は期待できないかもしれません。一方、もし当事者間は契約の真正性、例えばなりすまし契約の問題で調停または訴訟に発展した場合、立会人がいると、事実に基づく証言をしてくれるので、トラブルの早期解決につながるか、比較的公平な判決結果が出ることが期待できましょう。
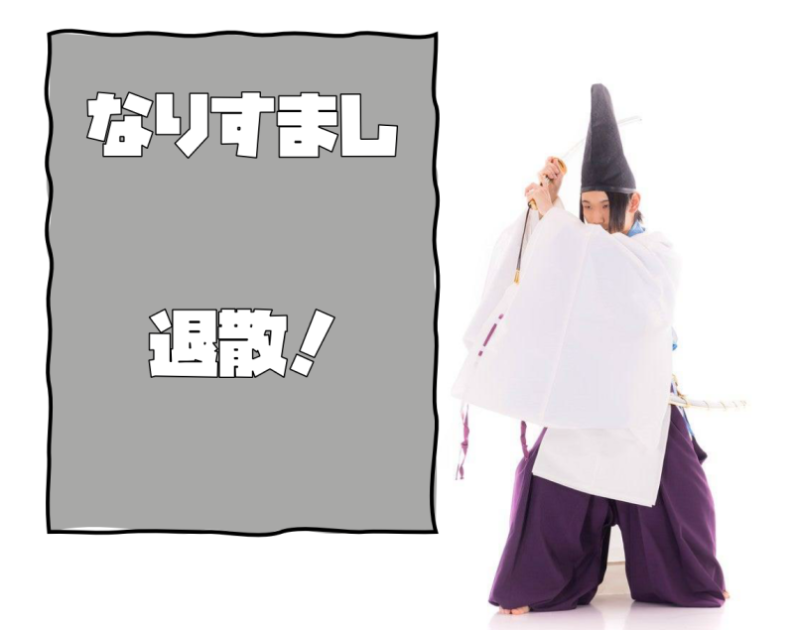
立会人をどうやって選ぶ?

立会人を立てなければ契約が無効になるわけではないが、契約期間が長いし、契約金額も高いから、客観的な第三者が契約時の様子を見守ってくれるほうが何かと安心だ!
第三者立ち合いのもと調印を進めようと決まれば、次は適任な立会人を頼むことです。台湾においては、契約の立ち合いを実施するのに特別な資格を予め取得しなければならないのような定めがないため、どなたでも立会人を務めることができます。例えば会社間で売買契約を結ぼうとする場合、買い手と売り手それぞれ自社の従業員を1名指定し、立会をさせてもいいし、大学生が寮を借りるための賃貸借契約を交わす際に、学校の先生に立ち合いを頼んでも問題ありません。
一般の個人にお願いしてもOKだという、契約の立ち合いは一見手軽に行えそうに見えます。確かに、契約の内容が分かりやすく、かつ契約期間も短いのであれば、適当な知り合いに頼んで契約の立ち合いを協力してもらっても差し支えありません。しかし、締結しようとするのは内容が多くて煩雑、法律の専門用語が多く書き込まれている契約書の場合、法律の専門家以外の個人に立会人として頼んだら、もし契約後において当事者間が契約条件に対する認識で齟齬が生じたり、契約に起因する損害賠償をどちら側が責任を負うのかについて双方がトラブったりすると、立会人から紛争解決につながる見解を得ることが難しいのみならず、いざという時に、立会人が裁判所に出廷して適切な説明を行ってくれる可能性も比較的低いです。従って、実務的には弁護士など法律の専門家に契約立ち合い業務を依頼することが多く見られます。
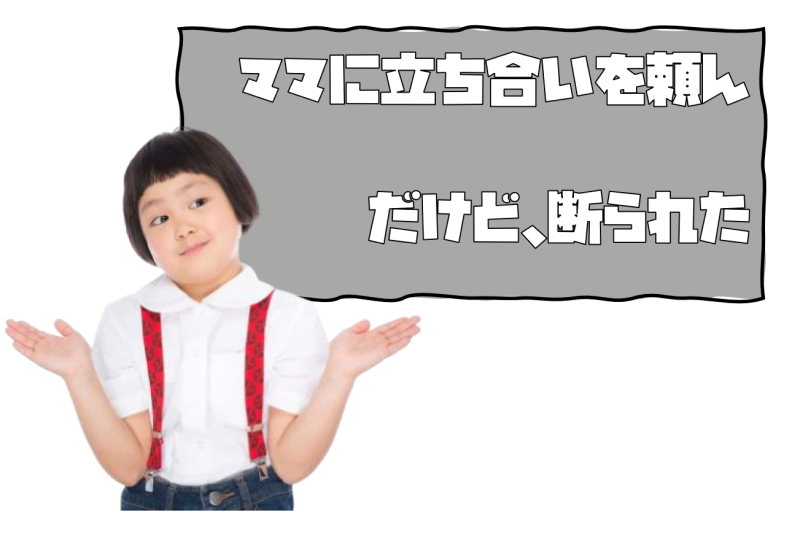
弁護士に立ち合いを依頼するメリット

知り合いに契約の立ち合いをお願いすると、無料でやってもらえるから、わざわざ報酬を支払って弁護士に立ち合い業務を依頼するメリットってある?
弁護士は契約の立ち合いを行うのに、その他の個人とは違い、いくつかの前提条件を遵守する必要があります。例えば、法律に違反する条項、もしくは法律上無効とみなされる行為を要求する条項が記載された契約書は、弁護士はそれの立ち合いを行ってはいけないとされます(台北弁護士協同組合弁護士立会規則第3条)。弁護士が契約の立ち合い業務の依頼を受けた場合、最初に行うのは、対象契約書に違法性のある内容が記載されたか、及びそれぞれの条項は法的に問題なく実施可能であるかのリーガルチェックです。弁護士は犯罪の可能性が潜む契約書を知ってなお立ち会ってしまうと、犯罪幇助として刑事裁判にかけられるので、対象契約書の合法性を見極めてから、立ち合い業務を請け負えるかを判断しなければなりません。そのため、弁護士立ち合いのもと締結された契約書は、法に反する可能性が比較的低いものです。
また、契約立ち合い業務の依頼を受けた弁護士は、調印の現場にて、契約当事者本人または当事者から委任状を受け取った代理人に身分証明書或いはパスポートの提出を求めるうえ、身元確認を行う義務があり、原則としてリモート方式で前述の確認作業を行うことができません(台北弁護士協同組合弁護士立会規則第4条、同規則第6条、同規則第7条)。そのため、契約当事者の一方が契約後、「署名したのは俺じゃない」、「署名したやつは俺の許可をもらっていない」などと言い出して、契約書の無効を主張したりするトラブルが起きにくいのです。
さらに、契約立ち合い業務を行う弁護士はただ単に調印の現場に赴き、参加者の身元確認を行って立会人の欄に署名してから、立会料を受領して現場を去るのではなく、対象契約書の内容をきちんと説明し、当事者に各契約条件がもたらす法的効果を確実に理解させ、そして当事者間の合意により契約内容の一部修正を行う必要があるほか(台北弁護士協同組合弁護士立会規則第8条)、契約の真正性について関係者から説明を求められ、もしくは訴訟で争われたとき、弁護士には説明及び証明の義務もあるとされます(台北弁護士協同組合弁護士立会規則第11条)。当事者間は契約についてもめたりするとき、調印時の立会人に連絡し証言してもらっても協力してくれないリスクがありません。
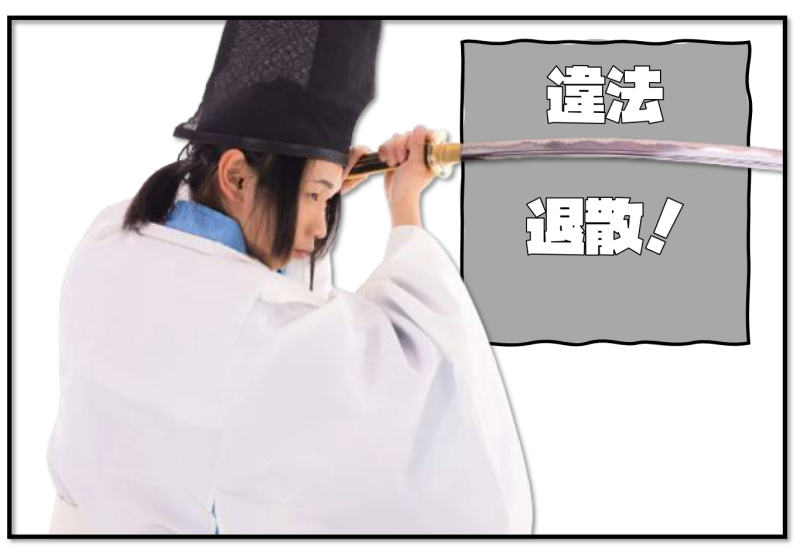
立ち合いと公証が違う?
「弁護士事務所は契約の公証手続きをやってもらえないか」、のような相談はたまに受けます。実は、「契約の公証」と「契約の立ち合い」は、「契約書そのものの真正性を証明する」効果を有する点は共通しているが、民事訴訟における証拠力は前者のほうが高いほか(民事訴訟法第358条)、当事者の一方が契約で定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合、他方は裁判を経ずして強制施行をすることができるという(公証法第13条)、公証を受けた契約書にはいわゆる「執行力」も付与されるため、両方の法的効果が異なります。なお、契約の公証手続きを実施する権限は弁護士が持っておらず、裁判所に所属する公証人及び民間公証人の専属的権限とされるため、「契約の公証手続き」を依頼しようとする場合、弁護士事務所ではなく、公証役場に相談しましょう。

今週の学び
取引を行う際に、口頭約束のみでは心もとないので、書面による記録が残せる契約書を取り交わすことが望ましいです。契約書が本物かどうか、調印した人が契約する権限を持つ人かどうか、といった契約の真正性について疑問が呈される可能性を回避しようとするならば、弁護士などに契約の立ち合い業務を依頼することがおすすめです。そして、契約書に法的執行力を持たせようとしたら、公証人に契約書の公証手続きを頼む必要があります。以上の基礎知識を、契約するたびに活用していただければ幸いです。