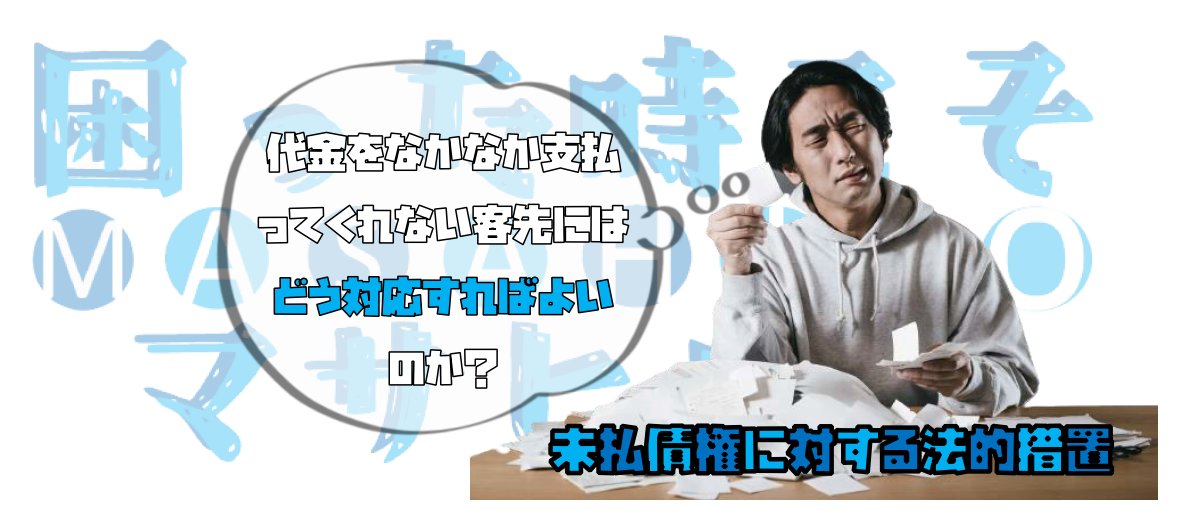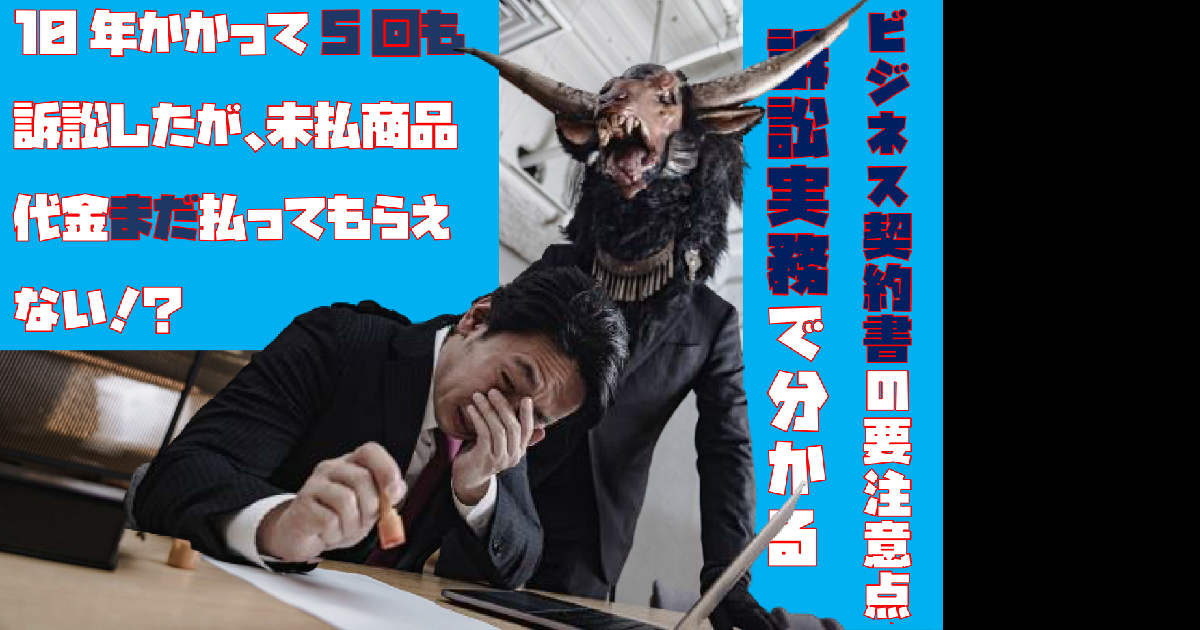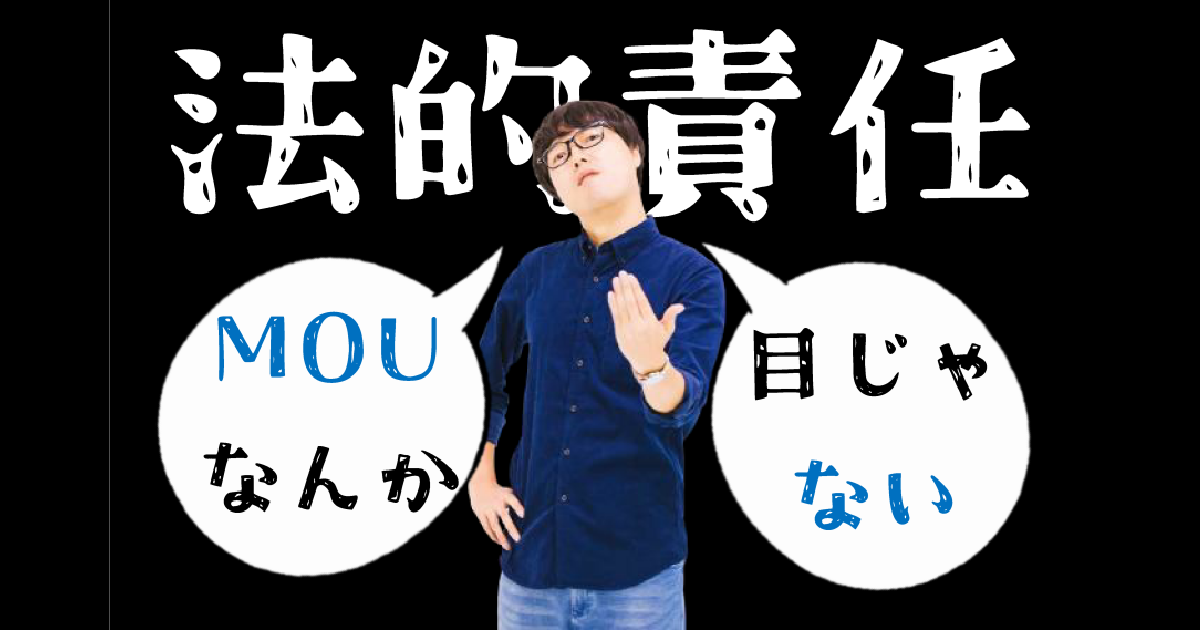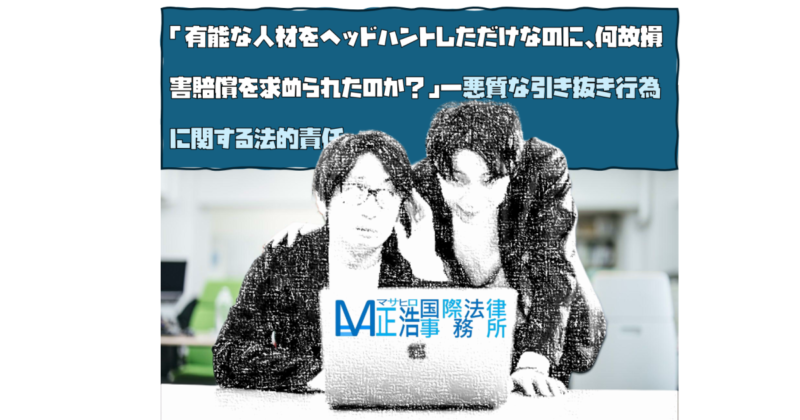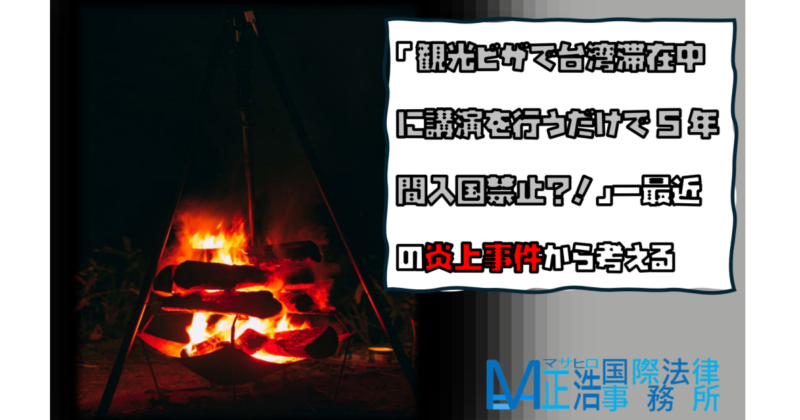「売り手は納品してから一方的に単価を決定して請求できるのか?」―裁判実務からみた合意なし取引の法的取り扱いについて

買い手が見積を依頼し、売り手が見積を提示し、双方が互い交渉した条件に合意すれば、取引が成立します。それに対して、買い手は売り手が提示した見積を受け入れることができず、交渉しても合意が達成できなければ、取引が成立せず、売り手は納品する義務がなく、買い手も代金を支払う必要がありません。
一方、買い手と売り手は発注書や見積書に関するやり取りを一切行っておらず、単価などの取引条件への合意に至ったのかどうかに関する認識もはっきりしないにもかかわらず、売り手は約束の品物を出荷し、買い手もそれらを受け入れた場合においては、果たして取引が成立したと言えるのでしょうか。もし取引が成立していないのなら、既に商品を受け取った買い手に代金を支払う義務が発生するのでしょうか。
上記の疑問点は台湾の法律でどのような扱いになるのかについて、この間ニュースで大きく取り上げられている、とある台湾芸能人夫婦と株主との間に起きた「商品代金の支払い請求」に関する訴訟を紐解きながら、回答を探ってみたいと思います。
事件の梗概
この事件のあらすじはこうです。
2020年12月
芸能人夫婦の①氏と②氏は食品事業を手掛ける③氏と④氏その他1名が合同で出資して、マーラー(麻辣)料理を販売する株式会社のM社を設立し、代表取締役に関連事業の経験が豊富な③氏が選ばれた。
2021年12月
M社の株主が集まって、これから販売する商品の品目、単価、原価などについて話し合っていた後、③氏が社員経由でG社に発注し、約1ヶ月後に注文の商品がM社に届いた。
2022年2月
在庫が少ないため、同社員が2回目の発注を行い、約1ヶ月後に注文の商品がM社に届いた。
2022年6月
商品の調達ルートや調達単価などについて互い納得が行くまで話し合われた前に、③氏が部下を指示して自分が総経理を務めるG社に発注させ、届いた請求書にめちゃくちゃ高い単価が記載されたが、M社に払わせようとする行為に憤りを覚えた芸能人夫婦は取締役会で代表取締役を交代した。
2023年2月
再三の催促を無視し、商品代金を支払おうとしないM社に対して、③氏が総経理を務めるG社は民事訴訟を起こして、代金支払いの請求を行った。
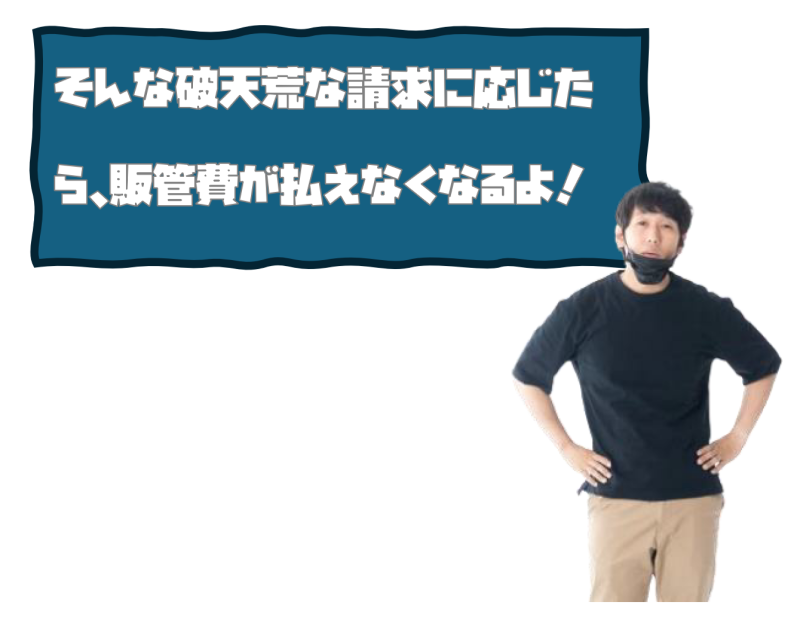
契約関係の有無について
台湾の民法では、当事者の一方が財産の所有権を他方に移譲し、他方が当該一方に代金を支払うという一連のやり取りは「売買行為」と称し、当事者間で対象となる財産及びその代金に関する合意がなされれば、売買契約が成立するとされます(民法第345条)。
G社は既に商品をM社に納品したが、当のM社はまだ代金をG社に支払っていないため、売買行為がまだ完成していないことが分かります。M社は商品代金をG社に支払い、売買行為を完成させる義務があるかを判断するために、M社とG社の間に商品売買という契約関係が存在しているかどうかを先にはっきりさせなければなりません。
証人の話によると、2021年12月にM社の株主が集まって、商品の試食及び売価に関する話し合いを行ったが、話しの内容は検討の段階にとどまっており、結論が出たわけではなく、商品の仕入れ単価についての言及もなかったといいます。
なお、請求書が届いて初めて仕入れ先がG社であると知ったM社の代表取締役(交代後)は事実関係を把握しようと、G社に対し取引が行われる前の見積書、及びM社が見積を承諾したことを証明可能な書類の提出を求めたが、結局証拠書類の提出がなかったそうです。
裁判官が以上の証言により、M社とG社とでは商品の仕入れ単価についての合意がなされておらず、売買という契約関係が存在しないため、G社が売買契約に基づいて、M社に対して行った代金支払いの請求が成立しないと判断しました。
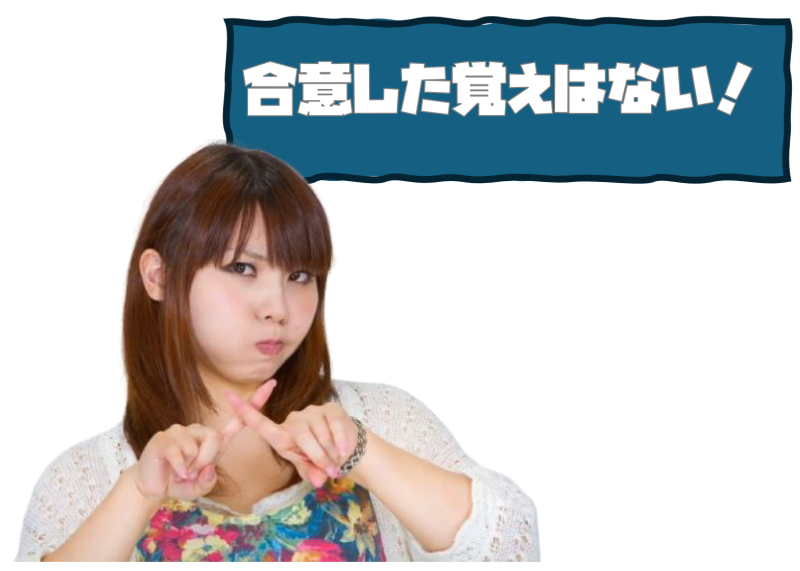
不当利得の有無について
台湾の民法では、法律上の原因がないにもかかわらず利益を受け、それによって他人に損害を及ぼした場合、当該利益が不当利得に該当し他人に返還しなければなりません(民法第179条)。また、不当利得を受領した者は、受けた利益だけでなく、当該利益に起因するその他利益も一緒に返還する必要があるが、返還すべき利益の性質その他原因によって返還できなかった場合、当該利益に相当する金銭を返還しなければなりません(民法第181条)。
M社とG社は商品の仕入れ単価についての合意がなされていないため、商品売買の契約関係は2社の間には成立していません。従って、G社には商品をM社に引き渡す義務もなければ、M社もG社に代金を支払う義務がありません。にもかかわらず、G社が商品を出荷し、M社もそれを受け取ったという事実がはっきりしており、売買関係が成立しない以上、G社にはM社に対して商品返還を要求する権利が生じることになります。
通常だと、G社が「商品を返してくれ」と伝え、M社が素直に指定された期日までに商品を無傷で返上したら事足りるが、肝心の商品の大半は既に売られており、残った分も賞味期限が切れて経済的価値がなくなったため、M社はお金でG社が受けた損失を補填するしかありません。
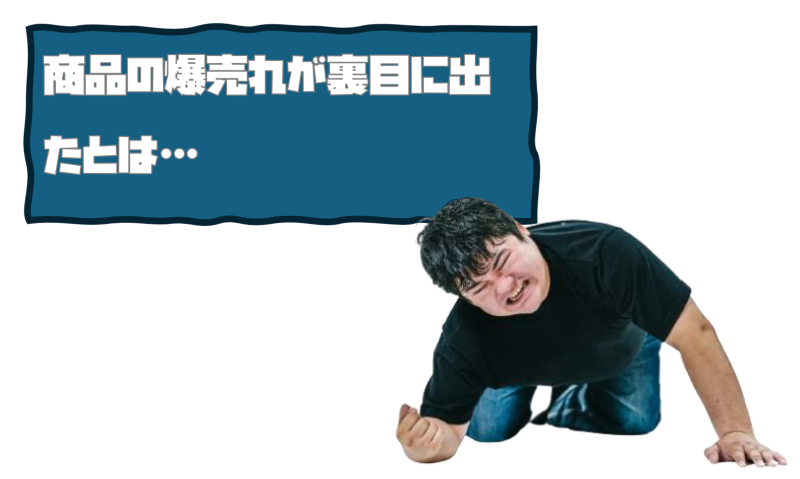
不当利得の金額の決定について
M社からは、G社は食品メーカーから対象商品を調達してから、一切加工処理を施さずにそのまま納品したから、同食品メーカーからの調達金額約NTD217万元をM社が受けた不当利得としてG社に支払ったらよいと主張したのに対して、対象商品はG社が開発したものであり、調達金額はあくまでも商品の原材料費に過ぎず、G社が請求した、NTD217万元に開発費を上乗せしたNTD315万元こそM社が返還すべき不当利得であるとG社が反論しました。
そして、百歩を譲って開発費の上乗せを認めたとしても、上乗せすぎんやろ、というM社のツッコミに対しても、うちここ5年間の粗利率は36.41%~28.55%なんで、本件開発費の上乗せ率はちょうどそこに収まるやで、とG社が決算書を出して跳ね返しました。
追い詰められたM社が喉からひねり出した最後の抗弁は、G社から仕入れた商品が高い値段かつ短期間で爆売れしたのは、ひとえに株主の芸能人①氏がソーシャルメディアで繰り返し宣伝を行っていたことによるものであり、そのため、①氏に支払って当たり前の広告宣伝費を、G社に返還する不当利得の金額から差し引くべきだと主張しました。
結局、広告宣伝費がいくらになるか、どのように計算したらよいかに関する証拠をM社は全く出せなかったため、G社が請求した、食品メーカーからの仕入れ価格に開発費を上乗せした約NTD315万元は、M社がG社に返還すべき不当利得として妥当な額であると裁判官から全面的に認められました(新北地方裁判所112年度訴字第93号判決)。
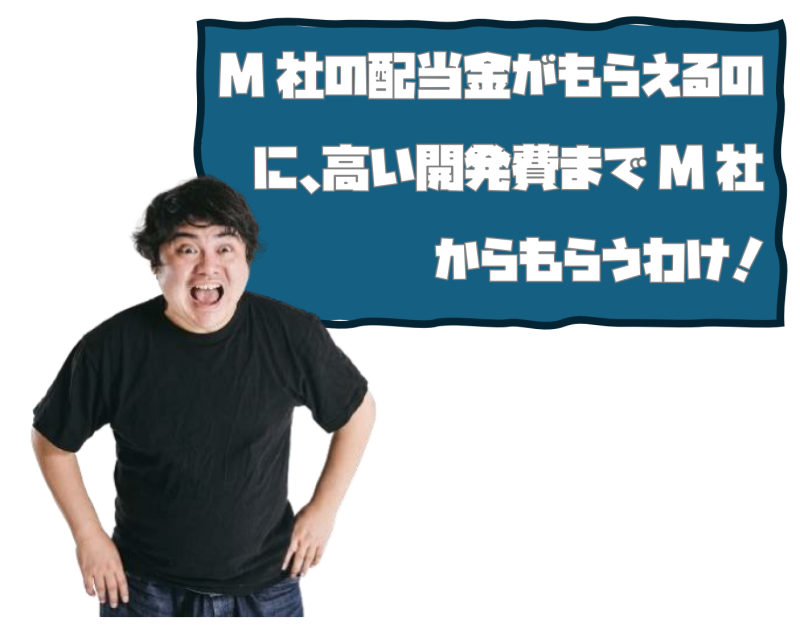
今週の学び
たとえ商品が確実に売り手から買い手に渡ったという事実があったとしても、売価又は数量に関する合意が確実になされなかったら、売買関係が成立するには至っていません。つまり、表題の「売り手は納品してから一方的に単価を決定して請求できるのか?」への答えはNOです。なお、既に受け取られた商品を買い手は完璧な状態で売り手に返還する義務があり、返還することが物理的に無理なのであれば、金銭で売り手が被った損失を補填しなければならないのだと、今回のケーススタディで分かりました。ただし、今回の件に関してやはり気になる点が残っています。
M社の株主である芸能人の①氏は、無償で知名度を利用して商品の宣伝を行ったおかげで、商品が比較的高い値段で売れました。他方の③氏は、M社の株主でありながら、商品の調達を利用して、自分が総経理を務めるG社に30%ぐらいの利ザヤを稼がせました。③氏の行いに利益相反の問題はないのか、あったとするとM社の株主総会で承認を受ける必要はないのでしょうか。なお、①氏の受領すべき広告宣伝費がいくらになるかについての立証ができなかったため、G社からの請求額が100%認められたわけだが、①氏がその他会社から依頼を受けた類似ケースをもって、合理性のある金額を算出できれば、G社への賠償金額がそれなりに減らされるのではないかとも考えられます。しかし、よくよく考えたら、もしM社の株主が最初からきちんと会議を重ねて行い、毎回議事録を丁寧に作って、かつ取引を行うたびに見積書や契約書などを作っておけば、事態はここまで悪化せずに済みましょう。
第一審で敗訴を喫した芸能人株主の話しでは、本件についての控訴を行ってとことん争っていく構えだそうなので、果たしてどんでん返しが起きるのか注目に値します。