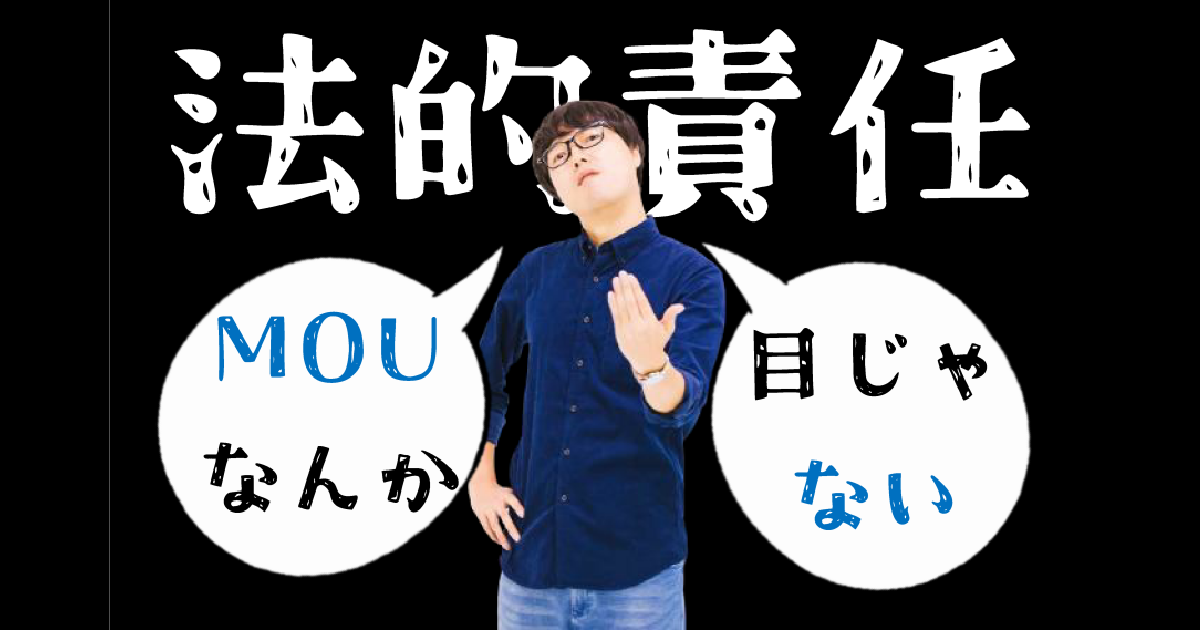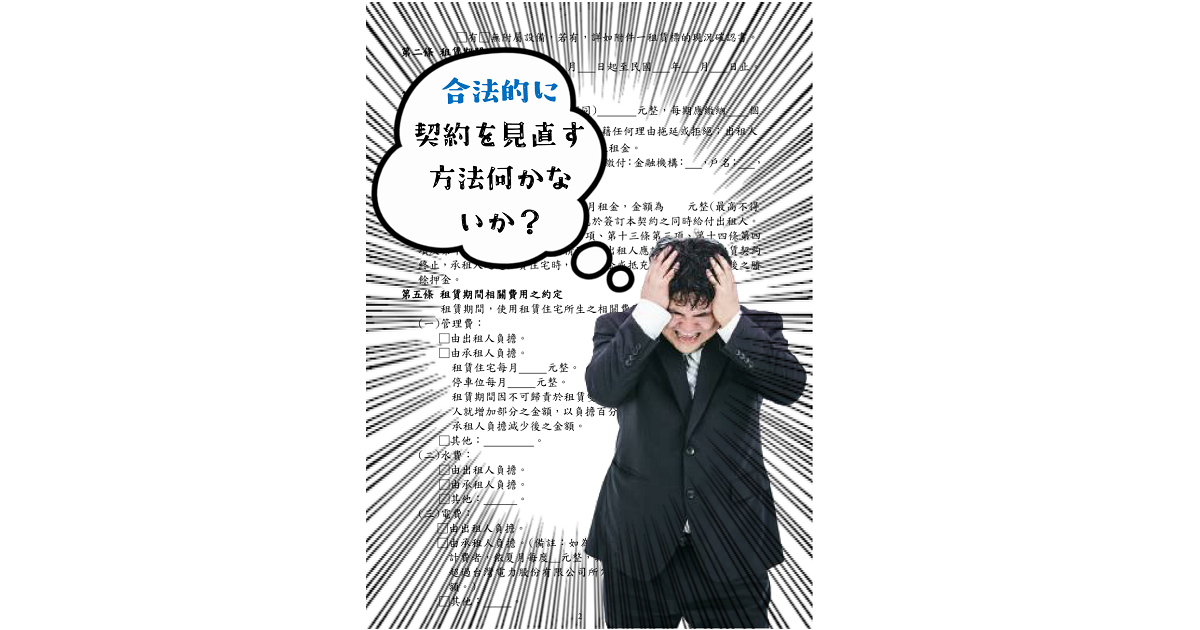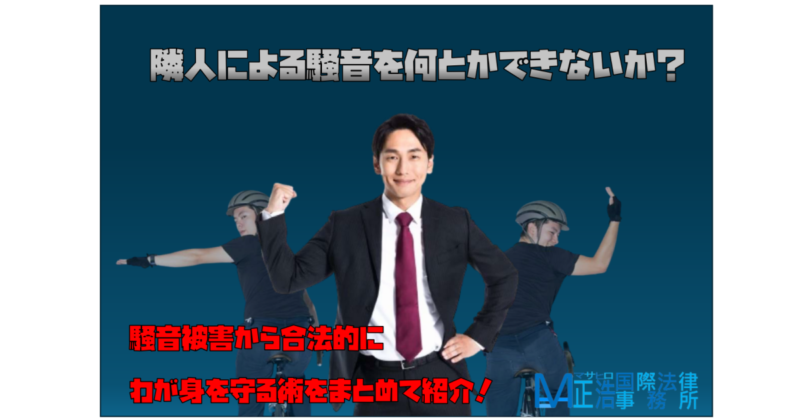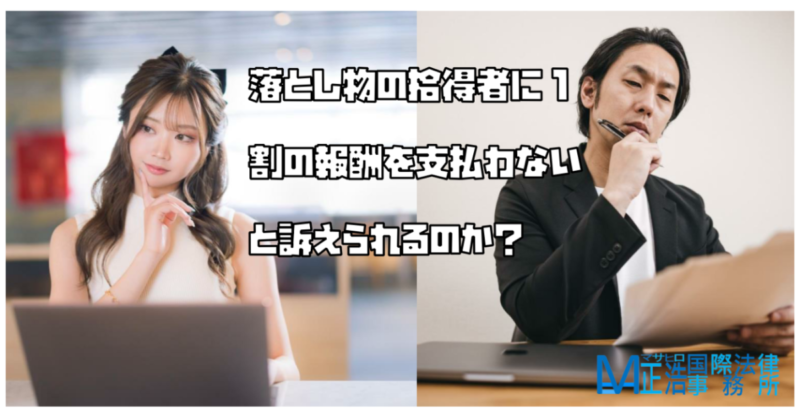「代理店と販売店とはどう違うのか?」―販売VS代理のメリデメ分析&エキストラを解説!

折に触れて以下のような相談を受けたりします。

マサひろん、ちょっと契約書を作ってほしいんだけど。

どんとお任せを!どんな契約書ですか?

販売代理店の契約書なんだけど

そうですね。その販売代理店というのは、具体的に販売店、代理店のどっちですか?
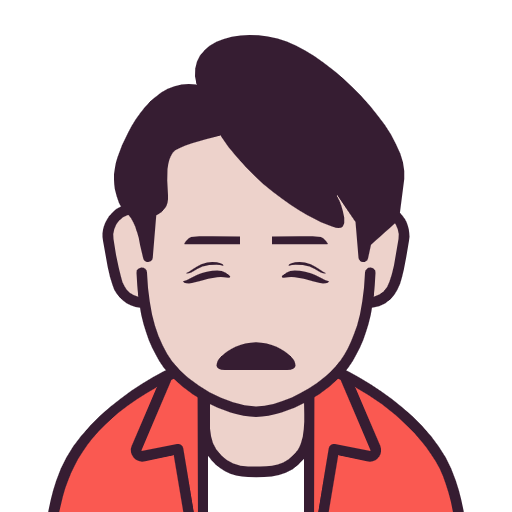
販売店と代理店の違いが分からんだけど…
メーカーと顧客の間に入って、メーカーが作った製品を顧客の手に届くビジネスに従事する会社を、普段はさりげなく「販売代理店」と称します。実は、一口に販売代理店と言っても、取引の形態によって大きくディストリビューター方式の販売店とエージェント方式の代理店に分けることができます。実務的には、この二つのコンセプトを混同して使用するケースが散見されており、正しく使い分けできるケースはむしろ稀かもしれません。
日常会話レベルの話し合いならまだしも、契約書を交わす段階となれば、販売店と代理店を慎重に使い分けしないと、トラブルの元になりやすいのみならず、予期せぬ連帯賠償責任を負わされる可能性も大きいため、両方の違いをしっかり認識してから契約の場に臨むことが望ましいと思われます。
以下、台湾における販売店と代理店に関する定義、及びそれぞれのメリデメ&エキストラについて解説したいと思います。販売代理店契約を結ぶときの一助になれれば幸いです。
代理店(Agent)とは?
メーカーと顧客との架け橋を務める代理店は、実際のところ、メーカーの製品の売り買いを一切行っておらず、たとえ自社の倉庫にメーカーの製品が置いてあったとしても、当該製品の所有権を有していなくて、あくまでも「製品を預かる」立場にあります。
メーカーから製品を実質仕入れていない代理店は、メーカーの「営業」として顧客に製品をアピールしたり推薦したりして、メーカーの代わりに注文を取ってきて、そしてメーカーから「販売手数料」をもらう形で収益を獲得しています。そのため、代理店は顧客への売価を自由に決定することができず、顧客から価格交渉を持ちかけられるとき、原則としてメーカーに判断を仰がなければなりません。
そして、代理店は立場的に、メーカーに顧客を仲介する位置づけなので、自らの名義で顧客と売買契約を締結することはありません。売買契約はメーカーと顧客の間に成立し、製品の代金も基本的にメーカーから直接顧客から回収する形となります。
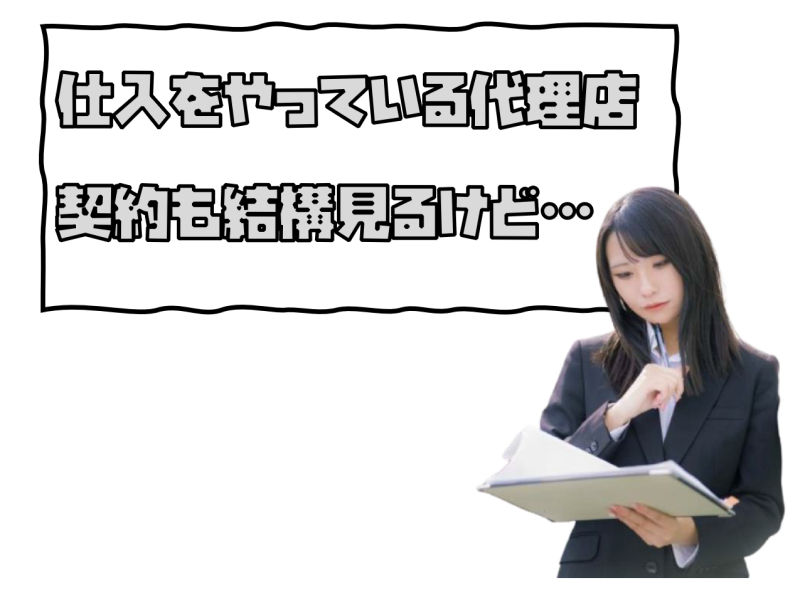
販売店(Distributor)とは?
販売店は、代理店と同じくメーカーと顧客をつなぐ機能を果たしているが、製品売買を一切行わない代理店と違い、販売店は自らの名義でメーカーから製品を仕入れて、自らの名義で顧客に販売するという、平たく言えば「転売」を行う事業者です。売買活動を行うわけなので、メーカーから製品の「所有権」を確実にゲットし、それから当該所有権を顧客に譲渡する形となり、いわゆるマージン(原価と売価の差額、もうけ、利ざや)を稼ぐ商売を営んでいます。
なお、メーカーは直接顧客と契約を交わすことはなく、売買契約はメーカーと販売店、販売店と顧客との間で個別に成立します。そのため、販売店は自社の利益UPを実現しようと、顧客への売価を自由に決めることができます。
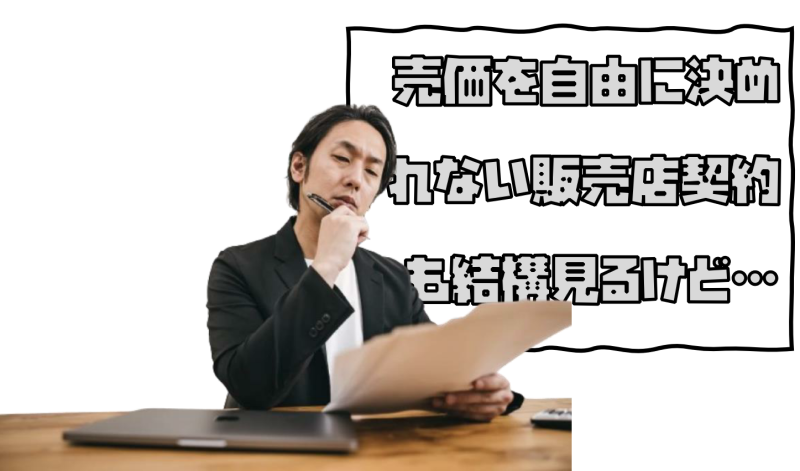
代理店のメリデメ
代理店は基本的にメーカーの方針に従い営業活動を行っており、製品の売価や販促キャンペーン、流通ルート、販売方法などについてはメーカーに提案する権利が付与されるかもしれないが、一方的にそれらを決定できないため、自由度が比較的に低いのです。つまり、代理店が注文を取りやすくする販促方法をようやく練りだしても、メーカーが頭を縦に振らない限り、それらの方法を安易に実施できないという制限を受けています。
一方、代理店はメーカーから直接製品を仕入れるわけでもなければ、自らの名義で顧客に製品を販売するわけでもないため、「在庫リスク」を負わなくて済むし、それによるキャッシュショート問題に遭う可能性も生じません。
なお、顧客が代金の支払いを渋ったりした場合、原則として顧客と締約したメーカーが何とかしなければならない立場にあるので、代理店はこういったリスクを対応する必要はありません。勿論、メーカーと締結する代理店契約に、「顧客から代金を回収できなかった場合、代理店に支払う手数料もパーになる」的な条項が盛り込まれると、話しが別ですが。
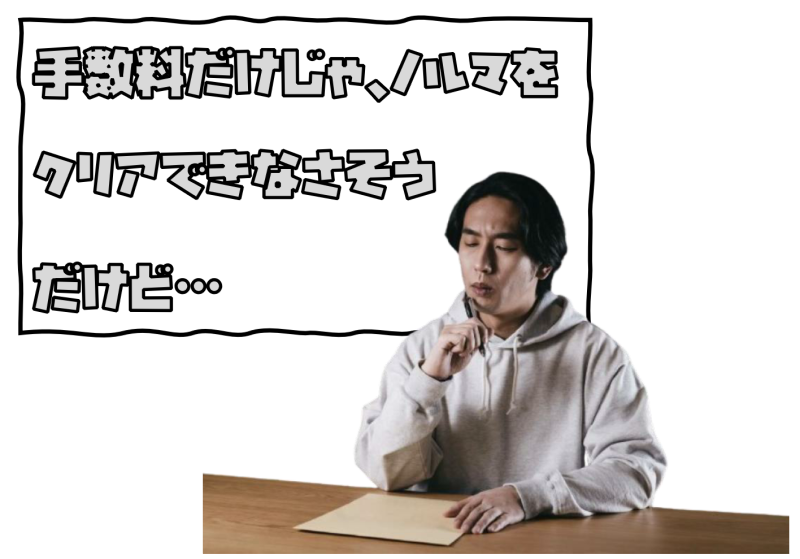
販売店のメリデメ
前述べたように、販売店はメーカーから仕入れた製品を自社名義で顧客に転売する取引を行っており、販売方法や流通ルート、製品の単価などを自らの意志で決定できるわけなので、代理店より自由度が高く、単価を高く設定すればメーカーより稼げるといったメリットも見込まれます。ただし、メーカーから仕入れた製品が売れるかどうか、売れにくいのであれば単価をどれぐらい下げたら売れやすくなるのかなど、自ら責任をもって戦略を立てなければならないため、売れば売るほど損が出たり、売れない製品を調達しすぎる在庫リスクやキャッシュがショートする問題なども発生したりします。そこで、一部の販売店は、一定の条件を満たせば一旦仕入れた売れない製品をメーカーに返品できる条項を販売店契約に盛り込むことで、在庫リスクを回避する方策を取っているが、メーカーがそのような条項を許すかどうかは互いの力関係によります。
また、顧客と売買契約を締結するのはメーカーではなく販売店であるため、トラブルが生じたら、販売店が真っ先に対応しなければならないという点からすると、代理店より損害賠償リスクが高いように思われがちだが、法律の定めによると、製品の設計、生産、製造、販売、輸入などに関与する事業者であれば、メーカーとともに製造者責任を負わなければならないとされるため、損害賠償責任を追及される可能性は、メーカーとの取引条件次第で、販売店も代理店もそれほど差がないかもしれません(消費者保護法第8条、消費者保護法第9条、民法第191-1条)。
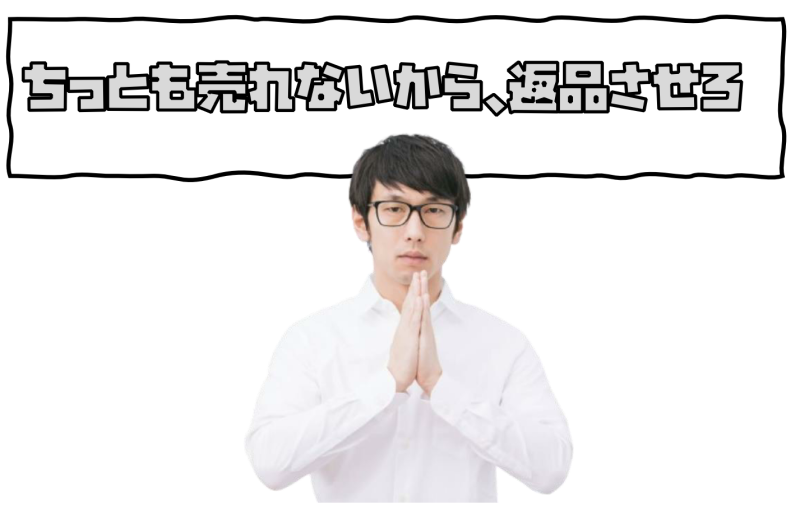
販売店は自由に単価を決定できないものか?
代理店と比べると、販売店は多く稼げるために、メーカーから仕入れた製品の単価を適宜引き上げて顧客に転売できる利点があると述べました。しかし、実務的には、転売価格をメーカーから厳しく制限される場合もあって、販売店がそれに違反して勝手に単価を調整したりすれば、メーカーから製品の供給がストップされる、的な条項が盛り込まれた販売店契約をたまに見かけます。メーカーとそのような契約を締結した販売店は、臨機応変的に単価を下げたり上げたりして利益の最大化を図ることができないため、販売店としての一大メリットがなくなってしまいます。とはいうものの、上記のような、販売店の転売単価に制限を掛ける行為は、台湾では公正取引法に反する行為に該当し、NT$10万~5,000万元の過料に処せられるのです(公正取引法第40条)。
事業者は、自社が供給する商品について、取引相手がその商品を第三者に転売する際の価格、または当該第三者がさらに転売する際の価格を制限してはいけない。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。
前項の規定は、事業者が供給するサービスについても適用される。
上記の法律によると、メーカーは自ら取引する販売店だけでなく、販売店の転売先に対しても、よほど説得力のある大義名分がない限り、原則として売価に制限を設けてはいけないことが分かります。従って、「販売店には自由に単価を設定できるメリットがある」という論点は成り立ちます。
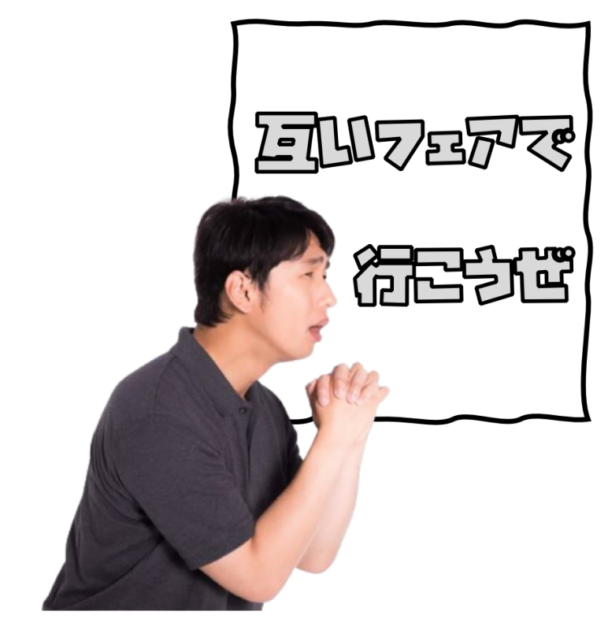
販売代理店になると税務リスクが高くなる?!
台湾の税に関する法律では、以下のような定めがあります。
「事業者が国内外の他の事業者と従属関係にある、または直接的もしくは間接的に他の事業に所有または支配されている」とは、事業者相互間に以下のいずれかの関係がある場合を指す。
(前略)
- ある事業者の生産・経営活動が、他の事業者が提供する特許権、商標権、著作権、営業秘密、専門技術、その他の特許権利なくしては行えず、かつその生産・経営活動の生産額が当該事業者の同年度の総生産額の50%以上を占める場合。
- ある事業者が調達する原材料や商品の価格および取引条件が、他の事業者によって管理され、かつその調達額が当該事業者の同年度の総調達額の50%以上を占める場合。
- ある事業者の商品販売が、他の事業者によって管理され、かつその販売収入が当該事業者の同年度の総販売収入の50%以上を占める場合
(後略)
代理店か販売店を問わず、メーカーから商標権やノーハウなどの実施許諾を受けてビジネスを行うケースが少なくありません。そのような代理店、販売店がたまたまとあるメーカーから単価がめちゃくちゃ高い製品、もしくは爆売れしている製品を調達したりすれば、メーカーと代理店・販売店との間に、「事業者が国内外の他の事業者と従属関係にある、または直接的もしくは間接的に他の事業に所有または支配されている」という関係性があったと認められます。そうすると、代理店・販売店が調達先であるメーカーはの「関連会社」にみなされ、互いの取引が「関連者間取引」に該当する形となります(移転価格審査準則第4条)。そして、関連者間取引に従事する会社は、「移転価格報告書」という大変面倒くさく、コストも非常にかかるコンプライアンス文書を作成する義務が生じており、下手をすれば追徴課税のリスクも伴ってしまいます。

製品の販売代理をやっているだけなのに、関連会社と言われるのは筋違いなのでは?ましてやその金がかかるなんちゃらかんちゃら文書を作成するなんで…
そのとおり、代理店または販売店はメーカーと持株関係がなく、それぞれの役員メンバーもダブっていない、なおかつ人事や財務、事業内容についてもメーカーから一切干渉を受けないのであれば、たとえ上記に列挙した状況があったとしても、メーカーの関係会社にみなされず、ややこしい移転価格報告書を用意せずに済むという公式見解が税務当局よりリリースされています(台財税字第09704555180号通達)。
関連会社に該当しない代理店・販売店には移転価格報告書を作る義務こそないが、税務当局から問い合わせが入るのに備え、予めメーカーと代理店契約または販売店契約を締結しておくことがおすすめです。
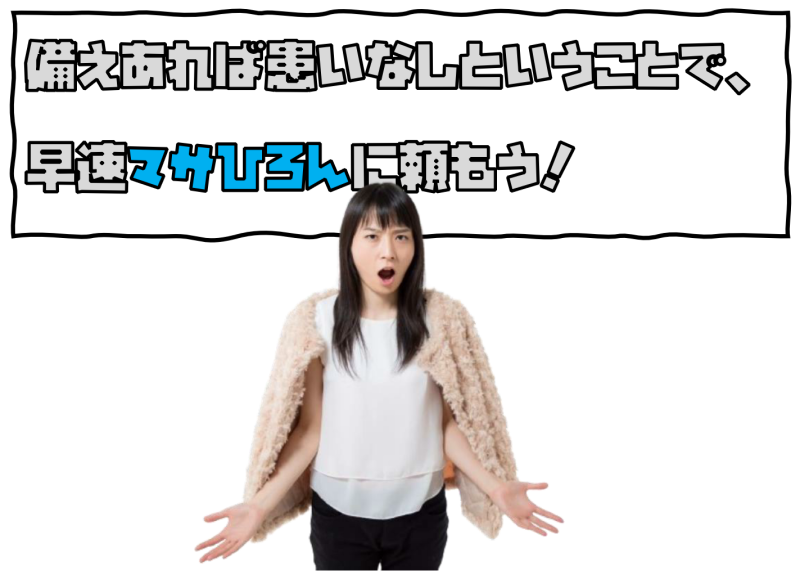
今週の学び
以上の説明で、代理店と販売店の違いがお分かりになりましたでしょうか。メーカーと締約するとき、きちんとそれらの用語を使い分けしないと、一部果たすべき義務と主張可能な権利が曖昧となる可能性があるのみならず、トラブルが生じた際にも如何にして自社の権利を守るかなどの戦略も立てにくくなります。「始めよければすべてよし」ということで、最初のステップである代理店・販売店契約書の作成協力を是非気軽にマサひろんへ相談しましょう~