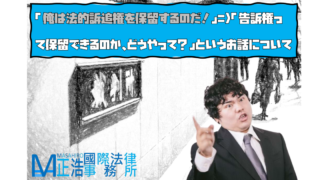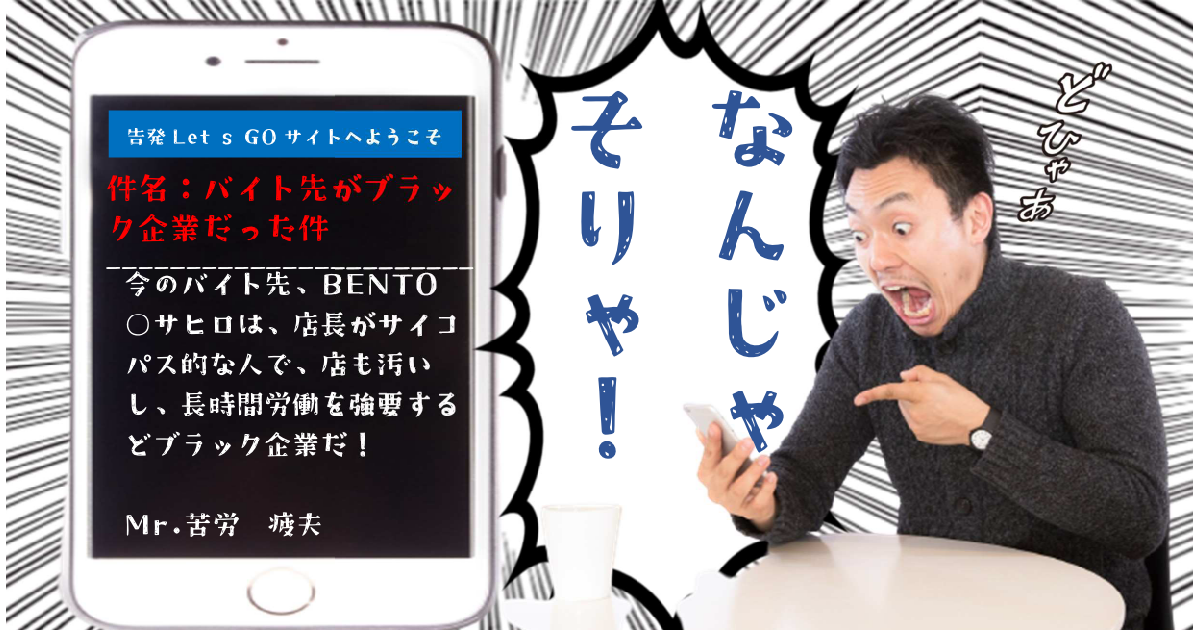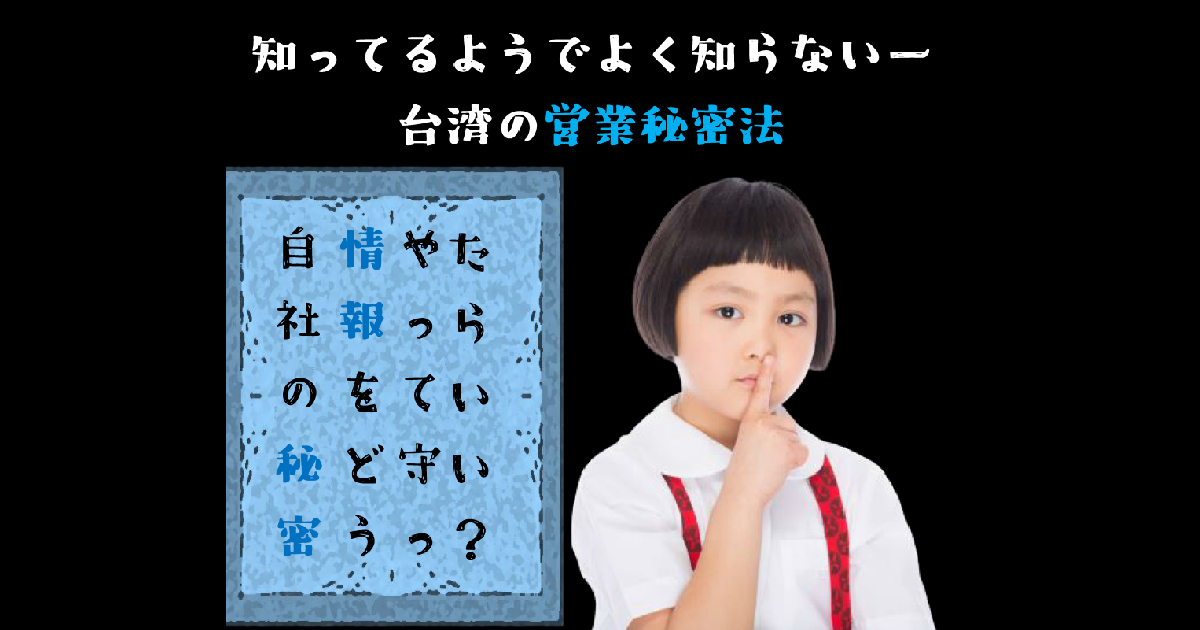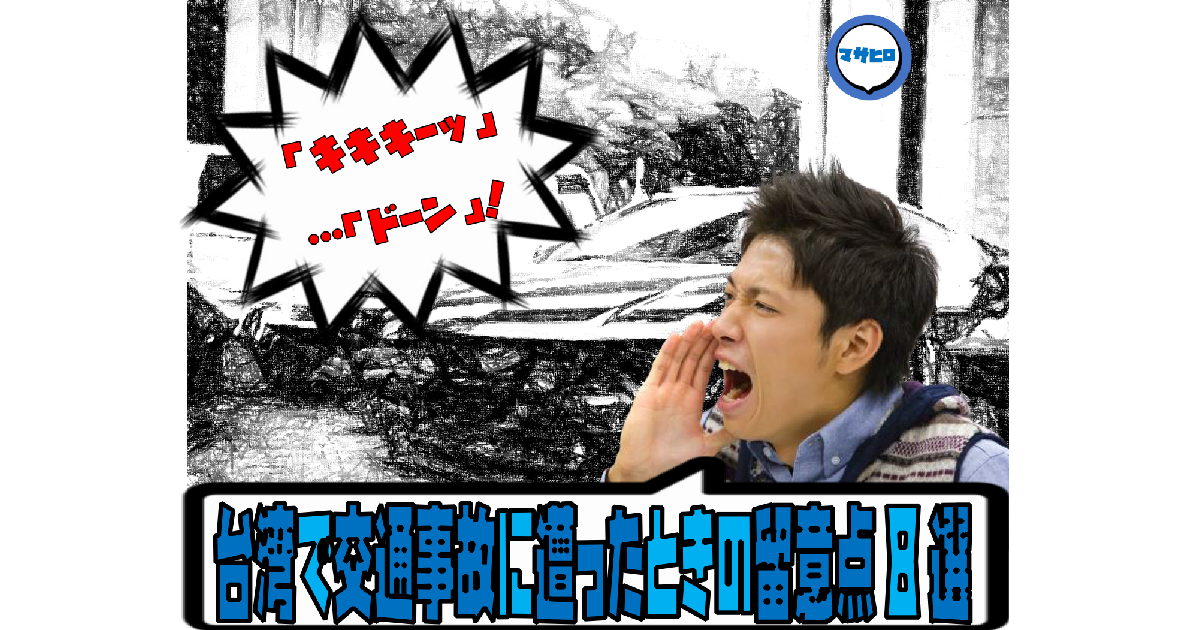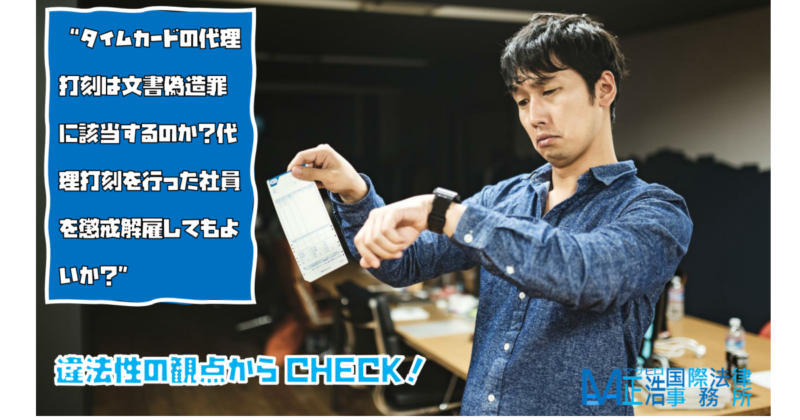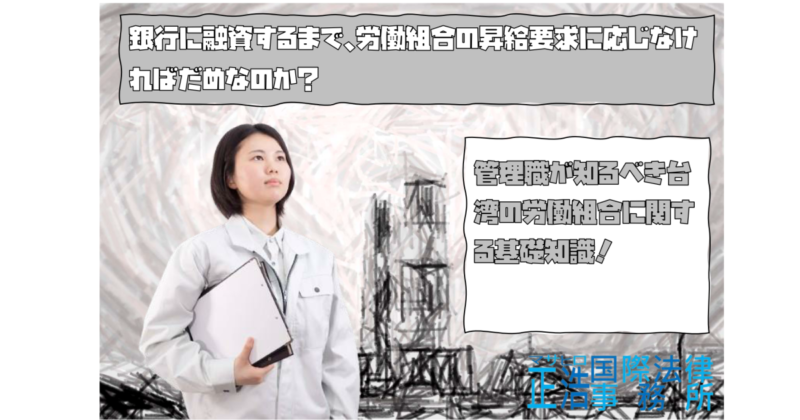「俺は法的訴追権を保留するのだ!」=>「告訴権って保留できるのか、どうやって?」というお話について
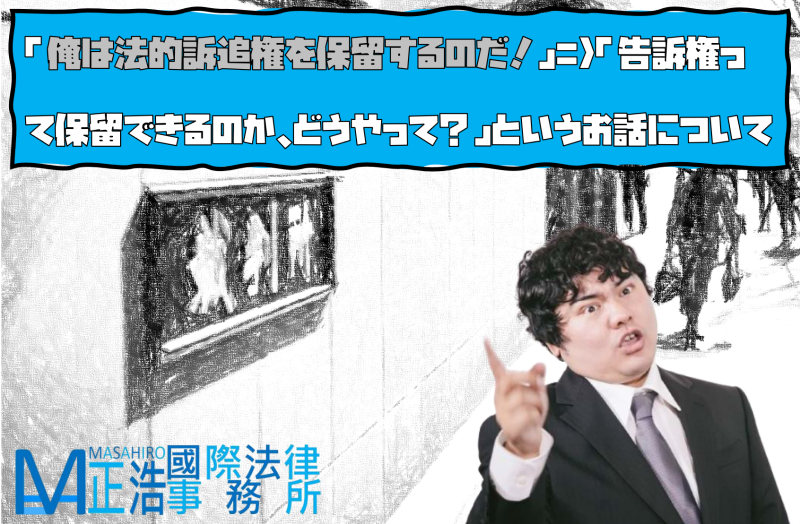

二度もぶった。親父にもぶたれた事ないのに!俺は法的訴追権を保留するのだ!
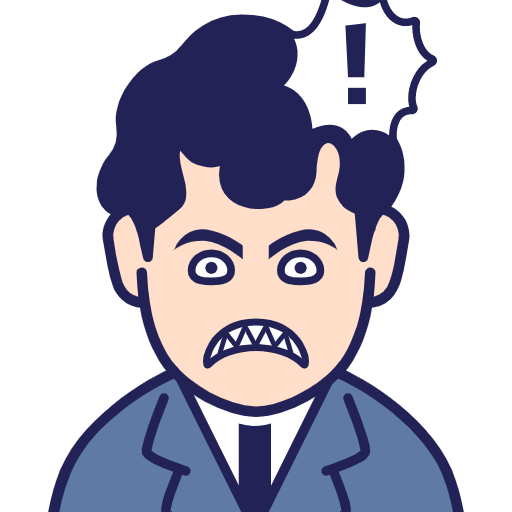
「あんた バカぁ?」って言ったなあ…法的訴追権を保留してやる!
「俺は法的訴追権を保留する」という表現を耳にしたことはありますか。台湾の政治ニュースを観ると、真実はともあれ、反対勢力から何かしら批判を受けた一方は、「法的訴追権を保留する」をテレビの前で宣言したりする場面によく出くわすのではありませんか。
また、ネット掲示板で言い争っている二人のネットユーザの一方は、「先の投稿はスクショで取った、俺は法的訴追権を保留するんだ!」といったコメントを付けて、何か法的アクションを取ろうとする言動を見せる事例も少なくないようです。
法的訴追権とは何か、それを自らの意志で「保留」できるものなのかについて、企業法務の観点から語ります。
法的訴追権とは?
「訴追」という動詞の意味は、「検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること」です。まず、訴追の対象になるのは「刑事事件」なので、損害賠償または慰謝料を請求する民事訴訟は関係なく、主な目的は「犯罪を追及する」ことにあります。
そして、「訴追」ができるのは、公訴を提起し、それを遂行する権限を国から与えられる検察官であり、検察官以外の個人又は法人は訴追できない形になります。
従って、政治家にせよ、ネットユーザにせよ、「法的訴追権を保留する」ことは原則としてできない、との結論にたどり着きます。では、「法的訴追権を保留する」ことを言い出すシチュエーション、例えば他人から社会的地位を貶める的な発言を受けた場合、代わりに何を宣言したらよいかというと、「告訴することを真剣に検討している」と表現したらしっくりくるかもしれません。
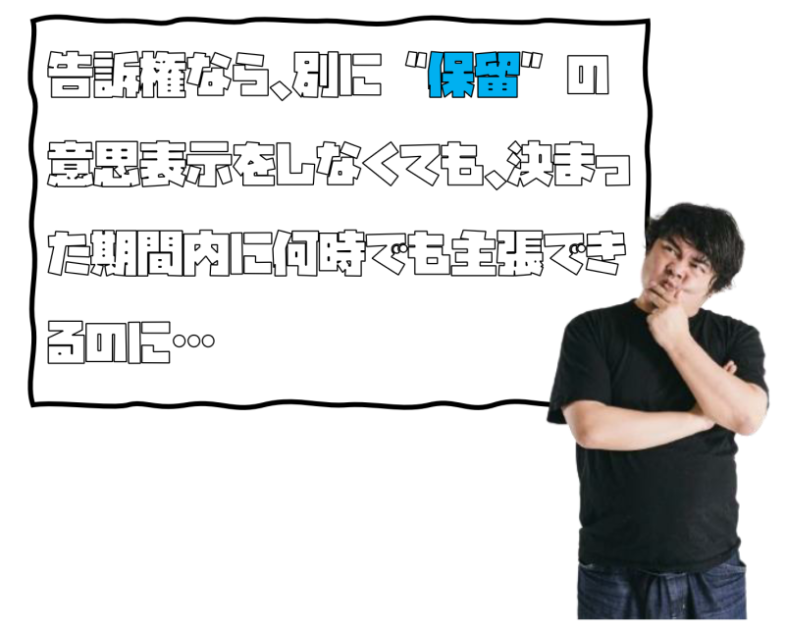
告訴期間はどれぐらい?
訴追権を保留できない代わりに、告訴するかどうかを検討することは可能です。一方、告訴を検討できる期間はHUNTER×HUNTERの連載期間とは違って、決まった時間帯が定められているので、この特徴から「…保留する」という動詞が用いられるのではないかと言われます。しかし、告訴を検討できる期間、いわゆる「告訴期間」というのは、ある個人が一方的に「保留する」と言い出した瞬間、自動的に延長するという都合のよい制度ではないため、「保留」は明らかな誤用であることが分かります。
民衆が保留したがる「告訴期間」は果たしてどれぐらいあるか、を考える前に、まず親告罪と非親告罪の違いを理解する必要があります。親告罪というのは、被害者が自らの意志で告訴をしない限り、加害者は刑事責任を問われない犯罪行為であり、非親告罪は、被害者本人が告訴しなくても、検察官は自らの調査結果により加害者を起訴して刑事裁判にかけられる犯罪行為です。後者の非親告罪には告訴期間が設けられず、5~30年(殺人罪などは期限なし)の公訴時効が成立しなければ、検察官は何時でも訴追できます(刑法第80条)。一方、親告罪には比較的短い告訴期間が設けられており、犯人を知ったときから6か月以内に告訴を行う必要があるとされます(刑事訴訟法第237条)。
台湾における親告罪と非親告罪の種類については、企業法務的によく言及される犯罪行為を取り上げて以下例示します。
親告罪と非親告罪の例示
上記からもわかるように、従業員が社外秘の情報を無断で第三者に漏洩したりする刑事事件については、、会社は6ヶ月以内に法的アクションを取る必要があるのに対して、現預金などを管理する従業員が勝手に使い込んだりする違法行為については、20年を超えなければ何時でもその刑事責任を追及することが可能となります。こういった告訴期間や時効に関する情報をしっかり整理のうえ、企業法務の整備に当たることがおすすめです。
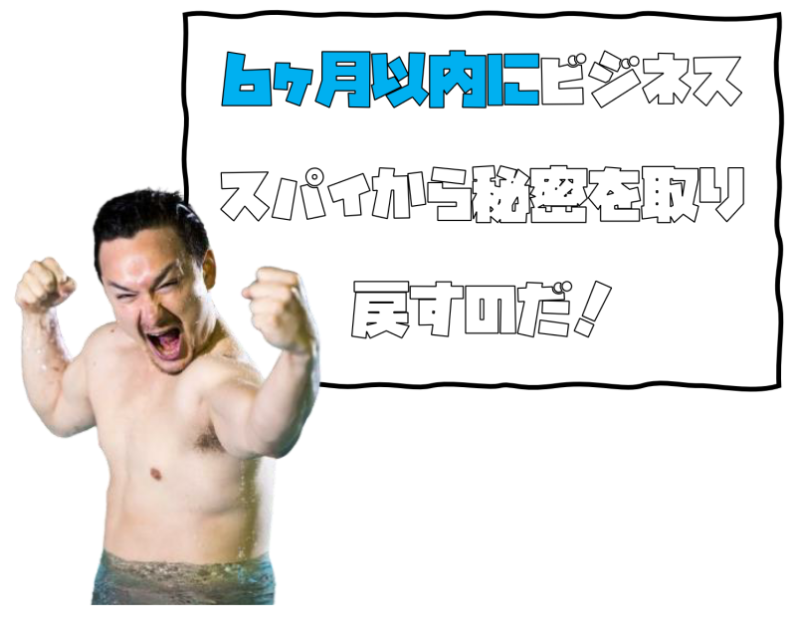
告訴ができるのは誰?

愚問だね、告訴できるのは本人に決まってるじゃん~
その通りです。親告罪の場合、被害を受けたのは法人か個人を問わず、被害者本人であれば自らの意志で告訴することはできます。ただし、告訴権者が個人の場合には、本人にはその気があるかどうかに関わらず、その配偶者は被害者の代わりに告訴を行うことが可能であり、告訴権者が未成年者の場合には、その両親も子供さんに代わって提訴できるとされます(刑事訴訟法第233条)。
なお、被害者が死亡したケースにおいては、配偶者や両親に加え、その直系血族、傍系3親等以内の血族、2親等内の姻族その他親族も告訴権者になれるが、被害者が死亡する前に、「訴えるな!」という明白な意思表示がなされたら、本人以外の親族が有する告訴権が消滅します(刑事訴訟法第233条)。
実務上においては、配偶者及び両親がいない被害者が昏睡状態に陥ったりする場合、その子女などの直系血族が被害者に代わって提訴できるか問題がちょくちょく持ち上がります。関連法律によっては、被害者はまだ死亡していないため、配偶者または両親(被害者が未成年者の場合)のみ犯人を告訴できるとされ、意識不明の親の権利を守ろうと子女が加害者の刑事責任を追及しようとしても、告訴権を行使できない形となります。
かといって、この理不尽な定めが原因で、加害者の負うべき犯罪責任がなくなる、というのもおかしな話なので、法律にはそのバグを修正する代替措置がちゃんと用意されています。告訴権者が存在しない、例えば配偶者や両親のいない被害者が重度の意識不明に陥った場合の親告罪については、検察官は利害関係者の要請により、もしくは自らの裁量権を使って、告訴権者を別途指定することができ、そうすると、「加害者が制度に助けられた」というバグがクリアされます。
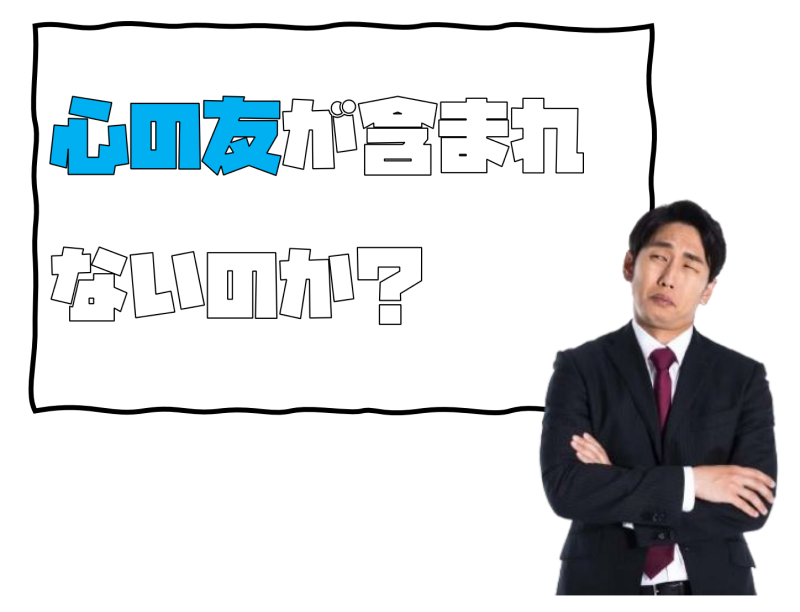
告訴期間はいつから計算?
パワハラや交通事故による傷害罪などの親告罪には6ヶ月という告訴期間が設けられており、当該期間が経過したら告訴権がなくなります。前述の「6ヶ月」の計算開始日については、「事件が起きた当日」と直感的に考えられがちだが、法律上、「犯人(加害者)を知った日」が計算開始日とされます(刑事訴訟法第237条)。
いわゆる「犯人(加害者)を知った日」というのは、金田一やコナンが人差し指をあさっての方向に向けて、「犯人はこの中にいる!」と宣言する謎解きスタート回ではなく、「真犯人を推理で追い詰めた回」の日です。
例えば、会社の秘密を外部に漏らしたのは紛れもなく従業員である、とおおよその範囲こそ絞ったものの、張本人までは特定できなかった場合は、6ヶ月間の砂時計はまだ動きません。社内で各種調査を行い、証拠がある程度揃い真犯人の顔が浮かび上がった時点に、6ヶ月のカウントダウンが始まる仕組みとなっています。
告訴期間を最初のうちから把握しておかないと、楽に勝てる訴訟も時効の関係で一発逆転を食らってしまうため、告訴期間の計算に迷うとき、早期に専門家に相談しましょう。

告訴を取り下げられる?
非親告罪は大体国や社会の公共利益と大きく関わる犯罪行為なので、一旦告訴すると原則的には取り下げることはできません。それに対し、親告罪は通常個人(法人を含む)対個人の紛争であり、個人の意思をできるだけ尊重する考えで、取り下げが可能とされます。
ただし、親告罪では告訴を取り下げることができるからと言って、原告がいつでも取り下げ権を行使できるものではありません。刑事事件の審理結果が分かるまで、裁判所においては公判前整理手続き、口頭弁論手続き、判決など3つのプロセスがあります。告訴の取り下げができるギリギリのタイミングは、第二プロセスの口頭弁論手続きが終わるまでとされます。なお、控訴審や上告審は取り下げ不可とされるため、ルール的には告訴の取り下げは第一審まで、そして一旦告訴を取り下げてしまうと、同じ理由でもう一度告訴することができないなどの点は要留意です(刑事訴訟法第238条)。
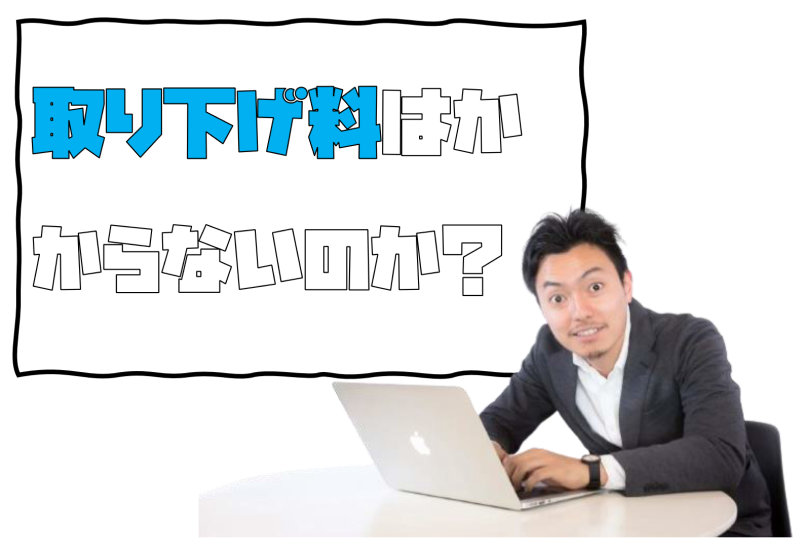
今週の学び
よく聞く「俺は法的訴追権を保留するのだ!」という発言は、中身を詮索すると、実はあまり意味をなさない表現であると、今週のマサレポで解説させていただきました。しかし、言葉的には意味が薄いとはいえ、言外の意味から、「これから訴えるかもしれないよ」という発言者の意図が汲み取れるはずなので、もし誰かさんにそのように言われたら、同人に対する言動をもっと慎んで、訴訟沙汰にならないよう気を付けましょう。