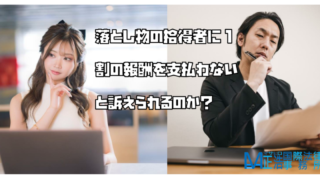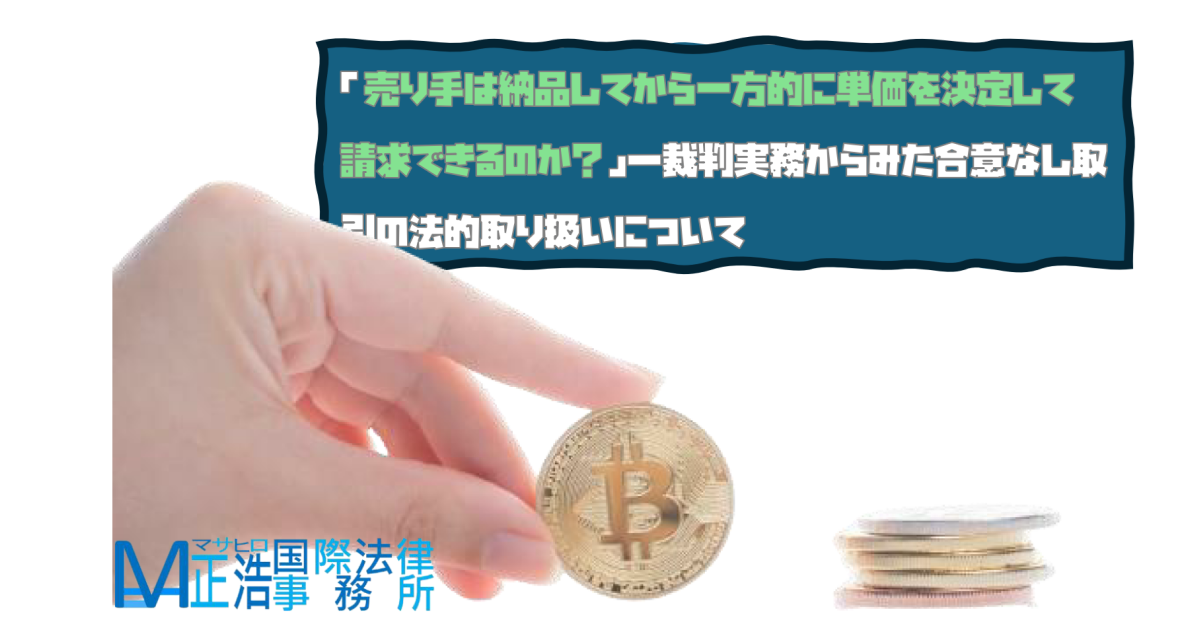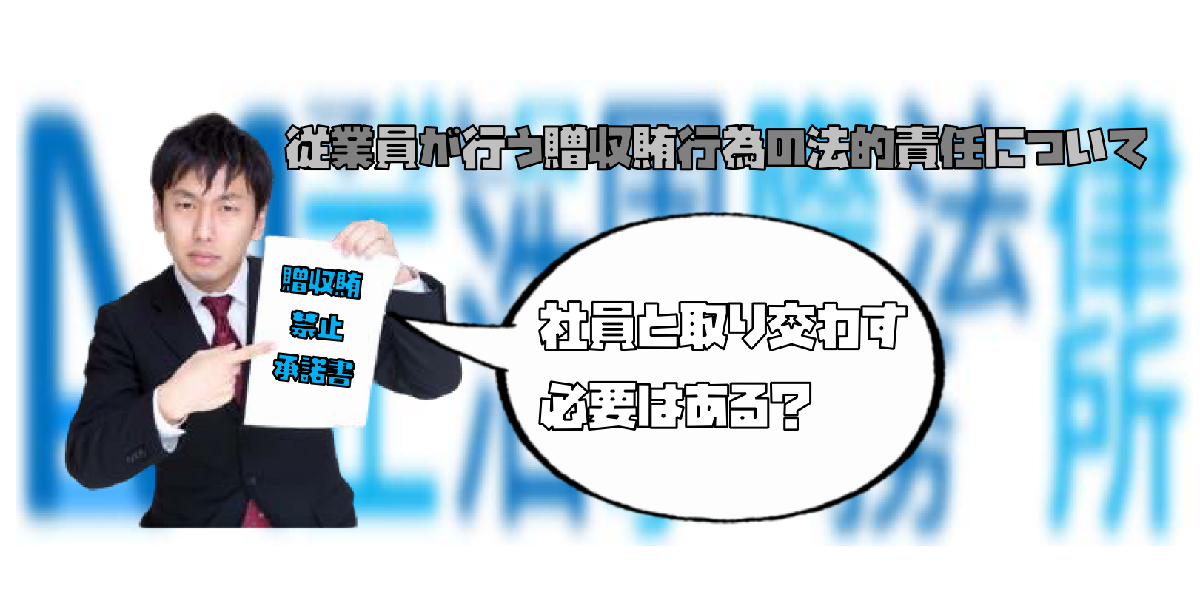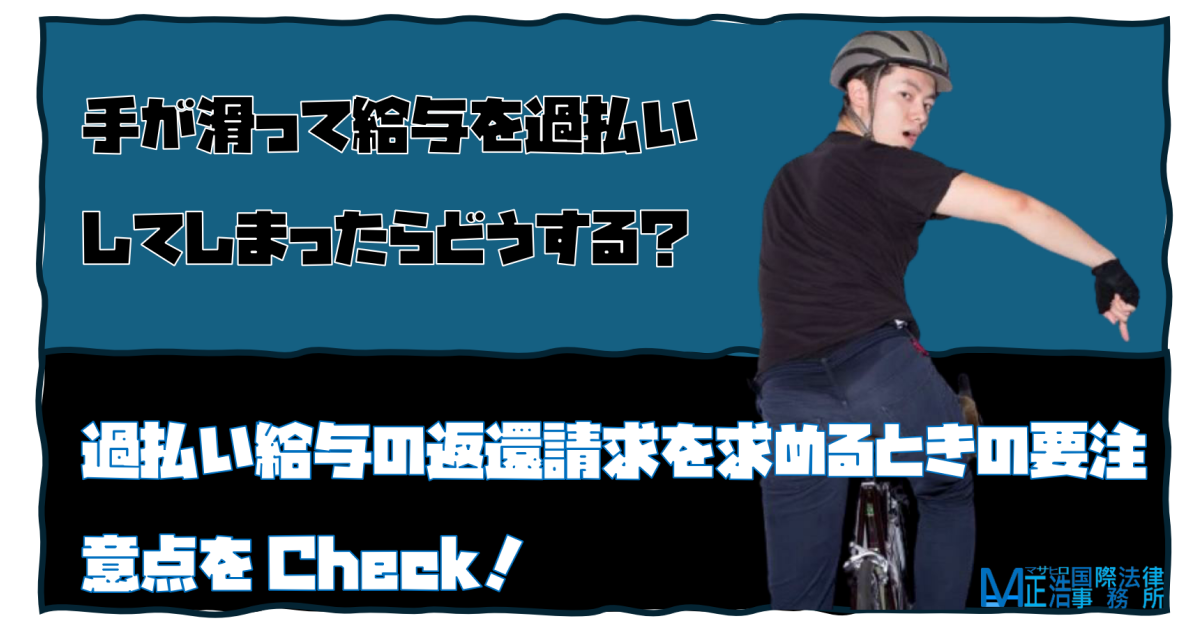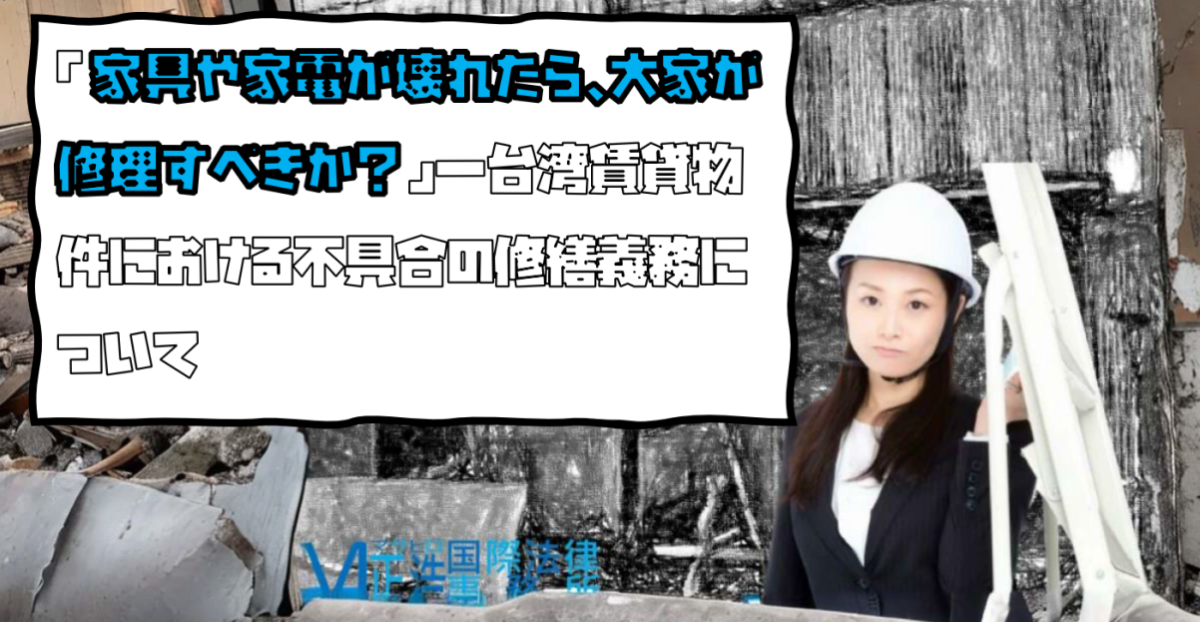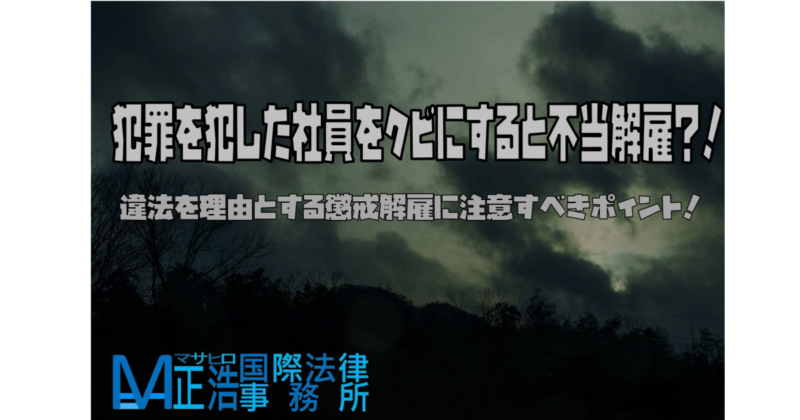「落とし物の拾得者に1割の報酬を支払わないと訴えられるのか?」―落とし主が知るべき法律知識!
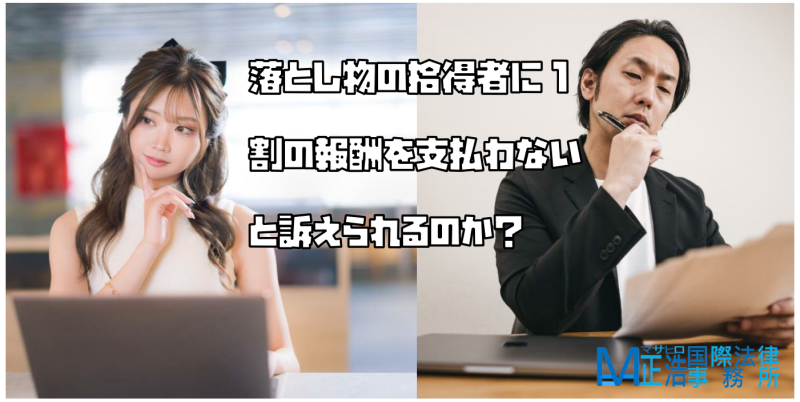
台湾では近日こんな新聞記事が出ていました。
高雄の某タクシー運転手が、昨年5月中旬に高級腕時計ブランドのオーデマ・ピゲの腕時計を拾って、警察に届けました。2日後、腕時計の落とし主が腕時計を受け取りました。その後、その腕時計の市場価値はNT$80万元に達していると調べて分かった同運転手は、報酬としてNT$8万元を落とし主に請求したが、拒否されたため、同運転手は民事訴訟を起こしました。結果、裁判所は同運転手の請求が正当であると認め、落とし主にNT$8万元の支払いを命じる判決を下しました。
新竹地裁112年度竹小字第813号判決

拾得者にお礼を言うだけじゃ足りないのか、報酬の支払いが必須なのか!?支払いが必須ならいくら払ったら妥当なの??

拾得者に報酬を支払わなければ訴えられるものなのか?
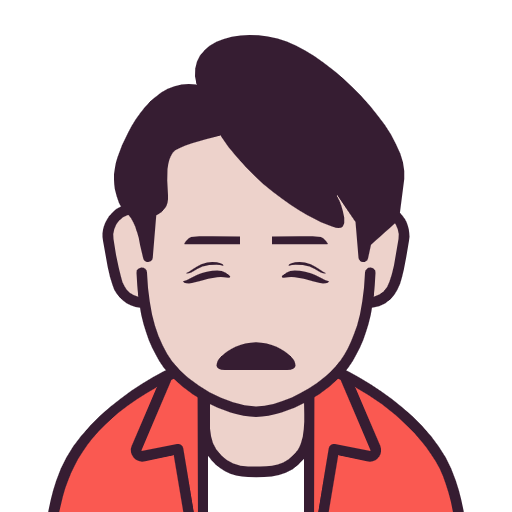
紛失した小切手を拾ってくれた人への報酬は、小切手の額面金額で計算すべきなのか?額面はめちゃくちゃ高いんだけど…
この辺のルールに関する質問は割と多いですね。心配ない、「落とし主が知るべき法律知識」に関してはどうかマサひろんのこれからの解説についてきてください!
目次
拾得者が落とし主に報労金を請求可能な法的根拠
大事な所有物を落とした人は、それを偶然に拾ってねこばばせずに警察局に届けてくれた親切な人がいれば、感謝の言葉をたくさん伝えたいと思っているほか、一部の人は謝礼として現金などを拾得者に渡したりします。「結婚式のご祝儀」を用意する気持ちで拾得者に謝礼を渡すのなら、別に強制じゃないので、少額の現金だけ渡したり、一切現金を渡さなかったりしても何も問題が生じないはずです。確かに、法律的には「拾得者に報労金を渡さなければならない」のような定めはありません。しかし、「拾得者は落とし主に報労金を請求できる」との定めは設けられています。
受領権者が落とし物を受け取る際、拾得者は報酬を請求することができる。ただし、その報酬は当該落とし物の価値の10分の1を超えてはならない。また、当該落とし物に財産的価値がない場合でも、拾得者は相当の報酬を請求することができる。
上記の法律からも分かるように、落とし主には能動的に拾得者に報労金を支払う必要はないが、拾得者から請求があった場合には、落とし主に支払いの義務が生じるという、報労金の支払いは「拾得者が一方的に行使できる権利」とされています。「一方的に行使できる」とはいえ、報労金の金額までは拾得者が勝手に決定できるわけではなく、「落とし物の価値の10分の1を超えない範囲」で落とし主と協議必要ともされています。
ちなみに、マイナンバーカードまたはマサヒロ国際法律事務所のブランドグッズなど、財産的価値のない落とし物を拾った場合であっても、拾得者は相当な報労金を請求する権利が付与されています。では、どれぐらいの金額が「相当」と言えるかというと、裁判実務では、落とし主が有する総資産、ステータス、落とし物への愛着その他要素を総合的に考慮して決定する必要があるとの見解がなされています。つまり、マサひろんのマイナンバーカードまたはテリーゴウのマイナンバーカード、どちらのカードを拾ったかによって請求可能な報労金が大きく異なる可能性があるわけです。
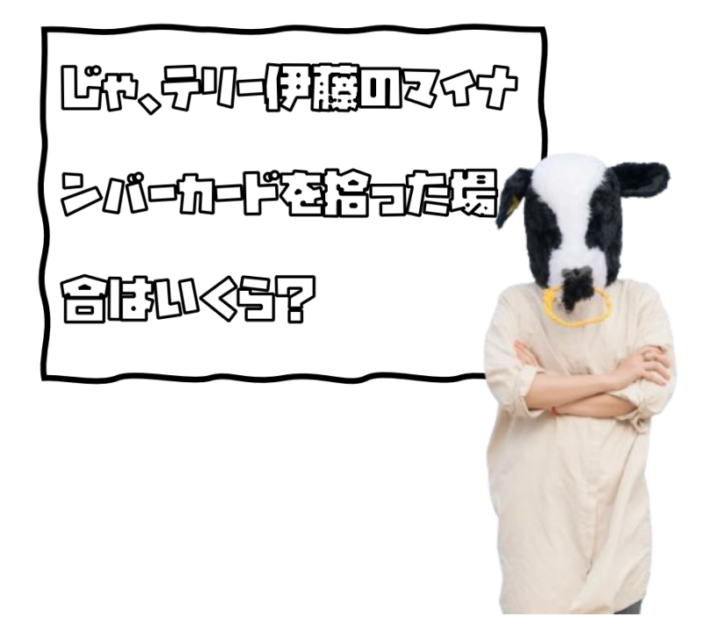
手形・小切手を拾ったときの報労金も1/10?
はい、そのとおりです。手形や小切手を拾い警察局に届けたら、拾得者はそれを無事に受け取った落とし主に対して1/10の報労金を請求可能です。しかしながら、その1/10は、手形や小切手の額面金額の1/10ではありません。
上記については、裁判所の見解はこうです。
111年度訴字第2457号判決
紛失した手形・小切手の価値は、必ずしも票面金額と同じではありません。手形・小切手を落としたとき、落とし主が公示催告の手続を行って、一定期日までに権利または請求の届け出がないとき、除権判決がありその証券の無効宣言がなされます。報労金の金額は、落とし主が除権判決を得るために必要な期間の法定遅延利息を基準として算定すべきです。
そして、公示催告の公告が裁判所のウェブサイトに掲載された日から、新聞に掲載される最終日まで、3か月以上9か月以下とされています。
したがって、本件手形の報労金について、公示催告の最長公告期間9か月を基準に、年利5%の法定利率で法定遅延利息を計算することが適切であると考えられます。
なるほどですね。手形や小切手の場合は、報労金の計算は額面を基準にするのではなく、額面金額の利息を基準にすればよいです。そうすると、
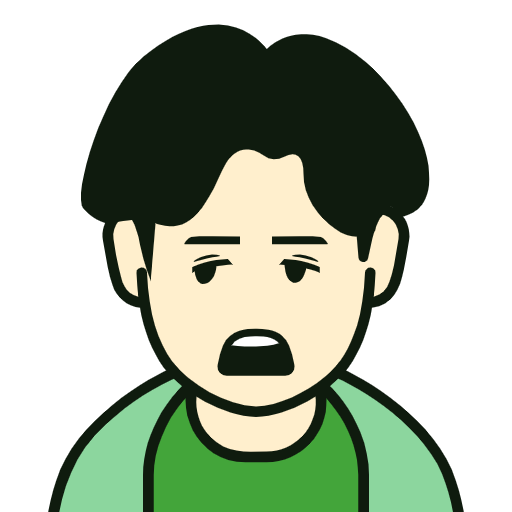
会社の預貯金を全額担保に出すつもりで、相当高い金額の手形を振り出したが紛失してしまい、運よく拾得者がそれを拾って警察局にも届けてくれたものの、結局額面1割相当の報労金を拾得者に支払わなければならないのであれば、その手形を拾う人がとうとう出ず、除権判決を待つほうがよほどお得だ!
と考えずに済むので、まさに理にかなっている司法見解ですね。

通帳と印鑑を拾ったときの報労金は?
通帳と印鑑の拾得者に支払う報労金の計算は、もし落とし主が既に金融機関に紛失届または印鑑変更届を出したりすれば、落とし物である通帳と印鑑のみでは現金を引き出すことができないため、原則として額面金額、つまり通帳が拾われた時点の残高を基準にする必要はありません。逆に言うと、落とし主が金融機関に一切報告しておらず、落とし物である通帳と印鑑のみで簡単に現金を全額引き出せるのであれば、通帳残高で報労金を計算することに妥当性を有すると認められる可能性が生じてきます(法律字第15334号解釈通達)。
また、相当なレアケースだが、もし通帳と印鑑が貴金属でてきて、かつ印鑑も有名な彫刻家の作品であり、その市場価値が残高より上回っている場合は、報労金はその市場価値で計算することを拾得者は主張できるようになる点も要注意です。
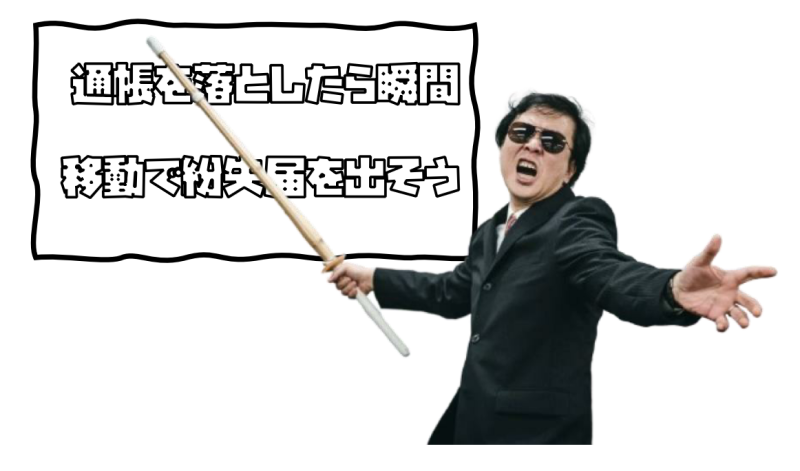
拾得者が報労金を請求できないケース
台湾の法律は、拾得者に落とし主に対して報労金を請求する権利を付与すると同時に、報労金を請求できない状況も設けています。
以下いずれかの状況に該当する場合は、拾得者は落とし主に報労金を請求できないとされます。
- 公衆が出入りできる場所や公衆の通行に供される交通設備内で、その管理人や従業員が落とし物を拾得した場合
- 拾得者が7日以内に落とし物を拾得したことを保管機関に通知・申告しなかったり、落とし物を保管機関に預けなかったり、調査を受けても拾得の事実を隠匿していたりした場合
- 受領権者が生活保護世帯、低所得世帯、中低所得世帯、法定の緊急救助や災害救助の対象者に該当したり、またはその他緊急の事情を有したりした場合
いわゆる「公衆が出入りできる場所」というのは、例えばホテルや駅その他公共施設であり、「公衆の通行に供される交通設備」には地下鉄や新幹線、航空機などが含まれています。こういった施設や交通機関に勤める管理人や従業員は、落とし物を公告・保管することはもともと業務の一環とされるため、報労金を請求できないわけです。
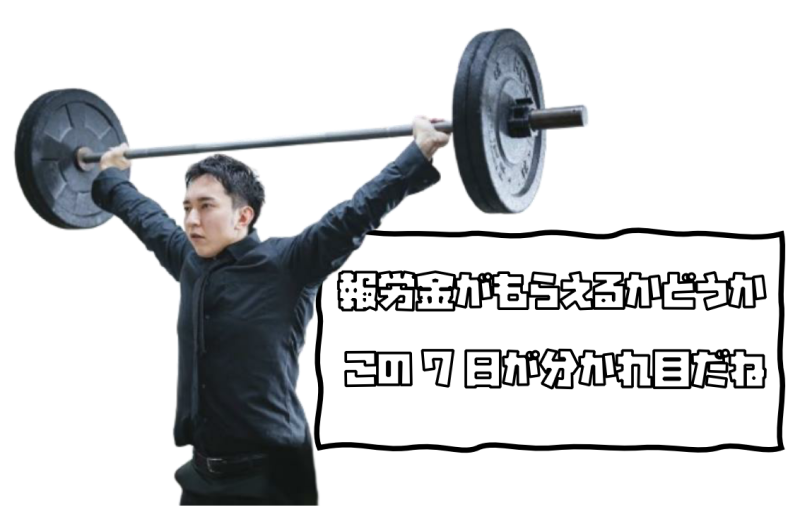
拾得者が落とし物をねこばばできるのか?

NT$1,000元の札1枚だけだから、こんな中途半端なお金で、落とし主がわざわざ警察局へ行って受領するとも考えられないし、黙ってポケットに仕舞おう~
と考えたりするのは非常に危ないのです。他人の落とし物をねこばばすると、遺失物等横領罪に該当し、当該犯罪行為は親告罪であるため、落とし主が被害届を出さなくても検察は能動的に取り調べを行うことが可能とされ、ねこばばした人は最高NT$1.5万元の罰金刑に処せられます(刑法第337条)。
また、落とし物のねこばば行為は刑事責任のほか、落とし主がそれによって損失を受けた場合、ねこばばした人は損害賠償責任も負わなければならないし(民法184条)、ねこばばした人に不当利得があった場合にもそれを落とし主に返上する必要があるという(民法179条)、報労金を請求するところか、落とし主から民事責任を追及されてしまう形となります。
なので、犯罪行為を犯して捕まる心配に囚われ続けるより、落とし物を潔く警察局に届けて報労金を請求するほうが健康な睡眠生活につながりやすいですね。

拾得者が落とし物を合法的にゲットする方法?
落とし物を黙ってわが物にすると、刑務所に送られることはないが、そこそこの罰金を支払わされ、前科もつくので、世界一割に合わない商売と言えなくもありません。でも、黙ってさえしなければ、落とし物を合法的にゲットすることもできます。
通知日または最後1回の公告日から6か月が経過しても、受領権者が受領しなかった場合、拾得者は落とし物の所有権を取得する。その場合、警察または自治体は、拾得者に落とし物の引き取りまたは売却代金の受け取りを通知しなければならず、通知できなかった場合は、公告しなければならない。
拾得者が前項の通知または公告を受けてから3か月以内に引き取らない場合、当該落とし物またはそれの売却代金は、保管地の地方自治体に帰属する。
法律の定めでは、落とし主が公告がなされた日から6ヶ月以内に落とし物をもらいにこなければ、拾得者は当該落とし物を合法的にゲットできるとされます。「鳴かぬなら鳴くまで待とう時鳥」とのことですね。
一方、10元玉や20元玉など経済的価値が非常に低い落とし物でも6ヶ月の公告期間が必要とされれば、あまりにも厳しすぎて、公告の手続きを対応する行政機関がパンクする恐れがありましょう。従って、市場価値がNT$500元以下の落とし物に対して以下のルールが設けられています。
落とし物の価値がNT$500元以下の場合、拾得者は速やかに遺失者、所有者、または受領権のある者に通知しなければならない。ただし、機関、学校、団体、またはその他の公共の場所で遺失物を拾得した者は、各場所の管理機関、団体、それらの責任者または管理者に報告し、落とし物を預けることもできる。
前項の落とし物について、受領権のある者が以下の期間を経過しても受領しなかった場合は、拾得者がその所有権を取得するか、その売却代金を受け取ることができる。
- 通知または公告した日から15日以内
- 通知または公告ができなかった場合は、拾得日から1か月以内
つまり、NT$500元以下の落とし物は警察局などの行政機関に届ける必要はなく、拾った場所の管理人に預けたり、自らソーシャルメディアなどで落とし物を公告したりして、15日以内に落とし主が現れなかったら、落とし物の所有権は拾った人に移る仕組みとなっています。
ちなみに、落とし物が中古の携帯電話の場合、決まった法定期間を過ぎても落とし主が出てこなかったときに拾得者の所有物となるルールは引き続き適用されるが、携帯電話に入っている個人情報はさすがに落とし物の所有権と一緒に拾得者に移るわけがないので、警察局は当該携帯電話をリセットしてから拾得者に引き渡します(法律字第11103501680号解釈通達)。
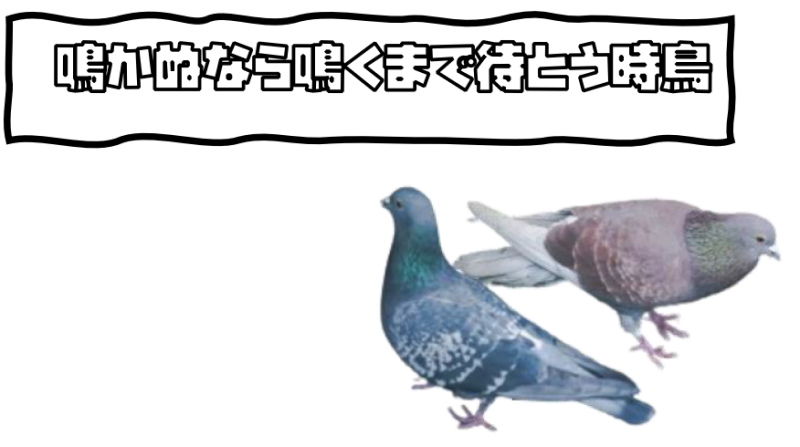
落とし主が報労金を支払わなかったら?
拾得者は法律に基づき、落とし主に対して落とし物の価値の1/10に相当する報労金を請求できます。もし落とし主が報労金の支払いを拒んだら、拾得者は落とし物の引き渡しを拒否できるという、いわゆる留置権を行使することができるとされます(民法第805条)。
留置権を正しく行使する方法はこうです。
- 拾得者が落とし主に報労金の支払いを求めたが拒否されました。
- 本日から1カ月以内に報労金を支払ってくれないと、落とし物を報労金としてそのまま受け取るか、落とし物を売却して代金から報労金を受け取るよと、拾得者が落とし主に通知。
- 1か月が経過しても報労金の支払いがなかったので、拾得者が報労金をもらう代わりに落とし物をゲット。
落とし物をただ文面通りに「留置」するだけでは、決着がついたとは言えません。「期限を定めて催告する」という手続きが抜けると、落とし物の所有権は拾得者に移らないため、「報労金不払い事件」に幕を下ろすには、催促という手続きが必要不可欠との点は要留意です。
一方、落とし主が報労金を支払わないのではなく、いくら払ったらよいかについて合意に達することができず、もしくは落とし物は既に警察から落とし主に引き渡され、拾得者が物理的に留置権を行使できなかった場合は、冒頭に共有した事例のように、拾得者が民事訴訟を起こして、裁判官に報労金の額を定めてもらって、強制的に落とし主に支払ってもらう、という比較的ややこしい局面に展開する可能性が生じてきます。
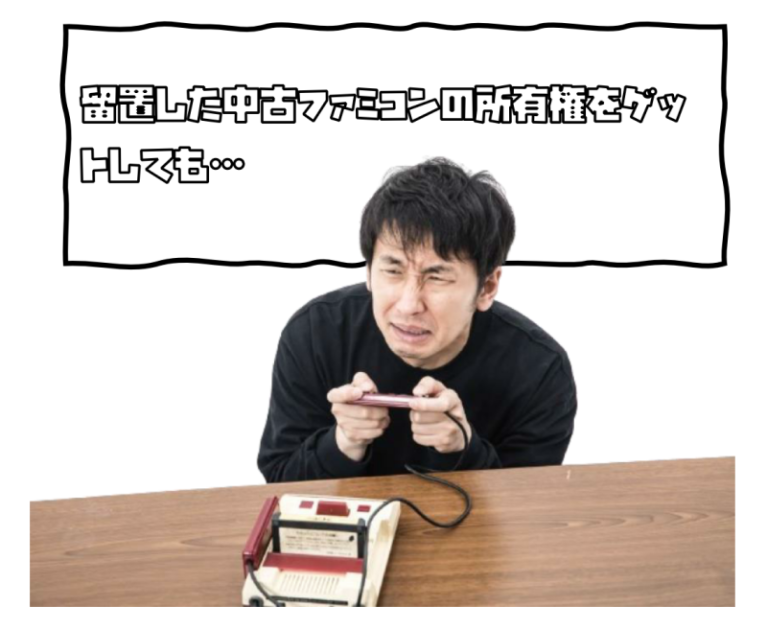
今週の学び
大事なものを無くして、いくら探しても見つかっておらず、諦めようと思う矢先に、警察から落とし物の連絡通知を受け、急いで拾得者に電話してお礼を言うや否や、「感謝するならお金をくれ」と言われると、気持ちが一瞬冷めてしまいましょう。落とし物を買いなおすより、1割程度の報労金を支払うほうがお得だから、それぐらいっていいや、というように、落とし主が報労金の請求についてポジティブに受け止めることができれば、裁判所の世話にならずに済むが、要は私物を大事に仕舞って、無くさないよう細心の注意を払うことです。