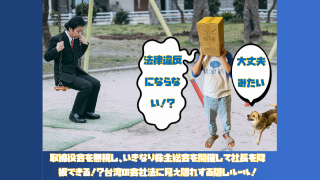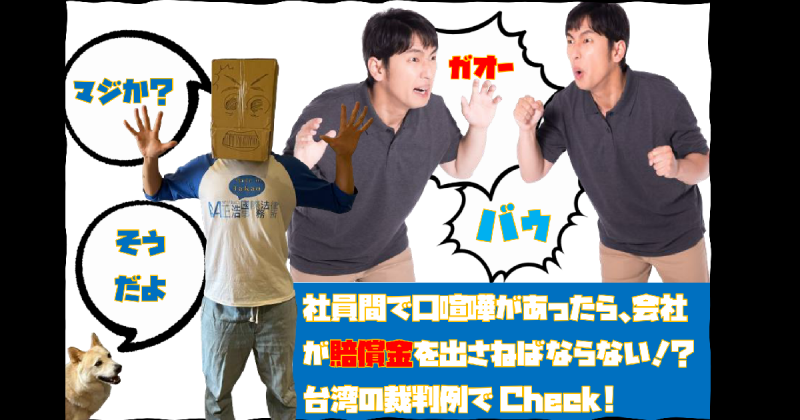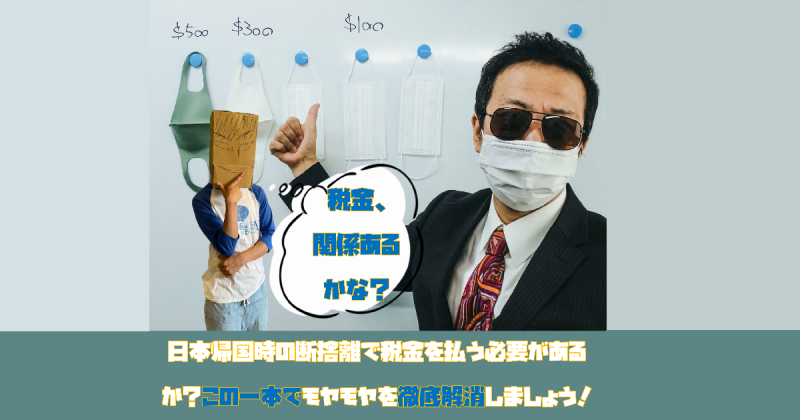取締役会を無視し、いきなり株主総会を開催して社長を降板するってのは法律違反にならない!?台湾の会社法に見え隠れする隠しルール!
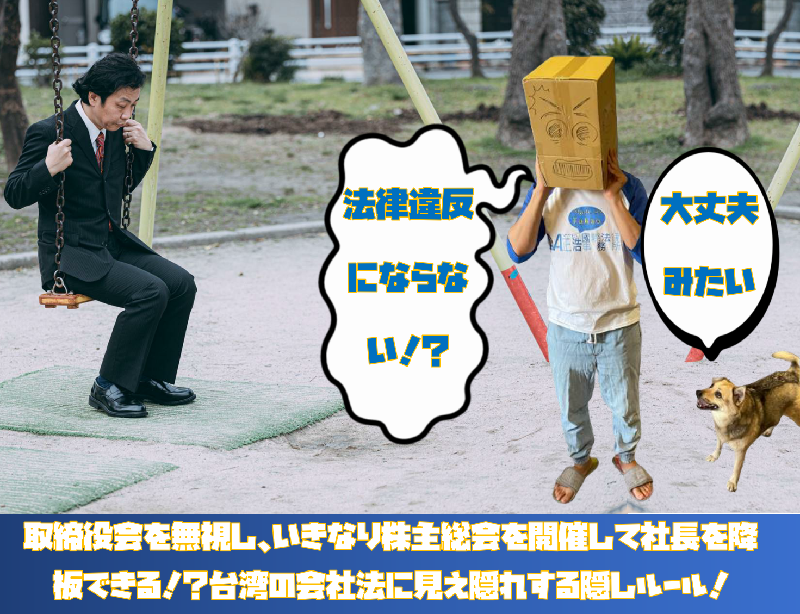
台湾に進出する日本企業は、日本の親会社が100%出資して現地法人を作ったり、日本の本店と同じ法人格を共有する支店を作ったり、台湾のビジネスに精通する台湾企業又は個人を少数株主に据えて会社を設立したりする進出形態がとられています。こういったケースでは、指名か選任を問わず、代表取締役をはじめとする役員メンバーの大半は、100%又は2/3以上の株式を保有する日本の親会社が決定できます。
一方、上記とは別に、その他台湾企業と折半又は51:49の出資比率で、若しくは台湾企業2社とそれぞれ1/3の出資割合で合弁会社を作る形で、台湾へ進出する日本企業も少なくありません。ただし、この辺の進出形態は、日本の親会社が100%又は2/3以上出資するケースとの大きな違いは、意志決定が難しい場合があるほか、「企業内部の経営権争い」が比較的発生しやすい体質を有する点です。
会社経営の実権を握るストレートなやり方として、できるだけ敵対取締役を排除し、賛同者を取締役会に送り込む手法が活用されています。台湾の上場企業はそれを成し遂げようと、通常のパターンでは到底考えられそうもないアクロバティックな方法を駆使してきました。例えば、会社定款を急遽変更し、取締役の選定方法を変えることで取締役の議席を独占したり、入場受付から会場までのルートをわざと遠回りにし、非協力的な株主を足止めすることで、役員改選を電撃的に終えたり、非協力的な株主が事前に指名した候補者を外す形で取締役の選任を行ったりするなど、法律的には完全にアウト的なやり方も平気で実施されていたほど、会社の支配権をめぐる紛争は想像を絶するほどの形で繰り広げられています。
台湾に進出する非上場な日系企業は、前述した台湾の上場企業と比べたら、株主の人数がずっと少なく、経営権争いが起きる確率が非常に低いですが、資本提携などで台湾現法の株式を一部台湾企業に譲渡したり、従業員持株会制度を実施したりすることで株主構成が分散化することとなったら、そのようなリスクも生じてくるかもしれません。
今週のマサレポは、平成26年の株式会社大塚家具における親子間の経営権争いを想起させる裁判例を紹介させていただき、「なるほど、会社の運営上、こんなことも起こりうるね!」的な知識共有ができれば幸いでございます。以下ご覧ください。
悲しいお父さん、やむなしの決断
C氏は個人資本を投じて、1977年に台中で一株当たり1万NTD、資本金2,600万NTDの株式会社、J社を設立し、自ら代表取締役社長を務める形で事業展開を始めました。その後、年齢を重ねていくC氏は、事業承継を考え、手持ちの株式を順次子供とその配偶者に譲渡しながら、取締役や監査役を就任させました。
C氏の手持ち株が6株になった2020年に、長男夫婦、長女夫婦、次女夫婦、三女夫婦主導のもと、J社内で臨時株主総会が開催されました。同会では、定款の変更決議がなされ、取締役の人数を6名から5名、監査役の人数を2名から1名にそれぞれ減少されたのみならず、C氏も代表取締役社長の座から引きずり降ろされ、取締役の当選すらままなりませんでした。

一人で77年に創業した会社であるにもかかわらず、よもや23年後の今になって、子どもたちが寄ってたかってワシを会社代表から追放したとは...
怒りとショックが収まらないC氏は、J社を相手取り、以下の理由をもって、J社が開催した臨時株主総会での決定事項を取り消すよう裁判所に訴えました。
●係争株主総会は、当時監査役を担当した三女が召集したものでした。台湾の会社法によると、株主総会は取締役会が招集するのが一般的で(会社法第171条)、取締役会が株主総会を招集せず、若しくは召集することができない場合においてのみ、例外的な召集方法が可能となります。今回のケースは別にこういった事情があったわけではないから、監査役が勝手に臨時株主総会を招集するのは理にかないません。
●会社の代表取締役が取締役会の開催を拒むのであれば、過半数の取締役は書面による通知をもって、代表取締役に開催請求を行うことができるとされています。それでも代表取締役が相手にしてくれなかったら、過半数の取締役は自ら取締役会を開催し(会社法第203-1条)、そこで臨時株主総会の招集を決議して、同臨時株主総会をもって代表取締役を解任する、という正しい手順さえ踏めばよかったのに、適正な法的プロセスを経ずに開催した臨時株主総会には正当性が欠けます。
●係争株主総会の招集通知では、「1.定款変更の議案 2.役員改選の議案」とだけ書いてあって、具体的にどういった内容の議案であるかに関する言及がなかったため、法律に違反しました(会社法第172条)。また、代表取締役社長のC氏は会議中、臨時株主総会の召集手続が違法であると、異議を申し立てたが、その他役員メンバーはそれを無視し強引に議案を通過させました。従って、会社法第189条に基づき、前述決議の取り消し請求を求めます。
C 氏の主張
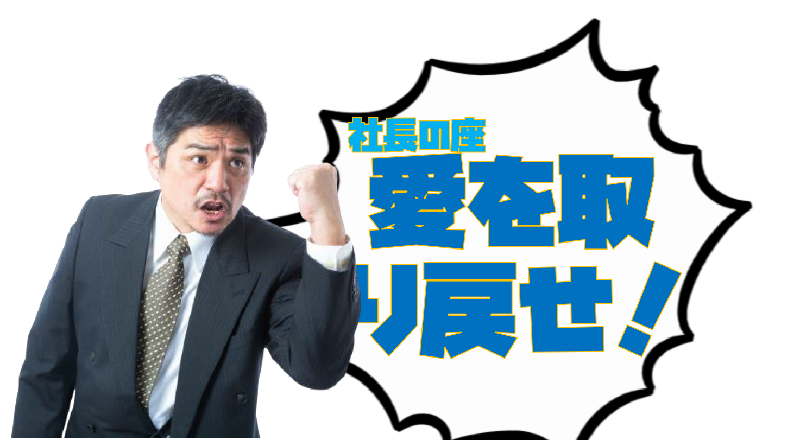
J社、会社を守るための苦渋の選択
生みの親であるC氏からの話しを受け、以下のように答弁しました。
●係争株主総会に出席したC氏は、ただ単に子供の親不孝を嘆きながら、自分はもう代表取締役社長ではないから、新しい社長がJ社をどんどん成長させていってほしい、との発言を最後に退席しました。C氏からは、会議中で召集手続に問題があったり、議案の決議方法が間違ったりする旨の話しが一切出ておらず、決議の取り消し請求を行う前提条件としての異議申し立てがなされなかったため、当該請求を行使する権利がありません。(民法第56条第1項但し書き)
●2001年に施行した改正会社法によっては、会社のためになるとの前提で、監査役は必要に応じて株主総会を招集できるとされています。(会社法第220条)係争株主総会は、監査役が「勝手に」召集したものではなく、「必要性を認めた」前提が存在するからこそ召集した次第でした。そのため、係争株主総会の招集手続は法律的に問題がありません。
●2008年に配偶者が他界したC氏は、資産運用の相談でコンサルタントのT氏と知り合い、2018年に結婚しました。C氏は2020年に、自ら保有するJ社株366株のうちの360株をT氏に贈与しようと、会社実印がJ社に適切に保管されているのを知りつつも、その他取締役に何ら断りなく、別途会社実印を作成、贈与手続に使用しました。それから数か月後、C氏はようやくJ社に当該事実を告白しました。C氏は当時J社の代表取締役社長であり、同氏が行った行為はJ社が全責任を負わなければならないことを考えたら、C氏のこれからの行いは、J社にとって何かしらの不利益をもたらす可能性が低くないと判断。
●C氏の保有株は6株しかなく、持株比率が1.6%に過ぎません。かつ同氏はJ社の経営に関与しようとする素振りを見せないため、それ以上J社を任せられないとその他株主が認識していました。なお、C氏はJ社の株式をほとんど現配偶者のT氏に贈与したのに、何故6株のみ保有し続けるのかと言えば、代表取締役社長の座を手放すことなく、毎月J社から引き続き高額な役員給与を受領できるからです。しかもC氏は、自ら作成した会社の印鑑をいまだにJ社に渡していません。以上の点により、C氏はJ社の社長としてふさわしくないことは明らかです。
●T氏は、C氏からJ社の株式を取得した後、J社に対して帳簿の閲覧請求を一度も行っていないのに、J社から帳簿資料の提出を拒否されたとして、裁判所に検査役の選任を申し立てており、J社の運営に支障を来していました。監査役はJ社の適正運営を図ろうと、係争株主総会を招集したわけなので、妥当性を有するものかと考えます。
●C氏は長年J社の代表取締役社長に務めており、社内事情や役員構成を熟知しているはずです。係争株主総会の招集通知では、定款変更と役員改選とだけ記載されていましたが、C氏は立場的、経験則的にもその内容を十分理解できると思われます。従って、同招集通知の発送は、C氏が主張したように、会社法第172条に違反したことにはなりません。
J社の主張
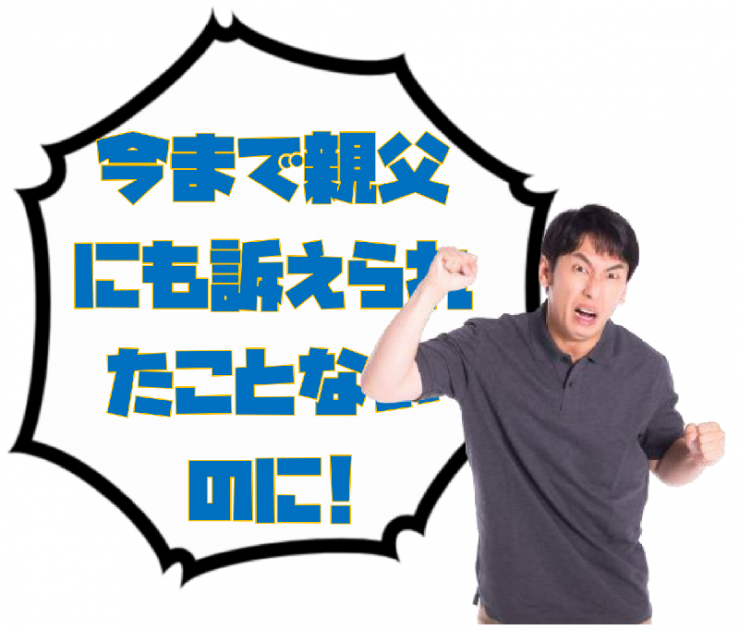
裁判官の見解
第一審の審理を担当する裁判官は以下の判断を下し、C氏に敗訴を言い渡しました。
第一審の見解
- 立会人として係争株主総会に参加した公認会計士が行った証言によると、C氏は会議時に、ただ会計士に子供の親不孝について文句をこぼし、子供はもう社長をやらせてもらえない、と嘆いたのみで、会議の招集プロセスに問題があるなどの発言は一切しておらず、そして会議がまだ終わらないうちに、テーブルをドンと叩いて会議室を後にしたという。C氏のこういった行為は、会議の参加者に不満を表すにとどまり、議長に対しての異議申し立てにはならない。従って、C氏には係争株主総会が行った決議を取り消す請求権を有さないと判断する。(台中地裁110年度訴字第239号判決)
前述した第一審の判決結果を見て、やはり腹の虫がおさまらないC氏は、控訴に踏み切りました。
控訴審を審理する裁判官は、以下のように自らの見解を述べました。
第二審の見解
- 台湾会社法の定めによっては、会社に損害が発生する兆候が認められたら、当該損害の拡大を回避しようと、取締役会が株主総会を招集するかを問わず、監査役は自らの判断で株主総会を招集できるとされている。(会社法第220条)C氏はJ社に何ら断りなく勝手に会社の実印を作り使用したことを、J社に大きな不利益をもたらしかねないと判断した監査役は、会社法に基づき、自らの権限で株主総会を招集した、との行為に違法性が認められない。
- 定款変更や役員改選などの議案は予め召集通知に開示必要、という会社法上の定めに関して(会社法第172条)、当該通知に議案のタイトルさえ明記すれば十分であり、例えば「○○の理由によって、定款の○○条を変更する」のように、詳細まで書く必要はない。従って、C氏が主張した、招集通知に記載すべき内容が不十分のため、決議は取り消せる、との論点は成立しない。
- 株主総会に出席した者は、会議時に一切異議申し立てを行っていないにもかかわらず、事後になって、同会の決議方法が違法のため、決議した事項を取り消す、という権利を安易に認めてしまうと、株主が自己都合で任意に株主総会の決議を覆せることとなり、企業ガバナンスがうまく機能できなくなる恐れがあります。そのため、株主総会の招集プロセス又は決議方法に瑕疵があって、裁判所に対して決議の取り消し請求を行おうとする者は、民法第56条第1項の定めに従い、会議時に異議申し立てを行わなければならない。会議の立ち合いを行った公認会計士の証言では、C氏は現場においては自分の不満をこぼしたが、議長への異議申し立ては一切行っていなかった。従って、C氏の取り消し請求を認めるわけにはいかない。(台湾高裁台中支部民事判決111年度上字第275号)
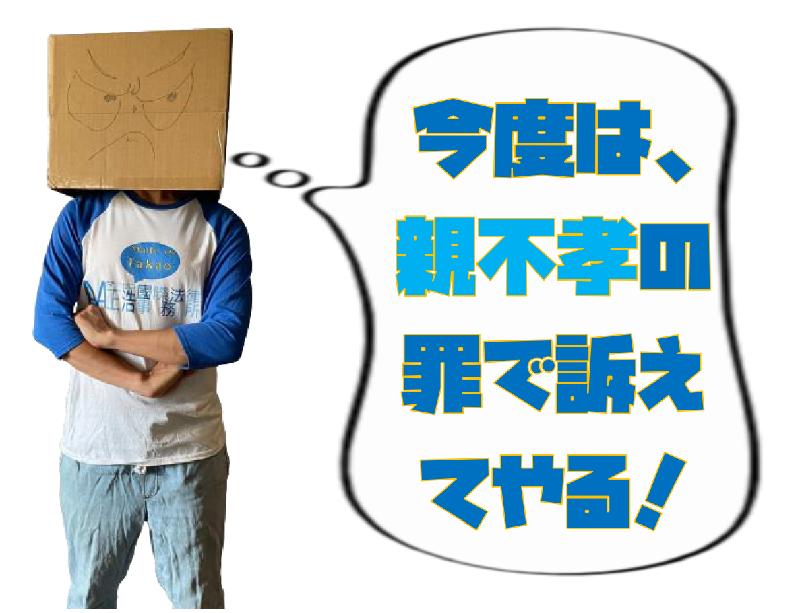
今週の学び
以上は、台湾のファミリー企業における経営権争いの事例です。台湾に進出した日系企業は同族経営が関係していないので、類似トラブルが発生する確率が低いかもしれません。ですから、今回共有させていただきましたケースは、同族関係ではなく、台湾の会社法で役員や株主にはどれだけの権限が許されるかをフォーカスしていただきたいと思います。
例えば、従業員持株会制度を設けたり、若しくは台湾の法人株主や個人株主を複数抱えたりする日系企業で、最初のうちは、互いすごく関係が良くて、会社を成長させるために、自分の身を削っても一生懸命貢献する的な絆があって、取締役会と株主総会の決議も毎回すんなりと通っていましたが、その後、個人株主に相続が発生したり、法人株主にやむなしの事情があって持ち株を他社に売却せざるをえなかったりするなど、会社の株主構成がだんだん複雑になってしまい、以前築かれた絆が希薄になりつつあって、最終的には経営権争いが起きた、との可能性もないとも言い切れません。
各種可能性に備えて、以下まとめさせていただきました台湾の会社法に関する要留意点をご参考いただけたら幸甚です。
マサレポ、今週の学び
- 株主総会は、取締役会だけでなく、監査役も必要に応じて召集可能です。
- 会議の招集又は決議に疑問を感じ、その場で異議を唱えなかったら、その後救済手段が取れなくなる可能性があります。
- 役員改選や定款変更(その他にも増資、減資、解散等)等の議案は、予め株主総会の招集通知に記載しなければ、会議時に緊急動議として提出することができません。
- 召集通知に記載する議案の内容は、原則としてタイトルのみで十分、内容の詳細まで記載することが求められません。