【マサヒロ起業支援コラム】台湾の税金制度-法人税について

マサヒロです!今日も脱サラしようかについて悩んでいますか。今まで培ってきた力を信じて、勇敢果断に起業の道へ突き進みましょう!
プロローグ
さて、起業に関する諸々要検討事項のうち、税金にまつわる話はよく取り上げられています。

会社を作りたいけど、株式会社と有限会社のどちらの税金が安いですか?
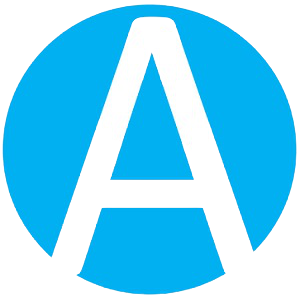
資本金を例えば何台湾ドル以上設定したら、税率が一気に上がる仕組みがあるか?

いくつかの事業をやりたくて、まず何を始めたら税金面で一番有利ってのはありますか?
という風に、税金に関しましたら、とにかく不明点だらけです。
確かに、税負担の軽減を念頭に、起業前の段階において丁寧かつ慎重に、いろんな条件に対して細かく設定したりしないと、後々になって、ようやく稼いだ利益がほとんど税金に取られてしまうなど、足元がすくわれることに後悔しまくっているところで、税金が戻ってこないのです。だから最初からしっかりと税金制度についての基礎知識を勉強し、過度な税負担からせっかく作った台湾の会社を守りましょう!
営利事業所得税って何?
会社イコール法人、法人と言えば「法人税」です。
法人税について、台湾では「営利事業所得税」とのネーミングとなりまして、営利事業って何となく一種の活動を意味する感じがしないもありませんが、台湾においては会社を意味しています。ここで日本の呼び名に準じて「法人税」で言い表しましょう。
日本と比べたら、台湾の法人税は非常に単純明快であり、法人事業税と法人住民税のような設定がないほか、会社の規模によって通常税率と軽減税率を個別に適用し税金を計算したりする面倒もなく、原則として課税所得に20%を乗じたら納税額が分かってきます。(年間課税所得が12万台湾ドル以下納税不要との嬉しい例外も設けられています)
二重課税の心配ないか?
課税所得に含ませなくてはならないのは、台湾国内の源泉所得のほか、海外での投資子会社から送金を受けた配当金等の海外所得も対象になります。
台湾の法人税は、いわゆる「属人主義」との性格を有すると言えます。(本店が海外にあった会社に対しは属地主義課税)香港やシンガポール等海外所得非課税の国と比べたら、台湾の法人税が重たく感じてきますが、一定の限度額を超過しなければ、海外で課税される分も台湾で控除が受けられるとの救済措置も設けられています。
ご留意いただきたいのは、当該控除を受けるためには、海外で課税された事実を証明可能なエビデンスを用意し、かつ台湾が対象国にあった出先機関(日本では台北駐日経済文化代表処)から書類認証を受けてから、台湾の税務当局に提出必要というひと手間をかけなくてはならず、自主的に〇〇元の税額を控除したいので、承認してくれ!とだけ申告書に書いてもすぐ認められるわけではございません。そして、2017年から発効することになった日台租税協定が、海外税額控除の適用に拍車をかける形となりました。
いきなり租税協定かよ!
「租税協定」または「租税条約」という税金に関する取り決めは、基本として「二重課税」、つまり同じ所得が日本においても台湾においても課税される問題を解消するために、両国の話し合いによって決まった税金の取り扱いに関する共通認識です。では、なぜ同じ二重課税防止の仲間である海外税額控除制度のハードルがそれによって高くなったのでしょうか。
例えば、日本では租税協定に関する所定の手続きを済ませたら、台湾への送金時に天引きされる源泉所得税が下がるにもかかわらず、それをあえてせず、一番重たい源泉税を日本政府に払ってから、払った分を全額台湾の支払い法人税から控除を受けようとする場合は、それが意図的に台湾の税収を減らす行為に該当すると認められるので、全額ではなく、軽減税率の恩恵を受けての源泉所得税のみ、台湾法人税の控除を受けさせてあげますよ~という風に、租税協定のことを棚に上げ、ただ単に海外税額控除一本のみで節税しようとするものなら、こういった政府からの、罰則に似た措置を触発してしまいます。それが、海外税額控除を完全無欠に攻略する敷居が高くなったゆえです。
海外税額控除を使おうとする前に、まず台湾とは租税協定を締結している国なのかを調査し、締結国だとわかったら対象国内ではまず所定の減税措置を行い、関連エビデンスを収集し書類認証を受け、そして台湾での法人税申告時に、ようやく最大限の控除が受けられるようになります。相当ややこしく、理解しづらいので、実施する前にやはり専門家の人と今一度相談されたほうが良いと思います。
話しが租税協定の方に逸れてしまいましたが、控除が受けられるかどうかは非常に大事な話なので、1台湾ドルでも無駄な税金を払いたくない立場に徹して、とりあえず上記のように基礎知識を共有した次第です。
エピローグ
台湾の法人税は以上述べた特徴を有するほか、日本と類似する中間納付制度及び欠損金の繰越控除制度もあります。日本起業経験者の方にとって、おなじみであり一発で理解できるように考えがちですが、台湾独特な考え方がこちらの制度にちりばめられていますので、丁寧に接していくことが望ましく、きちんと紹介したいものですが、本稿のボリュームを考慮し、別稿で取り扱わせていただけたらと思います。では、また別の記事でお会いしましょう!
Attention!
※こちらの文章は2021年6月24日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。



