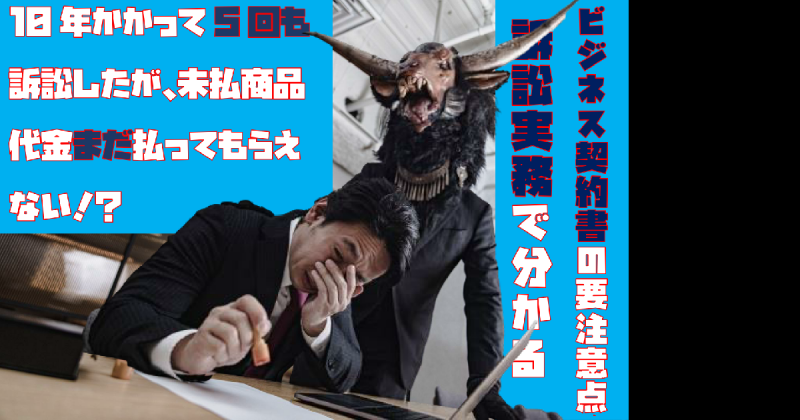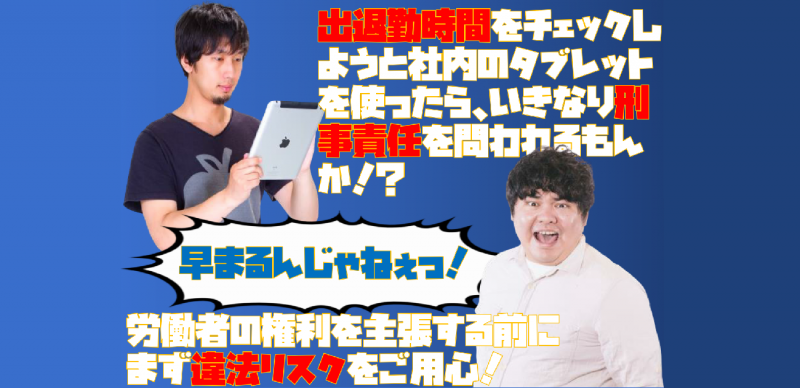忘年会という重役が揃った場面に、従業員からのちゃぶ台返しを食らった、というありえない屈辱を味わわされてしまったのに、それでも解雇できない!?

「退職合意書があった、試用期間中で実施、それでも不当解雇なのか!?台湾の最高裁が2022年に出した気になる判決とは!」や「脅威、不当解雇の逆襲!」等、今までのマサレポにおいては、不当解雇を何回か登場してもらっており、不本意ではあるが、常連客として定着しつつある節があります。
免疫ができるのと一緒で、不当解雇の事件が起きれば起きるほど、労務コンプライアンス意識が徐々に強化される一方、のはずだかと思いきや、この間リリースされた裁判例をさりげなく目通すと、不当解雇についての争いは相変わらず後を絶たないようです。まるで新型コロナウイルスのように、不当解雇ウイルスはいろんな変異株をあちこちに出し続け、決してなくなりません。
今週のマサレポは、第一審から10年が経過し、今年の8月にようやく落ち着いたという、台湾高雄で起きた不当解雇に関する裁判例を取り上げ、元社員側の訴訟権を制限することで、終焉が見えない裁判に終止符が打たれた、とのレアケースを考察していきましょう。
それぞれが見えた現実
空港での旅客ハンドリングやランプハンドリングを手掛けるT社は、団体交渉協約に基づき、来年の昇給幅と賞与額について、2011年末に社内労働組合の代表、Z氏、C氏、W氏をはじめとする面々と協議を行ったが、結論が出る前に、Z氏が社員代表の取締役として、社長は忘年会で5%の昇給率を公開するよ、と言いふらした。結局、社長が忘年会でのスピーチに昇給率に関する話し一切出なかったため、会場中のテーブルが従業員によってひっくり返され、現場は一時大騒ぎ。
数日後、3氏は残業拒否闘争を開始し、その他従業員に対して、8時間の通常勤務を終えたらすかさず帰宅せよと要求。そして、Z氏はその他従業員1名と車を使って無断で制限エリアに乗り込み、航空の安全を脅かす行為があったとT社が認定。また、C氏はW氏に、普段通りに残業するその他従業員に心理的揺さぶりをかけ、残業拒否闘争への参加を呼びかけろと命じ、W氏はその通りに行いました。
同3氏は就業規則の定めを無視し、重大なルール違反を犯したと考えるT社は、労基法第12条に基づき懲戒解雇を実施しました。
同3氏はT社が下した懲戒解雇処分に不服し、不当労働行為裁決委員会に対して裁決の申請を行いました。それを受け、同委員会は、T社が行った懲戒解雇処分は労働組合法第35条に違反したため、解雇は無効とみなし、同3氏が解雇された後の給与をT社が追加で支払わなければならない、との認定結果を出しました。
前述、行政からの認定結果に納得がいかなかったT社は、同3氏への懲戒解雇は有効であることを裁判所に訴えることにしました。
それに対して、3氏から依頼を受けた弁護士は、3氏の気持ちを以下にまとめました。
2011年末に、労働組合の代表者とT社の間に4回ほどの協議がなされ、来年の昇給率が5%だとの協議結果なので、T社が公開の場でこの情報を公開してくれるとの期待が持たれていました。
同年11月に開催された組合会議で、翌年早々に残業拒否闘争を決行するとの決議が出たものの、同年同月12月の組合会議で残業拒否闘争を一旦取りやめるとの結論がなされました。そして、翌年1月5日の忘年会に、社長は5%の件を一切口に出さなかったため、3氏その他労働組合の幹部一同はその場で、残業拒否闘争の再開を話し合いで決議しました。これらの決議は、T社との団体交渉協約によって従業員に付与された権利なので、違法にはなりません。
残業拒否闘争に参加した従業員は合計130名超であり、個別従業員が自発的に行った活動ではありません。なおかつ、残業拒否闘争の話しが出た11月の決議結果は既にT社に共有されており、たとえそれを何時本格的に実施するかを予めT社に報告していなかったとはいえ、残業拒否闘争自体はルール違反にはならないと考えられます。
労働組合の幹部は、それぞれの業務分担によって、組合参加者への周知連絡とフォローアップを行いました。確かにT社の管理運営活動はそれによって何等かの影響を受けたが、前述した労働組合の活動内容は、法律に与えられた権利だと認識。
Z氏は制限エリアに入っていた間に、車で故意に施設にぶつかったり、召集に駆けつけた組合の会員に違法行為を働かせたりしていなかったので、航空の安全を脅かすには至りません。また、C氏とW氏にも決してその他従業員をそそのかしたり、恐喝したりするような行為を行っておらず、残業拒否闘争に参加した従業員も全員通常勤務の8時間をしっかりこなしていました。ですから、3氏への処分は不当解雇に該当し、解雇が無効であることを主張。

証拠集めは日常から
地裁の見解
- W氏はC氏の指示を受け、通常出勤していたその他従業員にカメラを向けて、恐喝する形で残業拒否闘争の参加を強要した、というT社の主張については、現場の写真や動画等の証拠品をT社は提出しておらず、いわゆるW氏から恐喝を受けた対象従業員はそれによって心理的恐怖を覚えたかどうか定めでない、かつ現場に駆け付けたT社の幹部が止めに入ったら、W氏はすぐ問題視される行為を取りやめ、それ以降類似事件を起こしていなかった。W氏がT社に対しての服従心が垣間見える。
- C氏がその他従業員に行った呼びかけの趣旨は、出勤拒否ではなく、残業拒否闘争の参加である。その他従業員がC氏から恐喝を受けた証拠をT社も提出していなかったため、C氏に法律違反に該当する行為があったとは認められない。
- 証人の話しによると、車で空港の制限エリアに入ったZ氏は、その後やってきた従業員の勧告を受けてすぐ現場を離れ、勤務中の従業員とは口論又は喧嘩をしたわけでもなく、状況確認しに来た空港警察から取り調べを受けさせられることもなかった。また、Z氏を乗せた車は、制限エリアでの走行ルートはマニュアルとは少々異なるが、それほどめちゃくちゃなものではなく、かつその場で器物を損傷したり、人に負傷させたりすることもなかった。従って、Z氏はわざと騒ぎを起こし秩序を乱すような行為を働き、飛行の安全を脅かそうとすることがあったとは認めがたい。
- T社と社内労働組合で取り交わした団体交渉協約において、勤務時間の調整や残業の実施は、個別の従業員から同意を取得しなければならないと定められている。従って、T社からの勤務時間調整と残業の命令を受けず、8時間の通常出勤を行ったC氏には、T社が主張した無駄欠勤の行為があったとは考えられない。
- T社から5%の昇給率をないものにされたことで、3氏をはじめ従業員全員の不満が噴出し、忘年会で大騒ぎを起こしたうえ、その晩臨時会議を開き残業拒否の続行を決定した、との件については、台湾の社会通念上それほどおかしなことではなく、書面による記録はないものの、口頭のみの臨時会議をもって、この前許可された残業拒否活動の決行を本格的に決める、とのやり方も労働組合法第24条、第26条の定めに違反するわけではない。
- 忘年会1ヶ月半前の組合会議では、残業拒否の仮決議は既になされており、当時の議事録もT社に提出されたから、T社は予め残業拒否によって発生する人手不足問題をどう対処するか検討できる時間を有するはず。なお、実際残業拒否闘争に参加していた従業員はほかにも大勢いるのに、3氏にだけ懲戒解雇処分が下された。労働組合の重要幹部を見せしめにする思惑は見え見え。
- T社は、今回の残業拒否騒ぎで、外注先に支払ったスタッフの追加派遣料を含めた損失額に1,000万NTDを超えたと主張したが、スタッフの追加派遣期間は残業拒否闘争の実施期間とは食い違いがあるほか、人身事故や器物の損傷が発生したわけでもなく、顧客である航空会社からクレームを出されたこともなかったので、3氏の解雇は最後的手段の原則に反しており、労働組合法第35条に基づき不当解雇と認定。(高雄地裁101年度労訴字第107号判決)

忘年会という重役が揃った場面に、従業員からちゃぶ台返しを食らった、というありえない屈辱を味わわされてしまったのに、それでも不当解雇できない!?
こういった、宇宙をひっくり返しても納得がいかない気持ちを持っているのは、ギャラリーの我々だけでなく、T社もそうであったため、怒涛の勢いで高裁に殴り込みました。

運転に気を付けるべし
高裁の見解
- Z氏は、自分を乗せた車を運転する労働組合のメンバーは、別に空港の器物に故意にぶつかったりする素振りを見せていなかったので、止める必要はないと抗弁したが、T社から提出を受けた証拠によると、車の時速は、制限速度の15キロを優に超えている32キロで、指定された走行ルートも遵守されておらず、車両の走行中にちょうど旅客機が着陸しようとしているにもかかわらず走行を継続していたことが分かった。運が悪ければ、同機の着陸に支障を来し、それに乗り合わせた乗客と乗組員も大変危ない目に遭いかねない。Z氏はただ単に残業拒否闘争の実施状況を確認するとの理由で、そのリスクを知っておいてなお危険を冒した。Z氏の行いは、T社の就業規則に違反するところか、法律を平気で無視し、他人の安全をないがしろにした事実が明らかなため、T社がZ氏に下した懲戒解雇処分は有効と判断。
- 一方、デマを流したC氏は、まさにちゃぶ台返し事件の真犯人だとT社が主張したが、ちゃぶ台返しが起きたのは忘年会であることを考えたら、タイミング的にはC氏の勤務時間外で、事件の現場もT社の事業所外であるため、C氏の行いに対して社員として罰することに正当性があるのかは要考慮。そして、T社は前述した事件によって社内秩序が乱された証拠も未見。
- C氏はその他従業員に対して、残業拒否闘争への参加を呼び掛けていたものの、参加するかどうかはそれぞれの従業員個人で自由に決定可能で、C氏はそれを強要することはできない。なお、C氏が休暇手続きを取らずに労働組合会議に参加した件について、この辺の違反行為があったら原則として譴責処分が下されると、T社の就業規則に書いてある。にもかかわらず、C氏へは譴責ではなく、いきなり懲戒解雇処分が下されました。同処分は明らかに不当であると。
- 最後のW氏は、勤務時間外なのにあえて制限エリアに入って、残業拒否闘争への参加を呼び掛けていたが、参加不参加は個人の意志で決められており、かつT社はそれによって何か損失があったかを証明できないので、C氏と同じく、就業規則に基づき譴責処分が妥当であると。(高裁102年度重労上字第6号判決)
二勝一敗か、少し有利になった展開をもって、どんどん進もう!
T社は、最高裁の世話になることを決めたのと同時に、高裁で唯一脱落したZ氏も、T社と逆の方向で上告しました。

事実関係をはっきりさせるべし
最高裁の見解
- Z氏が組合メンバーの運転した車両で制限エリアに入った件について、当該組合メンバー自らの意志で制限エリアに乗り込み、乗り合わせたZ氏はそれを止めなかっただけなのか、それとも同2名は事前に話し合って、制限エリアへの乗り込みを決定したのか。事実がどちらなのかによって、Z氏の解雇に正当性があるかどうかを判断するうえでは必要不可欠であるにもかかわらず、高裁はそれについての言及がなかった。
- 忘年会の前、T社と社内労働組合とで話し合わされた昇給率と賞与額は実際どんな感じなのか、忘年会の場で昇給率を公表するとT社から承諾が得られたのか等、こういった事実をはっきりさせない限り、C氏にデマを流した行為の有無を判断しづらく、ちゃぶ台返し事件の是非も裁定しにくいため、C氏への懲戒解雇処分が不当であるかどうか認定が難しい状態。
- T社が主張し、W氏が否認した、その他従業員に対して行われた恐喝行為について、それが事実なのか高裁は真面目に審理を行っておらず、W氏の行いは、労基法第12条に定めた解雇の要件、「やってはいけない重大な就業規則違反」に該当するかもろくに考慮していなかったのに、W氏の解雇が不当だという高裁の判断はなかなか納得がいかない。(最高裁104年度台上字第2185号判決)
以上のように、最高裁は、高裁が出したT社にとって1勝2敗の結果を認めませんでした。振出しに戻った感じで、高裁で本件審理のやり直しが始まります。
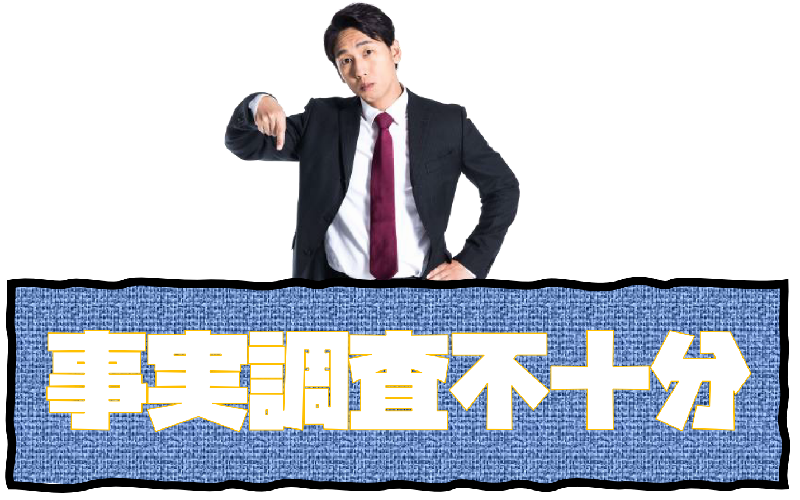
事件の張本人が浮き彫りに
高裁の見解-差し戻し審
- Z氏は今までの話し合いのなかで、T社の責任者は5%の昇給を明確に承諾したわけではなく、忘年会でそれを公表する約束もされていなかったのを知りつつ、それをまるで事実かのように言いふらし、当該目的を達成すべく忘年会でのちゃぶ台返し事件を計画、実施した。Z氏は同事件が事前計画によるものではなく、忘年会に参加した従業員が自主的に行ったのだと抗弁したが、全26卓のうち20卓もひっくり返されたという、被害に遭った食卓はなんと全体の8割弱であり、計画なしでも考えられない数字である。なお、その後のマスメディアの取材でZ氏は、社長が約束を破ったから、ちゃぶ台返し事件が起きた、と発言し、T社のイメージダウンにつながったのみならず、労使間の信頼関係もそれによって失われた。
- Z氏は労働組合の理事長を担当しており、組合のメンバーは理事長を乗せる車両の運転手として、走行ルートと時速を理事長の命令に従い調整していたのではと考えられる。また、Z氏は同社に勤めて10年超、規定を破って車両で制限エリアに入る危険さを知らないはずないのに、残業拒否の実施状況を確認するだけの理由でそれをやってしまった。目的と手段のバランスが全く取れていない。
- 労働組合会議への出席は、ルール上有給休暇が取れる。Z氏は残業拒否の実施を決定する同会議に参加するものなら、ルールに従い休暇を取らなければならない。にもかかわらず、休暇の取得手続に関する証拠は一切出さなかった。従業員の無断欠勤は会社の日常的業務に支障を来し、社内の人事管理にも混乱を招きかねない。
- Z氏は約15年間T社に勤め、社員代表の取締役と社内労働組合の理事長に上り詰めた。T社から懲戒解雇処分を受けた原因は、自分のためではなく、組合に参加した従業員全員により良い昇給率を勝ち取る目的ではあるが、それに至るまでの手段はやや非常識で、取締役又は理事に課せられる忠実義務に反するだけでなく、T社との雇用契約や就業規則にも違反しており、かつ違反行為が発生した頻度、重大さを考慮したら、解雇するしかないと考えさせられるほど、労使間の信頼関係が喪失した。従って、Z氏への懲戒解雇処分は有効だと判断。
- 一方、C氏はその他従業員に残業拒否を呼び掛けたのは、Z氏から嘘の情報共有を受けたものと考えられ、その目的も組合参加者の昇給にあるから、処分の対象にはなるが、懲戒解雇のレベルにまだ達していないと考えられる。また、C氏はT社からシフト調整の命令を守らなかったが、通常通りの8時間勤務をしっかりこなしており、T社はそれによって何か損害を受けたかを立証できなかったため、無断欠勤をもってC氏を罰することに妥当性が欠ける。C氏の行いを総合的に考えたら、懲戒解雇処分は重すぎて、不当であると。
- 最後のW氏は、T社の残業要請に協力した従業員に対して、労働組合から強制的に脱退させられるよ、旨の発言を行ったが、脅迫や威嚇と認められる程度の話しはしていなかった。実際、W氏から話しを受けた従業員は残業を辞めていなかったし、現場に駆け付けたT社の幹部が止めに入ったら、W氏はすぐその場を離れたことなどを考え、C氏と同じく、T社が下した懲戒解雇処分は過度に重く、認めがたい。(高裁104年度重労上更1字第5号判決)
更に悪あがきしても、よくて1勝2敗かもとの観点で、T社は本件訴訟からリタイアしようとしたが、よもや一番の敗者であるZ氏は、筐体にコインを入れてT社との一騎打ちでゲームを再開しました。

同一違反同一処分
最高裁の見解-2回目
- C社の就業規則に、諸々違反例を取り上げ、それぞれ戒告や譴責、減給、懲戒解雇等のどちらに該当するか定められている。Z氏の行いは、そのうちのどの違反例に該当し、どの程度の処分を下したら妥当であるかについて、高裁はもうちょっと丁寧にチェックすべきである。
- 過去において、とある従業員は非番なのに無断で制限エリアに入ったことがあったにもかかわらず、T社は同従業員に一切処分を下さなかったと、Z氏から証拠の提出があった。T社は、今まで同じ違反例に対してはどういった処理を行ったのか、同じ違反行為を行ったZ氏にいきなり解雇することに果たして妥当であるかどうか、要するにT社は「同一違反同一処分の原則」に反しないかについて、高裁はそれを審理していなかった。(最高裁107年度台上字第1172号判決)
スポーツマンシップ
高裁の見解-再差し戻し審
- Z氏とT社は2014年中、法廷外で訴訟制限契約書を取り交わし、「Z氏への懲戒解雇処分は不当解雇に該当するか」問題について、最近1回の判決結果が出たら、それぞれ上告可能な回数を1回とする、との合意がなされた。
- 前回の裁判においては、Z氏とT社それぞれ有する上告のチャンスは既に費やされたのに、Z氏は訴訟制限契約書での約束を破って、今回の訴訟を起こした。もしZ氏の提訴を認めたら、契約を任意に違反してもかまわない、という歪んだ考えを増強してしまう可能性があるため、それを認めるわけにはいかない。そのため、前回の裁判結果である、Z氏への処分は不当解雇に該当しない、との結論は引き続き有効とする。(高裁108年度重労上更2字第1号判決)
悪あがきするよりはや仕事を探せ!
最高裁の見解-3回目-確定判決
- 当事者間で取り交わした契約書は、内容はどうであれ、法律や公序良俗に違反しない限り、当該契約書に有する法的効力は認められるべきである。訴訟制限契約書に違反し提訴した一方に対して、他方がルール違反だ!と抗弁したら、当該一方はその場で提訴する権利が失われる。
- Z氏は、以前労働部裁決委員会が出した行政処分を証拠に、T社から受けた懲戒解雇は無効であると主張したが、同処分の内容は、T社がZ氏を解雇したことによって労働組合法第35条に違反した、との意味合いであり、T社とZ氏の間に雇用関係が存続するとは一言も書いてなかった。勿論、行政処分は司法機関の判断を拘束する力も有さない。
- 従って、Z氏の解雇は引き続き有効であると結論付ける。(最高裁110年度台上字第24号民事判決)

今週の学び
以上、T社とZ氏との長たらしい愛憎劇から得られるヒントについて、今週の学びとして以下まとめます。
マサヒロのまとめ
- 通常の社員ならともなく、労働組合のメンバー、若しくは労使会議の労働者代表に選出された社員を解雇しようとする場合には、会社に求められる立証責任が大変重いので、解雇に至るまでの因果関係を証明可能な各種証拠をしっかり準備してからアクションを取ること
- 社内の過去事例をできるだけ見える化にし、いざ処分についての公平性問題で争われるとき、「同一違反同一処分の原則」に違反していないか、何時でも事実検証ができるよう心掛けること
- 明らかに軽いミスであったにもかかわらず、比較的重たい懲戒処分を定める、若しく自社の業務形態を考慮せず、ネットからダウンロードしたテンプレをそのまま利用したことで、実際かみ合わない内容が散在している、等の問題点がないか、自社の就業規則の懲戒編を常に確認すること
- 訴訟制限契約書は裁判の場においても、その効力が認められる可能性があります。社員との話し合いのなかで、必要に応じて同契約書を活用できること
- 社員の解雇が法律違反だ!と行政に認定されていても、司法に訴えたら、最終的に不当解雇と見なされずに済む可能性も存在しているため、場合によって弁護士と相談すること
では、来週のマサレポにてお会いしましょう~