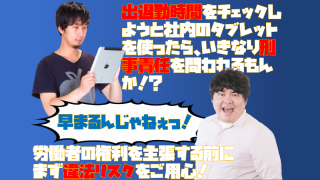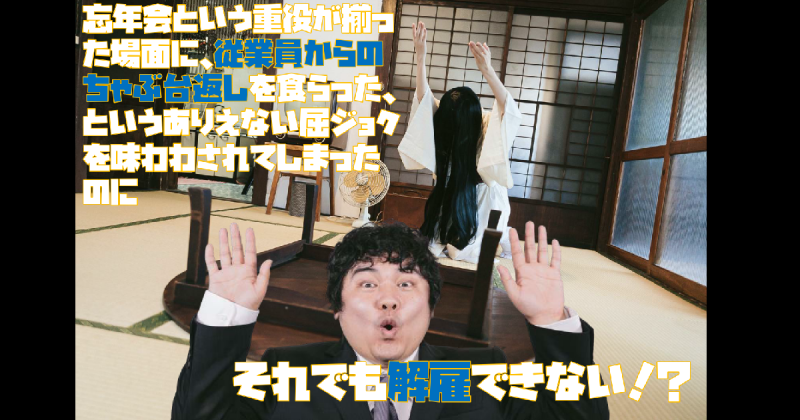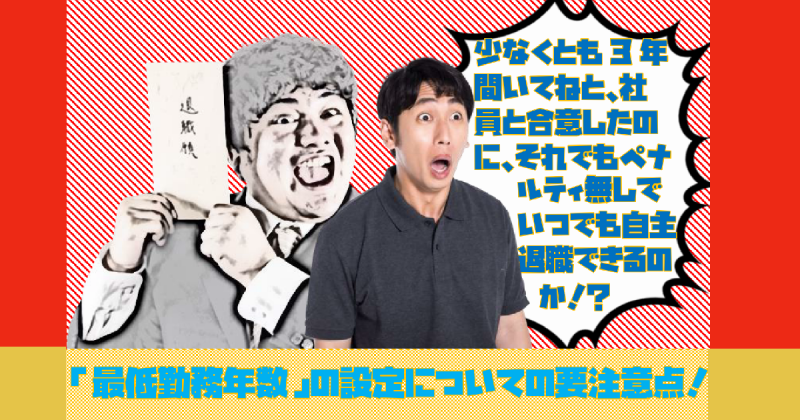出退勤時間をチェックしようと社内のタブレットを使ったら、いきなり刑事責任を問われるもんか!?労働者の権利を主張する前にまず違法リスクをご用心!
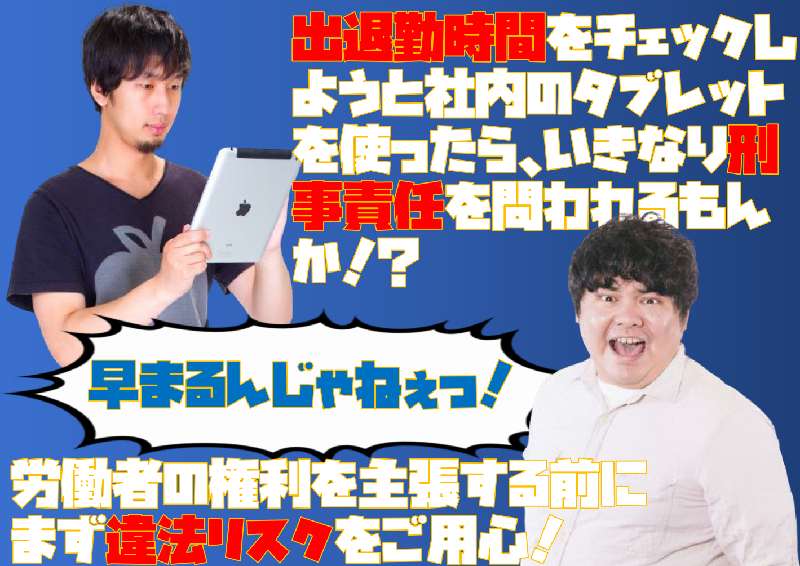
会社から違和感を覚える対応をされたら、帰宅後、違和感をもたらす事件の梗概で検索し、類似体験のあるネット住民はどういう対応を取ったり、労基法に照らし合わせると、会社に対してどのような主張ができたりする等を細かく調査するという、今の労働者は、昔なら考えられない労働リテラシーが身に付いており、“サービス残業が当たり前”、“有給休暇は正社員になってから”、といった労務管理上の考え方は絶滅危惧種のようになりつつあります。
こういった時代的変化に伴い、会社側にも労務管理リテラシーの向上が迫られ、ワンパターン的な人事マネジメントを取り続けるわけにはいかなくなりました。こうして、労働環境がますます良い方向へ進化し、労使紛争も減少する一途を辿っていくはずです。
しかし、会社と従業員とでは、リテラシーの成長に温度差があることは普通で、それが許容範囲を超えてしまうと、往々としてトラブルの火種につながってしまいます。
今週のマサレポで紹介させていただく労働事件は、もともと会社に問題があって、適切な方法さえ取れば、従業員側では妥当な補償がもらえる可能性が高いなのにもかかわらず、対象従業員はたまたま法律的に妥当性が欠ける対応を取ってしまったがゆえに、会社に労基法に定めた適正な対応をしてもらえるところか、会社から刑事責任を追及され、前科が付くかつかないか、というバッドエンドを迎えてしまうトラブルです。以下ご覧ください。
事件のあらすじ
とあるビストロに務める女性社員のC氏は、時間外労働を結構やっているにもかかわらず、店からはほとんど残業代の支払いを受けていないことに納得がいかなかったため、店主に事情を確認することにしました。
C氏から前述の質問を受けた店主は、今までの勤怠記録は保存していないから、物理的に提供できないとの理由でC氏を適当にあしらいました。その後、C氏は何回か勤怠記録の提出を店主に求めていたが、大体同じ説明が返され、一度も勤怠記録を自分の目で確かめることができませんでした。
途方に暮れたC氏は、勤怠記録を調べる方法何かないかを探そうとする一心で、ネットでいろいろ検索してみたら、なんと、店舗で使用するPOSレジに勤怠管理機能を有し、それにアクセスすると勤怠記録を把握することができるとの事実を発見しました。
その後、C氏は店主の目を盗んでセルフオーダー用のタブレットを使って、店舗支配人のアカウント名とパスワードでシステムのダッシュボードにアクセスし、C氏をはじめとする従業員合計3名分の勤怠記録を順調に入手できたため、グループLINEでその他2名の従業員に、入手したばかりの勤怠記録を共有しました。3人とも時間外労働の履歴があったとの確証を得たことで、数日後、C氏とその他2名は自分の勤怠記録を店主に突き付け、彼女たちが受領すべき残業代の請求を行いました。
しかし、C氏が行った前述した行為が店主の逆鱗に触れ、無断で他人のパソコンに不正アクセスしたとして、店主に訴えられました。

未払い残業代の請求は免罪符になりうる!?
ビストロの店主が提訴する法的根拠は以下です。
コンピューターその他関連装置で、不正に知得若しくは所持する他人の秘密を、正当な理由なく第三者に漏洩したときは、2年以下の懲役若しくは禁固又は1万5千NTD以下の罰金に処する。
刑法第318条の1
正当な理由なく他人のアカウント名とパスワードで、コンピューターのセキュリティ保護機能をかいくぐったり、システムのバグを利用したりして、他人のパソコンその他関連装置に不正アクセスしたときは、3年以下の懲役若しくは禁固又は30万NTD以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
刑法第358条
一方、C氏は、店主に断りなく勤怠管理システムのダッシュボードにアクセスしたことと、同システムから入手した勤怠記録をその他従業員が加入したグループLINEで共有したことを認めるが、こういった行為を働いた原因は、あくまでも店主が勤怠記録を一向に見せてくれることなく、法律に基づいて残業代を払ってくれない事実があったからです。労基法に保証される従業員としての権利を主張したい、という立派な理由があるから、「正当な理由なく」ではない!と抗弁しました。
それを受けて、本件の審理を担当する裁判官は、以下のように述べました。
地裁の裁判官の見解
- C氏の行いは店主が主張する犯罪行為に該当するかどうかを判断するポイントは、「正当な理由なく」との要件を満たしたかによらなければならない。最高裁の裁判例(最高裁107年度台上字第2187号判決)では、「正当な理由なく」というのは、「合理性のある理由がない」、「所有者から許可を得られない」、「権限がない」、「所有者の意志に反する」、「与えられた権限を逸脱する」等の意味合いが含まれるとの見解が示されていた。
- さらに、「不正アクセス」という行為に該当するかについては、何ら断りなく他人のパソコン等にアクセスしたとの事実さえ存在すれば、該当性が充足されるものであり、たとえこういったアクセス行為によって何人たりとも損害を受けていなかったとしても、「不正アクセス」に該当しない、との主張は成り立たない。
- C氏は店主の了承を得られることなく、支配人でしかアクセスできないダッシュボードにアクセスし、かつそれを無断で第三者と共有した。C氏は「正当な理由なく」こういった行為を働いた事実が明らかである。
- 一方、前述の不正アクセス行為は残業代を請求するための方法に過ぎない、とC氏は抗弁したが、権利の行使手段をもって犯罪行為を正当化する論理は認めがたい。なお、事業主にはもともと勤怠記録を保存する義務があり(労基法第30条第5項)、労働者から提出要請を受けたら事業主はそれを拒否することはできないとされている(同法同条第6項)。C氏はこういった法律に基づき店主に勤怠記録の提出を要求しようとせず、あえて「不正アクセス」で同記録を入手したから、犯罪事実が明白である。
- しかし、C氏は今まで犯罪履歴がなく、犯罪の動機も労働者の権利を守るためにあるので、諸々要因を総合的に考慮し、30日間の禁固刑に処することが妥当だと判断。(新北地裁111年度易字第356号判決)

今週の学び
本件裁判は今年9月23日に結果が出て、まだまだホヤホヤの状態であるため、検察官又はC氏はその後、控訴を行ったかどうかは未知数ですが、犯罪行為の重大さと量刑の結果からしては、第二審は恐らくないのではと思料しています。
では、今回の労使トラブルからどういった学びができるか、以下チェックしてみましょう。
マサレポ、今週の学び
- 会社が労基法を違反、従業員がその他法律を違反。裁判になったら、おあいこにすることはできません。
- 不正の手段をもって会社の違法事実を暴くことができたとしても、不正した事実の補正にはなりません。
- 勤怠記録の保存と提出義務は会社側にあって、勤怠記録がないと、ペナルティの対象は会社です。ただし、就業規則等で従業員に作成の協力を促すことは可能。
もしビストロの店主は最初から勤怠記録を用意していなかったら、まだ理解できますが、せっかく予算をつぎ込んで勤怠管理システムを導入したのに、勤怠記録を一切従業員に見せない、とのやり方はやはり感心できないものですね。
支払うべき残業代をケチることで、今回の裁判につながり、それによって、店もよくない意味で目立ってしまいました。確かに、会社は従業員との裁判には勝ったが、その後ビストロを対象に実施する労働検査で、店主はどれぐらいの過料を払わされるか、そして「労基法違反店舗」としての名声が広まったことで、客足はどのように変化するか等、店主は当初こういったコストを念頭に入れたら、早期にコンプライアンスの重視に目覚めるかもしれません。