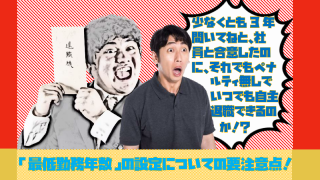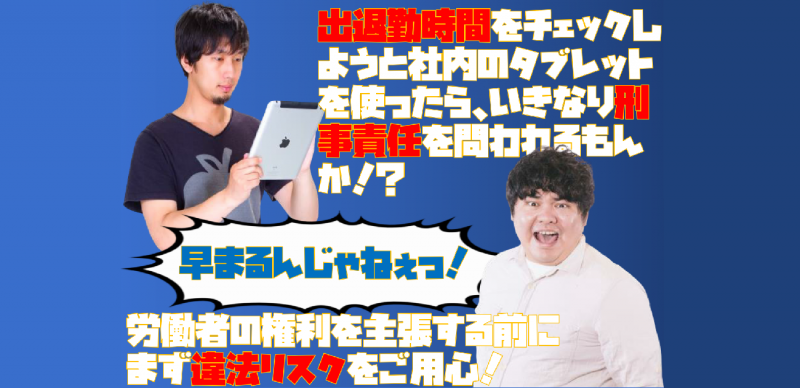少なくとも3年間いてねと、社員と合意したのに、それでもペナルティ無しでいつでも自主退職できるのか!?「最低勤務年数」の設定についての要注意点!
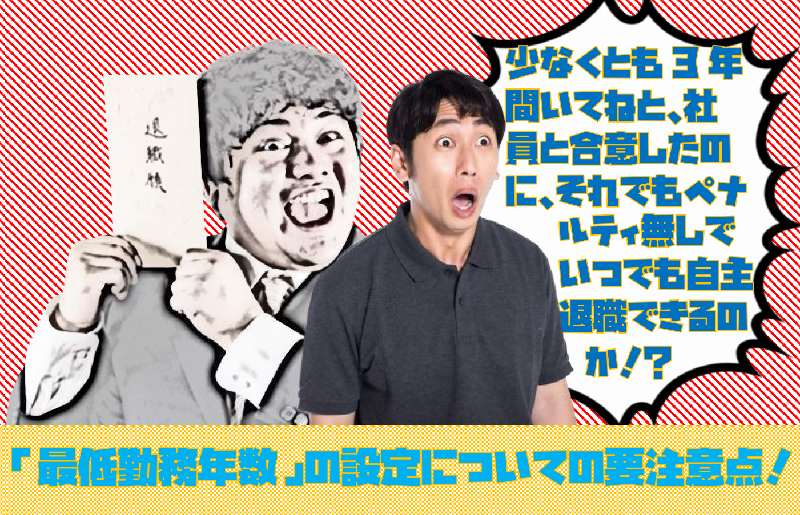
会社が実施する従業員の解雇で、法律上不当とみなされたえぐい事例をいくつか考察してまいりまして、事業主側でどのように証拠を強化すれば、正当性の主張が成り立つことをある程度掴めていただけたかと思います。では、逆のパターン、解雇ではなく、有能な従業員を引き留める手立てとして、「最低勤務年数」の設定に何か要留意点がないでしょうか?
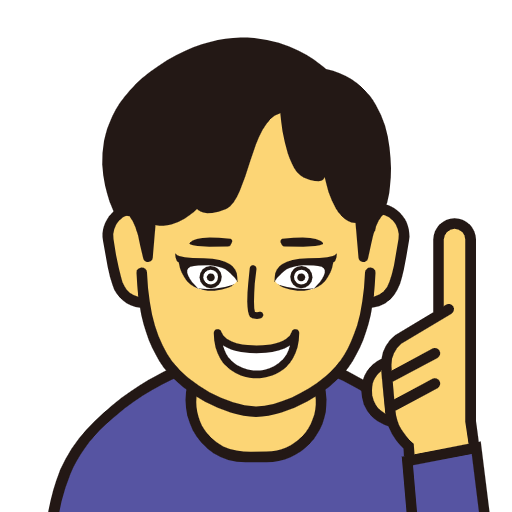
解雇は、従業員にとって不利になる行為なので、会社が取る一連の対応は厳しくチェックされるのは理解できるが、「最低勤務年数」の設定は、従業員が会社で継続的に働ける権利を守る措置であり、法律の縛りが比較的緩いはずでしょう。
と考えられがちかもしれません。実際、こういった設定があったら、労働者が有する「転職の自由」が制限されるわけなので、一定の要件を満たさないと、法律上では無効と認定されてしまいます。
労基法に定めた要件の関係で、最低勤務年数に関する既存の裁判例においては、当事者は9割前後が航空会社です。一般業種にも幅広くご参考いただけたらと、あえて主流から外れた、航空会社以外の事例をピックアップし、最低勤務年数の設定における要注意点を考察させていただきたいと思います。それでは、レッツ学びです!
登場人物とあらすじ
今回の事例に登場した原告は、台湾の大手地上波テレビ局のF社です。同社の主張は以下です。
F社は2016年7月に、新聞記者として2ヶ月ほど前に入社したC氏と最低勤続年数条項付きの雇用契約書を締結し、ニュースキャスターに至るまでの社員研修を提供するとともに、月次賃金を今の32,000NTDから段階的に41,000NTDまで昇給するが、その代わり、C氏は2019年7月までは退職不可で、違反したら月次賃金5倍相当額の違約金をF社に支払わなければならない、という風な合意がなされました。
一方、C氏は在籍期間中、F社の就業規則その他規約を無視し、一度ならず無断で兼業しており、F社から数回勧告があったが相手にされませんでした。なお、C氏は2018年4月から何かと理由をつけて頻繁に休暇を取得し、法定休暇日数の上限に達したと分かったら、2018年8月12日を最後に自主退職する旨を急にF社に告知した始末でした。
以上によって、C氏はF社との最低勤務年数の約定に反し、利息を付けて月次賃金5倍相当額の違約金をF社に支払うべきです。
そう考えたF社は裁判所に訴えかけました。
C氏の「異議あり!」は以下のような内容です。
C氏はF社に入社する前、既に大学のジャーナリスト学部から修士号を取得しており、別途ニュースキャスターになるための研修が要らないし、F社からも実際そのような研修を受けたことがありませんでした。
F社との雇用契約書に定めた最低勤務年数の条項については、それを従業員に受け入れさせるための合理的な補償は一切盛り込まれておらず、労基法第15条の1に反したため、同条項は法律的には無効です。
兼業はC氏が休み時間を利用して行ったもので、F社それに口をはさむ権利がなく、かつF社は2018年3月にC氏をニュースキャスターの担当から外し、支払うべきキャスター手当も支払っていなかったため、F社が労基法第14条に違反したとして、最低勤務年数条項付きの雇用契約書をC氏は一方的解約できる権利があります。
また、最低勤務年数条項付き雇用契約書の発効日から考えると、2018年8月までF社に在籍したC氏は実質21ヵ月分の契約義務を果たしたため、その分だけ違約金を減らすべきだと主張しました。

判官贔屓
本件審理を担当する裁判官は、まず最低勤務年数を定める前提条件として、以下の法律を引き合いに出しました。
会社は、最低勤務年数について従業員と約定を取り交わすには、以下いずれかの要件を満たさなければならない。
会社は、自ら費用を負担のうえ、従業員に専門性のある研修を受けさせること。
(労基法第15条の1第1項)
会社は、最低勤務年数の遵守に見合うだけの補償を従業員に与えること。
上記の前置きをしてから、裁判官が以下の持論を展開しました。
第一審の見解
- F社は、C氏が最低勤務年数の約定に違反したことで、莫大な損失を被ったと主張したが、どういった損失が発生したかの立証がなされておらず、C氏にかけた研修の関連費用を証明可能な証拠も未見。
- 「月次賃金を段階的に41,000NTDまで昇給する」件については、昇給額は性質上、C氏が提供する労働への対価に該当するため、「最低勤務年数の遵守に見合うだけの補償」とは認めがたい。
- 前置きの労基法ルールに照らし合わせると、専門性のある研修を提供したエビデンスもなく、「最低勤務年数の遵守に見合うだけの補償」もないため、F社とC氏との最低勤務年数の約定は無効とみなし、C氏は違約金を支払う義務がないと結論付ける。(107年度北労簡字第206号)

喧嘩両成敗
F社は台湾で名の知れるテレビ局のこともあって、第一審の判決結果をそのまま受け入れたら、示しがつかない恐れもあったりするから、第二審に名誉挽回のチャンスを託しました。
第一審では前置きとして労基法第15条の1の第1項が引用されたが、第二審の裁判官は同条の第2項にフォーカスしました。
会社は従業員と最低勤務年数を約定するにあたって、以下各号の内容を総合的に考慮する必要があり、合理的範囲を超える設定をしてはならない。
会社が従業員に専門性の有する研修を受けさせる期間とかかるコスト
(労基法第15条の1第2項)
対象従業員は、同様又は類似業務に従事するその他従業員に取って代わられる可能性
会社が対象従業員に提供する補償の金額と範囲
その他最低勤務年数を設定する合理性に影響する要因
第二審の見解
- 手塩にかけて育てた従業員がいきなり退職し、今まで研修にかけた時間と費用が無駄になるリスクを回避するには、会社に最低勤務年数を設定する必要性が生じるわけなので、法律に違反しない限り、契約自由の原則に基づき、当該設定を尊重すべきである。従って、C氏が主張した、F社は雇用主としての権利を濫用し、一方的に最低勤務年数の制限をかけることで、労働者に付与される転職の自由を妨害しようとするから、同制限は公平性がないとして無効とされるべきだ、との論点は認めがたい。
- 証人の話しによっては、C氏はキャスターとしての経験がなかったため、それに関する研修が必要とされ、かつ同研修は従業員全体に対して施す、決まった研修メニューではなく、予め実施する場所と時間を確保しなければならないとともに、C氏が台湾語でニュースを放送するには明らかに経験不足なので、台湾語の専門家が行う授業を受講させたり、放送の現場で専門家がそばでレクチャーをしてあげたりしていたという。たとえ研修の場所はF社が所有するスタジオ、講師もF社の従業員、一部の研修はC氏の退勤時間後に行われたとはいえ、C氏を一人前のニュースキャスターとして育てるために、F社が少なくない時間や労力、コストを費やしたとの事実を否定できない。従って、最低勤務年数の設定は有効である。
- F社のようなテレビ局にとって、ニュースキャスターは必要不可欠な存在であり、新聞記者から一人前のニュースキャスターに育てるまでは、相当な資源や労力、経費が注ぎ込まれたと考えられる。C氏の退職によって、F社はニュースキャスターになりうる人材を再度探さなければならず、適任な人材が見つかった後においても、一から研修をやり直す必要もある。そのため、C氏の仕事内容は明らかにその他従業員に取って代わられるものではなく、最低勤務年数の制限をもって、C氏のような人材の流出に歯止めをかける必要性があることを認める。
- C氏がF社によって提示された最低勤務年数条項付きの雇用契約書にサインした後、月次賃金がまず3,000NTDUP、3ヶ月後に3,000NTDUP、8か月後に3,000NTDUP、半年後さらに2,050元UPした。こういった給与面での優遇措置をもって、社内人材の流出を食い止めるとの考え方は、人事マネジメントの場面においてはよくある話である。C氏は契約する前に、スピーディ昇給の優遇を受けられる代わりに、退職の自由はある程度制限されることを全く知らないはずがないにもかかわらず、結局自分の意志で、スピーディ昇給という通常ではありえない待遇を選択したわけなので、C氏は、スピーディ昇給との形で、「最低勤務年数の遵守に必要とされる補償」を既にF社から受けたと判断。
- F社はC氏をニュースキャスターから外したことによって、労基法第14条の定めに抵触し、C氏は最低勤務年数を守らずともF社との雇用契約書を一方的に解約することができるとC氏が主張したが、同雇用契約書においては、ニュースキャスターの仕事をこなすための研修を実施しようと、練習を兼ねてF社は不定期的にニュースの報道をC氏にやらせる、とだけ記されており、ニュースキャスターの職位を保証する内容が未見である。F社の労基法違反が認められないから、同雇用契約書の解約は、C氏が申し出た自主退職によるものだと判断。
- 前述した理由により、本件最低勤務年数条項付きの雇用契約書は法律上では有効であることが分かったため、最低勤務年数がまだ満了していなかった時点で自主退職したC氏に対して、F社は契約に基づき違約金を請求する権利は認めるが、最低勤務年数として定められた3年のうち、C氏はF社に籍を置いたのは2年1ヵ月なので、契約違反となる期間は11ヶ月弱であるとの事実を考慮したら、民法第252条の定めに基づき、F社がC氏に請求可能な違約金をC氏の月次賃金の5倍から65,000NTDに減額するほうが妥当である。(108年度労簡上字第48号)

今週の学び
労使双方で取り交わした契約書のみ提出した第一審でボロ負けしたF社は、C氏に受けさせた研修に関する物的証拠を追加で提出のうえ、証人まで用意したことが奏功し、C氏に請求可能な違約金が腰切りされたとはいえ、最終的な勝利をついに呼び寄せました。この事件からも、人事管理の難しさが伺えましょう。
では、今週の学びを次見てみましょう。
マサレポ、今週の学び
- 従業員に最低勤務年数を要求するためには、契約書にサインさせるだけでは物足りず、専門性のある研修を従業員に受けさせ、かつそれを立証できなければなりません。
- 前述とは別に、最低勤務年数を要求可能な前提条件は、対象となる従業員が比較的高度な専門性を有する仕事に従事しているかどうかがポイントで、一般職や事務職、営業職を担当する従業員に対しては同じ制限をかけても、法律上無効と見なされる可能性があります。
- 最低勤務年数の設定に必要とされる「合理的な補償」に、通常の年次昇給や賞与、役職手当を充てることが認められず、その他従業員にない、対象となる従業員にのみ付与する「何か」、つまり差別化を図っての給付をもって、「合理的な補償」を行う必要があります。
- 裁判になったら、契約に基づき請求可能な違約金はいろんな理由を付けて減額される可能性は大きいだが、無いよりはましなので、オーソドックスな損害賠償とは別に、懲罰的違約金の条項を契約書に入れることがお勧めです。
ここまで来たら、冒頭に書いてあった、「裁判の当事者は9割前後が航空会社」の理由も分かってきますね。パイロットの養成にかかる研修費、パイロットの仕事はそれ以外の従業員はまず務まらない等、航空会社はまさに最低勤務年数の設定に関する教科書的な存在と言っても過言ではないかもしれません。