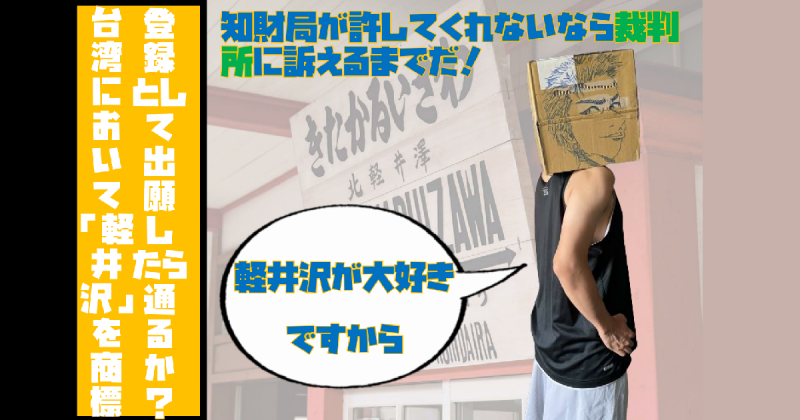ついに賃金として市民権を得た夜食手当!残業代や退職金の計算に気を遣うべき点とは?!
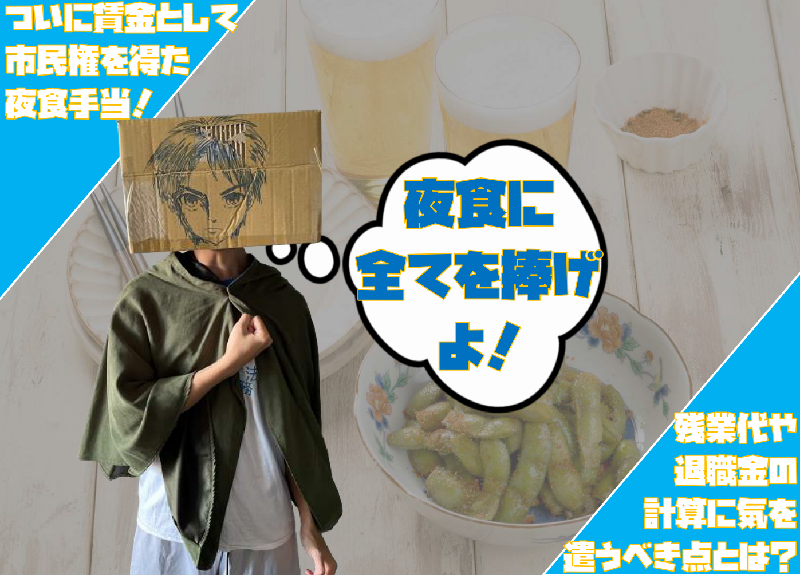
台湾の行政院(内閣と各省庁を併せたものに相当する)は先日、2022年11月より、退職金を計算する原資に夜食手当(中国語:夜點費)を含めることを、国有企業に適用される通知を正式に行い、現時点で在籍する社員約12,000人及び今から5年以内に定年退職した元社員3,400人が本件の恩恵を受けられると見込まれる、とのニュースが報じられています。
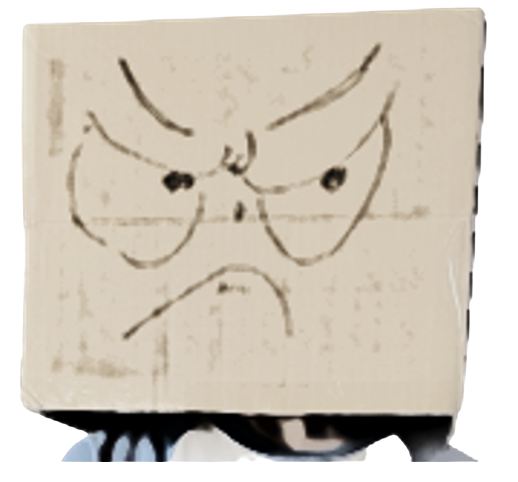
夜食手当は、夜間勤務に協力する社員をねぎらうための、デザート代的なものなので、賃金は関係ないのでは?ましてや退職金の計算に含めるんだなんで、不公平なんじゃないのか?
そうですね、直感的に考えたら、夜勤を担当する社員のみ夜食手当が付いて、カップラーメンを用意する代わりに当該手当が付けられるわけなので、労働対価としての賃金とは一線を画す存在になるはず、と思われがちですが、台湾の労基法に照らし合わせると、2005年の労基法一部改正で、もともと賃金に該当しない項目とされてきた夜食手当が指定リストから外され(労基法施行細則第10条)、当たり前のように、「夜食手当は賃金ではないよ」、と胸を張って言える時代に終焉を告げてしまいました。
でしたら、夜食手当は法律上賃金扱いになるんだね、と言えば、そうとも言い切れません。そのせいで、「夜食手当が賃金に該当するか」問題をめぐる訴訟が長期にわたって続いてきました。それ以上弁護士費用を払い続けて、こういった不毛な論争を継続させていくわけにはいかないと思う行政院は、冒頭の通知を行うことに踏み切り、当該論争に終止符を打つことにしたそうです(少なくとも国営企業はそうです)。
夜食手当に関するトラブルが起きたきっかけは果たしてなんなのか、何故労働当局はわざわざ労基法を改正するまで、思わせぶり的に、「夜食手当はやはり賃金の一部ですよ」、という風なほのめかしを行ったのだろうか、夜食手当を賃金に含めたら果たしてどういった影響が発生するか、といったサイダーのように湧き上がる質問事項を、マサレポ流に徹底解説したいと思います。続きをどうぞご覧になってください。
夜食手当の誕生、そして迷走
交替勤務に従事する社員への福利厚生として、多くの会社は現場に軽い夜食やお菓子を用意し、休憩時間などに夜勤シフトを担当する社員に取ってもらったりしています。こういった社内で予め用意するものは、必ずしも大半の社員に喜んで食べてもらえるとも限らない事実に気付いた経済部は、少しでも社員の満足度を上げようと、1948年に、24時間の通常稼働が必要とされる発電所、製油所、天然ガス製造施設、石化工場などのメンテを行う事業体に、食事を用意する代わりに、現金として「夜食手当」を交替勤務の担当社員に支給することを決定しました。また、「夜食手当」の支給はあくまでも現物の代わりに行われ、疲れが溜まりやすい交替勤務に協力してくれる社員へのねぎらいと励ましとの位置づけなので、残業代又は退職金の計算に夜食手当を含めない考え方が取られていました。
1985年に入って、労働者への残業代や退職金を計算するための「基礎賃金」を定義づけようと、台湾の労働部は労基法に、「経常的給付」に該当しないものとして夜食手当をリストアップし、「夜食手当を退職金に算入しなくても違法にならないよ」との考え方を法律に導入しました(1985年版労働基準法施行細則第10条第9号)。こちらの法律は、まさに夜食手当にめぐるトラブルに火種を付けたのです。
「夜食手当は法律的に賃金に該当しない」、という労基法の定めに気付いた一部の台湾企業は、今まで普通に支給してきた夜勤シフト手当などを夜食手当に衣替えして、大義名分を得たかのように、自社が支給する「夜食手当」が有する実質的な意味を顧みず、残業代や退職金の計算から躊躇なく外す手法を取るようになりました。
労働者意識が現在ほど育っていなかった当時多くの労働者は、月次の給与明細に記載された賃金構成を丁寧にチェックしたりする習慣がまだ根付かなかったため、夜食手当を「労働賃金」として扱われているかを知る由もありませんでした。ただし、これはあくまでも労働組合が組織されない中小企業に限っての話しです。
夜食手当を賃金として取り扱わないことで、まず大手石化メーカーの台プラ社(台湾プラスチックグループ)にトラブルが起きました。同社の社員はそれに納得がいかず民事訴訟を提起し、高裁まで抗争を続けた結果、社員側に軍配が上がりました。それで鼓舞を受けた鉄鋼大手のCSC社(中国鋼鐵)の社員も、台プラ社員に倣って勤め先を相手取って提訴し、夜食手当を賃金として扱え!との心情を訴えており、そして、本マサレポの主役である、国有企業であるCPC社(台湾中油)の社員もついに動き出しました。こうして、#夜食手当訴訟、というブームが工場労働者界隈で巻き起こりました。
夜食手当の取り扱いに関する訴訟があちこちで起きていることで、それ以上労働者の叫びを無視し続けるのはあかんとようやく認識し始めた台湾の労働当局は、一部企業の間で起きた、交替勤務手当や夜勤手当等何をどうひっくり返しても賃金にしかならないものを夜食手当に名目変えることで、残業代や退職金の計算から外そうとする妥当性が欠ける行為を正そうと、2005年に法改正を行い、労働賃金に該当しないリストから正式に「夜食手当」を除名し(2005年版労働基準法施行細則第10条第9号)、これからは実質審査を行って、ケースバイケース的に「夜食手当」が賃金であるかをチェックするよ、と公言しました。
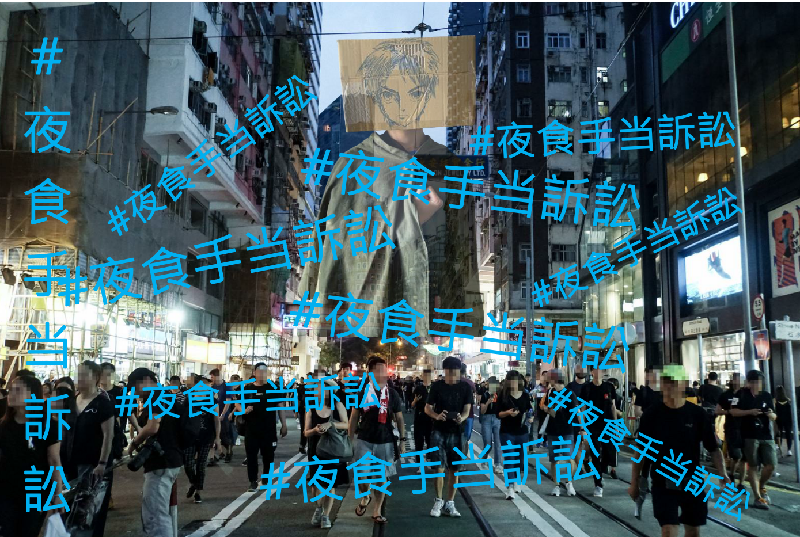
司法機関の対応
夜食手当訴訟の多発により裁判例が次から次へと作り出され、かつ2005年の一部法改正による影響もあって、夜食手当に対する認識は正しい方向で導かれたかと思いきや、現実は甘くありませんでした。
明らかに残業代や退職金の支給を抑える意図があって、強引に名目変更を行って出来上がった夜食手当、というオーソドックスな違法事例はさておき、夜食手当の支払い対象が交替勤務を担当する従業員、宿直の担当者(当直なのに、残業代ですか!?を合わせてご参考ください)、若しくはピンチヒッターとして夜中で急に出勤を命じられる社員なのかなど、受給対象者の就労形態がたくさん存在しているだけでなく、どういった条件を満たせば夜食手当がもらえるの?との条件設定も十人十色なので、裁判所にとっては、同じ夜食手当の支給に絡む事案であったとしても、全く同じ見解を導入し判決を下すことは難しいと感じせざるを得ないようでした。そのため、類似事案に対する認定結果はなかなか落ち着かない時期が続いていました。
ある程度決着をつけないままの状態が長引いてしまったら、さすがにヤバいと気付いた司法当局は、いくつか参考になる判例をもとに、「夜食手当が賃金であるか」問題を考えるには、まず当該手当を受領する権利は労働の提供と強い因果関係が認められるか(労働対価性)、当該手当が会社によって定期的に同じ対象者に支払われているか(経常的給付)、の2点に合致するかを、社会通念をもって見極めなければならず、手当の呼び方にとらわれてはいかない、という結論を下すことに至りました。
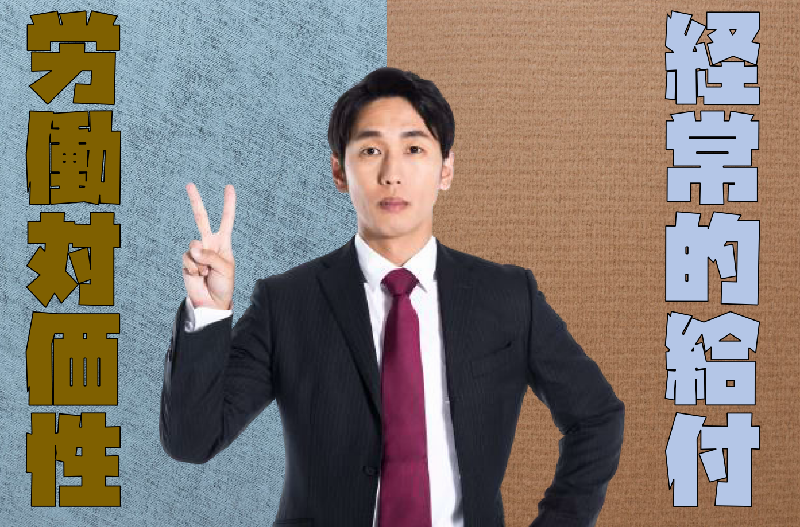
負け惜しみの行きつく先は
労働当局には法改正、司法当局には比較的分かりやすい判断基準を出したことによって、夜食手当に関するトラブルがだいぶ少なくなっているなかで、1社だけ、頑なに労働賃金として夜食手当を扱うことを拒否し続けている会社があって、それが国有企業のCPC社でした。
CPC社の話しでは、当初夜食手当を支給し始めたきっかけは、負担の大きい夜間勤務をこなす社員に少しでも喜んでもらおうと牛乳やお菓子を現場に用意していたが、全くそれに手を付けない社員もいるようなので、代わりに現金で支給することにしたとのことなので、自社の夜食手当は労働提供の対価としてではなく、会社の親心によるものなんだ(恩恵的給付)、との主張がなされました。それを受けた裁判所は、夜間勤務は社員に通常の生活のリズムを大きく逸脱させるマイナス効果があって、そのため、通常勤務より良い給与条件を与えるのが当たり前なので、より良い条件の一つとしての夜食手当は労働対価以外のなにものでもなく、かつ夜間勤務を担当する社員は、CPC社に入社する前に毎月夜食手当が支給されることを既に知っているから、経常的給付としての性質も有すると判断し、一貫としてCPC社の主張を認めませんでした。
夜食手当を賃金として取り扱わないことによって、残業代や退職金の過少給付があったと認められているCPC社は、行政から何度も罰され、社員から何度も訴えられていても、なかなかそのスタンスを変えようとしませんでした。公開された統計データーによっては、夜食手当の訴訟で負け続きのCPC社は、毎年数百万NTDの弁護士費用を払い続け、数千名社員の訴えに対応させてきましたが、勝ち戦はほとんどなく、敗戦処理として億単位の退職金を追加で払い出していたという。
コピペだけの訴状を書き、敗訴を承知のうえ、形だけの出廷を繰り返すだけの弁護士に、国民の血税で報酬を払うぐらいなら、そのお金を退職者に和解金として払い、夜食手当を潔く賃金扱いにしたら比較的賢明なのでは?とのそしりが頻繁に寄せられていたわけか、これ以上不毛な訴訟合戦を続けていっても全く意味がない、と腹をくくった経済部は公式発表で、国有企業が支給する夜食手当を一律に賃金と認め、退職金の計算に含むと公言し、「終わりなき夜食戦争」に決着をつけるのでした。
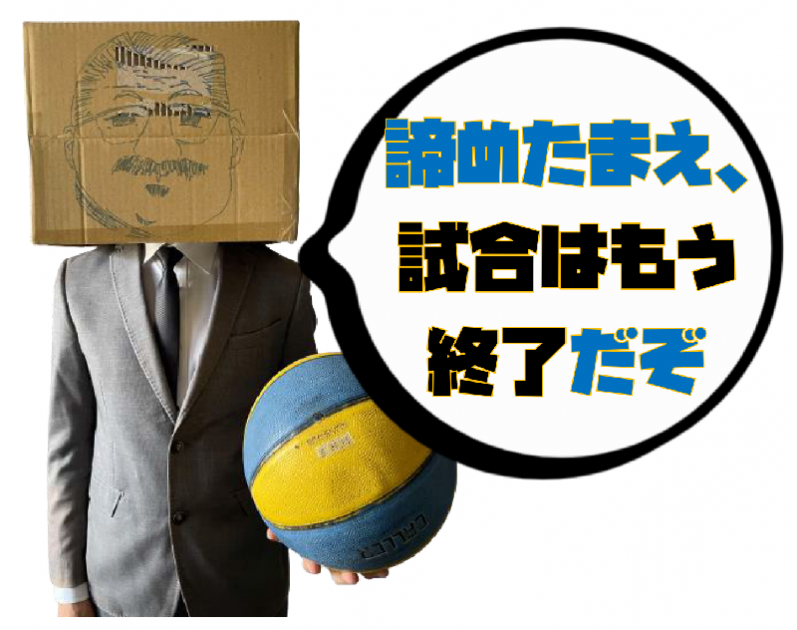
賃金であるかどうか問題が重要?

社内制度上、どうせ夜食手当を毎月支給するから、それが賃金に見なされるかどうか別にどうでもいいじゃん?
残業しない、人員整理がない、労災の発生率が0%、有給休暇の消化率が100%の会社さんなら、確かに夜食手当の性質がどう転ぶかは関係ないかもしれません。ただし、会社運営上こういった仮説を完璧に実現することは極めて難しく、夜食手当がらみの訴訟が既に3,000件超との数字もその事実を物語っています。
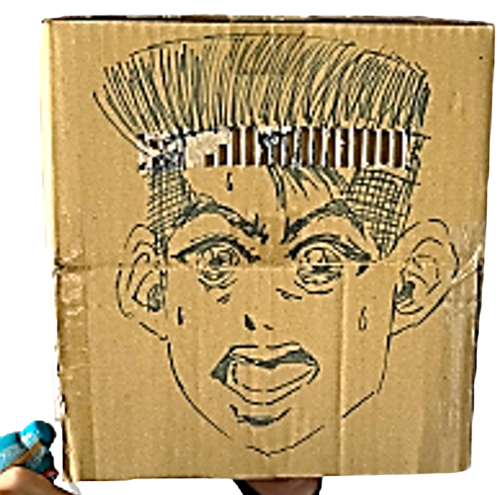
では、労働者は何故わざわざ面倒な訴訟を起こしてまで、「夜食手当が賃金である」との認識を正さなければならないのか、訴訟に係る費用を考慮すればコスパ的に大丈夫?
公開された情報によれば、台湾国有企業のCPC社とTPC社(台灣電力)の交替勤務社員は月次約4,000~6,000NTD/1人の夜食手当の支払いを受けていると伝えられています。旧退職金制度が適用される社員は、退職時におおよそ平均賃金40ヶ月分の退職金を受給可能なので、夜食手当を賃金にするかどうかによって、退職金に約20万NTD/1人前後の差が出て、残業代も含めて考えたら、差額がさらに膨らんできます。提訴したら勝算が極めて高い労働者側が、積極的にアクションを取ってきたことも納得がいくでしょう。
実際、以上の内容で言及された退職金と残業代とは別に、「賃金」で支払い額を計算しなければならない項目はまだまだあります。主な項目を以下共有させていただきます。
上記項目の相乗効果を考えたら、「夜食手当が賃金であるかどうか」問題がもたらすインパクトの大きさが伺えましょう。
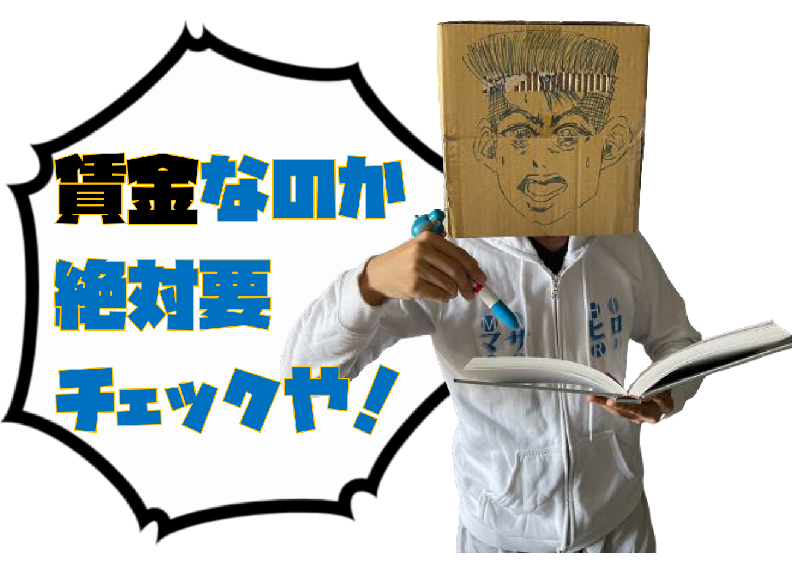
今週の学び
以上、夜食手当の支給に端を発する、数十年にわたる労務問題について、大まかではございますが、一通り紹介させていただきました。いかがでしょうか。会社の好意によって誕生した夜食手当は、それを給料とは別に受領できることは社員にとっても喜ばしいことのはずなのに、何時しか労使対立を招き、会社を訴えるための材料に変質してしまいました。考えられる主な要因は、恐らく前段落で言及した以下の内容かと思います。
...一部企業の間で起きた、交替勤務手当や夜勤手当等何をどうひっくり返しても賃金にしかならないものを夜食手当に名目変えることで、残業代や退職金の計算から外そうとする妥当性が欠ける行為を正そうと...
現状を改善しようと新しい制度を作り出し、そしてよこしまな考えの持ち主によってそれが悪用され、最終的には悪い制度、問題のある制度と評価されてしまいます。こちら大変馴染みのある方程式は、本件「夜食手当事件」に当てはめても違和感を覚えないかもしれません。
マサレポ、今週の学び
- 会社の支給する〇〇手当や〇〇保証金が賃金に該当し、基礎賃金に含めて残業代や退職金を計算必要かは、項目名称を根拠にしてはならず、その性質によって個別で判断することが望ましいです。
- 労働賃金であるかを判断する基準に、「労働対価性」の有無と「経常的給付」であるかといった点が用いられ、両方とも合致すれば賃金と認定されます。
- 社員の福利厚生を充実させようと新たに何かの手当を社員に支給しようとする前に、それに関するルール設定や書類づくりをきちんと行い、「賃金なのでは」と事後疑問視されたら、何時でも胸を張って立証できる準備を整えましょう。
- それが労働賃金であることを十分に認識しているにもかかわらず、残業代や退職金を節約する意図で、今まで社員に支給してきた手当を、賃金に該当しないリスト(労基法施行細則第10条)に記載のあった項目に合わせる形で名称変更しても、労働当局が行う実質審査で、それが徒労に終わる可能性が高いです。