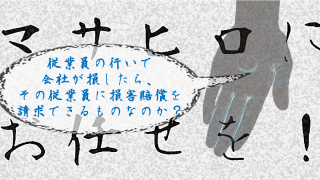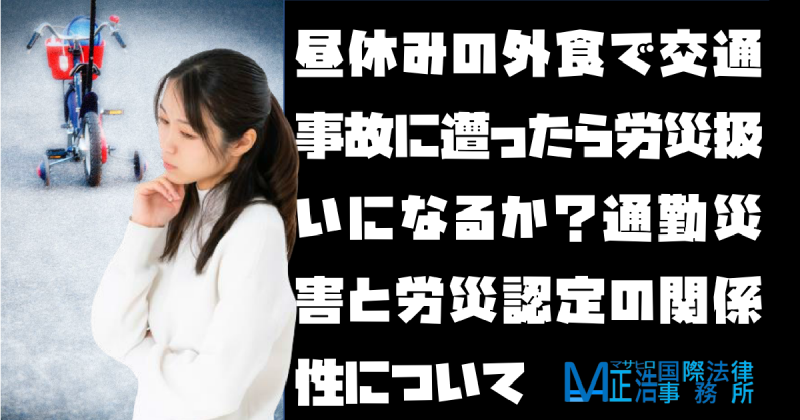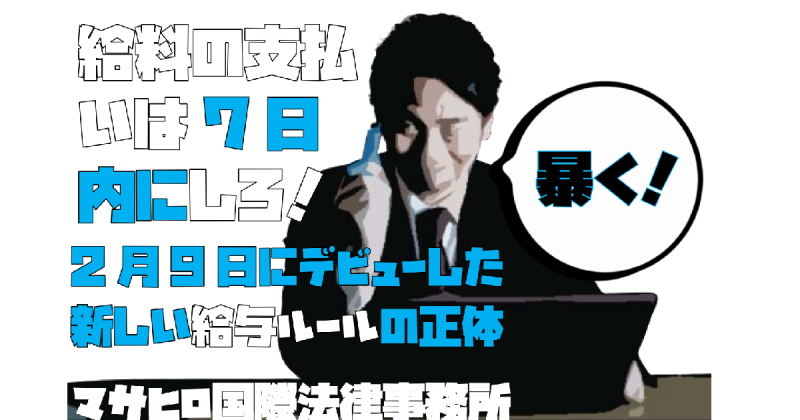従業員の行いで会社が損したら、その従業員に損害賠償を請求できるものなのか?
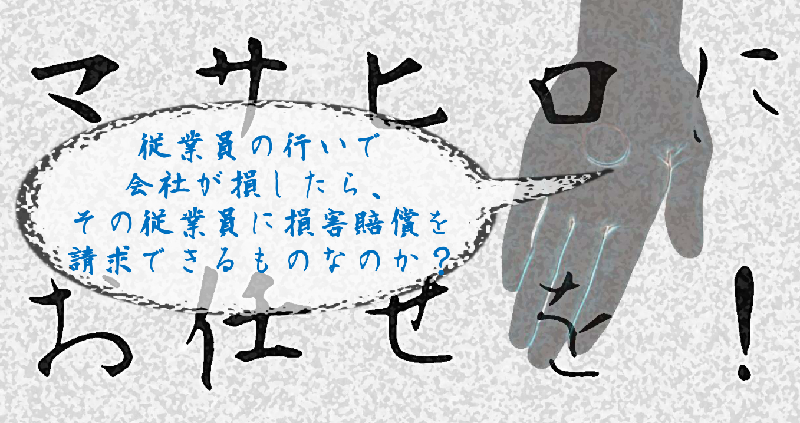
見込みのある従業員か、ぱっとしない従業員かを問わず、仕事上のミスや失敗はつきものです。ミスや失敗を恐れ、成長しないワンパータンな従業員になってしまったら元も子もないからです。
そのため、ミスや失敗があったたびに、会社がすぐ対象従業員をクビにしたり、降格・減給したりする処置は通常考えられません。
ただし、従業員が故意に不正行為を働いたり、法律に抵触する行いがあったりして、かつ当該行為や行いが会社に相当な損失をもたらしてしまったら、会社側になにかしらの対応がとられないと、社内の労務管理に多大な支障が出るだけでなく、コーポレートガバナンス的にも相当なマイナス影響を及ばしかねませんので、降格・減給はもちろん、懲戒解雇の実施もやむなしかもしれません。
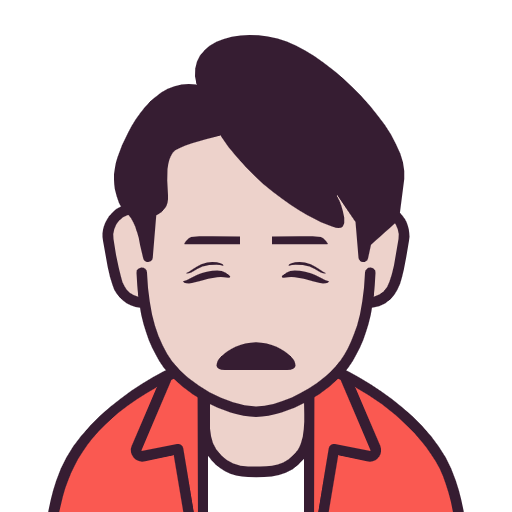
上記従業員による不正行為又は法律に抵触する行いが会社に与えた金銭的損失が数千万NTD規模に上ったほか、会社の社会的信用がそれによって失墜し、倒産まで追い込まれた場合には、労基法に付与された懲戒処分の権限とは別に、対象従業員に対して金銭的損害賠償を求めることも可能でしょうか。
ご存じの方も多いかと思いますが、2014年に廃油が食用の油に混入されていたという台湾全国を騒がせた社会事件が起きました。当事者のC社は2017年にすでに解散しましたが、事件当時から約9年が経った今でも損害賠償に関する裁判はまだ終わっていません。
2023年1月の後半、既に解散したC社から提起された元従業員に対する損害賠償の裁判について、最高裁から正式な判決結果が出ました。こちら一連の裁判を時系列で振り返って、裁判実務においては、会社が従業員に対する損害賠償請求のケースはどういった扱いになるかをみてみましょう。
事件の詳細
C社がわざわざ弁護士に頼んで訴訟を起こしてまで、3名の元従業員に損害賠償金を求める経緯について、原告のC社と被告のT氏、W氏、H氏が行った以下の主張でチェックしましょう。
C社の主張
- 副総経理を担当したT氏は、当社の検収基準に満たないのを知りつつも、ラード原料の調達は原則として事後承認という制度上の問題点を利用し、品質管理部課長であったW氏に検収データを偽造させました。それによって、当社が食用できない廃油を合格品又は特採品として闇工場を経営していたK氏から一度のみならず仕入れていました。
- また、品質管理部の監督業務を担当していたH氏は、T氏とW氏に上記社内ルールを違反した行為があったのをわかっていたのに、それを無視し続けたことで、当社が知らない間にたくさんの廃油を購入し、かつそれらをラードに加工したうえ、取引先に全部卸してしまいました。H氏は全く監督機能を発揮しておらず、業務放棄といっても過言ではありません。
- 以上3氏の行いによって、当社及び当社の代表は被害者から2,300万NTD弱の損害賠償金を請求されました。そのため、同3氏に合計1,000万NTDの損害賠償金を支払ってほしいと主張したいと思います。
T氏の主張
- C社の代表は原料調達の最終的決定権を握っており、廃油の購入は彼の指示があってこそのことでした。
- C社はK氏以外の2社からも廃油を購入していたから、K氏との取引にかかわっていた私に全責任を押し付けるのは不当です。
H氏の主張
- 私が担当していたのは製品の研究開発及びカスタマーサービスの業務であり、原料の調達又は検査は担当外なので、原料の検収で異常が認められたとしてもW氏からは共有されませんでした。
- 私が検査チェック表に署名したのは、カスタマーサービス業務を行おうと、出荷した製品の品質を確認する目的によるものでした。それのみで、私がK氏から廃油を調達する事実を確実に知っていた推論は成り立ちません。
- 当時、私はC社の代表とT氏に、K氏が経営する闇工場にて実地調査を行ったほうがよいと進言したが、相手にされませんでした。今更廃油事件の責任を私に押し付けるのはどうかなと。
W氏の主張
- 私の担当は品質管理業務であり、原料が調達先でどのように作られたのかを知るはずもなく、C社が仕入れた原料の品質チェックをきちんと行い、チェックの結果をT氏に報告すれば十分でしたし、検査で不合格だと分かった原料を受け入れるかを決定できる権限はありませんでした。ですから、C社が廃油を購入し続けていたのは私の責任ではありません。
- 私が提出した検査データからも品質問題がはっきりしていたのに、C社はそれを無視して廃油を購入していました。しかも、C社の代表とT氏は郭氏が闇工場を経営していたのを知りつつも、領収書を偽造してまで郭氏との取引を継続しており、彼らが法律を守ていれば、廃油事件は起こらないはずです。
- 2014年4月に行った原料の品質チェックは、一部の項目が不合格でしたので、T氏に報告したら、特採で受け入れろと言われ、処理シートに特採と記載し、別途実施した脂肪酸の構成に関する検査もOKの結果が出たため、追加で脂肪酸の構成に関する検査結果を記載しただけであって、文書を偽造したわけではありません。
結果、第一審を担当する裁判官がこう判断しました。
高雄地裁108年度重訴字第113号判決
- C社の代表は、原材料の仕入れ価格は普通1キロ当たり35~45NTDとの事実を熟知していたにもかかわらず、市場価格の約半分の値段、といういかにも胡散臭い価格で郭氏から購入することを決定したという。T氏から本件の調達稟議書の提出を受けた際に、何故その相場離れした値段を突っ込まずに、あっさりとそれに同意しサインしたのか?廃油だと分かった前提で、その取引を許可したとしか考えられない。
- 廃油の購入はC社の代表から同意を得てから実施したものなので、それに従うT氏に過失があったり、権限を逸脱したりするとは認めがたく、ましてや仕入れを決定する権限を持たないW氏とH氏に対して、C社への忠実義務をおろそかにしていたから、損害賠償の責任がある、との主張も成り立たない。

それなりの権限があるから、その分だけ弁償しろ!
第二審を担当する裁判官は、地裁の見解を一部否認する形でこう判決を下しました。
高雄高裁110年度重上字第62号判決
C社の社内ルールによると、調達金額が1,000万NTDを超えない場合は、T氏はC社の代表に報告しなくても、自ら決定できるから、廃油の特採は、C社の代表が許可する前にすでにT氏からOKサインが出ていた。
なお、T氏は一般社員としてC社で働くわけではなく、C社から委任を受けて副総経理という管理職に勤めていたから、C社の代表から明らかにC社が損する指示を受けたら、管理職としての善管注意義務を果たし、同代表にやんわりとアドバイスしてあげるべきであり、もしアドバイスを聞いてもらえなかったら、C社の監査役又は株主総会に報告する選択肢もあるはず。そうすると、代表も安易に廃油を購入できなくなるのであろう。従って、T氏がC社に損害賠償金として1,000万NTDを支払う義務があると考えられる。
一方、W氏とH氏が品質チェックの関連手続きを行う際に、廃油はすでに購入されたのであり、同2氏はただT氏の指示に従い書類の追加作成に協力させられていた。なお、同2氏はC社の代表とT氏に郭氏が経営する闇工場を監査するよう提言したものの、相手にされず、品質不合格な調査報告を彼らに提出しても、特採の決定がなされたのであった。従って、調達の実施について決定権を有さない同2氏にC社への損害賠償義務はないと判断。
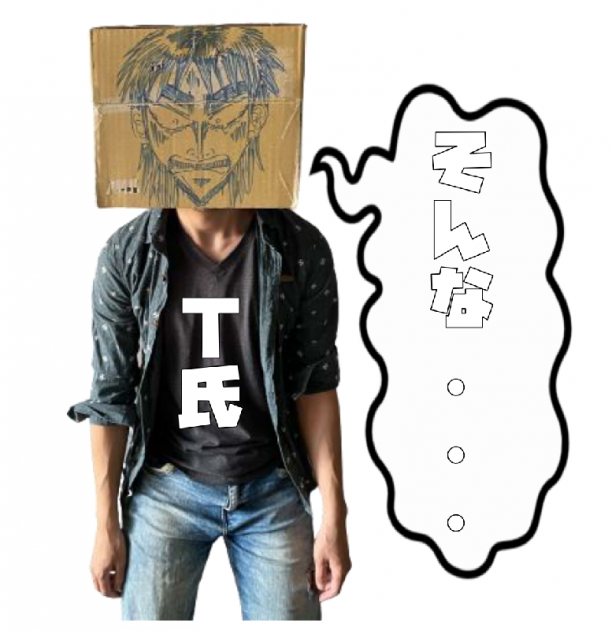
善管注意義務に役職は関係ない!
結局、本件元従業員に対する損害賠償事件が第三審まで継続していましたが、高裁が下した以下の判決で、決着がさらに持ち越されることとなりました。
111年度台上字第907号判決
- 仕入れた廃油の受け入れ手続きを完成させるための検査データの改ざんは、T氏から指示を受けたW氏が行ったものであり、それを知っていてもおかしくないH氏は無視を決め込んで職務を放棄し、善管注意義務を全く果たしていなかった。
- 果たして、W氏とH氏はT氏から命を受け、郭氏から廃油を調達することを隠す目的で、データを改ざんした事実があるかどうかは、C社が同2氏に対して損害賠償を請求する権利の有無につながるのに、高裁はそれを追及せず、ただ単に同2氏に調達の実施を決定する権限がないことにフォーカスしていたから、妥当性が欠けている。
- 一方、T氏は郭氏が販売するのは廃油だと知っておいても、特採でそれを購入するよう部下に指示しており、それによってC社に重たい損失を被らせていた。社内ルールをないがしろにし、管理職としての善管注意義務も果たしていなかったT氏は、C社に対して損害賠償責任があると認める。
- 以上により、W氏とH氏に対する判決を棄却し、高裁に差し戻す。

今週の学び
社内ルール又は法律に違反し、かつその情状が重大なのであれば、対象従業員を懲戒処分できる、というのは台湾の労基法から会社に付与される権利なので、比例の原則に反しない限り、問題なく実施できます。
一方、もし従業員のこういった違反行為や問題行為によって、会社側に看過できない損失をもたらしていたら、懲戒処分とは別に、対象従業員に金銭的損害賠償を求めることができるかと言えば、従業員の行為と損失が発生した原因との間にはっきりとした因果関係が存在するかによるところが大きく、裁判実務においても、この点が争点になるケースが多いです。
因果関係とは別に、今回共有させていただきました廃油事件に関する損害賠償の事例において、従業員が果たすべき「善管注意義務」という要素も考慮されることがわかりました。以下は今週の学びです。