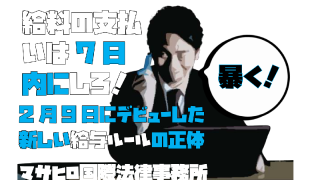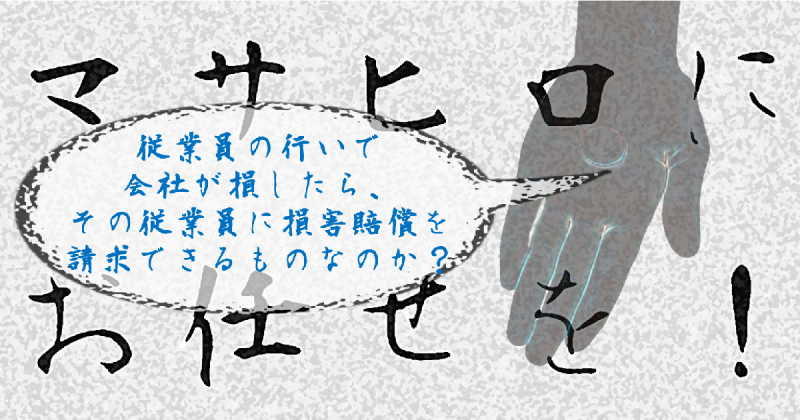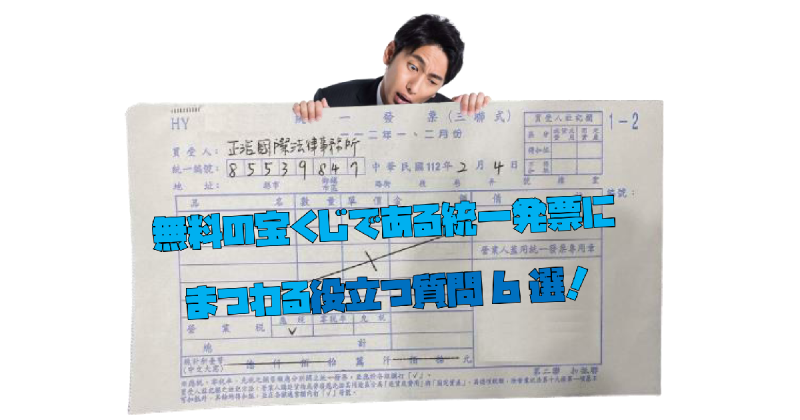給料の支払いは7日内にしろ!2月9日にデビューした新しい給与ルールの正体を暴く!
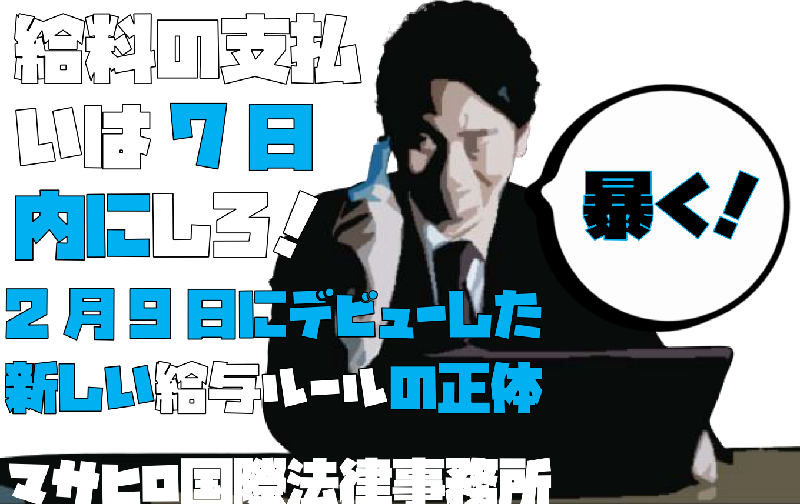
「7日内に」何とかしなければ、と聞いたら、「呪いを解く方法を探す」的な連想が頭をよぎったりするかもしれませんが、こういった1998年の時の話をいったん置いといて、今回共有させていただくのはホラーではなく、労働者への賃金支払いに関することです。
社員に支払う給料は1カ月2回以上が原則で(労基法第23条)、労使間の約定があっても、毎月少なくとも1回、かつ決まった日付に支払いを行わなけばなりませんが(労働條2字第1110140080号通達)、当該「決まった日付」の期限に関するルールは今までありませんでした。

30日間コツコツと仕事に励んでいるのに、翌月の25日になってようやく会社から先月分の給料をもらう。5日に家賃、6日にN〇tfl〇xの使用料、7日にインターネット料金、8日に水道光熱費、9日に保健所から引き取った犬への餌代を払わにゃあかんから、どうせなら早めに給料くれないかな。
のような嘆願書は会社に対するではなく、台湾の労働当局へは最近結構飛ばされていたようなので、その思いを何とかしなければ、労働当局の「労」が廃る恐れがあると考える台湾の労働部はついにアクションをとって、2月9日に「労使双方が約定する賃金支払日及び賃金支払いに関する指導原則」をリリースしました。
同指導原則の中身は何なのか、会社側にとって何か気を付けなければならないかなどの点について、蓋を開けてチェックしてみたいと思います。
賃金支払いの指導原則の主な内容
前述したとおり、会社の給料日が大変遅く、生活苦に陥った労働者からの苦情がたくさん殺到していることで、台湾の労働当局が国際公約を参考しながら、商工会議所や中小企業協会などとの話し合いで、今年の2月9日に「労使双方が約定する賃金支払日及び賃金支払いに関する指導原則」を公表し、即日施行されました。
当該指導原則の主な内容は以下です。
労使双方が約定する賃金支払日及び賃金支払いに関する指導原則
- 給料を支払う頻度は少なくとも1カ月に1回にしなければならない。
- 原則として締め日(給料の計算対象とする期間)の翌日から15日以内に給料を支払う必要があって、給料日がそれより遅い場合、行政指導が入る。
- 2026年末までに、雇用者数100名以上の会社は締め日の翌日から5日以内、雇用者数99名以下のの会社は締め日の翌日から7日以内に、従業員に給料を支払うこと。
- 超過勤務手当は原則として最近1回の給料日又は当月分の給料と一緒に支払う必要があり、労使間の合意があったとしても、支払い頻度は少なくとも1カ月に1回、遅くとも締め日翌日の15日以内で支払う必要。
- 特別賞与やボーナスの支払い日の設定に、合理性の有無は要チェック。
- 給料日が祝日・休日に当たったら、支払いを前倒しにすることは可能だが、会社が一方的に支払いを祝日・休日明けに後倒しにするのがNG。

賃金支払いの指導原則の罰則
結論を先に話すと、行政指導との位置づけである賃金支払いの指導原則には罰則が用意されないため、それを違反しても、原則として過料は食らいません。かといって、指導の内容を全く無視したら、場合によって労働法に違反したりする可能性もあります。
例えば、労働者本人から同意を得て、給料を2カ月に1回支払うケースについては、指導原則に定めた毎月1回の方針に反しましたが、罰則規定が設けられないので、お咎めなしでやり過ごせていけるかと思ったら、賃金支払いの頻度を1カ月に1回より低くした場合、労働者が定期的かつ即時に生活を維持できる報酬を得ることを確保するために作られた労基法第23条第1項の主旨に合わない(労働條2字第1110140080号通達)と認定され、2~30万NTDの過料を払わせるリスクが発生してまいります。
また、超過勤務手当は賃金じゃないので、給料日に支払う必要はなく、会社にとって都合のよいタイミングで支払ったらよい、的な社内ルールを実施する会社は、超過勤務手当は最近1回の給料日又は当月分の給料の支払い日に払うことを要求する、法的強制力がない指導原則の方針とも合致しませんが、いざ立ち入り検査に入られたら、超過勤務手当を支払わないとして、同じく2~30万NTDの過料処分を下される可能性があります。

賃金支払いに関する消滅時効のルール

今回新たに施行した指導原則に罰則がないから、それを真剣に相手にすることなく、自社の資金繰り次第で、必要に応じて給料の支払いを遅らせたり、残業代の計算をうやむやにしたり、社員の未使用の有給休暇を没収したりしても問題ないね。
という悪魔的な囁きがあちこち聞こえるかもしれません。しかし、前にも述べたとおり、指導原則自体に罰則規定はないが、一部労基法と重なるルールはペナルティがついているので、安易に無視してしまうと、相当な過料を支払わされることを覚悟せねばなりません。
また、労働者への賃金支払い義務は、政府に過料を払えば消えてなくなるものではなく、対象労働者に請求権がある限り、支払い義務はずっと会社に付きまとうわけなので、「過料を1回払ったら労働者へ支払わなくて済む」、との論理は成立しません。
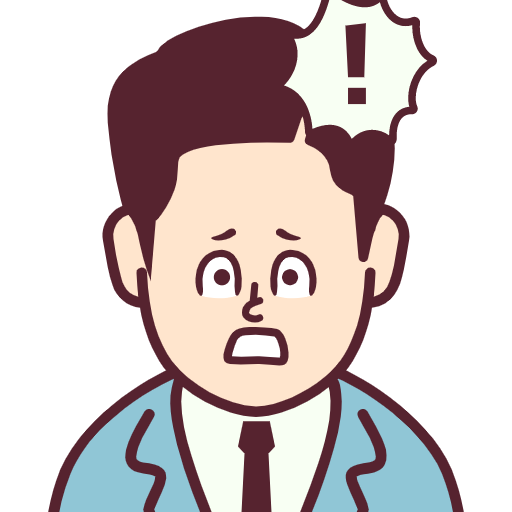
「対象労働者に請求権がある限り」って話について、例えば残業しても残業代が出ない場合、退職後においても、元いた会社に残業代を請求できるものなのか?
通常の金銭債権ですと、台湾においては、請求権が発生して15年経過したら時効になる(民法第125条)とされており、債権者(労働者)がこの期間内に債務者(会社)に請求しないと、債務者は消滅時効を援用し支払いの義務を免れることができます。ただし、労働者への支払いは、通常の給料のほか、退職金や社会保険による給付金、退職金など種類が多くあって、一律に15年間の時効が適用されるわけではないため、留意が必要です。
以下、労働者への支払いに関する時効年数の情報をもとめます。
労働者への支払いに関する時効年数
- 通常の給料、超過勤務手当:5年(民法第126条)
- 未使用有給休暇の買取賃金:5年(民法第126条)
- 解雇手当:15年(台労資二字第134376号解釈通達)
- 旧制度退職金:5年(労基法第58条)
- 労災補償金:2年(労基法第61条)
- 労工保険による各種給付金:5年(労工保険条例第30条)
- 失業給付金、育児休業給付金:2年(就業保険法第24条)
上記とは別に、会社に労働者への支払い義務を怠った事実が認められたら、労働当局は当該会社に対して行政処分を下す権限があり、権限を付与される期間は会社の違法事実が発生して3年以内とされています(行政罰法第27条)。
例えば、給料又は残業代などを会社から十分に支払われていない労働者が退職し、しばらく経ってから当該労働者が労働当局に当時の件を告発した場合、労働当局の調査で3年の時効になっていないとわかったら、当該会社には過料処分が下されます。そのため、実務的には、労使間のトラブルは対象者が退職して3年以内で起きるケースが多いわけです。

今週の学び
台湾は現在約54万社の企業があって、そのうちの98.6%が雇用者数99名以下の中小企業だそうです。比較的社員数を多く抱える製造業に関しては、2018年で退場した工場法により、大体早めの給料日を設定したり、1カ月に2回給料を支払ったりするので、今回新たに登場した指導原則の影響はあまり受けないのに対して、工場法の規制対象外であるサービス業は比較的遅い給料日を設定する傾向であり、会社の給料日が遅いから何とかしろと労働当局に訴えた労働者の多くはサービス業の従業員だといいます。
一方、台湾の労働当局が労働者の気持ちを汲んで、今回の指導原則をリリースしたことは評価されてしかるべきですが、罰則を同原則に導入していないから、一部の中小企業はそれを相手にしない可能性も考えられないわけでもないので、どうせやるなら、一度法改正を行い、労基法本文に指導原則の方針を組み入れるほうがより効果的なのではと、中途半端感はやはり拭えません。