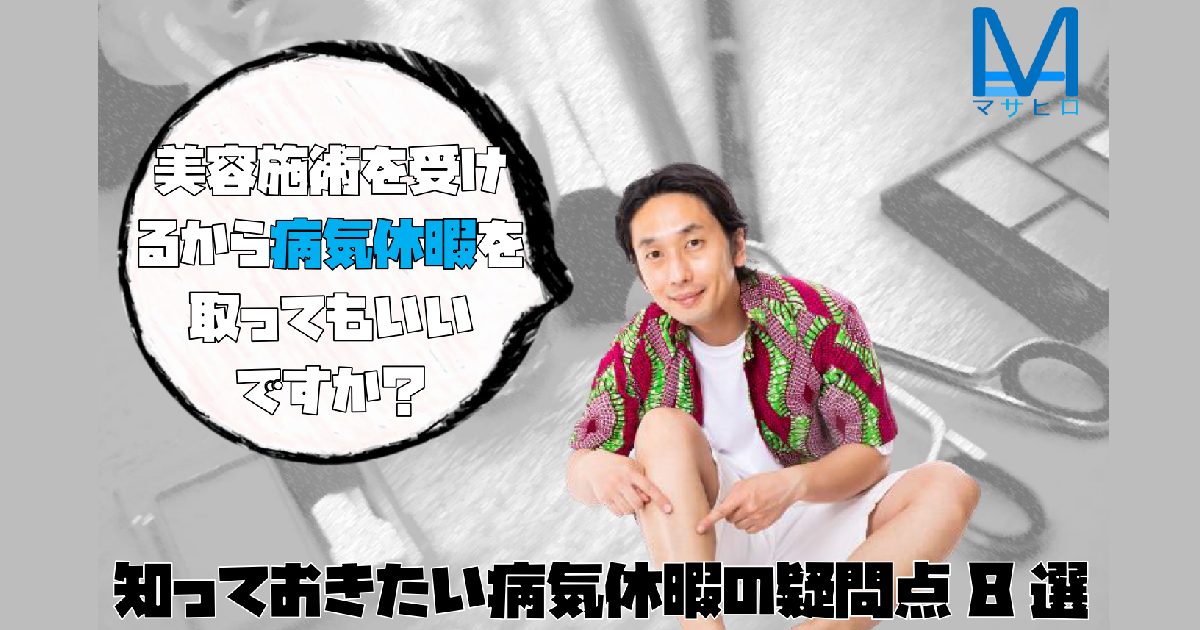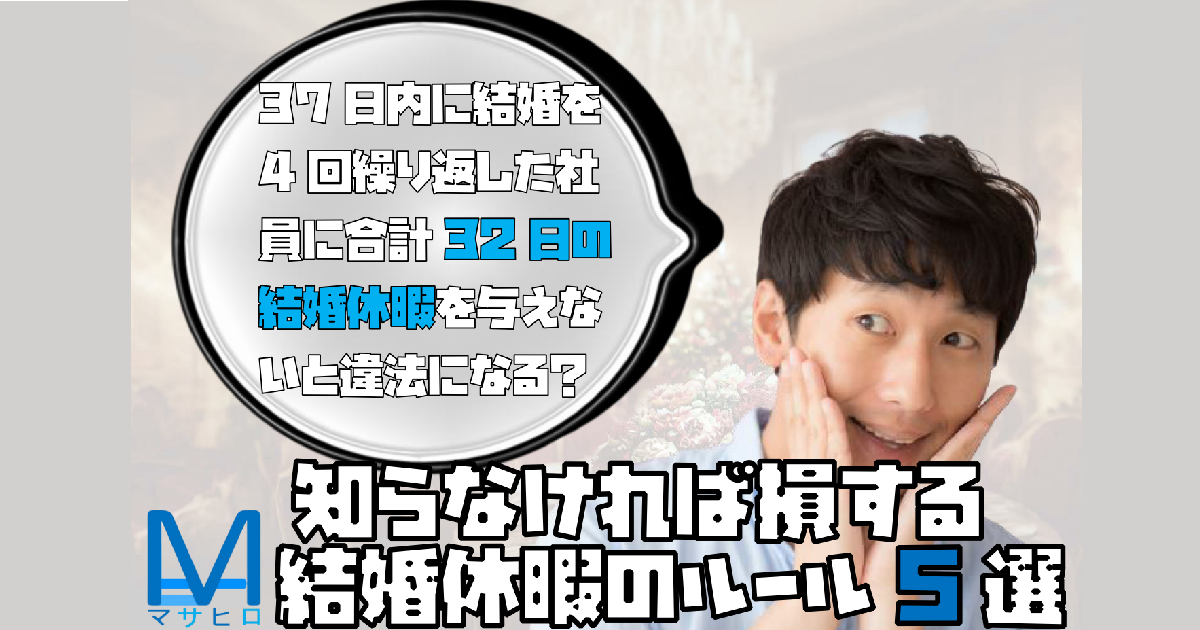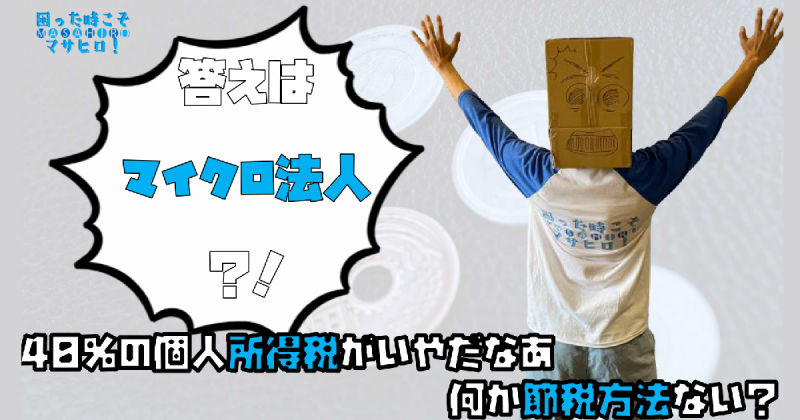「台湾では、流産でも8週間の出産休暇が取れるのですか?」―知られざる出産休暇に関する謎設定6選!

女性労働者が取得可能な出産休暇について、台湾の労働法は以下のように規定しています。
分娩(出産)前後の女性労働者に対して、就業を停止させるとともに、8週間の出産休暇を与えなければならない。女性労働者が妊娠3ヶ月以上で流産した場合に対しては、就業を停止させるとともに、4週間の出産休暇を与えなければならない。
また、関連法律では、出産休暇について以下の補足がなされています。
女性労働者が妊娠2ヶ月以上、3ヶ月未満で流産した場合に対しては、就業を停止させるとともに、1週間の出産休暇を与えなければならない。女性労働者が妊娠2ヶ月未満で流産した場合に対しては、就業を停止させるとともに、5日の出産休暇を与えなければならない。
流産は望むべくして起きたものではないため、働く女性の母性保護の観点で、会社が対象者に出産休暇を付与することを義務付けるのは至極当然の考え方です。そして、比例の原則を反映する形として、一律に4週間ではなく、妊娠期間に応じて5日から4週間の出産休暇が用意されているのも頷けます。
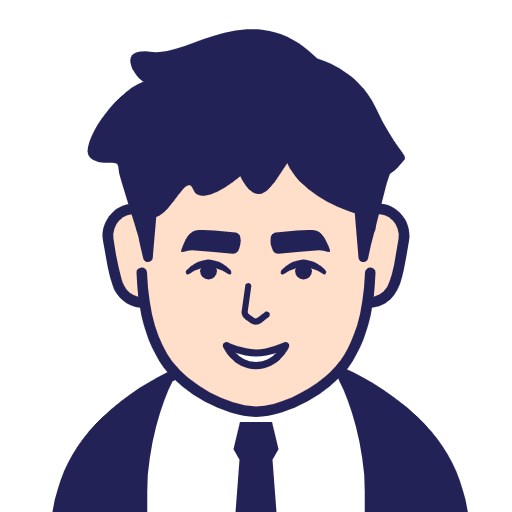
ボス、人事担当から、Aさんは流産のため8週間の出産休暇を申請したとの報告を受けました。休暇の許可をお願いします。
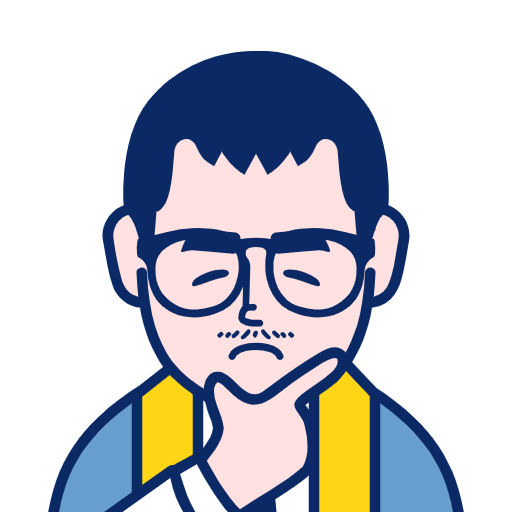
Aさんに、家の中でゆっくり休んで過ごしてください、と伝えてくれ。でも8週間ってなんかルールと違うような…
女性労働者の権利を守るとともに、労働法を徹底的に遵守する考え方としたら、上記のもやもや感をどう対処するかを含め、「出産休暇に関する謎設定6選」を以下解説致します!
目次
Q1:流産の場合でも8週間の出産休暇を付与すべきか?
前置きで説明したとおり、8週間の出産休暇を取得できるのは、「分娩(出産)前後の女性労働者」で、流産の場合、妊娠期間に応じて5日から4週間の出産休暇が付与される、との法律になっています。従って、就業規則または労働契約にて、最低基準を定める労働法よりよい条件が記載されていない限り、流産した女性労働者には多くとも4週間の出産休暇を与えれば問題ない、と理解されがちです。しかし、出産休暇には法律本文に書かれていない隠しルール的なものがあります。
出産休暇の法律における「分娩」と「流産」については、医学上の定義に則り、妊娠20週以上で胎児を産む場合を分娩、妊娠20週以下で胎児を産む場合を流産と定義づける。
以上労働部が発した通達によると、女性労働者が妊娠して20週目になったら、細かい区別なしで会社から8週間の出産休暇を取得する権利が付与されることが分かります。つまり、流産のタイミングが21週または23週など20週以上の場合、会社は対象者に8週間の出産休暇を与える義務があり、20週以下の場合、さらに満3ヶ月、満2ヶ月、2ヶ月未満などのケースに分けて、それぞれ法律の定めを下回らない日数の出産休暇を与えなければならないとされています。
妊娠した女性労働者が抱える体力的・心理的負担を考えたら、こちら医学上の定義を導入し、出産休暇の付与条件をより広く解釈する労働当局の通達にグッドボタンを押したい気持ちですが、労働法本文にではなく、存在感が比較的低い解釈通達にそれが定められたことで、企業間での浸透度がまだまだ低く、トラブルになったりしています。可能であれば、これからの労働法一部改正などで、20週ルールを本文に盛り込んでもらう方向で、当局に真剣に検討していただきたいものです。
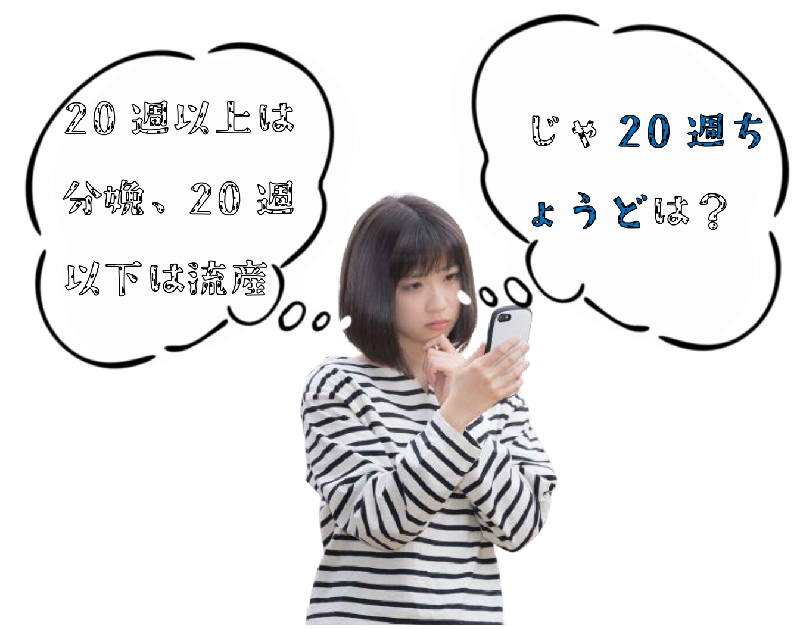
Q2:流産の場合で忌引休暇が取れるのか?
A社で働く女性労働者のB氏は、妊娠20週を過ぎましたが、母体保護のために、やむなしに人工流産を実施しました。手術が終了したB氏に、病院から胎児の死亡証明書を渡された後、胎児を荼毘に付しました。翌日、B氏は当該死亡証明書をA社に提出し、忌引休暇の申請を行いました。

B氏の心のケアを行おうと、上記の休暇申請を許可したいものだが、その他社員に対して公平性を維持する観点で、ルールを把握してから判断しようと思って、法律上の規定はどうなるのか?
台湾労働当局では、忌引休暇の取得に死亡証明書のあるなしはそれほど重要ではないほか、両親と子女との自然血族関係は出生により発生するとされているため、胎児が母体から離れた瞬間、独立して生存した事実が存在していなかったら、会社が対象社員に忌引休暇を付与する義務はない。
従って、B氏が行った忌引休暇の申請をA社が許可しなくても、違法に該当しない形になります。その代わりに、B氏はA社に対して8週間の出産休暇を申請する権利があります。
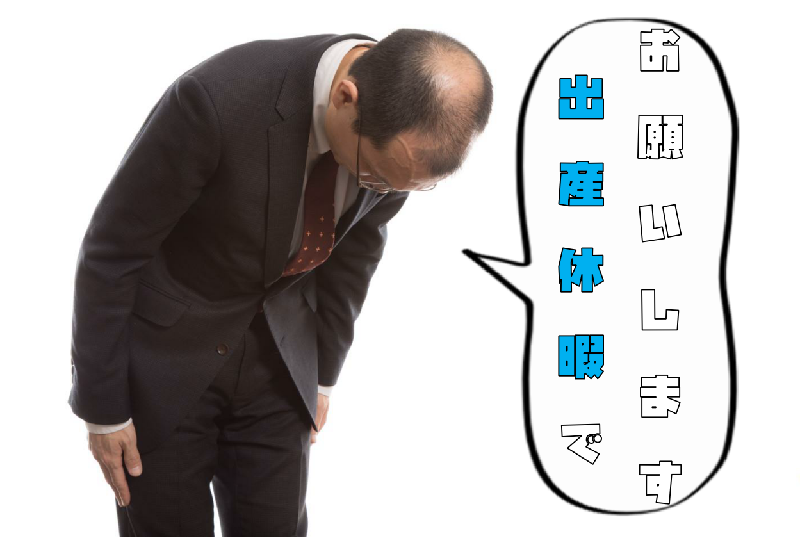
Q3:出産休暇は無給なのか?
台湾労働法の規定によっては、出産前後の女性労働者への8週間、妊娠3ヶ月以上で流産した女性労働者への4週間の出産休暇は、原則として有給なんですが、出産休暇が付与された時点で、対象者の勤続期間が6ヶ月未満の場合は、休暇期間中の給料を会社は半分のみ負担したらよいとされています(労働基準法第50条)。
一方、3ヶ月未満で流産した場合の1週間、及び妊娠2ヶ月未満で流産した場合の5日の出産休暇への給料の取り扱いに関しては、労働法ではそれについての言及がないため、会社は当該休暇期間中の給料を負担する義務はありません。しかし、こういった無給の出産休暇を取得した女性労働者に対しては、会社はそれを理由に皆勤手当を外したり、その他対象者にとって不利になる扱いをしてはならないともされています。留意が必要なのは、対象者は無給の出産休暇を申請する代わりに、病気休暇を申請し、かつ当該病気休暇は年間30日を超えない入院なしの病気休暇に該当するならば、会社は休暇期間中に対象者へ半分の給料を支払わなければなりません(労働三字第0910035173号通達)。
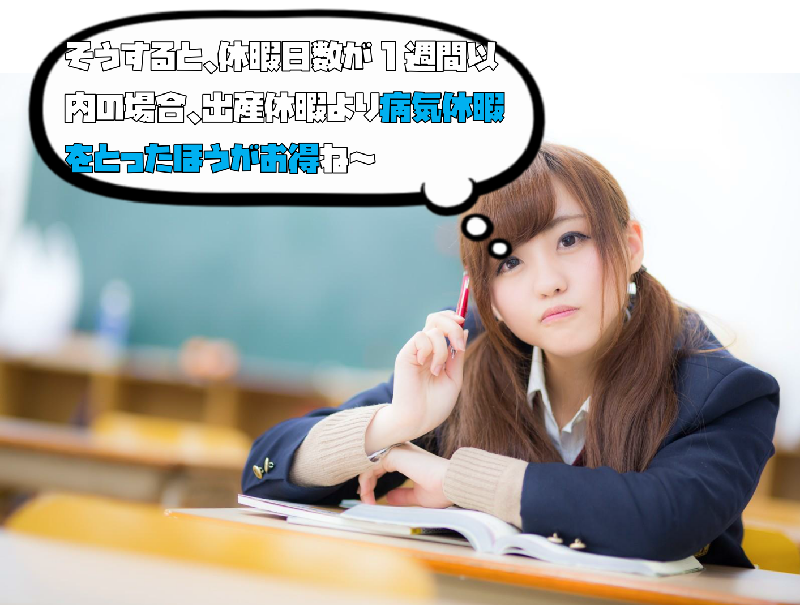
Q4:パートタイマーでも出産休暇が取れるのか?
パートタイマーも正社員と同じ労働者であり、台湾の労働法に定められた労働者の権利を享受することができるため、上記述べた要件を満たしたら、パートタイマーも出産休暇を取得可能とされています。
また、正社員と比べたら、パートタイマーの労働時間は比較的短く、全く一緒な休暇日数を与えたら公平性の問題が生じたりするので、年次有給休暇や結婚休暇、忌引休暇、病気休暇、自己都合休暇などの法定休暇は、会社はパートタイマーの実質的労働時間をもとに、比例計算した日数を対象者に与えれば問題ないとされていますが、母性保護の観点で、出産休暇は前述した比例計算の原則が適用されず、正社員もパートタイマーも5日~8週間の出産休暇を取得する権利があります(労働二字第22319号通達)。

Q5:出産休暇の日数計算に休日を外すべきか?
病気休暇の計算に、法定日数を超えなければ原則的に祝日・休日を外す必要があって、つまり休暇としてカウントされるのは出勤日のみとなっています。
一方、出産休暇の性質は病気休暇と違って、妊娠する女性労働者にしっかりと一定期間安静してもらうために作られた休暇制度なので、例えば、8週間または4週間の間に祝日・休日があったとしても、それらを外す必要はないとされています(労働三字第01425号通達)。この点は、年間最多〇日と定められたその他休暇とは異なり、出産休暇は原則として「週」単位で計算されるという特徴からも推測できましょう。
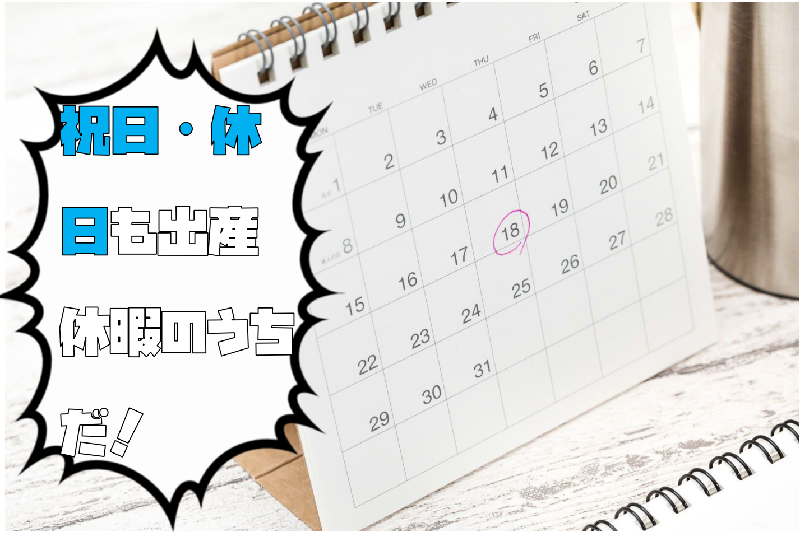
Q6:出産休暇は分割取得できるのか?
出産後のケアのみならず、出産直前~2ヶ月の間の母体の状況も大変重要なので、会社からの同意があれば、出産前のタイミングであっても、短日数の出産休暇を何回か取得したりすることも可能とされています(労働三字第000246号通達)。
こちらのポイントは、女性労働者が出産休暇の分割取得を希望する場合には、妊娠前の元の状態に戻る期間を確保する観点で、少なくとも4週間の休暇を出産後に取っておかなければならない点です(労働三字第0970063561号通達)。

今週の学び
台湾で悪化し続ける出生率を何とか助ける気持ちで、政府は近年において性別就労平等法その他労働法を矢継ぎ早に改正し、「出産助け」の活動を鋭意に取り組んでいる姿勢を見せています。
確かに、少子化問題がそれ以上深刻になっていくと、国の存続もが脅かされるわけなので、労働当局の心構えは評価すべきものであり、企業も社会的責任を果たし、母性保護に関する法的義務に尽力する義務がありますが、この辺、法律の設定に不明確な点はまだまだ少なくないようで、労使間でのトラブル事件がちょくちょく発生したりするのは少々残念に思います。お困りの際は、是非気軽にマサヒロへご相談してみてください。