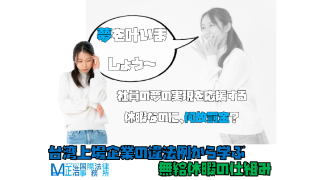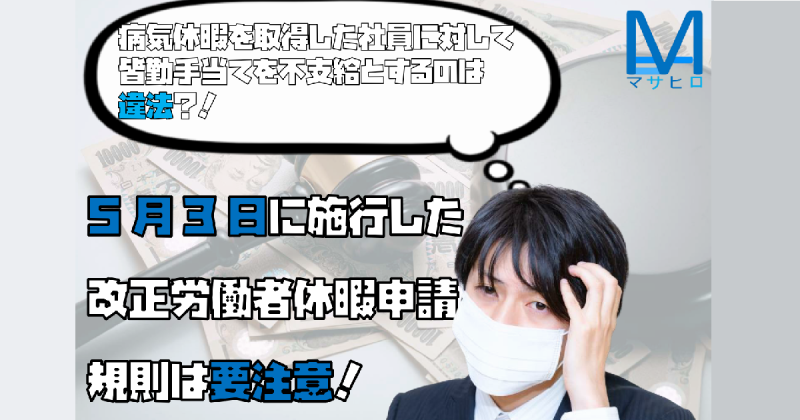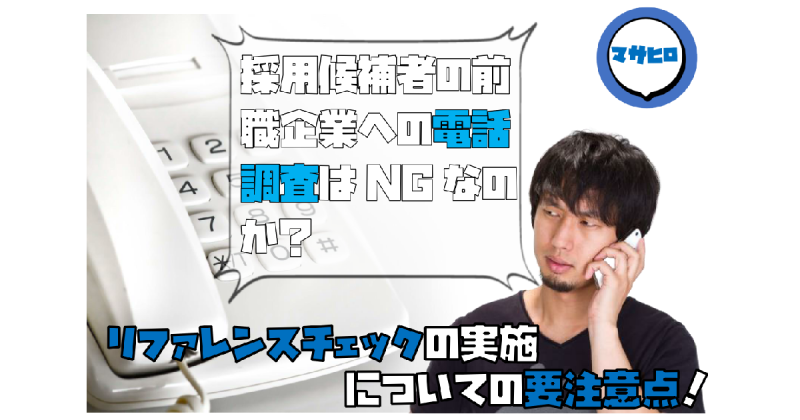「社員の夢の実現を応援する休暇なのに、何故罰金?」―台湾上場企業の違法例から学ぶ無給休暇の仕組み

台湾のプリント基板大手のユニマイクロン・テクノロジー社はこの間、受注大幅減などの原因で、従業員に夢を実現するための休暇(円夢休暇)の申請を要求し、内部のタレコミなどで労働当局から立ち入り検査がなされており、それによって同社に2万~100万NTDの過料処分が下されたと報じられています。
同社によると、従業員の間では里帰りしたり、今までやり遂げなかったことを海外で実現したりする希望者が少なからず、これらの目的を達成するにはそれなりの休暇日数が必要なわけなので、今回のスペシャル休暇はまさにそれの手助けになるのだそうです。
ユニマイクロン・テクノロジー社の説明にちょっとした説得力も感じますが、何故過料を払わされるのか、について、台湾におけるいわゆる「無給休暇」という制度を改めて確認しながら、本件の違法性探ってみましょう!
目次
無給休暇とは?
「無給休暇」というのは、台湾の労働法に定められた制度でもなければ、完全に「無給」であるわけでもありません。無給休暇の取り扱いに関する違反事例は、大体会社が言葉通りにそれを解釈し、対象者への給与支払いをピタッと止めることが原因のようです。
台湾労働当局の定めによれば、会社は経済要因などによって操業を停止したり、減産したりする場合、労使合意があれば、一時的に就業時間を短縮し、賃金を減額することができるが、毎月対象者に支払う給与は最低賃金を下回ってはいけないとされています(労働2字第0970130987号通達)。こちらの定めは、まさに「無給休暇」と一般的に呼ばれる制度の法的根拠となります。
そして、「毎月対象者に支払う給与は最低賃金を下回ってはいけない」との内容から察するに、同制度は完全に無給というわけではなく、対象者に対しては、月次の就業日数がどれだけ短縮されたかを問わず、少なくとも法律に定められた最低賃金を支払わなければならない義務は会社にあることが分かります。
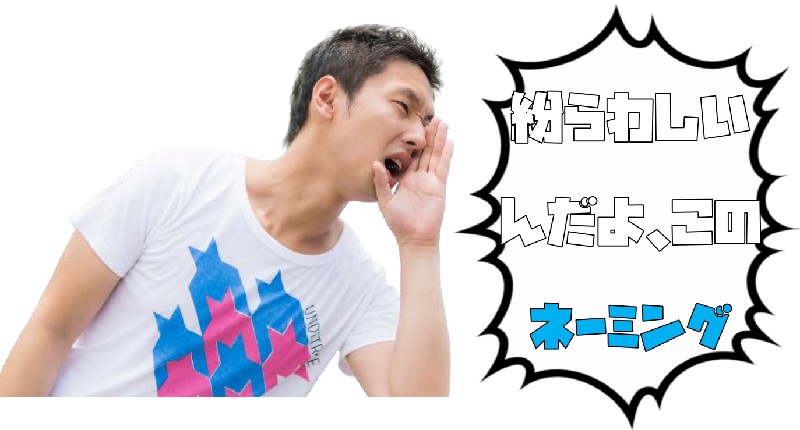
無給休暇の実施要件
無給休暇というのは、昇給や昇格のように、会社が何時でも、無制限的に行えるような代物ではなく、いくつか厳しい要件を満たしてはじめて実施できる制度とされているため、アクションを取る前に、それらの要件を悉く達成されたか丁寧に確認しておく必要があります。
無給休暇の実施でクリアすべき要件を以下のように整理しました。
- 市況の影響による操業停止または減産の事実があること
- 会社の代表・役員・支配人その他管理職へのボーナス又は福利厚生をカットするのを先に検討すべきこと
- 対象者個人から書面による同意を得ること
- 対象者に支払う給料が最低賃金を下回らないこと
- 無給休暇の実施期間は原則として3ヶ月を超えないこと
- 管轄の労働当局に届け出すること
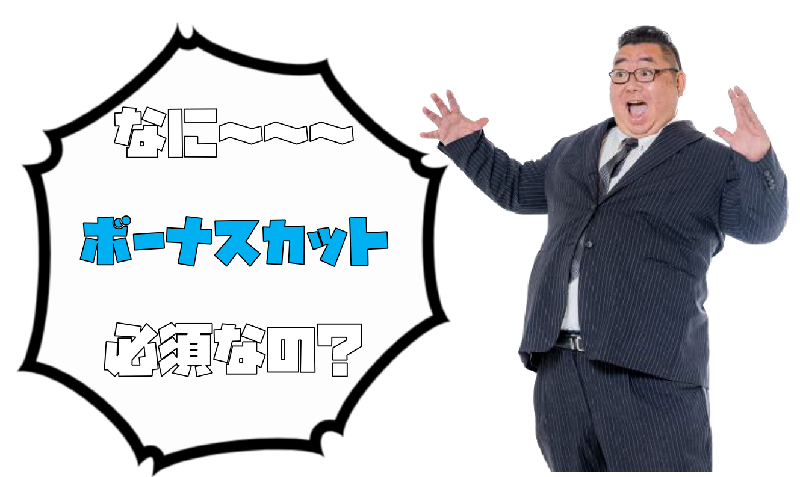
無給休暇の実施に必ず対象者個人から同意を得らなければならないのか?
労働組合がある会社はもとより、労働組合がない会社も法律に基づいて、少なくても3ヶ月に1回の労使会議を開催しなければなりません(労使会議実施弁法第18条)。

どうせ労働者代表が参加する上記の会議を開催する義務があるから、無給休暇の実施でいちいち個別の社員から了承をもらうより、会社は上記の会議で実施許可をまとめてとるほうが効率よいだね!
のように考えている会社は少なくないようです。
しかしながら、無給休暇の実施で、会社からもらえる給料が減少するのは対象者本人であり、組合または労使会議の労働者代表ではないので、法律上、会社は対象者本人から同意を取得しなければ、無給休暇を実施できない形となります(労働2字第0980070071号通達)。
また、無給休暇の実施に関する面談を行う際に、対象者本人は反対の意志表示がなく、ただ沈黙を守り通すようであれば、会社はそれを「実施への同意」と受け取ってはならず(労働2字第0980130120号通達)、きちんと同人と合意書を交わす必要があるとされています(景気の影響による就業時間の短縮に関する労使間協議における要注意事項第9条)。
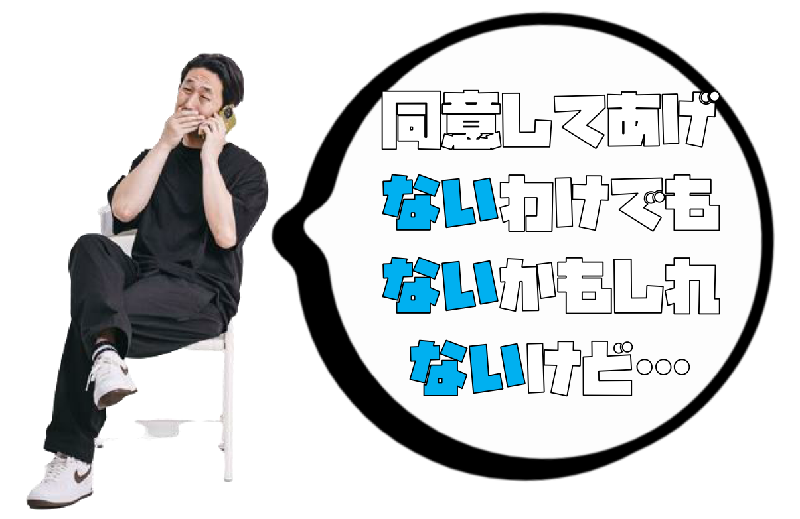
会社が一方的に無給休暇を実施したらどうなるか?
会社は対象者本人の同意をゲットしていない、もしくはその他前述した法定要件をクリアしていないにもかかわらず、無給休暇を実施してしまうと、賃金全額払の原則に反するとして、2万~100万NTDの過料処分が下されます(労働基準法第79条)。
上記過料処分のほか、無給休暇の実施を会社から一方的に命じられている対象者本人は、会社に対して通常通りの給料を支払うよう請求可能とともに、労働契約に定めた条件のとおりに賃金を支払わないとして、予告なしで会社との労働契約を打ち切り、別途解雇手当を請求することもできるとされています(労働基準法第14条)。

当局の許可なしでは無給休暇実施不可?
無給休暇の実施に、事前に対象者本人から同意を得ることが前提条件となっています。それとは別に、「管轄の労働当局に届け出すること」も必要な手続きとして関連法律に定められています。では、対象者本人と労働当局の両方から事前に了承をもらわないと、無給休暇を合法的に実施できないかと言えば、そうではありません。
労働当局の説明では、無給休暇の実施は早くとも、会社が対象者本人と合意書を交わした当日からスタート可能となり、届け出の手続きはそれから行ったらよいが、当該合意書の内容に法律に反する条件ないか、できるだけ早くそれをはっきりさせる観点で、なるはやで届け出を行うよう、とのことです。
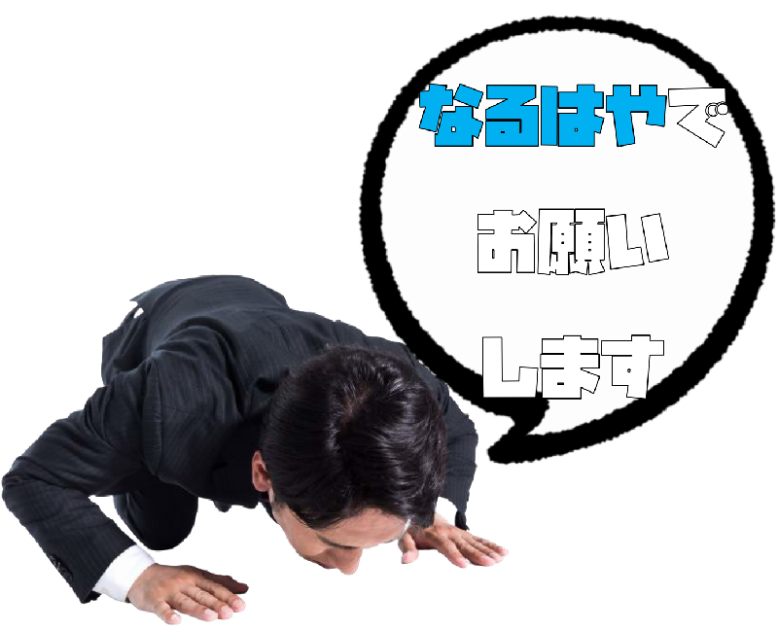
無給休暇の実施に無限ループに陥るリスクあるか?
前に説明したように、「無給休暇の実施期間は原則として3ヶ月を超えないこと」が実施要件として定められており、初回から2~3年という長めの実施期間を設定することはできない形となっています。
一方、3ヶ月間の無給休暇が終わろうとするが、無給休暇を実施する当初に起きた会社を苦しめていた問題点がなお改善されていなかった場合、再度対象者本人から同意が得られれば、無給休暇の実施期間を延長することが可能です(景気の影響による就業時間の短縮に関する労使間協議における要注意事項第8条)。
上記のように、無給休暇の実施期間を延長するためには、労使双方の合意が必要であり、いずれか一方から反対の意志表示がなされたら成立しないわけなので、無給休暇が回転ずしのように無限にループする可能性は極めて小さいと思われます。

無給休暇実施期間中の社会保険料と退職金はどうなる?
対象となる労働者は、無給休暇の実施期間中に会社から受領する給料は減少したが、会社は法律に基づき積み立てを行っている退職金は、無給休暇実施前の水準に則り、積み立てを継続しなければならない、つまり、無給休暇の対象にされるかどうかにかかわらず、労働者が退職金制度における権利は一切変わりません。
一方、退職金とは違い、労工保険及び健康保険などの社会保険については、会社は無給休暇期間中の賃金額に基づき、対象者の保険の加入等級を調整することもできれば、無給休暇実施前の等級で保険を加入させ続けることも可能とされ、退職金より自由度が高いが、無給休暇の実施を理由に、対象者が加入している社会保険を脱退してはなりません。

対象者は無給休暇実施期間中に兼業可能?
無給休暇は会社都合によって実施されるものであり、対象となる労働者もそれによって手持ちの給料が減ったわけなので、責任のない労働者がそのせいで生活が困窮に陥ったらおかしい、との観点で、労働当局は、会社との労働契約に兼業禁止の定めがあってもなくても、対象者は無給休暇実施期間中に兼業を行うことは可能である、との見解を示しました。ただし、兼業は可能とはいえ、対象者は会社が定めた協業避止義務と秘密保持義務を引き続き遵守する義務があり、バイト先が明らかに競合他社に該当すれば、さすがにNGだ、との補足説明もなされています。
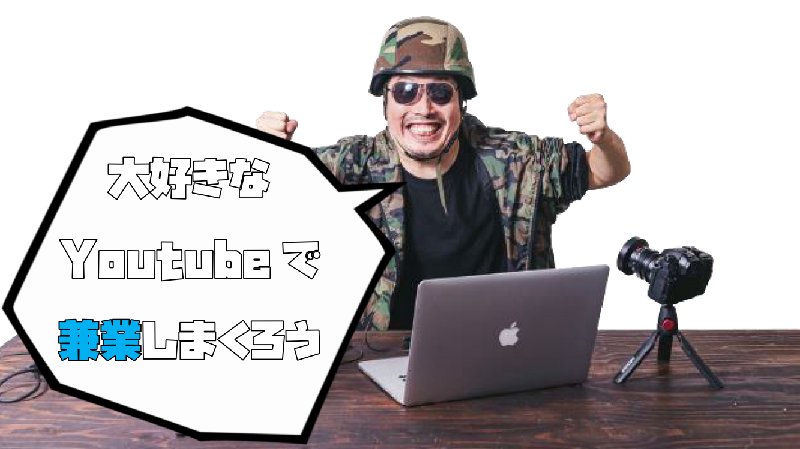
今週の学び
以上のように、無給休暇の仕組みについて一通り考察してまいりました。では、冒頭でのユニマイクロン・テクノロジー社の事例に立ち戻りましょう。
桃園市政府労働局がリリースしたニュースレターによると、同社は今年3月から、いわゆる「社員の夢の実現を応援する休暇」を実施しており、休暇の実施期間中に対象となる労働者へは賃金を支払ていないとして、労基法その他法律に反するほか、残業代の未払いも認められたため、それぞれの違法行為に対して2万~100万NTDの過料処分を下すといいます。
台湾マスメディアの報道では、受注の大幅減なら、無給休暇を実施すべきなのにもかかわらず、会社は「社員の夢の実現を応援する休暇」という名義の「休業」を社員に取得させようと強引に勧めており、乗り出る社員がなかなかいなかったから、くじ引きで強制参加との手法まで使ってしまった、という内部からのリーク情報がありました。
休暇の実施に労働者からの同意が得られていない、休暇実施期間中において賃金も一切支払われていない、といった点は法律上完全にNGなので、ペナルティを食らってもしょうがないとしか言いようがありませんね。