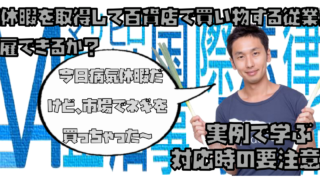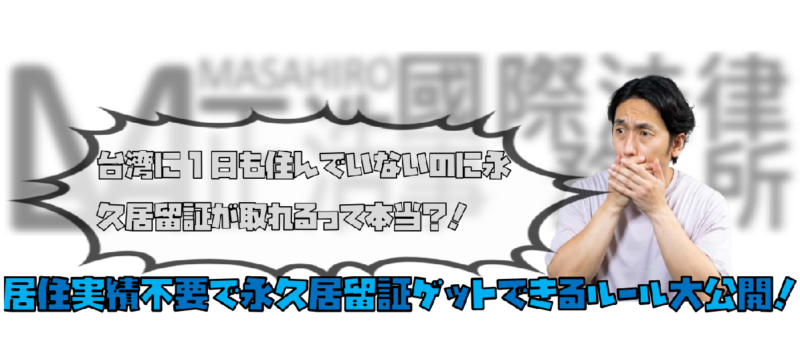病気休暇を取得して百貨店で買い物する従業員を解雇できるか?実例で学ぶ対応時の要注意点
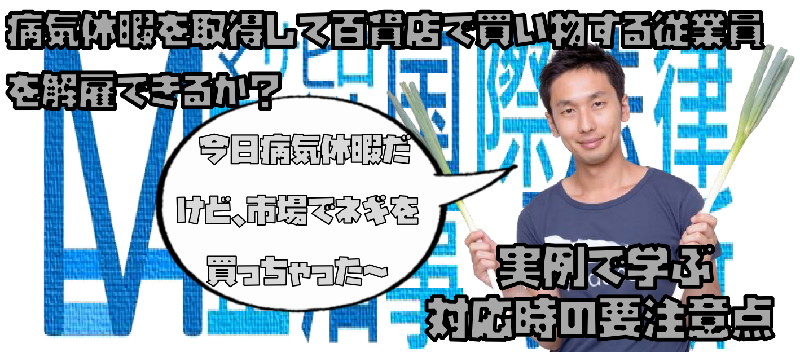
最近、以下のようなご相談をたまに受けています。

うちの従業員に、休暇を取りすぎるやつがいて、全然やる気を感じないのに、自主退職を申し出る気配もない。そいつをすぐ解雇したら法律上大丈夫なのか?
休暇の取得は、労働法に守られている労働者の権利なので、原則として「休暇を取った」ことを理由に解雇を行うことはできません。なので、問題は「休暇を取りすぎる」点にあります。
何をもって、「従業員が休暇を取りすぎる」と言えるかというと、法律上、それに関するはっきりとした判断基準が存在しておらず、社内規程を考慮し、ケースバイケースにチェックする必要があるため、実務的に結構トラブったりしています。
R氏という労働者が2016年の間に、各種休暇合わせて、1年の間C社から94日の休暇を取得していました。担当業務を遂行する意志が乏しいと判断したC社はR氏を解雇した後、不当解雇でR氏から訴えられました。訴訟が進行するにつれて、R氏がダイエットの治療を受けたり、映画鑑賞を行ったり、デパートでショッピングを楽しんだりすることで休暇を過ごした事実が判明しました。
上記の事例をもとに、「休暇を取りすぎる」ことと、病気休暇を取って娯楽活動を行った従業員を解雇可能か問題を取り上げ、不当解雇にならないよう、会社は事前にどういった手続きを実施必要かについて考察してみたいと思います。
目次
社員の休暇申請に、会社は不許可にできるのか?
R氏の2016年での休暇日数は94日に達しており、仕事をさぼる気満々なので、担当業務を遂行する意志が認められないとして、解雇を実施したとC社が主張しました。

R氏は94日間も欠勤したわけではなく、社内規程に従い申請手続きを行い休暇を取ったわけなので、休暇日数が明らかに多すぎるなのにもかかわらず、それでも休暇申請を許可してあげたC社にも何らかの問題があるのでは?
との突っ込みを入れたくなるかもしれません。
労基法に定めた年次有給休暇については、それをいつ取るかは原則として労働者本人の自由であり、よほどなことがない限り、会社がそれを不許可にすることはできません(労働基準法第38条)。
また、R氏が頻繁に取得していた病気休暇及び私用休暇についても、会社は必要に応じて、労働者に証明書類の提出を命じることができるが(労働者休暇申請規則第10条)、社内都合で当該休暇申請を不許可にする法的権限も与えられていません。
そのため、いくら年間94日の休暇日数に大変疑問を感じて、「取りすぎやろ」と心の中で何回もツッコミを入れたい気持ちがあったとしても、C社はそれのみを理由に、R氏の休暇申請を拒否できない形になっています。

休暇を取りすぎる社員に、会社はどう反応したらよいのか?
R氏は、自らの在職期間中、休暇の申請はキチンとC社の内部規程に則って行っており、かつ休暇の取りすぎでC社から懲戒処分が下されたこともなかったので、C社がいきなりそれを理由に解雇を実施したことが不適切であると主張しました。
C社が提出した記録によると、R氏が休暇を取得したタイミングは、大体大型連休の前後、又は仕事が忙しくなる時期に集中しており、そのせいで、C社はもともと有給休暇の取得を予定しているその他従業員に相談し、一旦有給休暇をキャンセルして、R氏の仕事を手伝うよう協力してもらわなければならなくなるため、問題の改善を促す目的で、C社は今まで16回もR氏と面談し、厳重注意も何回か行ったが、R氏は一向に改善しようとしないのみならず、休暇日数が増える一方であることがわかりました。
不当解雇の案件について、会社が不利な立場に立たされる主な理由は、非常に労働者寄りの観点で作られた労働法を置いといて、大体は書面による証拠が不足し、もしくは完全に欠如している点です。
労働裁判においては、会社側に比較的重い立証責任が課されています。会社が行ったいかなる判断も法律に違反していないことを証明するためには、対象労働者との面談記録、対象労働者に対する人事評価の記録を丁寧に作成し、そして同人にきちんとそれらの内容を共有することが望ましいです。
「もう解雇するしかない」、と会社が決定してから、急いで適当な人事評価を作成して、対象労働者に5分ぐらい一方的な話しを聞かせた後、「お前はクビだ」と言い放って、雇用関係を終了する、のようなやり方は、昭和時代ならまだしも、以前と比べ物にならないほど労働者意識が高くなった今では、非常にリスクが高いのです。
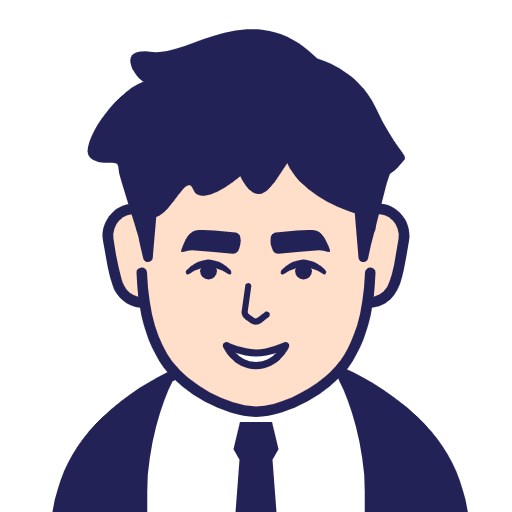
R氏を解雇するのに、前後合わせて16回も面談を行い、記録をこまめに作ったC社は、なんかえらい忍耐力の強い、時間のかかる作業も惜しまない会社だな。
との印象が持たれがちだが、まさにこういった塵も積もれば山となる的な事前準備のおかげで、R氏が起こした不当解雇の裁判に優位性が保たれるわけです。
ちなみに、面談記録のような文書的証拠のほか、面談に参加した第三者の従業員が行った証言、会話の録音なども活用可能な立証材料となりえます。
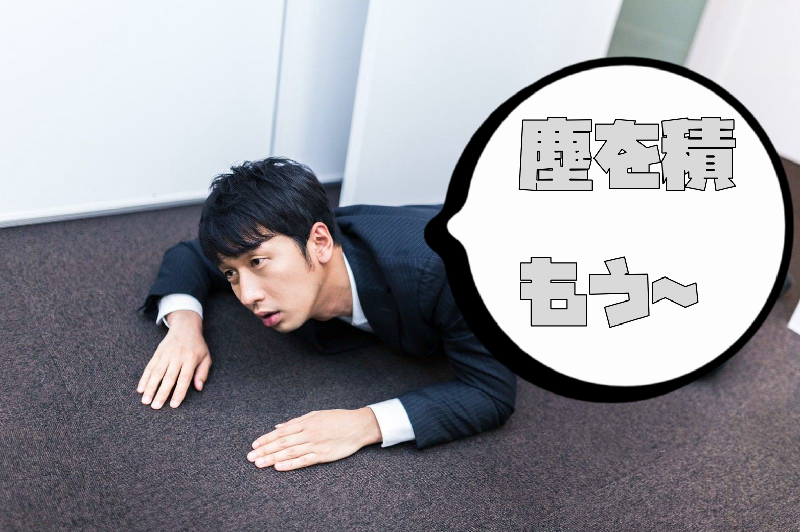
最後的手段の原則が守られているのか?
C社は、「労働者は自らの担当業務を確かに遂行できない」という法定事由をもって、R氏を解雇しました(労働基準法第11条)。この法定事由は、実務的に利用される頻度は非常に高いだが、それを利用する合理性の有無もよく突っ込まれています。
本案件の審理を担当する高裁の裁判官は、もしR氏が自らの担当業務をこなせないなら、配置転換などでその他部署の業務をやらせることができないのか、つまり解雇を実施する代わりに、別の代替手段は果たして存在していなかったのか、とC社に質問しました。
裁判官が上記の質問をC社に投げる主旨は、C社がR氏を解雇する前に、できるだけの企業努力を尽くしたのかを確認するためです。配転や降格、減給その他懲戒処分を行うことで、対象労働者に問題点の改善を促したにもかかわらず、改善の兆しはちっとも見せてくれなかったら、ほかに当該労働者との雇用関係をつなぎとめる手段も存在しない、いわゆる「万策尽きた」状態においては、会社がやむなしに解雇を実施する、という流れは、合法的な解雇に求められる要素です。この要素を専門用語で表現すれば、「最後的手段の原則」になります。この原則が守られるかどうかは、往々にして勝訴と敗訴の分かれ目にもなりえます。
話しが戻るが、裁判官から配転の可能性について聞かれたC社は、R氏が担当する業務はその他部署のより全然楽だし、社内のシフトも1ヶ月前もって公表したにもかかわらず、R氏はいつもギリギリなタイミングで休暇申請を出していたから、配転レベルで解決できる問題じゃないと主張しました。証拠品としてC社から提出された2桁回の面談記録を見て、裁判官もC社の言い分を受け入れたようです。

病気休暇を取得して百貨店で買い物したら、解雇されてしかるべき?
「社員の休暇申請に、会社は不許可にできるのか?」の段落にて、休暇を取る法的事由さえ充足されれば、会社は原則として労働者が出した休暇申請を拒否できない、と説明しました。ただし、これはあくまでも「法的事由が充足されれば」を前提とする話です。
R氏が1年の間に取得した94日の休暇のうち、病気休暇や家庭介護休暇が占める割合がそこそこ高くて、休暇を申請する理由は、長期疾患に悩まされる母親の面倒を見たり、風邪や筋肉痛があったりするなどまちまちでした。しかしながら、C社が事後行った調査で、なんとR氏は休暇日を利用して、百貨店でショッピングしたり、映画鑑賞を楽しんだりするなど、娯楽に興じる日数は、94日の休暇日のうち70日以上もあった、という驚異的な事実を発見してしまいました。
母親の面倒を見るために会社から休暇を取ったのに、母親に付き添うのではなく、電気屋で家電を買う、筋肉痛を覚えて休暇を取ったにもかかわらず、ショッピングモールで個人用品を購入する、といったR氏の行いを看過できないC社は、16回に及ぶ面談を実施し、何度も何度も改善の機会をR氏に与え続けたが、休暇日数が減ることはありませんでした。
適当な理由をでっちあげ、いやな業務から逃れる行為を繰り返し行ってきたR氏に対して、もしC社は改善の機会を全く与えず、一方的に解雇処分を言い渡したら、不当解雇と認定される可能性が生じるかもしれないが、C社は16回も問題行為を指摘し、反省のチャンスをあげていたが、R氏はそれらを相手にしていませんでした。このような状態においては、C社とR氏の間にいかなる信頼関係を求めるのは無理な話しで、会社を騙すまで休暇を取り続けようとするR氏に、C社が安心して仕事を任せるとも考えられません。結果、C社が行った解雇手続きには最後的手段の原則が守られたとして、違法性が認められないとの司法判断がなされました。

今週の学び
今回共有した、従業員がショッピングなどの目的で、1年の間に94日の休暇を取った民間企業の事例について、「これは極端な事例だね」、との感想を持つかもしれないが、実はこれ以上えぐいケースは公的機関においてごく普通に起きているようです。
ニュースで報じられた内容だが、とある税務調査官は2017年からの4年間、合計701日の休暇をとったにもかかわらず、休暇期間中に約105万NTDの手当をもらったケースもしかり、某市役所の公務員は、勤務時間中に救急車を呼んで、無断で職場を離脱した回数が6ヶ月の間計12回にも及んで、そして年間104日の休暇を取得した記録を残しながら、四六時中にパワハラの被害を上司に訴えたなど、まるでマンガでしか存在しない事例もありました。解雇というコンセプトがない、制度上ほぼ終身雇用の公的機関も大変だなと。
こういったどうしようもない労働者を雇用してしまうリスクが完全になくならない以上、如何に自社の人事・労務管理に関する内部統制をしっかり整い、有事の際にすかさず最適な対応措置をとっていくかは非常に重要です。今回の事例に登場した、法的に認められる対処法を参考にしていただき、必要に応じていつでもマサヒロにご相談ください。