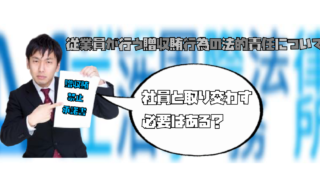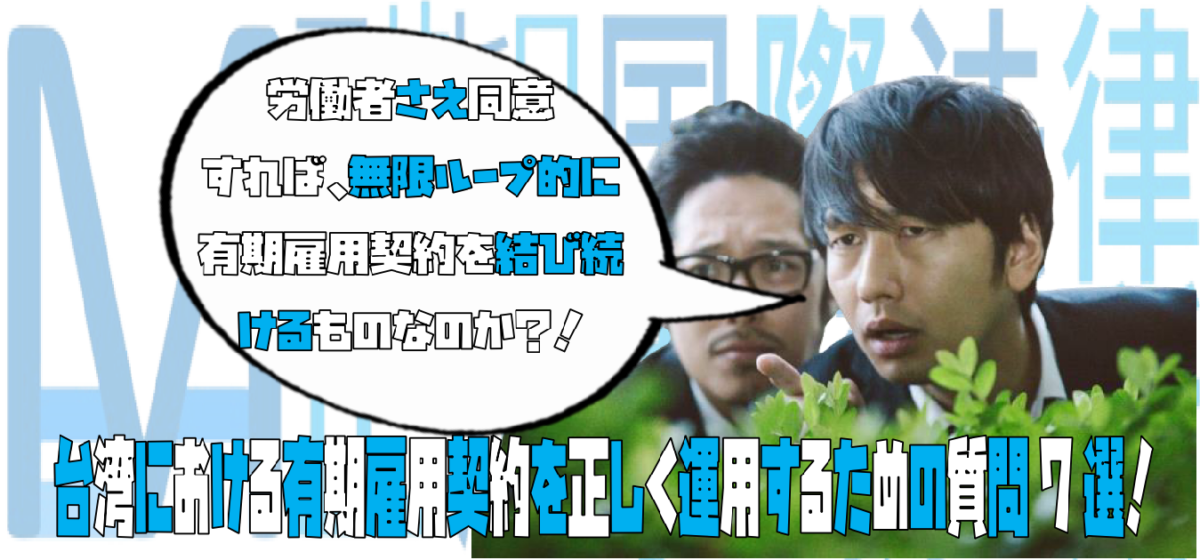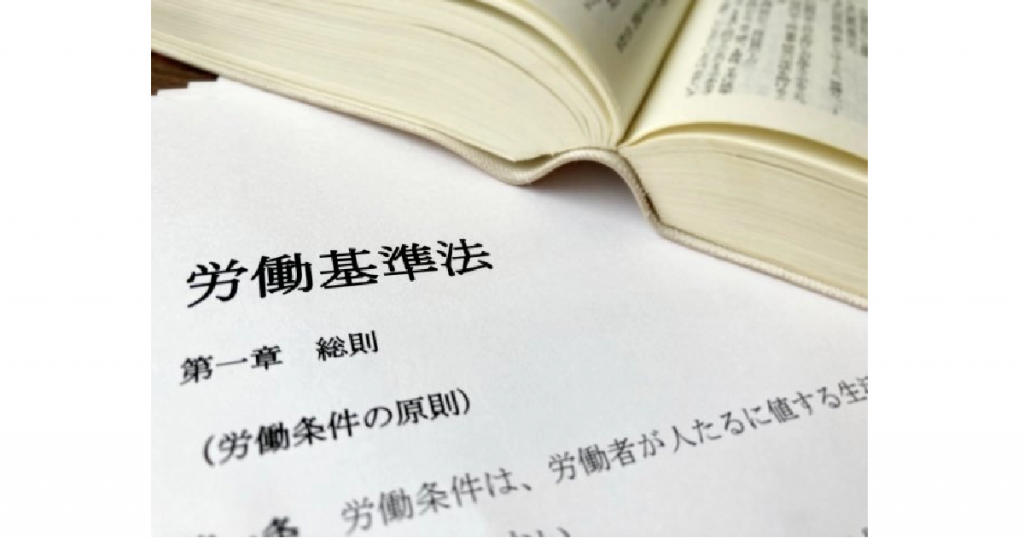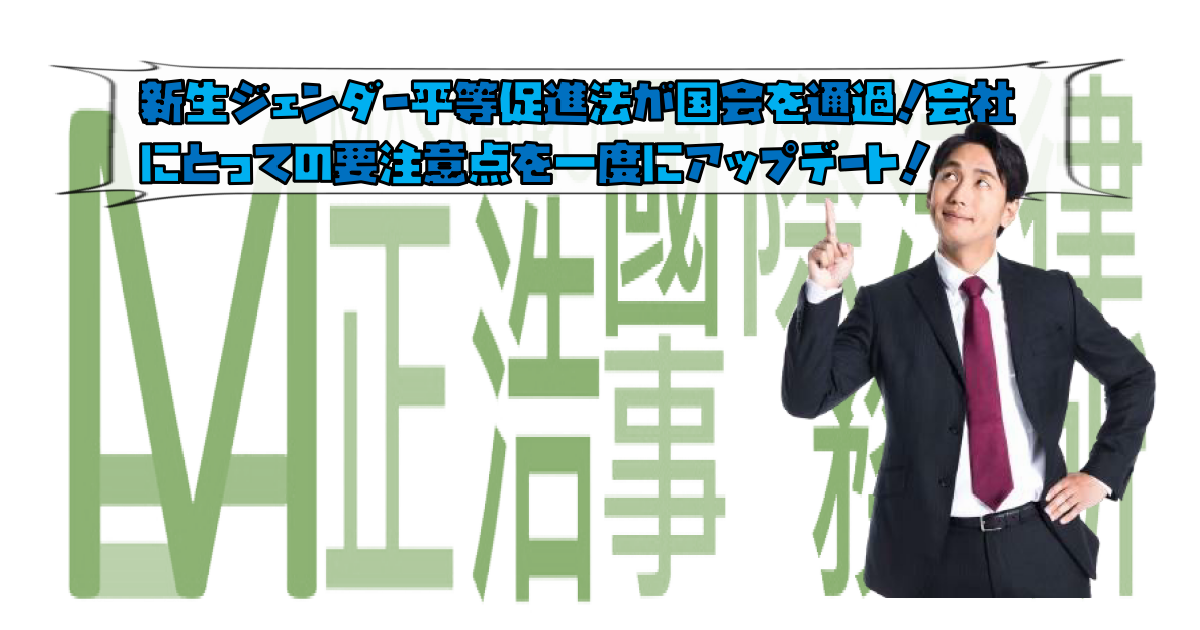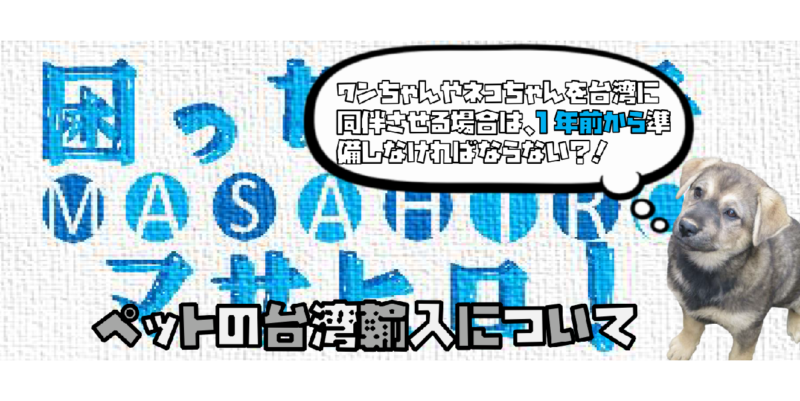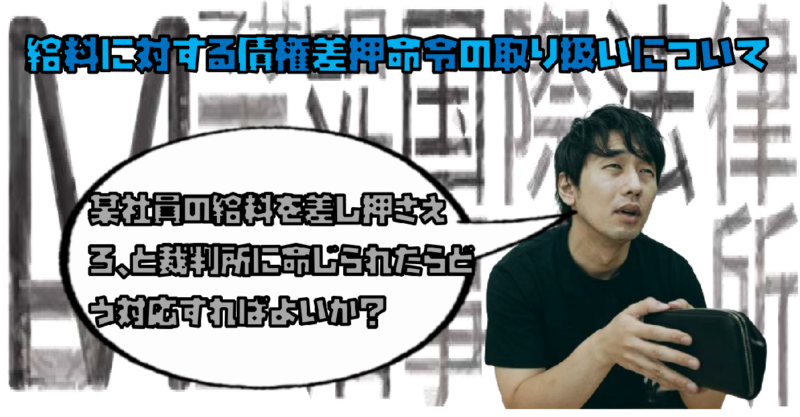【社員と贈収賄禁止承諾書を取り交わす必要はある?】―従業員が行う贈収賄行為の法的責任について
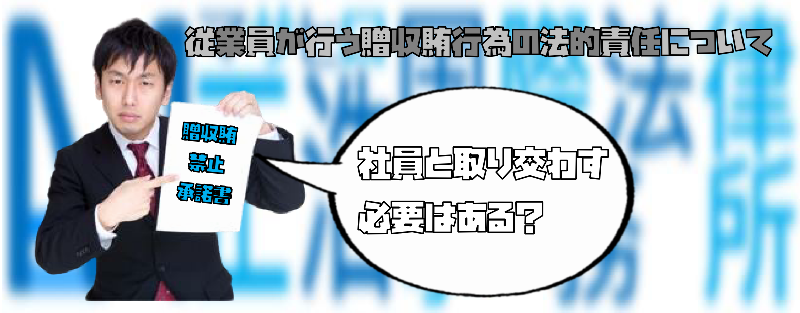
仕事の内容や賃金をきちんと記録に残さないと、いざ労働条件について労使間の認識違いが生じたら、会社は立証責任を負わなければならないので、たとえ法律上必須ではなくても、入社時に従業員と雇用契約書を締結することは一般的です。
就業規則の作成は、ルール的に30人以上の会社に課される義務なんだが、それがないと、社内での要遵守事項を従業員に周知させることが難しくなるほか、従業員に違反行為があっても、どう懲戒するかも分からないため、人事管理の観点で、30人未満であっても、就業規則を作っておく会社も少なくありません。
セクシャルハラスメント防止への取り組みについて、今までは30人以上の会社が対応すべき法的義務とされてきたが、一部改正後の性別平等就業法により、来年の2024年3月8日から、10人以上30人未満の会社でも、セクハラ被害に関する相談窓口を設置し、社内に周知しなければならなくなります。来年になって急いでそれを対応し、慣れないうちに何か間違ったりすると、すぐ当局から罰金通知書が届くリスクが伴うため、今年から軽く試行錯誤しながらスタートしてみよう、と検討する会社も増える傾向です。
一方、労働法で比較的はっきりしている前述の事項とは違い、「贈収賄禁止承諾書を従業員と取り交わす」ことは、法律的に強制されるわけでもなく、人事管理の面においてどのような役割を果たしてくれるかも不明瞭です。親会社はESG関係などでそれをやるようにと命じられたり、それを従業員と締結しないと発注してあげないと取引先から言われたりだから、そのとおりに行った、との声を会社から聞きます。
果たして、「贈収賄禁止承諾書」の効果は何か、「従業員と取り交わす」メリットは何なのか、従業員が行う贈収賄行為の法的責任を考えるうえで、「贈収賄禁止承諾書」の有用性を考察してみます。
取引先に贈賄するのは有罪?
ビジネスを円滑に進めるためには、契約金額の〇%をコミッションまたは口銭として取引先、仲介業者に支払うのは普通の商習慣であり、その「〇%」の妥当性について国税に突っ込まれる可能性があるにせよ、「取引先にコミッションを支払った」のみで、脱法行為には該当しません。
また、コミッションや口銭は取引先の「会社」ではなく、その会社に所属する「とある個人」、つまり取引先の従業員にリベートとして支払った場合、支払われたリベートをどのような形で会計処理を行えばよいか問題を別としたら、取引先はそれによって損害を受けていなければ、リベートを支払った会社によほどのことがない限り、罪に問われることはありません。
では、「よほどのこと」とは何かというと、例えばリベートを受け取った取引先の従業員から、

あなたの会社に便宜を図ってあげるためには、ダミーの見積書を寄越せ。うちの者から連絡が行ったら、俺の言うとおりに回答してあげろ!
と言われ、かつその通りにやってしまえば、私文書偽造罪に該当するとともに(刑法第216条)、背任罪の共同正犯とされるリスクがあります(刑法第31条)。そのため、「他社にリベートを支払う」行為に限定すれば、刑事責任には該当しないが、リベートの支払元がその他付随的不正行為を働いたら、場合によって犯罪行為にもなります。
一方、リベートの支払先は会社ではなく、台湾の国家公務員である場合には、その他付随的不正行為の有無を問わず、リベートを支払ったら即贈賄罪が成立し、1~7年の懲役刑並びに最高300万NTDの罰金刑に処せられます(汚職治罪条例第11条)。
留意が必要なのは、いわゆる「国家公務員」とは、実質台湾において公務員の身分を有する人物だけでなく、公的機関から業務を任せられ、例えば地方自治体から公共工事を請け負った民間企業、もしくは公的機関から権限をもらって公共事業を実施している、例えば国営企業の購買担当などの「みなし公務員」もカウントされ、それらに対する贈賄行為は同じく刑事責任が発生します(刑法第10条)。
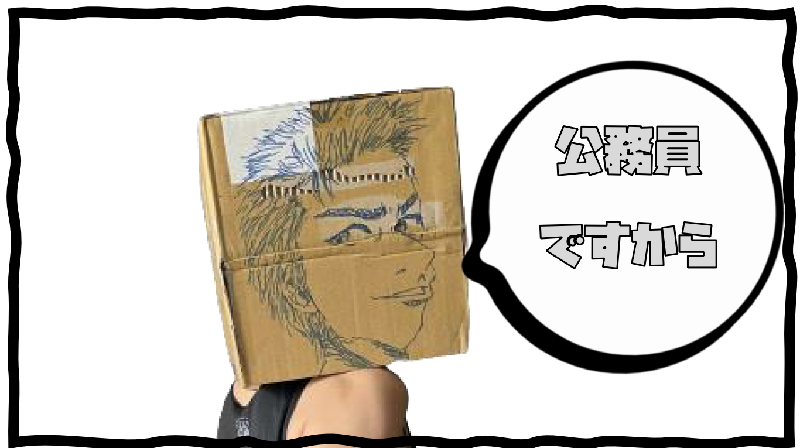
取引先から収賄するのは有罪?
「取引先に贈賄する」ケースと同様、取引先から商品代金とは別に、コミッションまたは口銭なども受け取った会社は、それらのコミッションまたは口銭収益を確実に国税に申告しておけば、違法にはなりません。ただし、取引先からリベートを受け取ったのは従業員個人であれば、話は別です。
前述べたように、「よほどのこと」がなけれが、取引先の従業員にリベートを支払った側には違法性がないが、それを受け取った取引先の従業員本人においては、場合によって、以下の犯罪行為に該当する可能性があります。
収賄行為に関連する刑事責任
実務的には、従業員が取引先からリベートを受け取った収賄行為で、業務上横領罪または詐欺罪が成立する可能性はそれほど高いわけではなく、証拠不足で不起訴となるケースは少なくありません。手元の証拠が足りない場合、成立可能性が比較的高い背任罪をもって、収賄行為を行った従業員を取り締まる傾向があります。にもかかわらず、「従業員が会社に何ら報告せず、取引先からリベートを受け取った」行為は、必ずしも背任罪に該当するとも限りません。
台湾とある大手テレビ局の事例なんですが、プロジェクトを担当する従業員が無断でドラマ制作会社からリベートを受け取ったことを勤め先のテレビ局にばれ、同テレビ局に背任罪で訴えられました。第二審では、従業員に有罪判決が出たが、最高裁は、「従業員が担当するドラマに品質問題があったり、撮影の進捗に問題が発生したりすることがあるか、あったとしてもリベートの支払いとは何か因果関係があるのか」、といった点をテレビ局側が立証しなかったと指摘し、第二審の判決結果を一蹴しました。結局差し戻し審で、同従業員に無罪判決が出る形となりました(台湾高裁110年度上更一字第185号判決)。
背任罪の成立には、仕事関係で取引先から不正にリベートを受け取ったのは勿論、リベートを受け取った従業員はそれによって自らの業務を怠ったり、会社からの指示に明らかに反する行為を働いたりして、会社に損害を与えた事実が必要とされます。従業員は「取引先から不正にリベートを受け取った」ものの、それによって会社に一切損害ももたらしていなければ、同人に対して、背任罪で責任を問うことが難しくなります。
違法性を判断しにくい民間企業の従業員と比べたら、リベートを受け取った国家公務員またはみなし公務員にはそれほどラッキーではありません。自らの勤め先である公的機関がこういった収賄行為によって、何か損害を被った事実があってもなくても、リベートを受け取った行為さえ認められたら、7年以上の懲役刑及び最高6,000万以下の罰金刑に処せられます(汚職治罪条例第5条)。

社員と贈収賄禁止承諾書を取り交わす必要はある?
従業員が行う贈収賄行為の法的責任について一通り説明しました。次は、「社員と贈収賄禁止承諾書を取り交わす必要はある?」、についても考えてみましょう。
冒頭にも言及したが、贈収賄禁止承諾書は、法的に作成義務のある就業規則とは性質が異なっており、会社の権利を守る目的で積極的に活用されている秘密保持契約書または競業避止契約書との位置づけも違ったりします。従業員と贈収賄禁止承諾書を取り交わすきっかけは、大体親会社または取引先からの要請があったり、会社が一定の規模に成長し、ESGに関連する方針として贈収賄禁止措置を取り入れたりするなどの場合です。では、外部からの要請がなく、サステナに取り組む余裕もない中小企業にとっては、贈収賄禁止承諾書は無用の長物になるのかと言えば、そうでもないようです。
「従業員が取引先からリベートを受け取る」ケースにおいて、リベートの受け取りで勤め先に何か損害をもたらしたのかを立証できなければ、背任罪で対象従業員を断罪できない、と説明しました。もし勤め先の会社は刑事責任ではなく、受け取ったリベートを不当利得として対象従業員に返金請求を行おうとする場合、「従業員の収賄行為により、会社が具体的にどういった損害を受けたのか」をはっきり立証できなければ、裁判所から当該請求の正当性を否認されるリスクが高くなります。それへの対応策は、まさに「従業員と贈収賄禁止承諾書」を締結することです。
例えば、「取引先からリベートを受け取ることを固く禁じる。従業員がそれに違反したら、受け取ったリベートを違約金として当社に支払わなければならない」、的な条項を予め贈収賄禁止承諾書に盛り込み、かつ従業員と締結しておけば、収賄行為が認められるたびに、会社は対象従業員に対して、受け取られたリベート相当額の違約金を請求可能となり、手間暇かけて証拠を集め、損害額を立証せずに済みます。この点はまさに「従業員と贈収賄禁止承諾書を取り交わす」最大のメリットと言えましょう。

今週の学び
腐敗の防止に関する国際連合条約が発効して約20年が経っており、台湾も2010年に贈収賄防止についてのガイドラインを導入し、コーポレートガバナンスを評価する要素として上場企業・店頭公開企業に遵守を促しています。にもかかわらず、台湾一部の業界において、それなりの贈収賄を行わなければ取引は成立しない、と言われるほどに、贈収賄の習慣が相変わらず根強く残っており、自社の管理職の名義を借りてペーパーカンパニーを作り、取引先に対する贈賄用の金庫として運用するエグイ事例も存在するぐらいです。それを何とかしようと、国家公務員と同じく、「リベートを受け取ったら即実刑」的な法律を民間企業にも導入しようと国会で一度ならず提案されていたが、悉く不発弾で終わってしまいました。
贈収賄ゼロまでの道のりはまだまだ長い今、贈収賄禁止承諾書をできるだけ活用して、自社の権利を守っていくことがおすすめです。