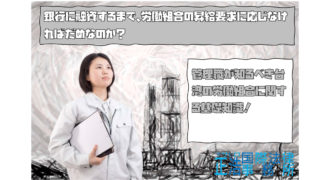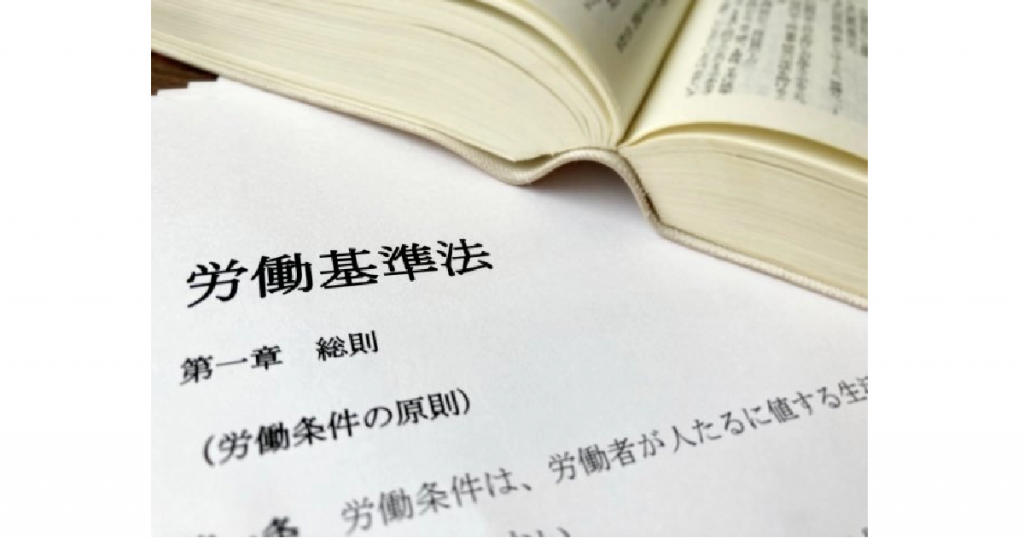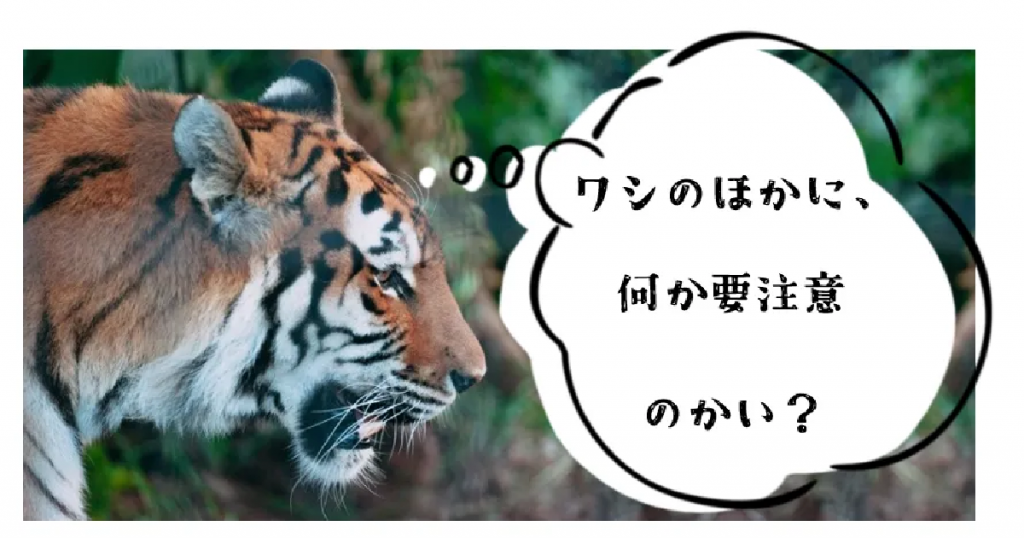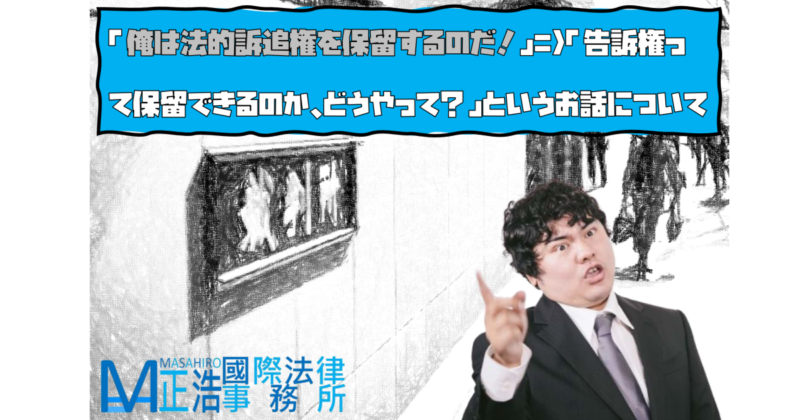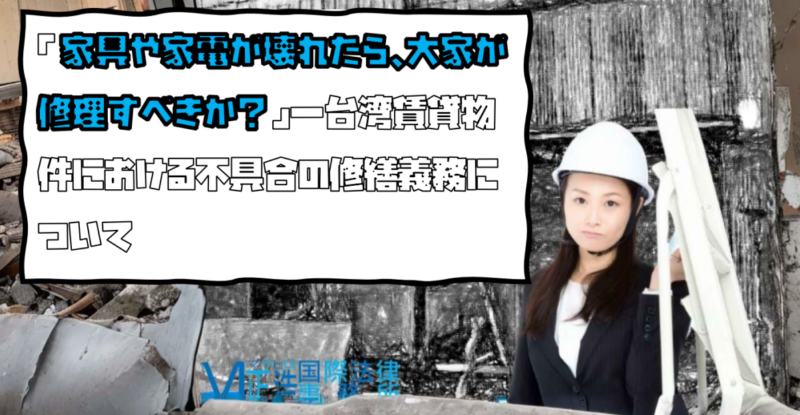「銀行に融資するまで、労働組合の昇給要求に応じなければだめなのか?」―管理職が知るべき台湾の労働組合に関する基礎知識!
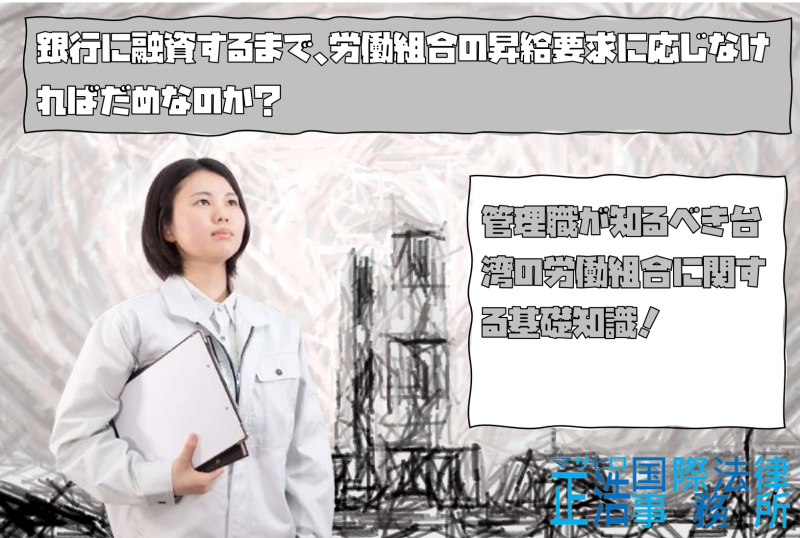

この間、社員の欠勤問題が深刻になっていて、それを是正しようと懲戒規則を修正してみたら、労働組合から激しい反発を受け、頓挫してしまった…
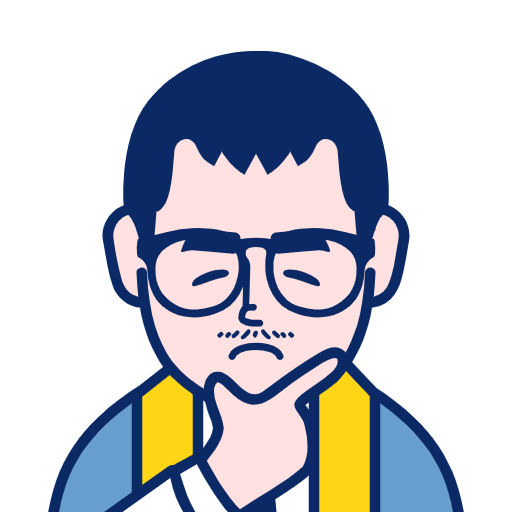
最近は売上が少し伸びたが、在庫の安売りだけなので、全然利益が出てないにもかかわらず、組合の代表からは臨時ボーナスを支払えと言われ、お金の余裕がないのに…
労働者が一定の人数集まり、かつ主務機関に登記すれば、労働組合を結成することができます。労働組合は個別の労働者または一企業で働く労働者全員を代表し、給与や休暇などの労働条件について企業と交渉することは可能とされ、妥当な理由なしでそれらの交渉に応じなければ、企業は過料を支払わされます。
こういった労働組合から持ち掛けられた交渉は、果たして何時でも無制限に発動できるものなのか、会社は労働組合からの要求に応じなければ何かリスクがあるのかなどについて、台湾の労働組合に関する基礎知識を紹介しながら、以下解説していきます。
労働組合はいかにして誕生するのか?
台湾の労働組合との付き合い方を理解するためには、まずその生い立ちから入るのが筋です。
労働組合は台湾において、大きく3つの種類に分かれています。
- 企業別組合:同じ工場または同じ会社で働く労働者で結成される組合
- 職業別組合:同じ地方自治体で、同じ職業に従事する労働者で結成される組合
- 産業別組合:同じ産業に従事する労働者で結成される組合
一社に一個の企業別組合、一地方自治体に同種類の職業別組合は一個に限定されるが、産業別組合には特にそのような制限は設けられません(労働組合法第9条)。
また、労働組合の結成は種類を問わず、結成方法は共通しています。最初のステップは、労組を作るのに興味のある労働者を30名以上集めることです。頭数が揃えば、発起人の資料や定款などの作成や組合員の募集を行い、結成大会を開催して幹部の選挙や規約案を作成して、開催後の30日内に主務機関に登記を行った後、労働組合の誕生です(労働組合法第11条)。
ちなみに、会社の管理職は、原則として企業別組合に参加できないため(労働組合法第14条)、30名以上の発起人にカウントされません(労働組合施行細則第12条)。それは、労働組合を忌み嫌う可能性のある会社のマネジメント層がスパイを潜り込ませ、諸々破壊工作を働かせることにより結成大会をめちゃくちゃにするリスクが考えられるということで、政府は予めファイアウォールをインストールしたわけです。
なお、ここでいう「管理職」というのは、会社の支配人(総経理など)や工場長、副工場長、部門長、副部門長その他同等の役職に就く者との定義づけがなされているが(労資1字第1000126886号通達)、実務的には認定に迷う役職も少なくないため、会社の組織図を添え、主務機関に説明のうえ了承を取ったりする対応方法が取られています。
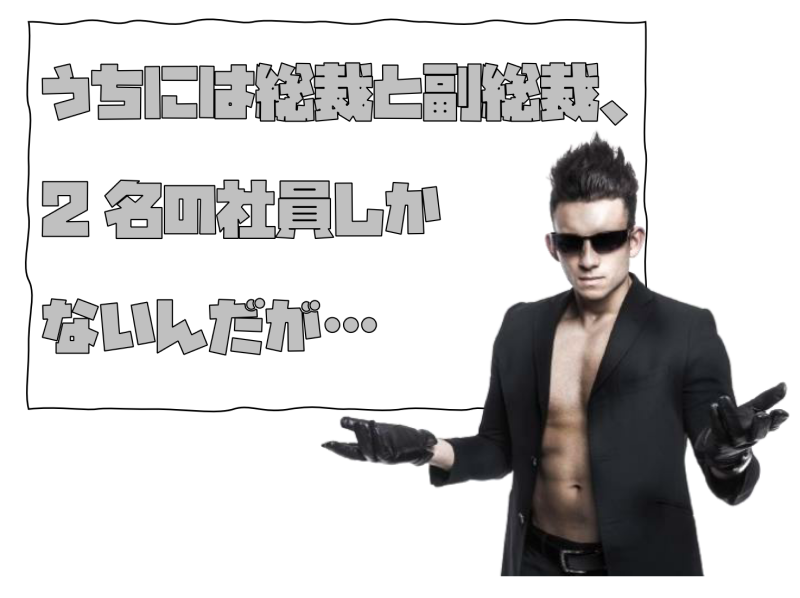
労働組合から同意を得なければならない?
台湾の労働組合には、原則として以下の役目を果たす義務があるとされます。
- 労働協約の締結、修正及び廃止
- 労使紛争の処理
- 労働条件、労働者の安全衛生及び組合員の福利厚生事項の促進
- 労働者政策及び法令の作成と修正
- 労働者講習会の開催
- 組合員就職支援
- 組合員娯楽活動の開催
- 組合または組合員のトラブルの調停
- 法律に基づく事業の実施
- 労働者に対する家計調査の実施及び労働統計資料の作成
- その他
以上の任務を全うするために、組合員から相談があれば、労働組合は必要に応じて組合員に代わり、その勤め先の会社に対して交渉を行うことができる、という法的権限が与えられるわけです。また、行われるのは「交渉」なので、会社は労働組合からの要求を全て受け入れる義務はなく、互いがそれぞれの言い分をぶつけ合い合意点を見いだせればよいとされます。ただし、以下の事項について、労働組合から了承を得なければ会社は一方的に実施できない、という労基法上の定めがある点は留意が必要です。
労働組合から了承を得ることが義務付けられる事項
- 変形労働時間制の実施
- 残業の実施
- 残業の実施は、対象となる労働者本人の同意は勿論、予め労働組合の了承も得なければなりません(労基法第32条)。
- 月次残業できる時間数の延長
- 通常の場合、月次の残業時間は毎月46時間に限られているが、労働組合からゴーサインが出れば、毎月の制限時間数を54時間に引き上げることができます。ただし、3ヶ月の残業時間数を合わせて138時間を超えてはならないとされます(労基法第32条)。
- 勤務間インターバルの短縮
- 会社は合法的に交代勤務を実施するためには、少なくとも11時間の勤務間インターバルを用意しなければなりません。ただし、指定事業に該当し、かつ労働組合もそれに同意すれば、インターバルを11時間から8時間に短縮することができます(労基法第34条)。
- 休日の振り替え
- 会社は7日のうち、所定休日として1日、法定休日として1日を労働者に与える義務があり、必要に応じて所定休日に労働者に残業を命じることも可能だが、不可抗力が生じない限り法定休日に労働者に出勤させてはいけません。この縛りも、「指定事業+労働組合の同意」という条件を満たせば突破できます。つまり、7日に1日の休みルールを破り、労働者に12日連続出勤させることは可能になります(労基法第36条)。
- 女性の夜間勤務
- 原則として、女性労働者に午後10時~午前6時に出勤させてはいけないが、労働組合がOKすればその限りではありません。しかし、女性の夜勤禁止は2021年に憲法違反と認定され、無効とされました(大法官釈字第807号解釈)。
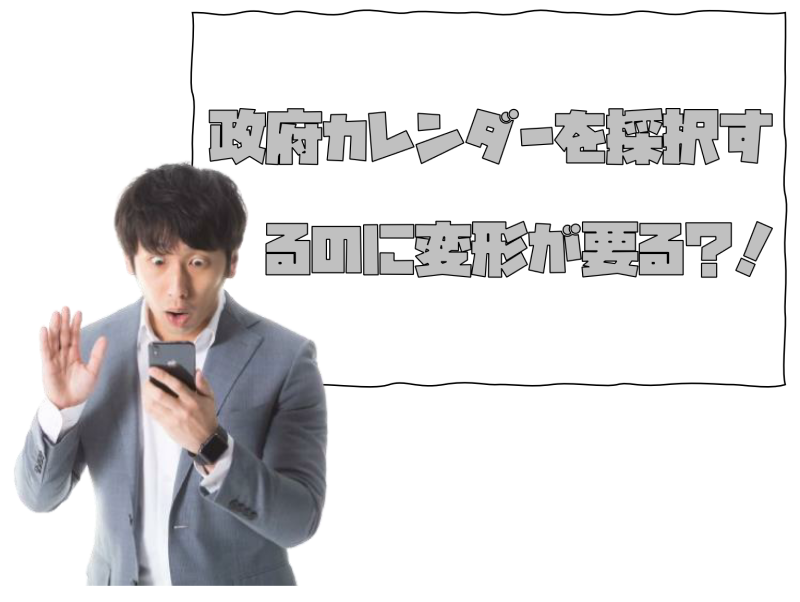
労働組合がよく利用する交渉の武器
以上に述べた6つ(実質は5つ)の事項は労働組合の同意なしでは実施できないとされているが、いずれも会社は運営管理上の都合による調整事項であり、どちらかと言えば、労働組合は立場的に受身的な存在でしかありません。一方、賃金や休暇、職場環境、労働時間など労働者の雇用条件を改善する目的で、労働組合が主体となって、能動的に会社に交渉を持ち掛けることのできる「労働協約」という制度もあります。
台湾の労働協約という制度は、それに関わる労働者の同意が得られるかどうか、労働者個別の雇用契約書にてどのような労働条件が盛り込まれたかを問わず、協約で合意した内容はそのまま適用される、という直接的効力を有するほか、法律に抵触した場合を除き、社内規程を優先するという強力的効力を兼ね備え、そして新たな労働協約が締結されるまでずっと有効である、という継続的効力もあります。なお、労働協約の締結というのは、会社はただ単に上から目線で労働組合からの話を聞いて、会社にとって都合のよい形で作成された合意書にサインするというものではなく、法律によって定められた義務を会社が少しでも間違えれば、不当労働行為に該当すると認定され、過料処分が下るので、慎重を期する対応が望ましいのです。
労働協約の締結に関して、会社側でよく指摘を受けるNGポイントは以下です。
NGポイント
- 交渉に応じる会社代表に妥当な権限を与えず、伝言ゲームで終わった場合
- 労働組合は組合員以外の専門家を交渉に参加させようとするが、会社は理由なく断った場合。
- 労働組合から協約の草案を受け取った60日内に、会社は書面による返答をしないか、交渉に応じようとしなかった場合
- 会社は正当な理由もなく交渉日に出席しなかった場合
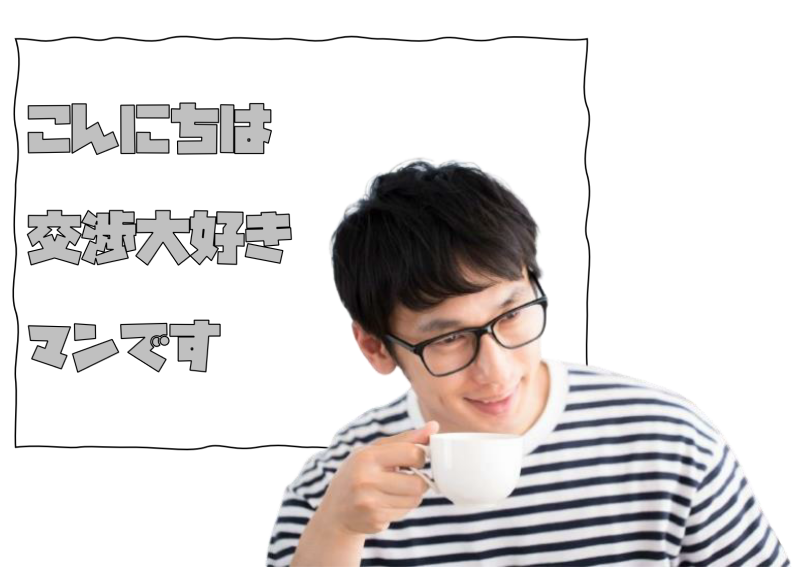
労働組合の最終奥義
会社は残業や変形労働時間制などを実施しようとすれば、予め労働組合の同意を得なければなりません。労働者との雇用契約書や就業規則に記載された労働条件は時代遅れで、それらを修正するために労働組合は会社に団体交渉を求め労働協約を締結することができます。双方はギブアンドテイクの精神で、例えば残業可能時間の解禁を条件に、残業代を労働者寄りの計算方法に修正するなどで、合意に達したりします。しかしながら、実務的には双方はどうやっても妥協点を見いだせない場合は多々あって、こういった拮抗状態を打破すべく、労働組合に与えられたのは「ストライキを行う」権利です。
ストライキとは、会社が言うことを聞いてくれないから、午後にでも暴れだそう、という軽い気持ちで何時でも条件なしで行えるものではありません。決まった法的要件をクリアし、かつ順序よく丁寧にやっていかないと、違法なストライキと認められ、数十万元の過料処分が下されてしまいます。
合法的にストライキを行うためには、以下の基本ルールを遵守しなければなりません。
- ストライキを発動できるのは労働組合のみで、個人または複数の労働者が集まれば発動できるわけではありません。
- ストライキを発動するきっかけは、会社が残業代を支払わない、もしくは解雇手当を没収するなど、労働者個々人に対して行われた不適切な処置は対象外で、労働者全体の賃上げ、福利厚生の充実などに関する交渉ならOKとされます。
- 労使交渉が暗礁に乗り上げたとき、まず最初は調停を試みて、調整が不成立の場合、無記名で組合員の投票に問い、過半数で賛成すればストライキが開催可能となります。
なお、労働組合が上記のルールをきちんと守って行ったストライキについて、会社はそれによって営業損失を被っていても、労働組合に対して一切損害賠償を求めることができない代わりに(労働紛争処理法第55条)、ストライキ実施期間の給料を対象者に支払う義務も無くなります。
一方、会社は原則的にはストライキによる損失を請求できないとはいうものの、ストライキを行う労働者は出勤拒否だけでなく、意図的に会社に対して営業妨害を行ったりすれば、それによる損失への賠償請求を会社は求めることは可能との司法判断がいくつかも出されていたので、行儀よくストライキを行うことが大事です。
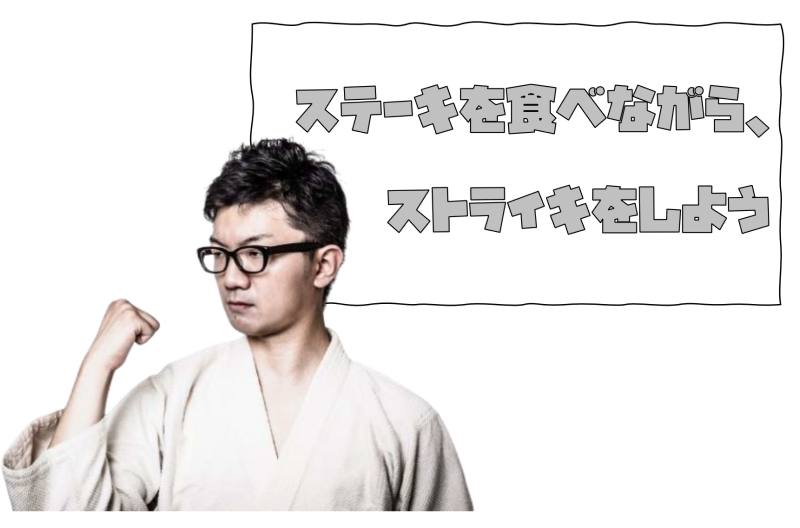
今週の学び
台湾の労働組合に関する基礎知識を以上のように紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。法律上、会社といい労働組合といい、それぞれ決まった権利と義務があって、法を逸脱する形で一方通行的に他方に対して自らの要求を突き通すことができないのです。労働組合との付き合い方に悩んでいるようであれば、気軽にマサヒロにご相談ください。