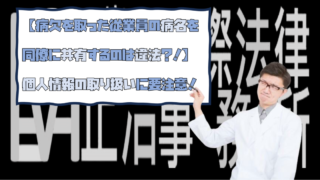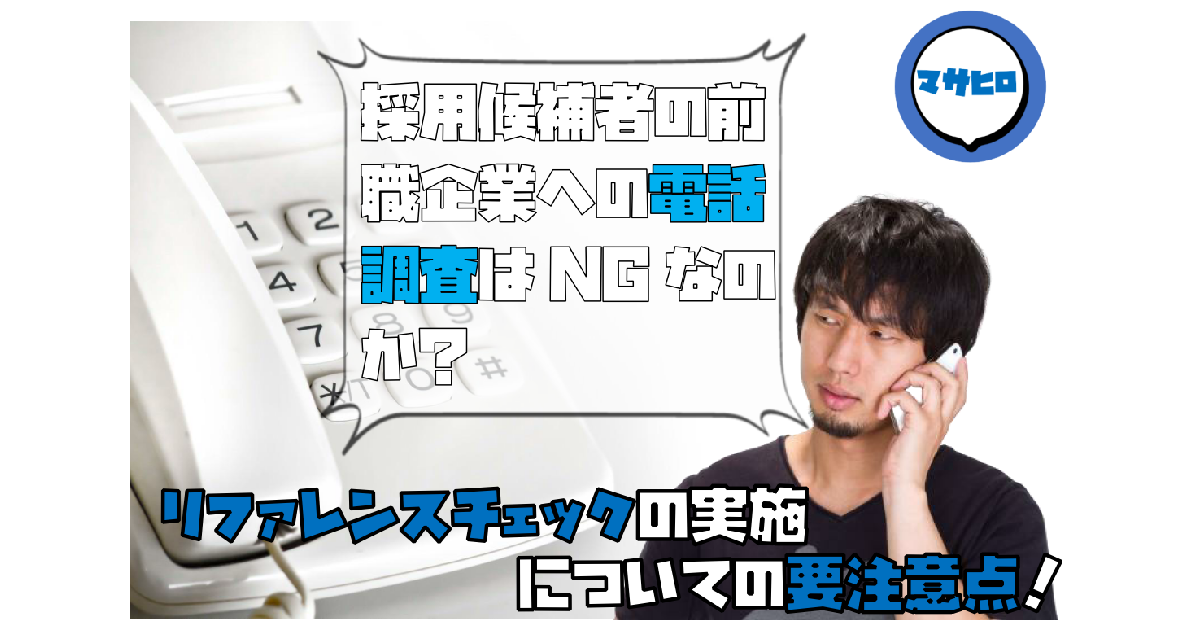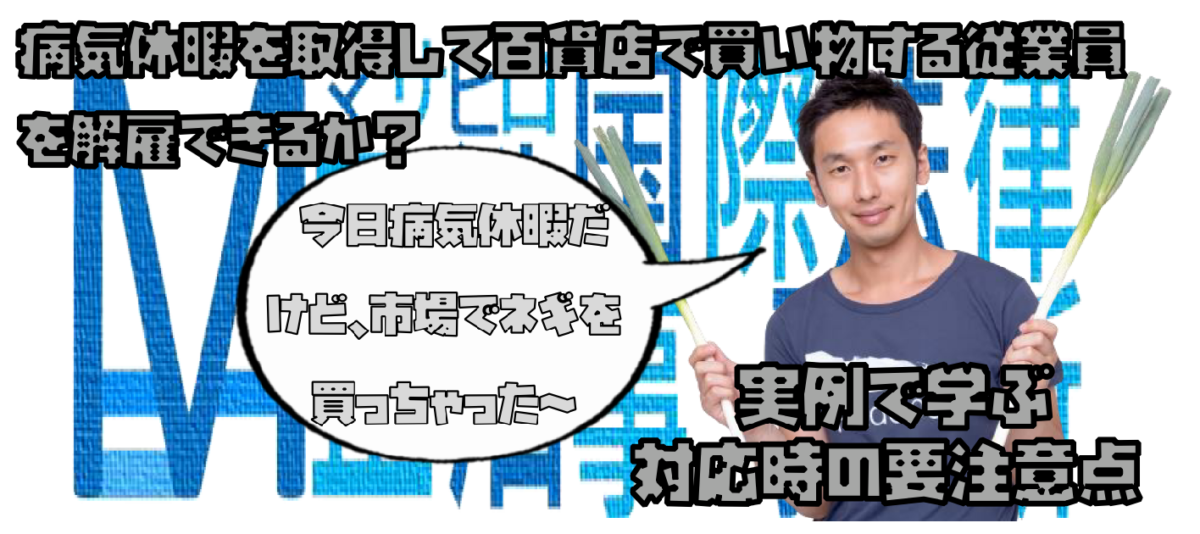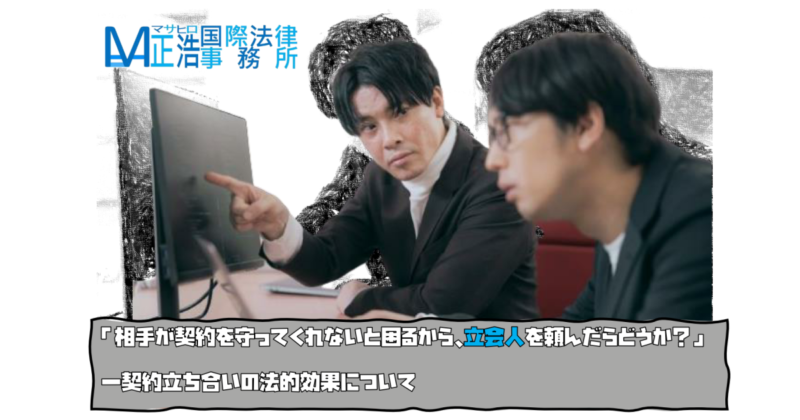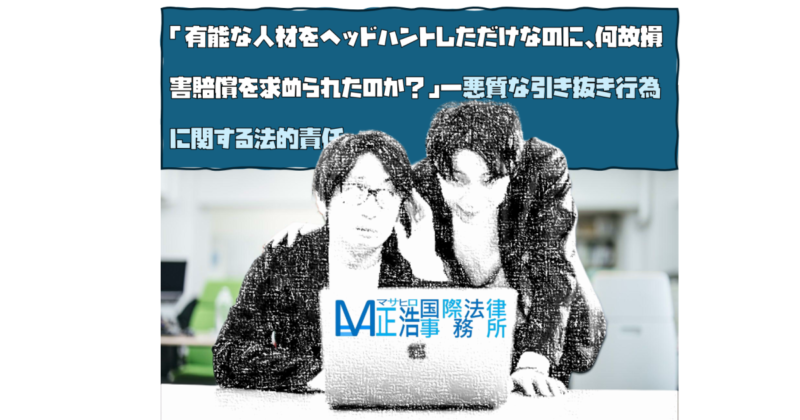【病欠を取った従業員の病名を同僚に共有するのは違法?!】個人情報の取り扱いに要注意!
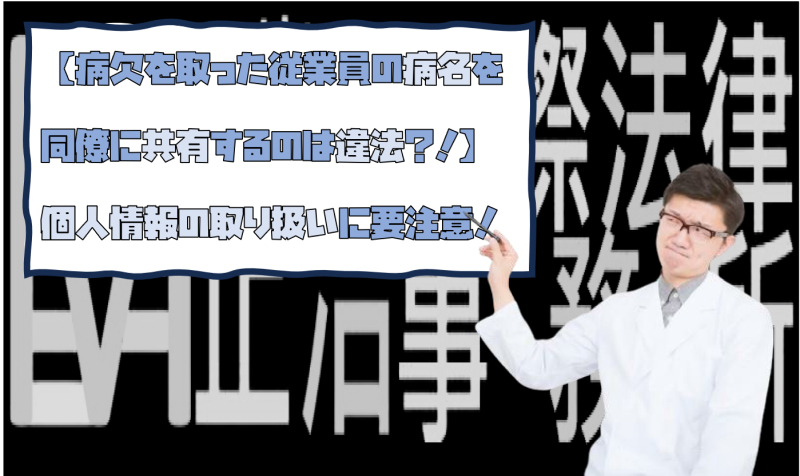
女性従業員が生理休暇を申請するとき、会社は病院の領収書または診断証明書の提出を求めてはいけないが(台労働三字第16614号通達)、従業員が病気休暇を申請した場合、会社は病院の領収書または診断証明書その他証明書類の提出を求めることができるとされます(労働者休暇申請規則第10条)。
また、従業員から提出を受けた病院の領収書または診断証明書に記載された病名や症状などは個人情報には該当するが、雇用関係にある従業員に対する人事管理を行う目的があったため、従業員のこれらの個人情報を収集しても、原則として法律違反にはなりません(個人情報保護法第19条)。
実務的には、部下から病気休暇の申請を受け、社内で代理人を見つけるために、病気休暇の件をその他従業員に共有したりする場合が少なくありません。一般論で言えば、病気休暇を取得することを代理人に伝えるだけでは問題ないが、思わず一線を超えるような伝え方をしてしまうと、刑事責任に問われる場合があります。気になる「一線」とは何なのか、以下事例でチェックしましょう。
事件の経緯
TS〇C社に勤めるS氏は、部下のL氏から病院の領収書を提出されて病気休暇の申請を受けました。病院の領収書を見てL氏は帯状疱疹を患っていると知ったS氏は、社内のビデオ会議ソフトの通話機能を使って、複数の部下とオンラインミーティングを行っている最中に、「L氏が帯状疱疹で病気休暇を取得した」という事実を全員に共有しました。その後、この件を知ったL氏は、個人情報保護法に違反するとして、警察局に出向きS氏を相手取って告訴しました。

個人情報保護法の定めをCheck
台湾の個人情報保護法によると、「個人情報」に該当するのは以下の情報です。
- 氏名
- 生年月日
- 身分証明書の統一番号
- パスポート番号
- 身体の特徴
- 指紋
- 婚姻状態
- 家族構成
- 教育水準
- 職業
- 病歴
- 医療関係情報
- 遺伝子
- 性生活
- 健康診断
- 犯罪経歴
- 連絡方法
- 財務状況
- 社会活動
- その他直接的または間接的に当該個人を識別できる情報
上記12番の「医療関係情報」は具体的に何を指し示すかというと、治療、矯正、人体の疾病、傷害、障害の予防を目的とする、またはその他の医学上の正当な理由に基づき、医師もしくはその他の医療従事者が行う診察並びに治療、または上記の診察結果に基づいて行われる処方、投薬、施術または処置によって生じる個人情報、及びカルテの情報です(個人情報保護法施行細則第4条)。
また、他人の「医療関係情報」を収集、処理、または利用するに当たって、以下要件のいずれかを満たす必要があるとされます。
- 法律で明示的に規定されている場合
- 公的機関が法定の職務を執行する、または非公的機関が法定の義務を履行する必要な範囲内で、かつ事前または事後に適切な安全保護措置が施された場合
- 上記公的機関または非公的機関に協力する必要な範囲内で、かつ事前または事後に適切な安全保護措置が施された場合
- 当事者が自ら公開したり、既に合法的に公開された個人情報である場合
- 公的機関または学術研究機関が医療、衛生または犯罪予防の目的で、統計や学術研究を行うのに必要とされ、かつ情報が提供者によって特定の処理がなされて、もしくは収集者が取った開示方法により当事者が識別できないようになっている場合
- 当事者の書面による同意がある場合。ただし、特定の目的に許容される範囲を超えたり、その他法律によって禁じられたり、当該書面による同意が当事者の意思に反したりする場合は、この限りではない。
以上6つの要件を満たしていないにもかかわらず、自己または第三者の不当な利益を得るか、他人の利益を害する目的で、他人の「医療関係情報」を収集、処理、または利用し、かつ当該他人に損害を生じさせる恐れが認められた場合は、5年以下の懲役刑に処せられ、または100万NTD以下の罰金を併科されます(個人情報保護法第41条)。
関連法律を一通りチェックした後、次はS氏が行った行為が犯罪に該当するかを確認しましょう。
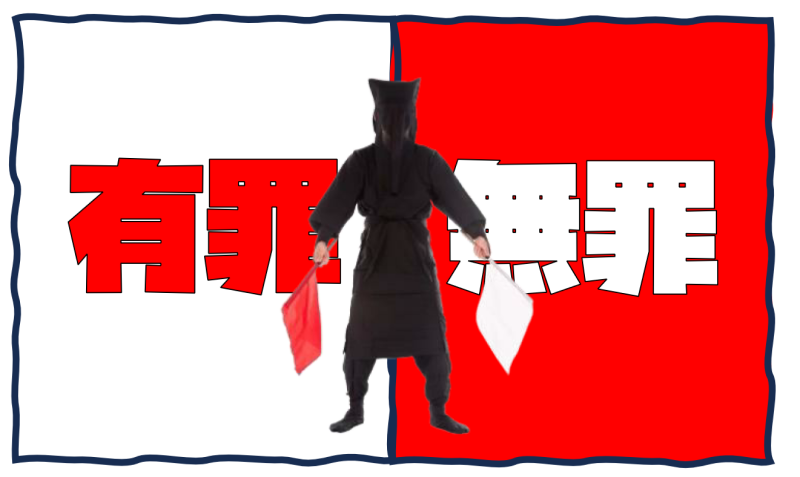
犯罪性の有無をCheck
S氏の話しによると、部下のL氏は病欠を取る頻度が高く、L氏の業務を協力するその他部下に納得してもらうためには、L氏の病名を伝える必要があって、L氏に不利益をもたらす意図は全くないそうです。確かに、代理人の人はもとより自らの業務をこなさなけばならないから、休暇を取得する同僚の業務を支援すると、業務量が倍増することとなり、もし同僚が頻繁に休暇を取得しているのであれば、不平不満も生じたりします。そこで、休暇を取得した人の実情を代理人に説明して理解を求めるのも頷けましょう。
一方、S氏の主張を受けて、裁判所は一連の事件に対して以下の判断を示しました。
112年度上訴字第111号判決
- 病名は「医師が診察結果に基づいて行った処方、投薬、施術または処置によって生じる個人情報」であるため、「医療関係情報」という個人情報に該当します。
- L氏は病気休暇の申請に必要な証明書類として病院の領収書を上司のS氏に提出したが、領収書に記載された病名情報を開示できる権限をS氏に与えたわけではありません。そのため、「他人の医療関係情報を収集、処理、または利用できる6つの要件」のいずれも満たしていないにもかかわらず、オンラインミーティングの参加者にL氏の病名を公開したS氏は、無断で他人の医療関係情報を「利用」する行為があったと認められます。
- 「L氏が体調不良」とだけ代理人に説明したらよいのに、会議に参加していないその他従業員にも知られる可能性が大きいことをある程度予測していたはずのS氏は、あえて意図的に会議中にL氏の病名を開示しました。当該行為は明らかにL氏のプライバシーを侵害しました。
上記の理由により、S氏に懲役刑2ヶ月の有罪判決が言い渡され、最高裁に上告されても判決結果が覆されませんでした。
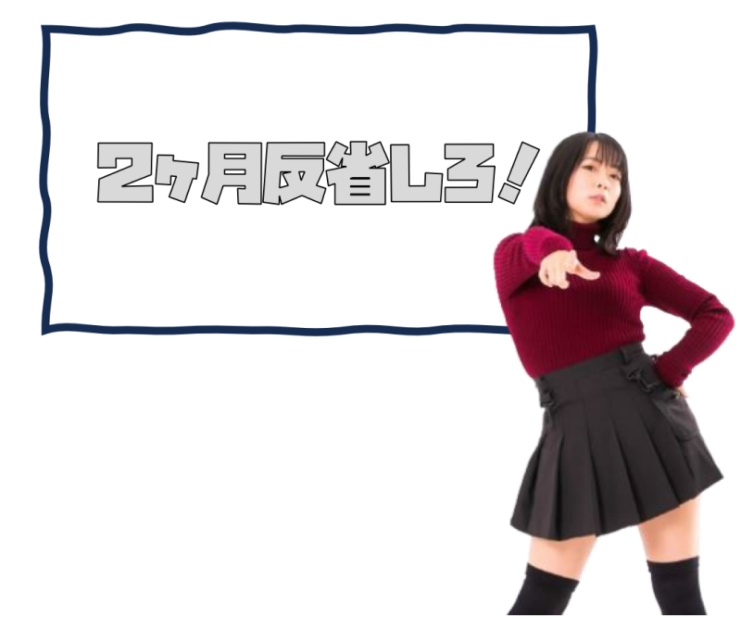
今週の学び
会社は従業員の人事管理を行うとき、個人情報に該当するとはいえ、人事管理の目的を果たすために本人から収集することは可能です。例えば、会社は労働者の雇用時に、身分証や卒業証書のコピーなどを本人に提出してもらったり、病気休暇の申請手続きに、病院の領収書や診断証明書の提出を求めたりするのが一般的です。これらの個人情報を収集する行為は、法律上別に問題にはならないが、従業員自らの意志で提供を受けたから、これらの個人情報を自由に運用できると考えるのは、非常に危ないのです。
ある会社の人事担当者が、濃厚接触者に対して注意喚起を行う目的で、コロナの発症を理由に病気休暇を申請した従業員の氏名や写真などの個人情報を会社の入り口に公開したそうです。「濃厚接触者に対して注意喚起を行う」という大義名分があったものの、前述の行為は個人情報保護法だけでなく、伝染病防止法及び刑法も同時に違反する可能性が大きいと考えられます。
今回紹介したS氏の事件は、「代理人への説明義務を果たす」といういかにも理屈に合いそうな主張がなされたものの、「病名まで話す必要があるのか」、「意図的に病名を開示した」、「他人へのプライバシー侵害という結果をもたらした」などの点において違法性が認められる形となりました。今回の事例を参考に、従業員から預かった個人情報を慎重に取り扱っていきましょう。