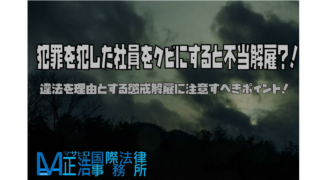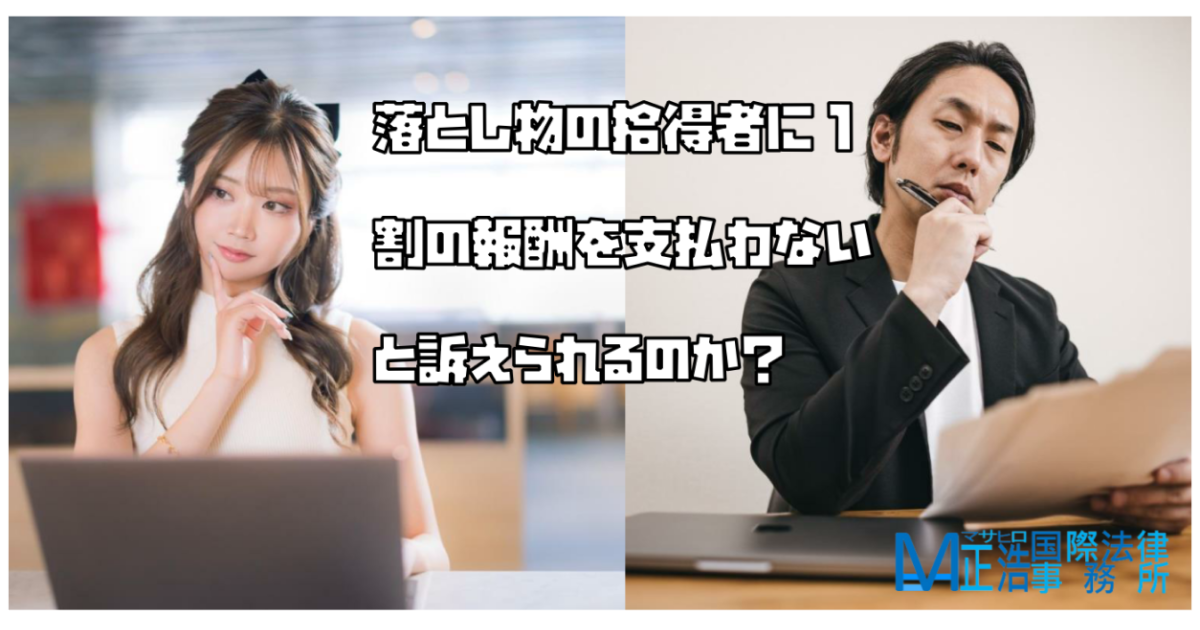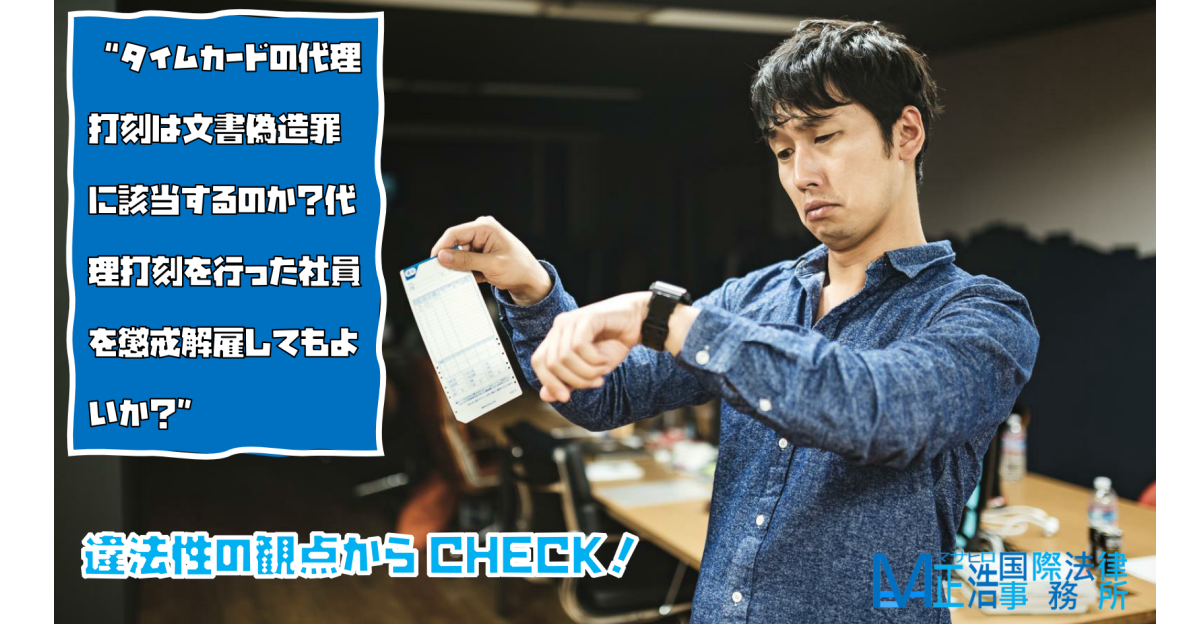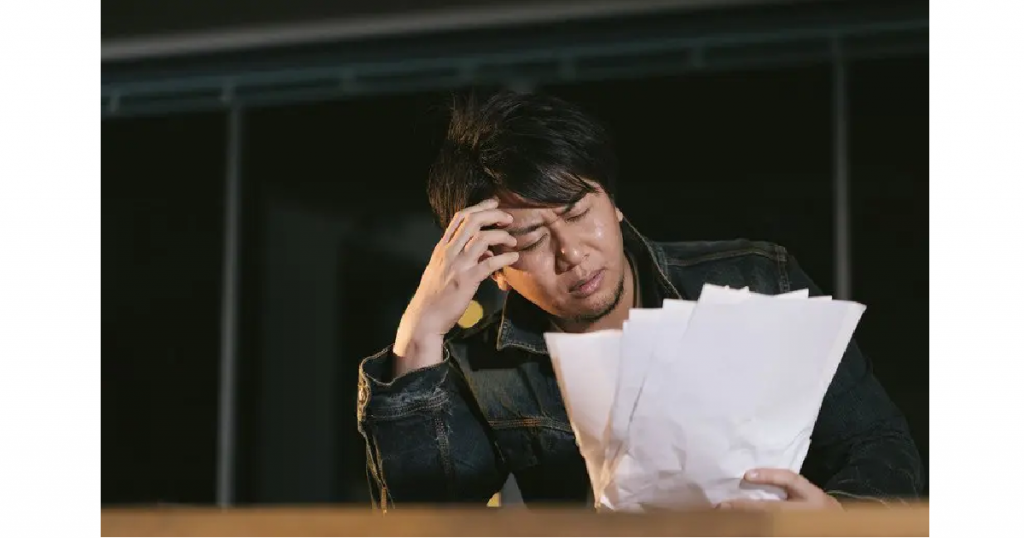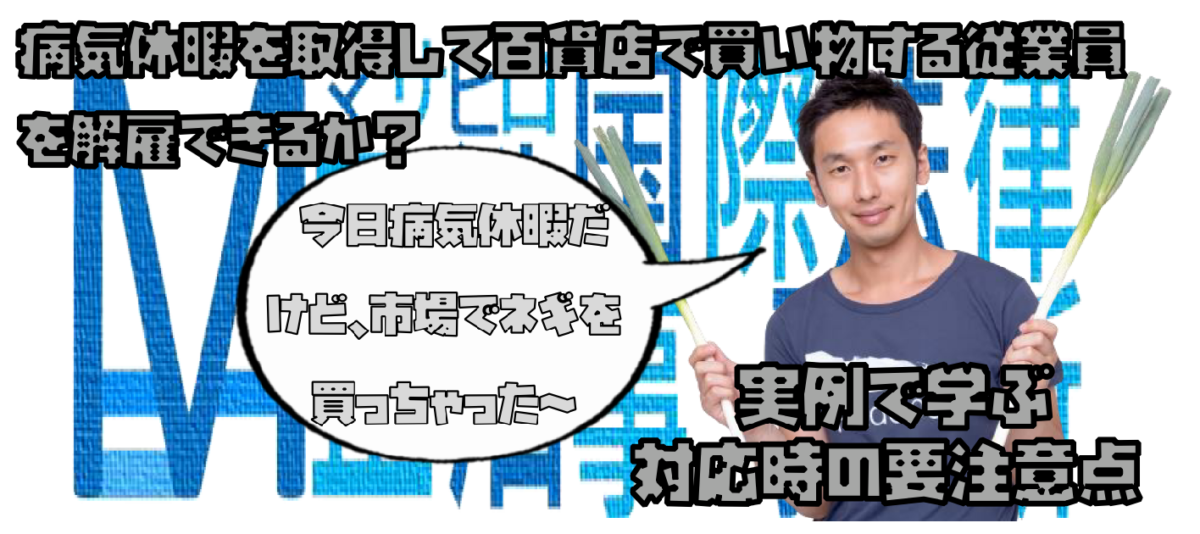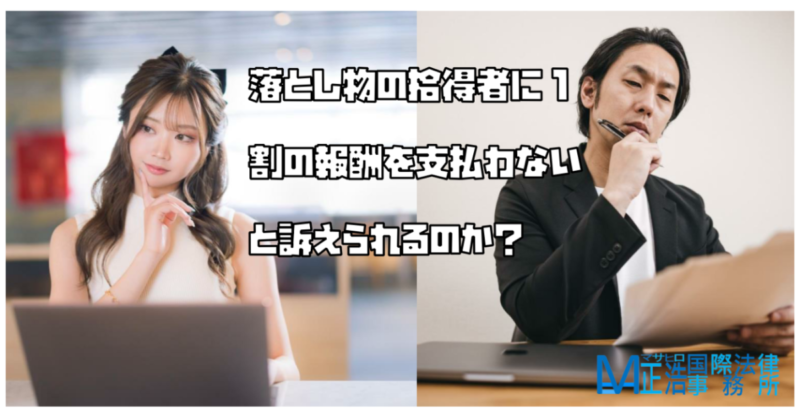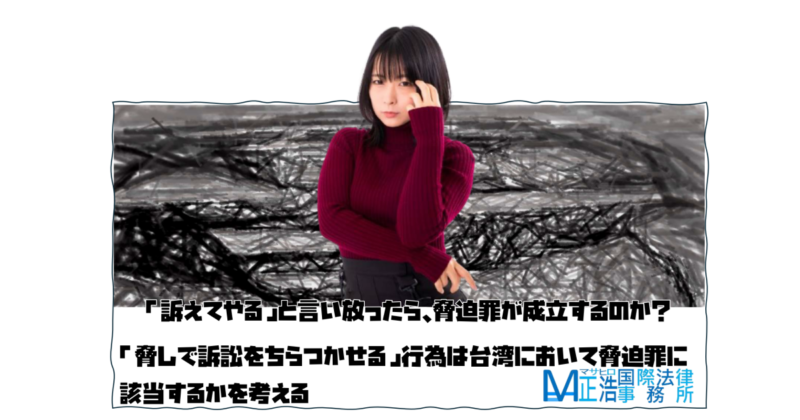犯罪を犯した社員をクビにすると不当解雇?!違法を理由とする懲戒解雇に注意すべきポイント!
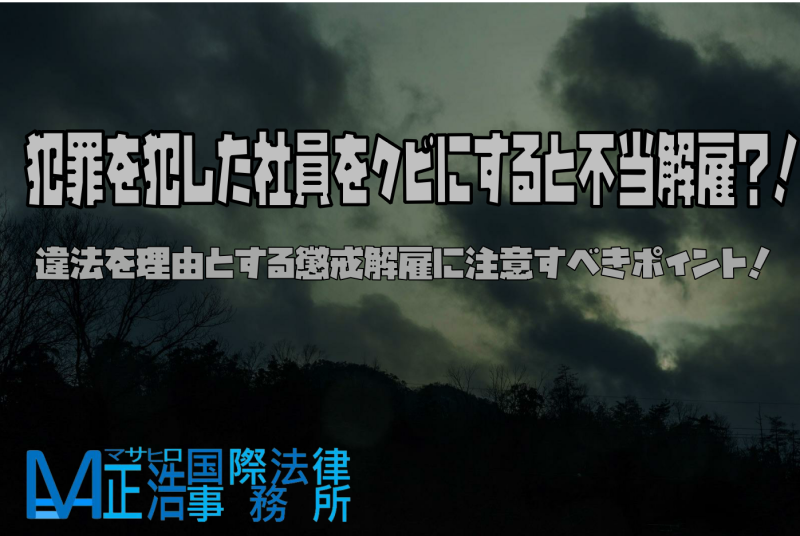
社員に業務をこなすのに十分なスキルがなければ、会社は解雇を実施可能です(労働基準法第11条)。にもかかわらず、当該社員に改善のチャンスが与えられているかどうか、「最後的手段の原則(ultima ratio Grundsatz)」が守られているかどうかなど、それに起因する不当解雇の事例がとにかく多いです。
また、十分なスキルがあるかを問わず、会社の就業規則に違反して、かつその違反の程度が重大であった場合でも、解雇が実施可能とされます(労働基準法第12条)。しかし、何をもって「程度が重大である」と断言できるか問題で、実務的にはよく争われ、結果的に不当解雇と判断される事例は決して少なくありません。
そして、会社の企業秘密を漏洩したり、一定日数以上の無断欠勤をしたりするなどの理由を除き、解雇手当の支払いが必要でない、不当解雇にもならないという、比較的分かりやすい解雇事由があります。それが、「社員が犯罪行為に手を染めた」場合です。
分かりやすいとはいうものの、「犯罪行為に手を染めた」という理由で解雇された社員が、裁判所から不当解雇のお墨付きをもらって会社に舞い戻り元の業務に復職するケースも存在したりします。

分かりやすい解雇事由なのに、不当解雇って何故?!
以下、マサひろんとともに、上記の「何故」の正体を突き止めていきましょう。
目次
「犯罪行為に手を染めた」社員を解雇手当なしで解雇できる法的根拠
法的根拠なしじゃ始まらないので、台湾の労基法ではどのように定めたのかを先にチェックしましょう。
労働者が以下のいずれかの状況に該当する場合、雇用主は予告なしに労働契約を終了することができる。
- 労働契約締結時に虚偽の意思表示をし、雇用主を誤信させ、雇用主に損害を与える恐れがあった場合
- 雇用主、雇用主の家族、雇用主の代理人、またはその他同僚に対して暴行を加えたり、重大な侮辱行為をした場合
- 有期懲役以上の刑罰の確定判決を受け、執行猶予または罰金刑への変更が認められなかった場合
- 労働契約や就業規則に重大な違反があった場合
- 故意に機械、道具、原材料、製品、またはその他雇用主の所有物を損傷し、または雇用主の技術上・営業上の秘密を漏洩し、雇用主に損害を与えた場合
- 正当な理由なく3日以上連続して無断欠勤したり、または1ヶ月以内に6日以上無断欠勤した場合
雇用主が前項の第1号、第2号、および第4号から第6号の規定に基づいて労働契約を終了させた場合、その事情を知った日から30日以内に行わなければならない。
上記法律の第3号は、まさに「犯罪行為に手を染めた」社員を解雇できる法的根拠です。そして、この辺の解雇手続きは、通常の会社都合による解雇と比べたら、10~30日前もって(労基法第16条)対象社員に「予告」しなくてもOKとされており、最高月給6ヶ月分相当の解雇手当を同人に支払わなくてもよいので(新制度の場合、労働者退職金条例第12条)、会社にとってはより負担の軽い解雇方法と言えましょう。
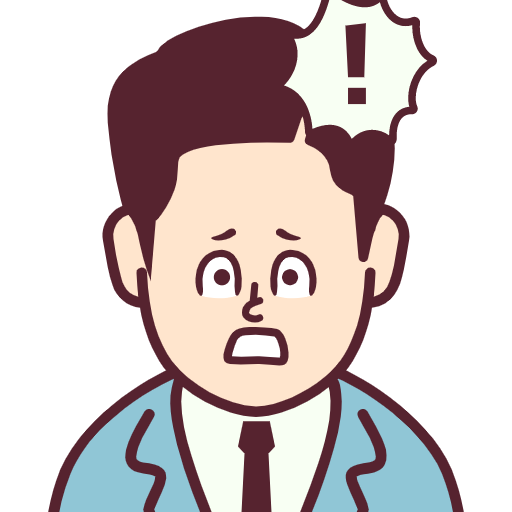
待ってよ、「その事情を知った日から30日以内に行わなければならない」というのは、社員の犯罪行為が分かって30日以内に解雇しなければできないわけなのか?
「解雇予告無し」の解雇は、社員にとっては解雇手当ももらえなければ、週2日の再就職休暇も取れない、いわゆる懲戒解雇に該当するので、会社側に「30日ルール」というハンデが付けられるわけなのだが、当該ハンデは「第1号、第2号、および第4号から第6号の規定」にのみ適用され、「犯罪行為に手を染めた」第3号には適用されないため、社員が犯罪行為で確定判決を受けたという事実を知った日から30日経過した後においても、会社は引き続き解雇権を行使できます。
しかし、「社員が犯罪行為に手を染めたら、予告無しで懲戒解雇できる」、という図式が一見分かりやすく見えるだが、実務上での運用はやはりトラブルが付きまとっており、最終的には不当解雇のレッドカードが出た場合も散見されます。
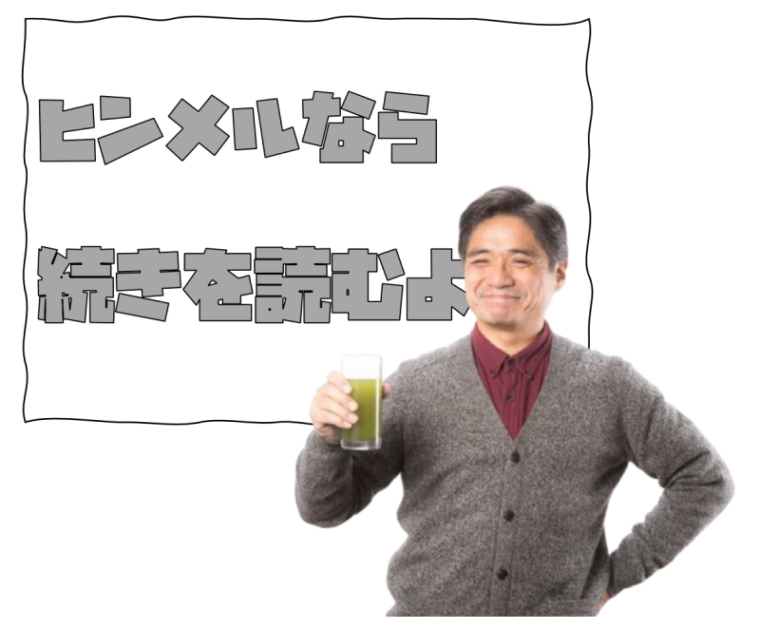
犯罪なのに不当解雇?その①―せっかちによる失敗
一部の雇用主は、社員が会社の文房具またはトイレットペーパーを私物化して、自宅に持ち帰って使用するのを発見して、「横領罪」に該当するからすぐ社員をクビにしたり、警察から呼び出しがかかり、もしくは裁判所から出頭命令を受けたのを理由に、予告なしで社員を解雇したりします。確かに、会社のものをねこばばしたのは横領罪に該当するかもしれず、警察または裁判所から呼ばれたのも、犯罪の取り調べや刑事事件の審理を行うためにあるかもしれません。ただし、いずれかの状況においても、対象となる社員が犯罪者であることを決めつけられる段階には至っていません。
法律の原文に書いてあったように、判決結果が出て、かつそれが確定して、そしてその結果が有期懲役以上でなければ、犯罪を理由とする懲戒解雇はできません。そのため、会社の財産を私物化する行為を会社が監視カメラなどで捉えたからといって、裁判所ではない会社は当該行為に対して有罪判決を言い渡す権限が与えられていないから、「監視カメラでそのような事実を把握できた」ことを「社員が犯罪行為に手を染めた」とみなし、予告無しで社員を懲戒解雇したら不当解雇のリスクが生じてきます。
同じ理屈で、警察から呼び出しを食らっただけで、「社員が犯罪行為に手を染めた」と認識し、社員を懲戒解雇することもNGです。
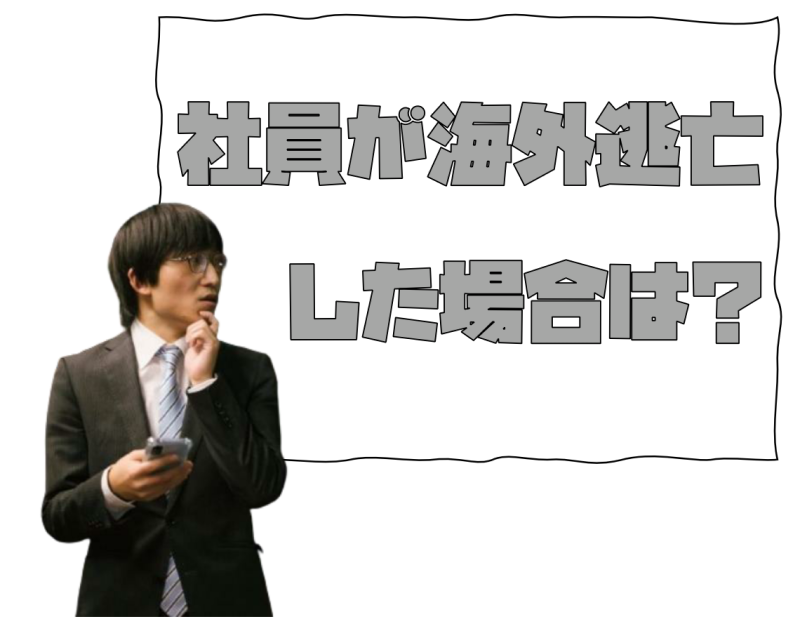
犯罪なのに不当解雇?その②―判決文の誤解による失敗
「犯罪行為に手を染めた」のを理由に予告無しで懲戒解雇を行うためには、「判決が確定した」という前提条件が必須であることはその①で説明しました。なので、とある社員が裁判所から有罪判決を言い渡され、控訴や上告がなければ、当該判決が確定する形となり、その段階で当該社員を即日解雇すると、不当解雇のリスクを冒さずに円満解雇できる、と思いきや、そうとも言い切れません。
裁判官の審理で有罪を下された場合、被告への処罰として懲役刑、拘留、罰金、執行猶予などの可能性があります。予告無しの懲戒解雇を実施できる前提として、「有期懲役以上の刑罰の確定判決を受けた」という事実が必要とされる点を考え、もし犯罪行為を犯した社員に言い渡された処罰が懲役刑ではなく、拘留、罰金、または執行猶予であった場合は、予告無しの懲戒解雇を合法的に実施できないとされます。
また、懲役刑を言い渡されたが、犯罪行為の情状が軽く、「罰金刑に変更できる」というコメントが判決書に付けられるのであれば、予告無しの懲戒解雇ができない点も留意が必要です。
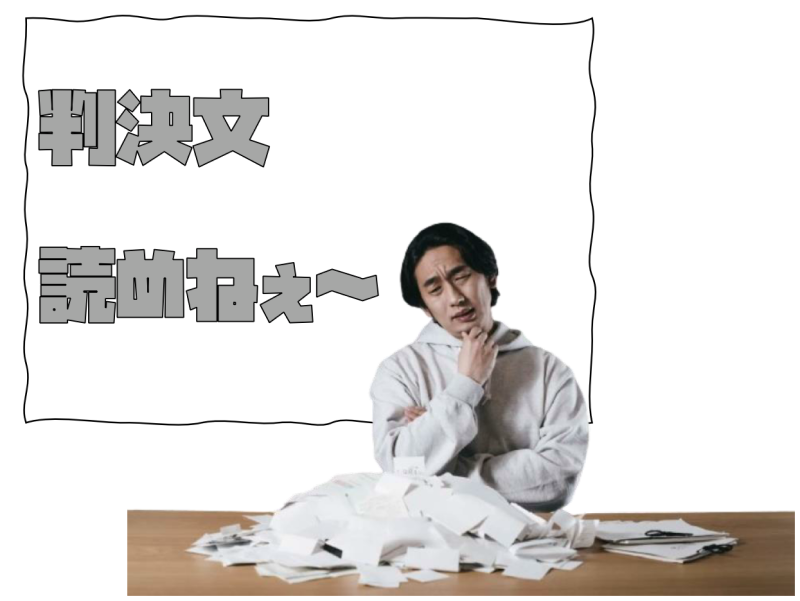
犯罪なのに不当解雇?その③―言葉足らずによる失敗
「犯罪行為に手を染めた」ことを理由とする懲戒解雇は、労基法上に定められた雇用主への権利です。当該解雇権は「権利」なので、実施するかどうかは雇用主次第であり、自動的に発動されるものではありません。従って、

あなたは〇〇罪により、〇〇年〇〇月〇〇日に〇〇裁判所から、罰金刑に変更できない懲役刑を言い渡され、かつ当該判決結果は既に確定したため、労基法第12条第1項第3号に基づき、本日付であたなとの雇用関係を終了とする!
的な告知事項を解雇対象社員に通知すれば、解雇手続きが法的に有効となります。
にもかかわらず、実務的には、「あんたが犯罪行為に手を染めたから、明日は来なくていい」、「お前はあんなことをしでかして、うちとの信頼関係が破綻しているから、うちには不要な人間だ!」というようなLINEメッセージだけ解雇対象社員に転送して、解雇を実施したりする会社があります。確かに、こういった表現は解雇の意思表示として受け取れないでもないが、事後当該解雇の合法的について裁判で争われたら、解雇通知に明確性が足りないことで、不当解雇と認定される可能性も無きにしも非ずのです。
解雇の有効性は、社員側にとって死活問題にかかわるため、解雇通知に使用する表現などをできるだけ丁寧に練りましょう。
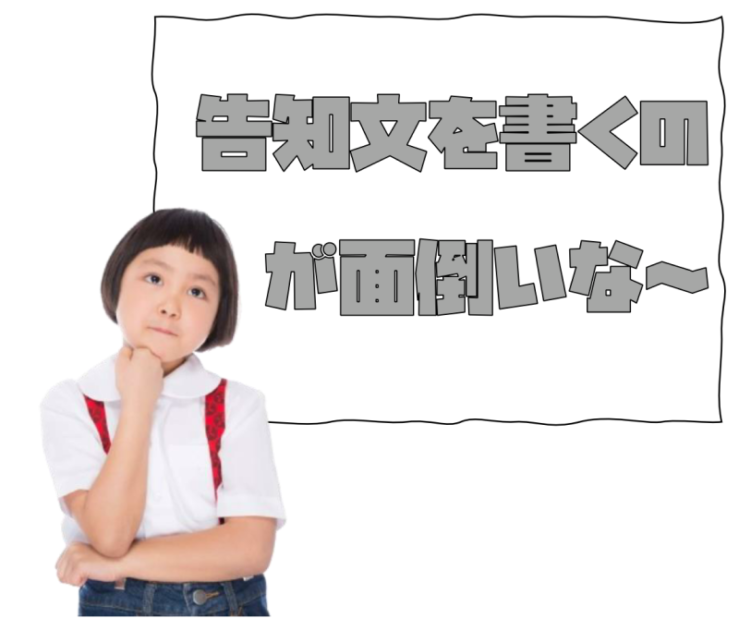
犯罪なのに不当解雇?その④―事後補正による失敗
こんな事例があります。
社員Aが会社の財産を横流しして、それで得たお金をねこばばしたことをA社にばれてしまい、当該事実を「社員が犯罪行為に手を染めた」と捉えたA社は社員Aをその日のうちにクビにしたものの、クビになった元社員Aに訴えられてはじめて、社員が「確定判決」を受けないと「犯罪行為に手を染めた」とは言えない法律を知ったA社は、解雇の理由を急遽、「会社の財産を横流しした行為は自社の就業規則に違反し、かつその程度が重大であった」に変更し、解雇の合法性を補強したのも空しく、結局不当解雇と認められ、裁判所から敗訴を言い渡されました。
「会社財産の横流し」というのは紛れもなく犯罪行為なので、もしそれが事実なら、確かに予告無しで社員を懲戒解雇できます。しかし、上記の事例においては、A社財産を横流しした社員Aが裁判所によって実刑を言い渡される前に、A社は既に解雇を実施しており、それが不適切だと分かったときごろりと解雇の理由を変えたので、解雇の理由は本当は何なのか、最初の理由に不備があるから、事後補正をする形で適当に理由を付けて解雇を正当化しようとするのはどうかな、といった点で突っ込まれ、解雇ならずとなりました。
上記の事例に沿って言えば、確定判決を待つのが嫌で、早急に不正を行った社員を解雇しようとするならば、解雇の理由をゴロゴロ変えるより、最初から「会社の就業規則に違反し、かつその程度が重大であった」のを理由に解雇を実施するほうが比較的スムーズかもしれません。勿論、「しっかりとそれなりの就業規則を作る」ことと、「程度が重大であることを証明可能な証拠を残す」ことが前提条件という点も忘れてはいけません。
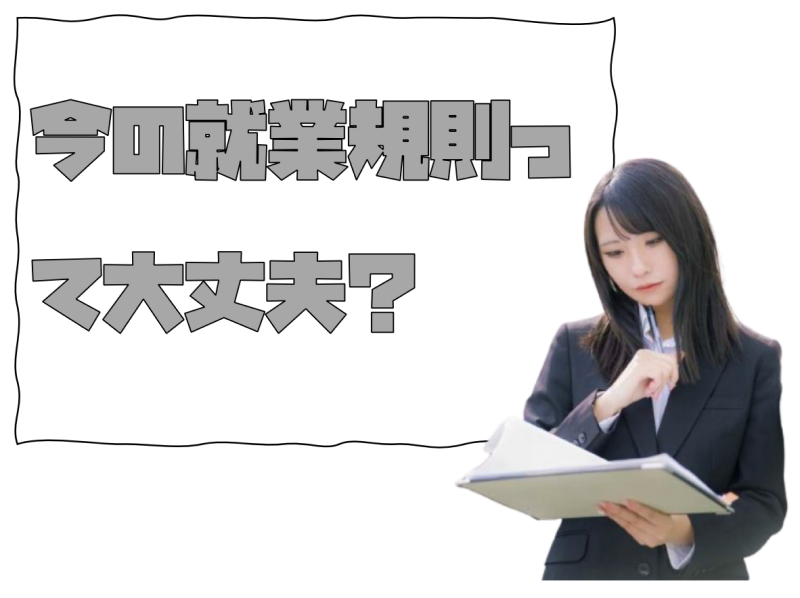
犯罪なのに不当解雇?その⑤―公私混同による失敗
社員が訴えられ、敗訴も言い渡されて、尚且つ判決が確定したから、心おきなく解雇できるのだと思い、いざアクションに移すと、コケてしまうのである、のような場合もあります。何故なら、前述の訴訟は民事訴訟だからです。
社員が退勤後の時間に何かやらかして、結果的に会社と関係のない第三者に損害を被らせ、そして裁判所から損害賠償を命じられた場合、当該事実は、あくまでも当該社員にプライベートの時間に何かしら正当性を欠く行いがあったことへの証明に過ぎず、会社との労働契約を履行し労働を提供できなくなったり、会社に損害を与えたりすることは一切ないので、会社は民事訴訟の敗訴を「犯罪行為に手を染めた」と同じレベルで取り扱い、それを理由に懲戒解雇を実施すると、不当解雇と認定される確率が高いのです。
ただし、社員が休日に行なった不適切な行為がマスメディアなどに大きく報じられ、それにより当該社員の勤め先の取り扱う商品が不買運動のターゲットにされ、多大な損失を受けたのなら、会社が当該社員を解雇しても不当と認められない可能性があります。

今週の学び
社員が「犯罪行為に手を染めた」ら、労基法に基づき懲戒解雇を実施するという、一見めちゃくちゃ分かりやすいルールだが、実務的に案外しくじり事例が多いことはちょっと驚きですね。訴訟は民事か刑事、処罰が実刑か罰金、罰金を支払えば刑務所に入らずに済む的な実刑であるかどうか、そもそも判決が確定したのかどうか、これらの謎を全部確実に解いてみないと、安心して「犯罪行為に手を染めた」のを理由に懲戒解雇を実施できないわけです。判決書の見方に迷ったり、不当解雇にならないかとの心配があったりすれば、迷わずマサひろんに即コールです!