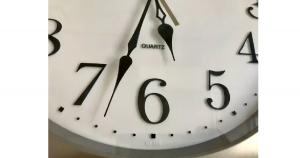子育て社員への後押し!育児環境の改善を図る3本の法改正(新規追加法規定を含む)

仕事と育児の両立に疲れ、どちらかと言えば育児に専念したいと考えるサラリーパーソンの方々は、育児休業取得のハードル及び休業中にもらえる育児休業手当の額を考慮し、なかなか行動に移せないことが多々あります。これらサラリーパーソンの声が聞き届けられたかのような、今年6月上旬の法改正で、果たしてプチ育児休業ラッシュを引き起こすかについて、これからは要注目です!気になる改正のポイントを早速押さえましょう!
育児休業取得の敷居を下げる
子供が満3才になるまでは、所定の手続きを踏めば、長さ30日~6ヶ月を超過しない育児休業を会社に対して申請できます。育児休業期間が6ヶ月未満の場合、取得回数が2回以内とされています。
(改正対象法案:無給育児休業実施弁法第2条)
育児休業手当の20%増額
育児休業を取得し、就業サービス法に基づき育児休業手当の受領申請を行おうとする対象者に対しては、今までの給付額を、標準報酬月額平均の60%から80%へ引き上げるという、いわゆる子供がもたらしてくれた昇給話でした。増額分は会社にではなく、政府が負担しますので、事業者の方の負担にはなりません。
(新規追加法規定:無給育児休業給与補助要点第5条)
6~7日間の妊娠検査休暇の実施に対しての奨励
妊娠検査休暇は法律上もともと5日と定められていますが(まもなく発効する改正性別労働平等法で7日に引き上げられる予定(リンク先の文章を参考))、会社が別途用意した福利厚生で、対象となった社員は6日~7日間の妊娠検査休暇を取得した場合は、7日間に2日分、6日間に1日分の日割り給与を政府から補助金が出る形となります。
(新規追加法規定:妊娠検査休暇給与補助要点第4条)
ここまで見れば、大体の変更点が分かってくるかもしれませんが、実際の運用時での要注意点、使用上の制限等、会社側にとってはまだまだ不明な点が多いことを想定し、台湾の労働部が公布した質疑応答の一部内容を参考に、分かりやすく日本語に直して下記のように共有させていただきます。ご参考の一助になれば幸いです。
運用中によくある質問まとめ
-
育児休業の申請は、20日前もって会社に対して提出必要との会社ルールってあり?
-
法律上は最長10日との定めがあったため(無給育児休業実施弁法第2条第1項)、労使双方の合意があれば、10日以内に短縮可能ですが、10日超える設定は違法となります。
-
ニュースで、夫婦共働きであっても、夫婦ともに育児休業休業 を取得可能との報道を見ました。じゃなぜ育児休業の申請に「配偶者の在職証明」を提出必要なの?
-
ニュースで報道された内容は今法改正の手続きが進められていまして、正式に発効するまでの間は、現行の法規定に従い、配偶者が無職でないことを証明できる書類を提出してから、育児休業を取得必要との形となります。
-
6/15~7/14の間に育児休業を取得しました。手当増額の20%はもらえるかね。
-
新規追加した育児休業給与補助要点は7月1日から発効しましたので、増額分は7月1日以降の育児休業を対象とします。同要点が発効する前から取得する育児休業で、発効後に続く場合は、増額分は7/1以降が対象とのロジックで比例計算したうえ支給される形となります。
-
去年、2020年12月20日から2年間の育児休業を取得しました。しかし、ルール上、育児休業手当の支給は今年、2021年6月19日に来て満6ヶ月となったため、これからは手当なしの育児休業となります。今まで受領した手当を全額返上し、7月から改めて育児休業手当の受領申請を行い、20%増額後の手当をもらうことは可能ですか。
-
返上後再申請はNGです!
-
20%増額後の手当はどれぐらいもらえますか。
-
増額前同様、最長6ヶ月となっています。
-
7月、会社に対して、6日間の妊娠検査休暇を申請しましたが、会社からは6日目を出してもらえませんでした。それは違法じゃありませんか?
-
妊娠検査休暇を7日に引き上げる法改正は今進行中でして、正式に発効する前までは、5日超の妊娠検査休暇は法定強制事項ではありません。ただ、現行ルールでは、6日目の日割り給与は政府から100%の補助金が出るので、例え6日目の妊娠検査休暇を社員にあげても、会社側に給与支払いに関する経費負担が出ません。この点をもって会社に説得することがお勧めです。
-
交渉の末、やはり会社は6日目の妊娠検査休暇をくれませんでした。代わりに出生前検査目的で、病気休暇か有給休暇を別途1日取得した場合は、当該1日分の日割り給与同様、政府から補助が出ますか。
-
妊娠検査休暇の枠で取り扱わないと、補助対象外となります。
-
会社は何時、労働保険局に対して、妊娠検査休暇への補助金を申請できるのでしょうか。
-
6日目、7日目の妊娠検査給与を確実に支払を行ったら、補助金の申請が可能となります。
以上のように、今回の法改正についてのQ&Aの要点を共有させていただきました。なお気にある点、ご不明な点がございましたら、気軽にマサヒロへお問い合わせくださいませ。