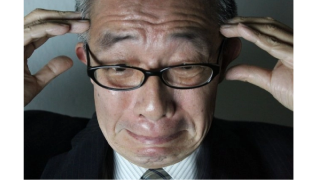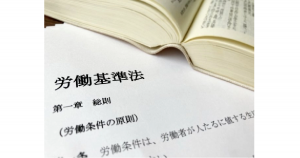脅威、不当解雇の逆襲!

企業のオーナー又は管理職をやっていたら、多かれ少なかれ、「従業員の解雇」を経験したことがあると思われます。解雇に至るまでは、多種多様な会社都合、又は対象となる従業員に何かしらの帰責事由があったと認められた場合が想定されますが、何をもって正当、不当をジャッジできるかと言えば、労働法に依拠し判断すれば概ね大丈夫であろうと思いきや、法律条項が表そうとする意味合いを間違って読み取ったり、労働法にあった曖昧な表現を自分なりに解釈したりすることで、事後になって、「不当解雇だ!」と突き付けられる事例が後を絶ちません。今回のレポートでは、いくつか不当解雇についての事例を共有させていただき、台湾においては果たしてどのようなシチュエーションが不当解雇に該当するか、についての認識が少しでも深まったら幸甚です。
台湾労働法における予告解雇
台湾の労働基準法では、対象社員に予告通知のうえ、解雇を実施することができる5つの事由が定められています。話し言葉的に直したら以下のような内容になります。
- 会社が解散したり売却されたりする場合
- 会社に赤字が出たり事業規模が縮小したりする場合
- 不可抗力があって事業停止1ヵ月以上の場合
- 事業内容の変更によって必要とされる労働者の人数が少なくなって、かつその他配置転換可能な部署がない場合
- 労働者は与えられた仕事を確実にこなせない場合
ここは、解雇手当が出る解雇手段です。第5号は一番よく使われる解雇要件ですが、何の基準をもって、「仕事を確実にこなせない」と判断できるかについての言及は労働法では未見なので、実務上、不当解雇につながる確率が相当高い要件の一つとなっています。
台湾労働法における懲戒解雇
上記の予告解雇はどちらかというと、会社都合による解雇の意味合いとされるのに対して、従業員に著しく問題があり、会社はそれによって何等かの損失を被ったことで実施可能な懲戒解雇もあります。台湾の労働法上では、懲戒解雇の事由を以下6つ用意されています。
- 従業員は雇用契約を結ぶ際に何かしらの嘘をついて、会社はそれを信じることで損害を受ける恐れがある場合
- 雇主、雇主の家族、雇主の代理人、同僚等に対して、暴行又は重大な侮辱を加えた場合
- 従業員が有期刑又はそれ以上の刑罰を受け、執行猶予又は罰金刑に換えられない場合
- 従業員が雇用契約又は就業規則に違反し、かつその情状がひどい場合
- 従業員が機械設備、器具、原材料、製品その他会社の所有品を故意に消耗したり、会社の技術、営業秘密を故意に漏洩したりすることで、会社が損失を受けた場合
- 従業員が正当な理由なく3日間連続して無駄欠勤したり、もしくは1月間無駄欠勤の合計日数が6日に達したりする場合
また、第3号を除き、その他の事由をもって解雇を実施しようとするならば、対象事由の存在を知った日から30日内に実施しなければできない形となる点は要留意です。
この6つのなかで、実務的に解雇要件として使われている頻度が高いのは第4号ですが、予告解雇の第5号と同じく、何をもって「情状がひどい」と言えるのかについての基準がなされていないから、こちらは労使紛争の火種と言っても過言ではない要件となっています。では、いくつか不当解雇と判断される事例を見てみましょう。
不当解雇の事例その1
D事業部門とB事業部門を有するDB社は、B事業部門がこの間どうも採算が取れない様子で、何とか持ち直そうと考え人員削減を実施しようと、社員のヤムチャ君をクビにしました。大食いペットを飼っているヤムチャ君はそれによって、生活難に陥ったわけなので、警察官をやっている友達のクリリンに相談したら、DB社を相手取って「雇用関係存在確認」の訴訟を起こしたらと言われ、ヤムチャ君はその通りに行いました。
結局、裁判官は、ヤムチャ君の解雇に理由のないものとして不当であると判断し、ヤムチャ君がクビになった日から不当解雇の判決が確定する日までの給与を、DB社は彼に払わなければならないとしたうえ、ヤムチャ君との雇用関係を継続せよとの判決を言い渡しました。
DB社は当初、ヤムチャ君をクビにした理由は、上記に話しのあった予告解雇の第2号、「会社に赤字が出たり事業規模が縮小したりする場合」です。B事業部門でのセグメント別財務データでは赤字が出て、労基法に基づいて合法的に人員削減を行っただけなのに、なぜだめなのかというDB社からの抗弁に対して、裁判官は、赤字や事業縮小を解雇事由とする場合には、個別の事業部門又は営業項目ではなく、会社全体の経営状況や経営能力を総合的に判断する必要があり、1部門にしばらくの間で赤字が出て、これからは全く好転しないとも言い切れず、なおかつその他部門が好調で、雇用拡大さえ実施するのであれば、配転を行えば済む話しなので、あえてヤムチャ君を解雇するまでもないのではと、だから本件は解雇の最後的手段の原則に反するものとして不当であるとの結論を下しました。(最高裁判所2020年度台上字第1518号民事判決をもとに)
ポイント:単に一時的な赤字又は1部門のみの赤字による解雇は問題になりやすいのです。
不当解雇の事例その2
ナント社は199×年に子会社を設立しました。設立当初は人手が足りなかったため、ナント社は人事担当のケンシロウ君に、子会社の人事業務もやれと命じ、こういった兼務体制がしばらく続いていました。
ある日、ケンシロウ君はナント社から、”自らの意思で兼務を行う”との同意書にサインしろと言われ、サインしなければ昇進や昇給に響くよとのはんば脅しのような説明を受けました。兼任生活が始まって以来、1日の寝る時間は長くても2時間のみで、今まで日課にしてきた北斗神拳の練習さえままならず、自分に「兼任を希望する」のような嘘をつくことはどう考えてもできないと思い、ケンシロウ君は同意書にサインすることを拒否しました。
翌週、ケンシロウ君は直属上司のジャギから呼ばれ、貴方は会社から与えられた業務をもはや遂行できないので、You are FIRED!と宣告され、即日クビとなりました。
繁忙なサラリーマン生活から解放され、ようやく北斗神拳の練習を継続できたものの、上の空の状態で無機質的に拳を繰り出し続けるケンシロウに、ずっと憧れの先輩であるトキから声を掛けられ、どうしたのとの一言に、ケンシロウは急に泣き出してクビになった経緯を話し出しました。正義感溢れるトキはそれを看過できず、ケンシロウに信用できるとある国際法律事務所を紹介し、不当解雇の裁判を起こそうと助言しました。
出廷したナント社から委託を受けた弁護人は、ナント社が作った子会社は、自らの事業部を切り離し子会社化にしただけの実体であって、形上こそ両方の人事業務を兼任するように見えますが、2社の意思決定は全てナント社に委ねられているので、ケンシロウ君は実質1社の人事業務のみやっていると主張しているほか、ケンシロウ君を解雇したのは兼務同意書にサインしなかったとの理由ではなく、あくまでも彼が199×マイナス1年のときから、頻繁に遅刻したり、会社が要求する社内訓練に出席しなかったり、レポートの作成が遅かったりといった事実があってからだと。
裁判官の見解では、ケンシロウ君には遅刻等の問題があったものの、解雇年度を含めここ数年間の人事考課で甲の評価結果であったことを考慮し、ナント社にとってケンシロウ君の問題点は実際取るに足らず、些細なミスであったことが分かります。なお、子会社業務の兼任を要求するには、ナント社とケンシロウ君が当初締結した雇用契約の内容を一部変更しなければならないため、当事者双方の同意なしでは成立しないほか、配転5原則に違反する節もあったようなので、ナント社には不当解雇の行為があったと認め、ケンシロウ君は不当解雇期間中の給与を全額ナント社に請求できるとともに、雇用関係の回復を請求する権利を有するものとしました。
ポイント:仕事の兼務には雇用条件の変更に該当し、会社がそれを一方的に要求できず、かつ配転5原則に違反していないかは要チェックです。
不当解雇の事例その3
ジオン社に務めて10年超のベテラン社員はある日、労働組合を作ろうと動き出し、賛同する社員たちが互い協力し合ったおかげで短い間に組合ができました。それを知ったジオン社は、組合に加入したベテラン社員に組合の脱退を要求するほか、別途委任契約の締結を強要し、労基法から守られている立場から外そうとしていました。ジオン社と別途委任契約を締結することに違和感を覚えたギレン君はそれにサインすることを拒否し、ジオン社はそれを理由にギレン君を解雇しました。
ギレン君が解雇になったことを受け、同社の労働組合はそれに徹底的に抗議する意思表示として、ジオン社の自社ビルの入り口あたりでデモ活動を行うと同時に、ギレン君の解雇が不当解雇であると裁判所に訴えました。
本件裁判の審理を担当する裁判官からは、ギレン君の解雇は、労基法での予告解雇又は懲戒解雇に定めのあった事由のどれにも該当せず、正当性のない解雇としてジオン社に敗訴を言い渡しました。
本件事例は、あからさまな不当解雇なので、特に争点となり得るポイントはなさそうに見えますが、ジオン社から強要され、委任契約にサインしたベテラン社員の扱いはどうなるかというと、労働法の観点では、単なる契約の名義で雇用関係の有無を判断するのではなく、会社と社員の間には実質的な「従属性」があるかどうかで判断すべきとされています。例えば、社員が業務を遂行するにあたって、会社の指揮命令に置かれているか、それとも自らの判断で仕事を行えるか、若しくは通常の社員と同様な出退勤時間を守って出社する必要があるかといった点は、従属性の有無を評価するポイントとなります。
その意味で言うならば、ベテラン社員が仕方なくサインさせられた委任契約は当局から無効とみなされる可能性が非常に高く、対象社員たちは引き続き労働法に基づいてジオン社に社員としての権利を主張することが可能となっています。
ポイント:文面証拠を作ることも大事ですが、実質的な関係を疎かにしたら、文面を作る努力が無駄となりかねないんです。
不当解雇の事例その4
シノブ君はコエンマ社の現場作業員として、6年もの間現場作業に一筋で頑張ってきました。6年が過ぎたとある日、シノブ君はコエンマ社から、当社は完全自動化生産を導入し、現場作業は必要なくなったため、残念ながら労基法第11条第4号、「事業内容の変更によって必要とされる労働者の人数が少なくなって、かつその他配置転換可能な部署がない場合」に基づき、貴方を解雇しなければならないと言われ、予告期間終了後コエンマ社から去りました。
頑張り屋のシノブ君は、その後まもなくして探偵事務所のアシスタントの仕事を見つけ、セカンドキャリアを始めました。ある日、コエンマ社時代から親交が深いイツキ君から情報が入って、オフィスの実務担当という、シノブ君とは部署が違いますが、シノブ君最後の年と全く一緒の賃金で入社した新人、ユウスケ君がいったとの話しを受け、じゃ、その時自分を事務担当のほうに配転したらよいものの、クビにしてからすぐ新しい人を募集するってあり?と思い至ったシノブ君は、自ら訴状を書いて裁判所へ送りました。
コエンマ社は完全自動化生産を導入したため、「事業内容の変更」があったと認めるが、シノブ君を解雇すると同時に新入社員を迎え、かつ賃金も全く一緒で、仕事内容もシノブがこなせない専門的なものではなく、「その他配置転換可能な部署がない」との要件を適合しないと考えられるため、シノブ君の解雇は違法であると、裁判官が結論付けました。
上記事例とは別に、例えば同じグループに属するA社とB社があって、A社に「事業内容の変更によって必要とされる労働者の人数が少なくなって、かつその他配置転換可能な部署がない」状況が生じた場合には、 一部の社員を解雇できるかというと、もしB社は実質A社の管理下にあって、A社はB社の人事、財務、経営等をコントロールできる場合には、「その他配置転換可能な部署がない」を検討する際、B社も検討に入れなければならないとの裁判所からの見解がなされており(最高裁判所98年度台上字第652号民事判決)、気を付けなければなりません。
ポイント:事業内容変更の有無に気を取られ過ぎて、その他配置転換可能な部署についての検討が疎かになっていないかは要留意。
不当解雇の事例その5
スラム銀行の社員である花道君は、競合のダンク銀行が実施するクレジットカードキャンペーンの特典が欲しくて、インターネットの掲示板で、ダンク銀行のクレジットカードを申請し、カードが下りて1ヵ月内に1回以上使っていただける方に、展示会のチケットを贈呈します、との書き込みを残しました。それを知ったスラム銀行は、競合銀行のカード発行業務に手助けをしたことを理由に、花道君を懲戒解雇にしました。当該懲戒解雇の処分に納得がいかない花道君は、裁判所に不当解雇の訴えを起こしました。
本件裁判を担当する裁判官は次のような見解を示しました。花道君の行いには確かに問題がありますが、「最後的手段の原則」の観点からして、こういった問題行動はスラム銀行との雇用関係の継続に支障を来すとは考えにくいです。なぜなら、花道君がインターネットでの書き込みでは、スラム銀行に関する言及がなく、連絡先にスラム銀行の電話を使ったが、一般人が見たらそれがスラム銀行の電話だとすぐわかることはあり得ません。そのほか、花道君が書き込みをしたのは、競合銀行のクレジットカードの宣伝目的ではなく、単に特典が欲しいとのことと、ネット住民とのやり取りでうっかりスラム銀行のメールアドレスを使用してしまったことで、花道君がスラム銀行の社員であることが知られただけで、故意に自分がスラム銀行の社員であることをアピールする意図がないように思います。問題行為を起こした花道君に対しては、けん責処分を下したら結構であり、懲戒解雇の実施は過度な措置なのではと思われます。なお、花道君がスラム銀行に勤めて既に満10年、スラム銀行もその後マスメディアや関係者からの問い合わせに対して適切な説明を行っており、実質な損害を被ったわけではないため。労基法第12条第4号の、「従業員が雇用契約又は就業規則に違反し、かつその情状がひどい場合」の事由をもって花道君を解雇することに正当性が認められないとしました。
ポイント:社員が就業規則に違反した場合には、比例の原則と最後的手段の原則に踏まえ、懲戒解雇の実施に正当性があるものかをしっかりと検討必要。
To Be Continued...
星の数だけ、不当解雇の事例がある。解雇行為はごく普通に、毎日のように繰り広げられています。その中では、果たしてどれぐらいの割合で適格な解雇行為に該当するか、何パーセントが不当解雇と判断されるかについては、100%完全無欠な解雇を実施しており、当局から問い合わせが来ても胸を張って、うち絶対大丈夫だよ!という風に主張できる雇主は恐らくそう多くなく、通常の場合は大体、なんとも言えないもやもやな気持ちがあったものの、解雇を実施しなければ示しがつかないから、とにかく解雇しよう!とのシチュエーションは一般的かもしれません。一番怖いのは、解雇を実施して1ヵ月が経って、3ヶ月が経って、6ヶ月が経たないうちに裁判所から通知書が来て、貴社は元社員の人から不当解雇で訴えられて、〇月〇日に説明に来てください、のような展開です。そうならないように、解雇を実施する前にしっかりと関連法律を調べ尽くしたり、労働法の専門家の意見を聞いたりすることがお勧めです。
Attention!
※本稿は2021年10月14日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。