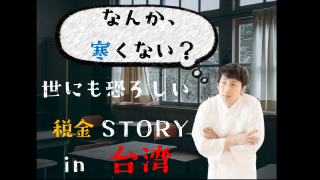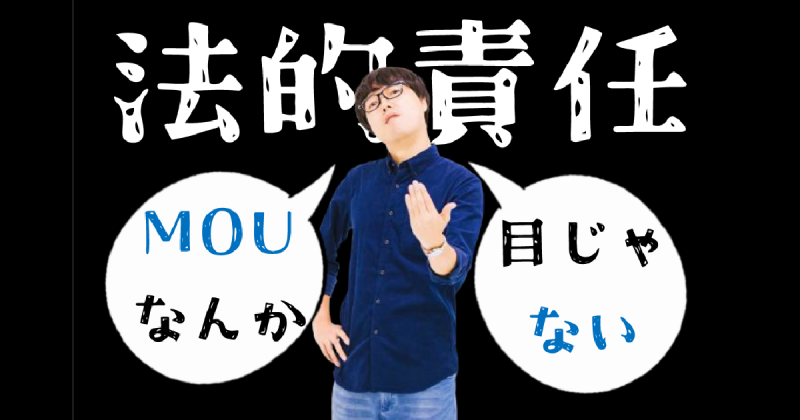世にも恐ろしい税金STORY in 台湾
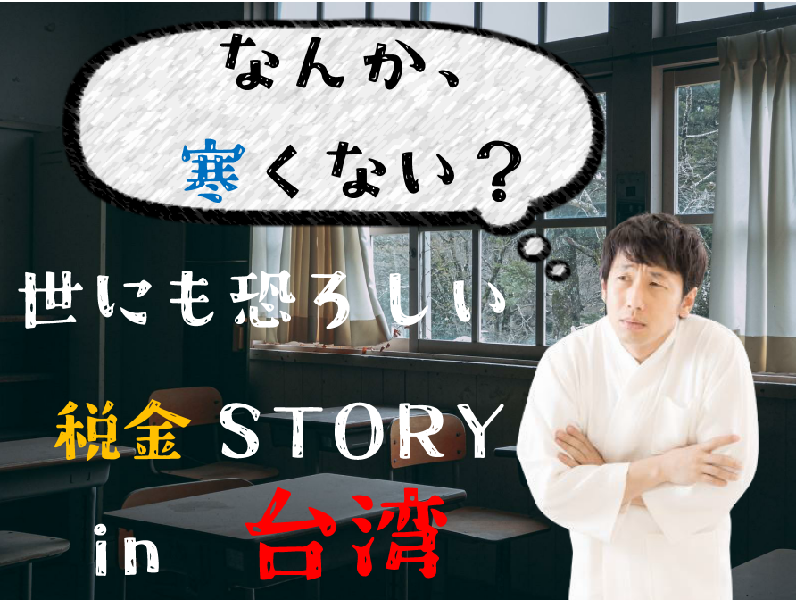
利益を得れば、そのうちの一部を税金として国に納めます。それが宇宙に通用する常識です。ただし、利益のどれぐらいで納税したらよいかといえば、ここは見解が分かれるところです。
所得の種類が単純で(例えば給与所得のみのサラリーパーソン)、金額も低い場合でしたら、国税が自動計算してくれたり、みなし課税制度を利用したりすることで、税金計算に手間をかける必要はなく、政府から納税書が届いたら、それを素直にコンビニや銀行等へもって支払ったら終了です。(昨今、クレジットカードやデジタル決済で納税する方法もすごく人気)
一方、会社から給与を受領しながら、株投資で配当金がもらえ、休日祝日はプログラマーとして業務委託料を稼いでいる等、得られる所得の種類が複数であったら、自ら適正な納税額を算出しなければならない場合があります。そこで、「どのように計算したら節税可能か」との質問が自然に出てきます。
節税活動のポイントは、主に以下2つの目標を如何に達成するかになります。
節税活動のポイント
- 課税所得を非課税所得にすること
- 適用する税率をなるべく下げること
法に逸脱する形で上記の目標を達成しても、結局脱税行為になってしまい、追徴課税を食らうのみならず、ペナルティを受ける可能性も極めて高いです。そうならないよう、なおかつ節税効果を限界まで押し上げるためには、家族の力を合わせ、自ら出資した会社やそのグループ会社を巻き込んで、法律に触れない形でアクロバティック的な調整を諸々行うことで、節税対策に積極的に取り組んでいる活動が一部の富裕層の間でなされています。
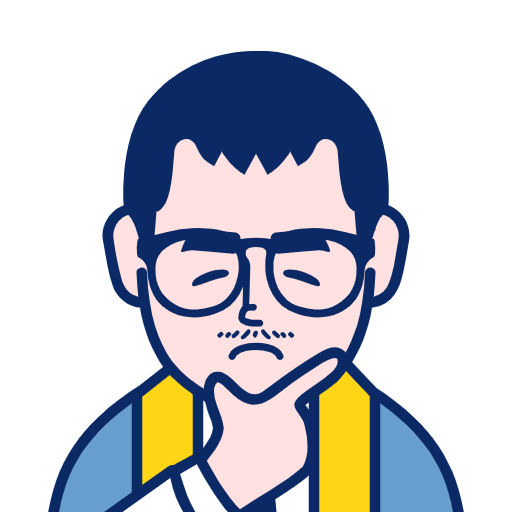
違法していないから、こういった節税活動がなされていても、台湾の国税も黙るしかないのでは。
と考えられるかもしれません。ただし、台湾の国税が本気になって、通常では課税されないかもしれないケースであっても、「実質課税の原則」、という形上のルールを無視できる最終兵器を持ちだしたら、如何なるタックスプランニングも形無しになってしまうかもしれません。
今週のマサレポは、2000年前後の台湾に起きる、めちゃくちゃ泥沼にはまり込んでいる数億NTD規模の節税作戦を紹介させていただきたいと思います。分かりやすさを考慮し、かつ物語の当事者を特定される可能性を低くするため、一部の内容を適当に改変のうえお伝えする形になりますので、ご理解のうえご覧になってください!
目次
第1話 きっかけは、黒船の来航・・・
2000年ごろ、台湾のファンド(投資信託)事業が高成長を続いていました。それが外資企業の目に留まり、片っ端から台湾の投資ファンド会社に声掛けし、資本参加の意欲を強くアピールしていました。そのとき、一攫千金のチャンスを狙おうと、運営実績がよいYファンドの責任者であるV氏が手をあげ、いくつか名だたる外資企業とファンド譲渡の可能性について交渉し始めました。
Yファンドの譲渡に関する話し合いを何回か繰り返しているうちに、比較的よい買収条件を提示した某アメリカの大手保険会社が一番の有力候補であることが浮き彫りとなりました。同保険会社を買い手とする前提に、V氏が諸々事前準備作業を水面下で始めようとしていました。手始めに対処しなければならないのは、Yファンドの売却で得られる利益に課される税金をできるだけ抑える方法等ないか、という課題でした。
第2話 億万長者ならではの節税術
一切対応方法も講じず、そのままYファンドを売って、そして素直に納税すれば、売却益のほぼ半分ぐらいが税金として消えてなくなってしまいます(2000年前後、台湾個人所得税の最高税率は40%)。それだけは何とか阻止しようと考えているV氏は、大手会計事務所に相談を持ち掛けました。相談会議を重ねて得られた結論は、V氏の家族メンバー及びメンバーそれぞれが出資した会社を巻き込んで、売却益自体を「消滅」するか、またはその性質を「免税所得」に変身させる、という一世一代のビッグプロジェクトを、アメリカの大手保険会社にYファンドを売り渡す前に実施する、とのスキームでした。
Yファンドの株式はV氏が直接に所有するわけではなく、自ら及び家族が出資した2つの会社が保有していました。通常の場合、Yファンドの株式がアメリカの大手保険会社に売却されたら、当該2社に売却益が発生し、そして売却益が会社の配当金としてV氏やその家族に分配されたら、40%の個人所得税が取られます。それを回避しようと、V氏はまず当該2社を操作し、Yファンドの株式を非常に安い対価で自ら及び家族が100%出資したその他会社3社及び知り合いのL氏に譲渡させ、そして、当該3社と個人にアメリカの大手保険会社との取引に応じさせることで、Yファンドの譲渡を無事完成させました。
当時、個人が取得する株式の譲渡益は免税所得であったため、L氏が譲り受けたYファンドの株式をアメリカの大手保険会社に売却しても、税金は発生しません。また、V氏及びその家族が100%出資したその他3社は、Yファンドの株式を譲り受ける直前は欠損状態であり、アメリカの大手保険会社から多額の売却益をもらっても、過去の欠損金と相殺させたら、課税される利益分はほとんどなくなって、実質の税負担はゼロに等しいものとなっていました。
今回の株式譲渡取引で、予測として数億NTD程度の税金が発生しているものの、緻密な計画を事前に立てて、関係者が一丸となってその通りに実施できたおかげで、ほとんど税金を払わずに膨大利益を得られたと、V氏及びその家族にめでたしめでたしの雰囲気で溢れていました。
その後、Yファンドの持株会社だけに作ったV氏ファミリーが所有するいくつかのグループ企業は、株式の譲渡により機能がなくなったため、そのまま放置しておいても無駄なランニングコストが発生するばかりと考えるV氏は、最短期間で債権債務関係を綺麗にしたうえ、順序よく会社の解散手続きを行うことにしました。こうして、通常のパターンでは到底考えられない、少額な税金を払うことで、膨大な株式の売却益を享受できる大作戦が一段落しました。ただし、宴のあと何が起きるのか、当時のV氏及びその家族メンバーは知る由もありませんでした。

第3話 忍び寄る国税の影
Yファンドの株式を売却した年におけるV氏ファミリーの個人所得税は、国税から変に思われることなく無事申告手続きが終了し、その翌年も似たような感じでやり過ごすことができました。事の始まりは、当初Yファンドの持株会社として作った、とあるV氏のファミリー企業の解散手続でした。
台湾の会社を解散するには、まず主務機関に解散登記を行い、各種税金を申告し、債権債務者の公告を行って、そして裁判所に対して清算人選任の申し立てや清算結了の報告を行う、といったプロセスが要求されます。そのうち、一番時間がかかり、問題が起きやすいのは税金に絡む手続きです。V氏が行った節税大作戦は、後一歩で完璧に仕上がるところ、よもや当初の持株会社の解散に必要とされる税金の申告手続きで、国税に目をつけられてしまうとは、想像だにしていなかったはずでした。
マスメディアで一時的大きく報じられていたYファンドの売却取引においては、取引が行われる直前に、その株式はいきなりV氏の持株会社からその他V氏が出資した会社や個人に、市場価格より全然安い値段で譲渡され、なおかつアメリカの大手保険会社から相当な売却益を受領していたにもかかわらず、結局持株会社を含めた関係者はほとんど税金を払っていませんでした。解散した持株会社の法人税確定申告書にこういった尋常でない点に気付いた国税は、それに関与した関係者数人にヒアリングを行ったり、銀行側に対して本件取引に関わる金の流れを調査したりして、事実関係を深堀っていきました。
いろいろ調査の結果、V氏はYファンドの譲渡取引において、租税回避を行うだけの目的で、一見法律に違反していないに見える、経済的実質が伴わない不正行為又は仮装隠蔽行為と認定される処理を行ったとして、国税はV氏及びその家族に対し、合計数億NTDの追徴課税及び過料を課すことを決定しました。(所得税法第66条の8。2018年の法改正で同条が削除され、追加された同法第14条の3に受け継がれた)
第4話 エンドレスな敗戦処理の始まり
国税からの納税命令を受けたV氏は寝耳に水でした、大手事務所の公認会計士から受けた提案の通りに実施していたのに、何故っと。「諦めたらそこで試合終了ですよ」ということで、諦めの悪いV氏はまず顧問弁護士を通して国税に不服申し立てを行い、国税からの再審査結果で税金がほとんど減らなかったことが分かったら、今度は裁判所に行政訴訟を提起し、法廷で国税と激しい弁論を繰り広げていました。
V氏が数年かけて、たくさん弁護士費用を払い、最高裁まで行ったものの、とうとう朗報を聞くことが叶わず、最終的に過料を含めた数億NTDの税金を国税に払わなければならないとの結果が決定となりました。
できるだけの努力を行ったうえ勝負に負けたのだから、このとき潔く税金を納めれば、少なくともスポーツマンシップを示せたと考えられますが、このときのV氏はいくつかの投資案件に大損を出したようで、手持ち現金が非常にピンチな状態でした。海外の持株会社から資金調達を行うしかないと思うが、どういった大義名分をもって台湾へ送金したらよいかを悩んでいるV氏は、公認会計士に提案を求めました。
海外の持株会社が保有する現金は、以前台湾の持株会社から移したもので、送金の際に一切会計処理をやっていなかったから、今になって台湾へ返金する名目に困り始めたのでしょう。じゃこうしよう。まだ存続している台湾持株会社の決算書を遡って修正し、以前行った海外への送金を「株主への貸付」として処理。そして資金を海外の持株会社から台湾へ移したら、当初の貸付への返金として、「株主への貸付」の残高を相殺する、との案で行こう!
という風なアドバイスを会計士から受けたV氏は、直ちに会計士に決算書修正申告の業務を頼んで、海外の持株会社から台湾へ送金させる作業に取り掛かりました。

第5話 納税、そして...
公認会計士の協力があって、決算書数年分の修正申告手続きがあっという間に終了し、それを合図に、V氏は間髪を入れないスピードで海外から台湾への送金作業を完成させました。

これで、ようやく若気の至りを清算できる数億NTDの軍資金を手に入れたな。
通帳を手に残高を遠目に眺める(老眼?)V氏は感無量的にこの一言を漏らした後、台湾憲法に定める納税義務を果たしました。こうして、「世にも恐ろしい税金STORY in 台湾」が幕を閉じた、かと思いきや、ストーカー根性を丸出しにした台湾の国税がまだ動き出しました。
第6話 ブーメランの如く
台湾の所得税法第24-3条の第1項においては、株主、取締役、監査役が会社に代わって金銭を受領したものの会社に返金しなかったり、もしくは会社の資金を私的利用したりするとき、受領又は私的利用した者が会社に返金するまでの期間に応じて、会社にそれなりの利息収入があったとみなし、それをもとに納付すべき税金を算出したうえ課税しなければならない、と定められています。
納税目的で、数年遡って決算書の修正申告を行ったのはよいだが、この修正作業によって、過去の帳簿上に数億NTD規模の「株主への貸付」が爆誕し、税金に飢えている国税にとって、まさに最高の餌食でした。
まもなくして、国税は前述した所得税法第24-3条を法的根拠とし、台湾持株会社修正後の決算書(過去の分)にあった「株主への貸付」に見なし利息を付けて、V氏に対して2度目の追徴課税を行いました。

数億NTDの納税を行ったばかりなのに、またもや訳の分からない理由で税金を強奪してくるとは...
国税から納税通知書が届いたY氏は魂が一瞬火星へ飛んでいきました。しばらくしてから、

まあ、どうせこれが最後なんだから、国税への手切れ金として払おう。
気持ちを持ち直したV氏は、その後台湾の持株会社の口座から数百万NTDの税金を国税へ振り込むようにしました。

第7話 国税、アビスからの覗き込み
国税からのクリティカルアタックを2回も食らったV氏は、ようやく落ち着いて、これからの人生についていろいろ考え始めようとしているところ、まだまだ国税から憎たらしい納税通知書が届いてしまいました。
当初、台湾の持株会社から海外の持株会社へ資金を動かしたときの送金先口座と、この前資金を海外から台湾の持株会社に動かしたときの送金元口座が一緒ではないため、海外からの振り込みは以前の借金に対しての返金ではなく、明らかにその他目的による送金である。従って、帳簿上における「株主への貸し付け」の相殺は認められず、みなし利息による追徴課税を継続する。
という悪魔の理不尽があふれる文書がY氏に突き付けられました。

国税のATMじゃないから、黙ってそれ以上払うものか!
と憤ったV氏は、すかさず弁護士に架電し、国税に反旗を翻す準備をすぐ整えろと指示しました。
結局、V氏が行った絶望への反抗をものともされず、国税とその上級機関である財政部に対しての不服申し立てが悉く撃沈され、高裁で行われた行政訴訟もあえなく負けてしまいました。
第8話 希望の花
対国税的に負け続けていることもあって、心は既に折れたV氏は、心底では「Lets it Go」の気持ちが強くなる一方だが、どうせそれ以上失うはないと思い、ダメ元で弁護士に最高裁への上告手続を依頼しました。
おかしいことに、訴状を提出してから3ヶ月、半年、1年が経っても、最高裁から一切音沙汰がありませんでした。ただ、最高裁で行われるのは法律審であり、口頭弁論は必要とされないため、出廷して進捗を確認ことはできず、V氏は指をくわえて待つしかありませんでした。
関係者の間では、本件行政訴訟がほとんど忘れられ、訴状の提出日から2年が経とうとするとき、ついに最高裁からの判決書が送付されてきました。
台湾の持株会社の帳簿上での「株主への貸し付け」は、海外からの送金で相殺処理できるか問題について、単に口座名義の違いを根拠とし、V氏が行う相殺処理に合理性が伴わないと判断するには説得力が欠くように思う。こういった追徴課税のケースにおいては、国税に要求される立証責任がもっと重いはずなので、しっかりと当該海外送金・返金の件に関する事実調査を行うべきだと考えられる。
台湾の行政最高裁はこういった判決理由を述べ、原判決を破棄し高裁に差し戻しました。
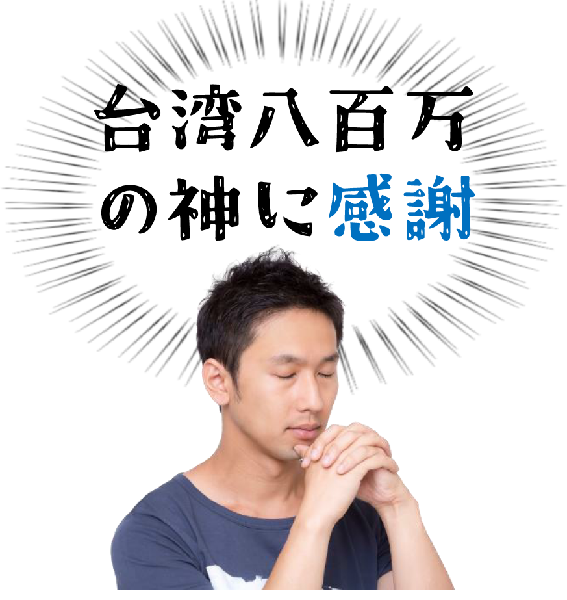
エピローグ
V氏の案件は、2022年現在になってなお、台湾の行政高裁で審理が進んでいます。ただ今までと違うのは、国税の態度が少し柔らかくなったようで、貸付金の相殺について比較的V氏に有利な観点を取るようになり、双方で妥協点を見つけるうえ和解する方向で、V氏に提案してあげたようです。
一方、貸付金の相殺は認めるが、V氏が台湾の持株会社の資金を、譲渡益による追徴課税の納付に充てることは、また新たに「株主への貸付」を作り出し、みなし利息による更なる追徴課税は免れない、という風な見解を国税が示してしまいました。このままだと、どこで妥協点を探ったらよいか、という極めて難しい課題をV氏はこれから直面しなければならないでしょう。
上記、台湾の税金に纏わる怖い話からも分かるように、節税活動は線引きが非常に難しいことです。手間暇かけて、形式を万全に整えたと認識したとしても、明らかに税金の法律に違反したわけではなく、「経済的実質が伴わない」、「通常のビジネス行為にしてはおかしい」、「取引に関与するのはほとんど関係者」、「結果として納税額が結構減った」といった比較的主観性が強い特徴が存在すれば、追徴課税のリスクがいきなり上昇してきます。
かといって、ただ素直、無機質に、年間で稼いだ所得に税率を乗じて納税額を算出するだけではちっとも面白くありません。国税のHPも折に触れて節税可能な措置を紹介し、無駄な税金を払わないような記事をリリースしているから、過度にならなければ、節税活動はむしろ推奨されるべきものです。
今行っているビジネスで、何等かの節税活動ができそうですが、いざ実施してしまうと、台湾の国税から租税回避と認定し、追徴課税されるリスクないか、と心配するようであれば、博打的に思いついたタックスプラニングを実施する代わりに、当該プラニングの詳細を書面にまとめ、それが租税回避行為に該当するか予め判断してもらうよう国税に提出する対応方法がお勧めです。もし国税からOKサインが出れば、安心してプラニングの実施ができるというわけです。V氏の話しを教訓に、節税活動を丁寧かつ慎重に行いましょう。
節税活動への助言、節税活動に関するリスクマネジメント、又は将来における節税活動について国税に見解を述べてもらう書状の作成代行をご希望の方は、是非とも気軽にマサヒロへご相談くださいませ。