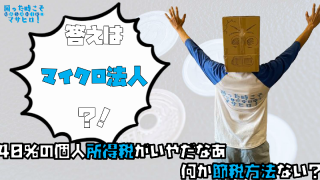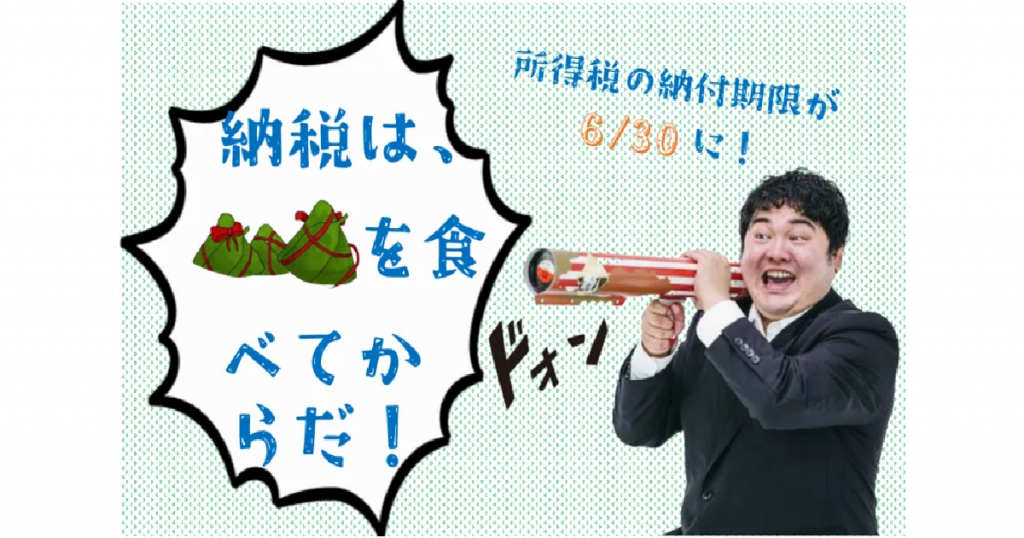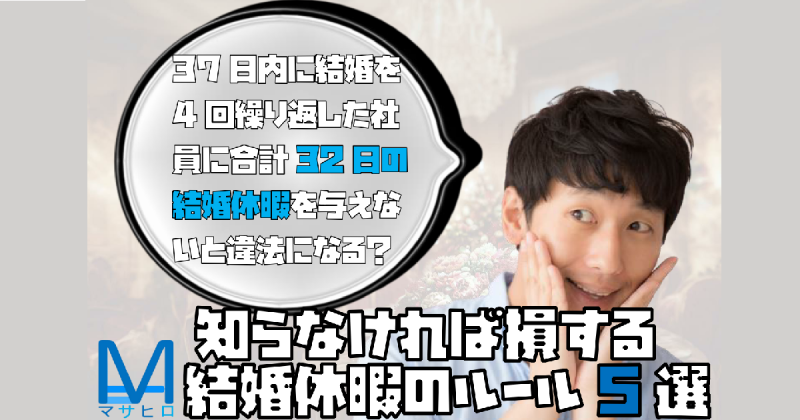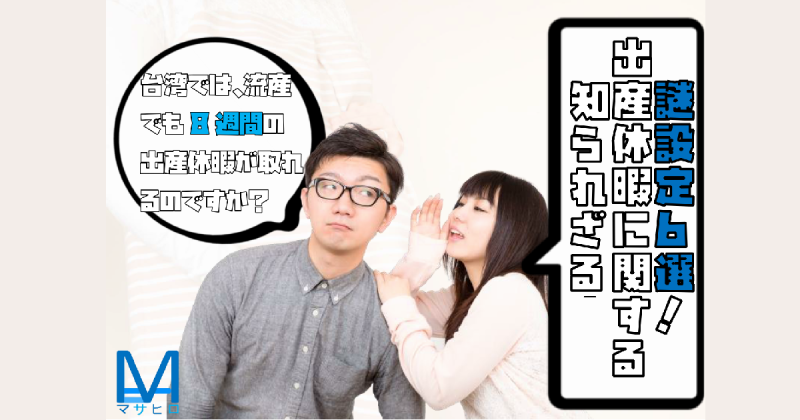40%の個人所得税がいやだなあ、何か節税方法ない?答えはマイクロ法人?!
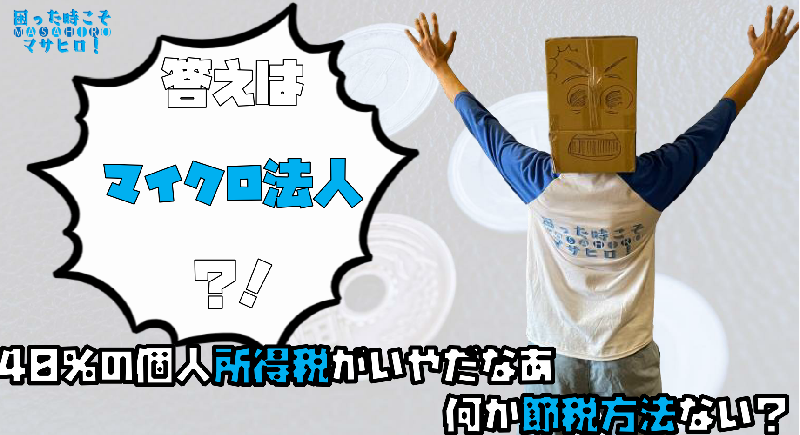
日本人の方が日本と台湾を行ったり来たりして、台湾での年間滞在日数が183日未満であれば、所得税法上は非居住者扱いであり、稼いだ所得は原則として18%課税されるのに対して、1年の半分以上が台湾に滞在すれば、居住者扱いとなり、稼いだ所得は最高40%の超過累進税率で課税されます。
前者のほうは税率がめちゃくちゃ高いわけではなく、一定の要件をクリアできたら、租税協定を利用して税金は全額還付を受けられる可能性もあるので、そのままでもいいかもしれませんが、後者のほうは、ほぼ所得の半分が取られてしまうので、それを考えたら、仕事に一生懸命取り組んで、体を壊すまで給料を稼げば稼ぐほど虚しさが募るばかり、といった気持ちを持つ方は少なくないかもしれません。
たくさんの家族メンバーを扶養したり、家賃または不動産ローンの利息を払ったりすれば、一定額の所得控除が受けられ、それなりの節税効果が得られますが、それらのみでは、30~40%の税率が適用される事実はやはり変わらない可能性もあるりますので、何かもっと根本的な節税方法ないかと言えば、

「マイクロ法人」を作ったらどうですか?
との声があがったりしています。
何故「マイクロ法人」という選択肢が浮かんできたのか、マイクロ法人を作ったら、リスクなしで完璧に節税できるものなのか、といった疑問点を中心に、台湾の税金に関する法律を踏まえて軽く考察してみたいと思います。気になる方はどうかついてきてください!
個人所得税VS法人税
台湾での年間滞在日数が183日未満の外国人に適用される所得税率は18%であり、台湾の法人税率が20%であることを考えたら、マイクロ法人を作るメリットはあまりないとのイメージが強いなので(実際はそうとも限らないですよ~)、以下は最高税率40%が適用される、滞在日数が183日以上の外国人居住者を前提に話を展開いたします。
どストレートな話し、例えばサラリーパーソンとして年間500万NTDの給与所得を受領するとして、40%課税されると、手取り給与が300万NTDとの計算になります。一方、マイクロ法人を作って、就職先の会社と業務委託契約を締結し、そして業務委託料として年間500万NTDを受領したら、20%の法人税を差し引くと400万NTDが手元に残ります。

手取りが100万NTDも違うから、マイクロ法人を作るの一択っしょ!
「課税所得をより有利な種類に調整する」ことと「できるだけ税率を低いほうを選ぶ」といった、税活に必要不可欠な2本柱的な要素が考慮されるわけなので、本筋が間違っていない考え方と言えましょう。ただし、以下の設定に考えが及ばなかったふしがあります。
ATTENTION!
- 個人所得税の計算は超過累進税率に基づき行われますので、たとえ40%の税率が適用されたとしても、「課税所得×40%」ではなく、「A×5%+B×12%+C×20%+D×30%+E×40%(課税所得=A+B+C+D+E)」との算式で納税額が計算される形なので、給与所得として500万NTDをもらうケースの手取りは300万NTDより多くなります。
- マイクロ法人で稼いだ所得から法人税を差し引いた「配当金」は個人に配られます(もちろん無配にすることもできます)。個人が当該配当金をもらう対価として別途個人所得税を納付する必要がありますので、マイクロ法人スキームを採択する税負担は法人税だけでなく、「配当金にかかる個人所得税」も要考慮です。
- 個人所得税の計算は、会社からの給料に直接税率を乗じて税金を求めるわけではなく、どなたでも享受できる免税額(基礎控除に相当)と諸々控除を差し引いて課税所得を求め、それに税率を乗じて納税額を計算する仕組みです。一方、法人税の計算も同じ理屈で、年間売上から売上原価と諸経費を差し引いた課税所得に税率を乗じて法人税を求める形となります。後者のほうは減算項目が多いため、税活のインパクトが大きいだが、しっかりとした記帳作業が必要とされるため、税法に疎い方にとってはハードルは高いかもしれません。
- 会社の税負担を考慮するにあたって、法人税とほぼ同じ存在感を有する営業税も考えなければなりません。営業税の仕組みを簡単に説明すると、販売税額から仕入税額を差し引いた残額を2カ月に1回政府に納付する、との手続きです。マイクロ法人の税負担が20%の法人税のみだと思い、すぐ脱サラして税活に取り組んだりすれば、営業税の仕組みに見え隠れする落とし穴にはまる可能性が低くありません。何故なら、サラリーパーソンからマイクロ法人のオーナーに鞍替えしたとしても、毎月決まった調達活動が急に発生してくるわけではないので、控除可能な仕入税額がほとんど手に入らないなかで、業務委託料×5%の営業税を2カ月に1回払わなければならなくなり、そうすると、マイクロ法人スキームの税負担は実質20%の法人税+5%の営業税となってしまうからです。

423,000NTDの壁
台湾のサラリーパーソンが毎年の5月に個人所得税の確定申告を行うとき、何ら努力をしなくても、会社でもらう給料から少なくとも423,000NTDの控除が受けられ、年間給料がそれを超えなければ、納税額が0NTDになります。当該免税額とみなし控除額の合計である423,000NTDは、まさにサラリーパーソンが納税必要かどうかの境目となります。
また、こちら自動的に付与される423000NTDというみなし経費的な控除額は、独身かつ扶養家族がいないサラリーパーソンが2023年に確定申告を行う場合を前提とする額で、物価水準の上昇幅が3%以上に達したら、当該額が引き上げられますので、これからもずっと固定されるわけではありません。
ですから、年間給料が423,000NTDを超えなければ、税活に取り組む必要はありません。
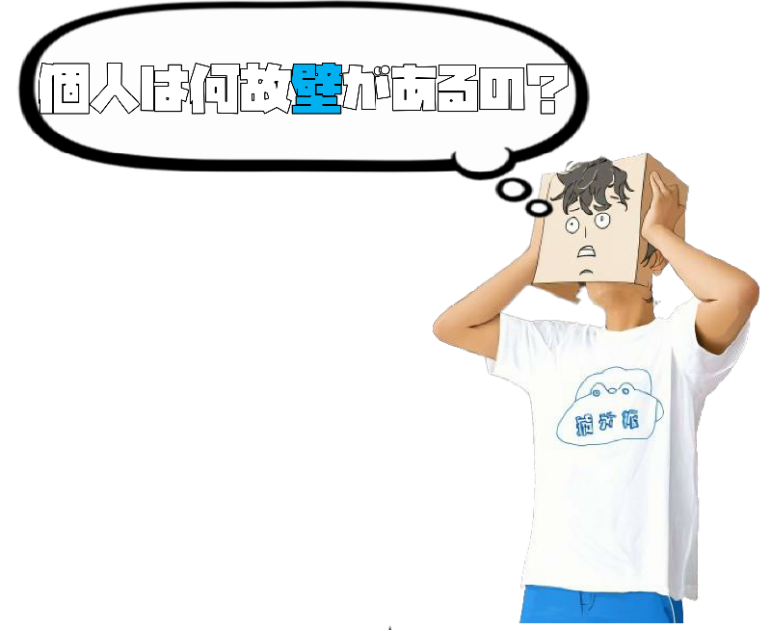
マイクロ法人スキームを本格的に検討必要なタイミング
法人税の税率が20%という設定を考えたら、個人所得に適用される税率が少なくとも30%以上でないと、マイクロ法人スキームを検討する意味がないように考えられがちかもしれません。果たして話はそれほど単純なのでしょうか?
上述でも申し上げましたとおり、居住者の所得税計算は超過累進方式なので、例えば年間300万NTDの課税所得があった場合、納付すべき税金は300万×30%ではなく、56万×5%+70万×12%+126万×20%+48万×30%で計算する形になります。そのようにややこしく算出した個人所得税の税額をもって、マイクロ法人で稼いだ300万NTDの課税所得×20%で求める法人税と見比べてはじめて、どちらのスキームが有利かわかるわけです。
年間の課税所得が300万NTDの設例ですと、個人で納付すべき個人所得税が508,000NTDで、マイクロ法人スキームで計算した法人税が60万NTDとの結果です。個人がマイクロ法人から配当金を受領する際にまだ税金が発生することを考えたら、まだまだ個人のほうが有利かなあとの結論にたどり着くかもしれません。ただし、この辺の判断では、法人に特有な、破壊力が大変大きいみなし申告制度が考慮されないのも事実です。
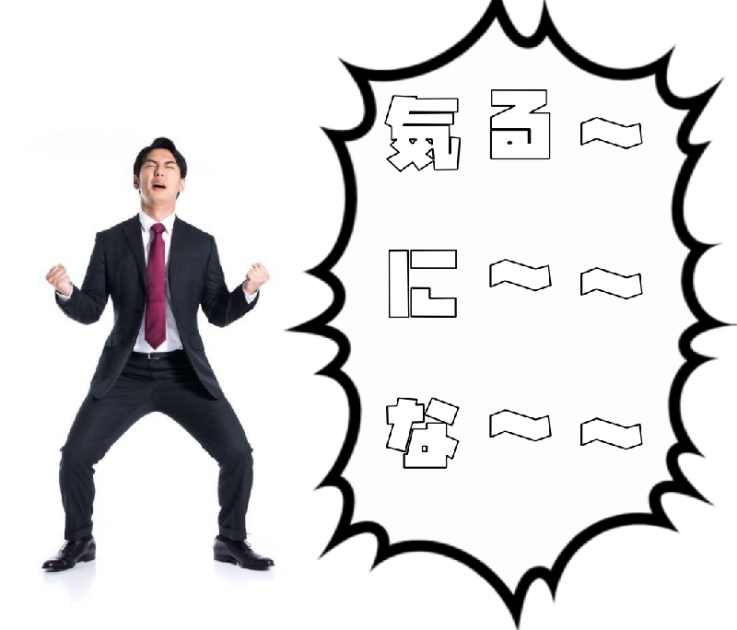
法人税のみなし申告制度
法人税の確定申告制度には通常の白色申告と青色申告とは別に、日本にはない、台湾独自のみなし申告もあります。
みなし申告を採択するメリットはと言えば、台湾税務当局が実施する税務調査で対象にされる確率が比較的低いほか、当局が定めた事業別利益率で課税所得を計算することができるといった点です。後者のほうは節税の面においてどれほどインパクトが大きいか、年俸300万NTDの台湾居住者を例に以下考えてみましょう。
独身で扶養家族がいないサラリーパーソンとして勤め先から300万NTDの年俸を受領するケース
- 年俸=300万NTD
- 課税所得=300万―42.3万=257.7万NTD
- 個人所得税=56万×5%+70万×12%+126万×20%+5.1万×30%=381,100NTD
- 税負担合計=381,100NTD
マイクロ法人のオーナーとして元勤め先から年間300万NTDの業務委託料を受領するケース(みなし申告を採択)
- 売上=300万NTD
- 課税所得=300万×6%=18万NTD
- 法人税=(18万―12万)÷1/2=3万NTD
- 営業税=300万×5%=15万NTD
- 配当金=18万―3万=15万NTD
- 個人所得税=15万―9.2万(免税額)―12.4万(みなし控除額)―12,750(配当金控除)=0NTD
- 税負担合計:3万+15万=18万NTD
上記の計算でも分かるように、営業税というハンデを付けたとしても、マイクロ法人の税負担がサラリーパーソンの半分以下になる結果です。
マイクロ法人スキームの優位性を際立たせるポイントは、課税所得の計算に登場する6%となりましょう。当該6%の存在はまさしく法人税みなし申告制度の醍醐味であり、台湾の中小企業が愛してやまない設定です。
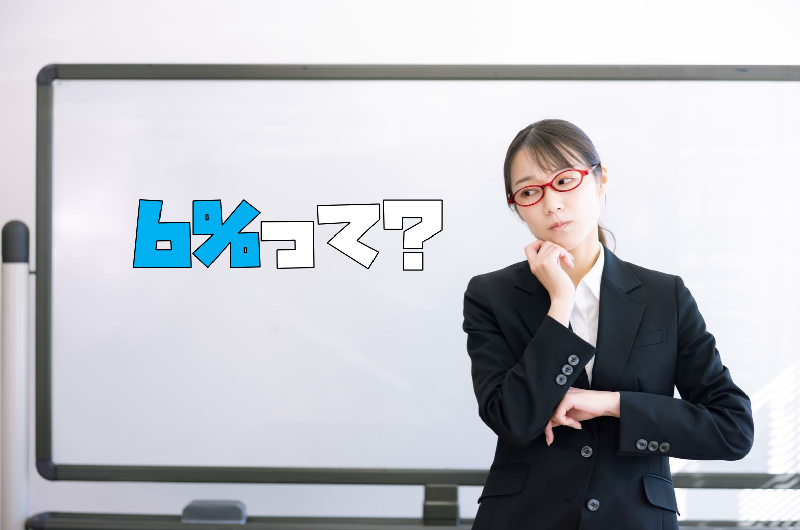
みなし申告制度の法的根拠?
節税観点で考察させていただきました「サラリーパーソンVSマイクロ法人」においては、勝負の分かれ目ともいえる法人税のみなし申告制度に関して、その法的根拠は「営利事業所得税(法人税)確定申告案件拡大書面審査の実施要点」であり、以下三つの条件を満たせば、みなし申告の利用は可能となります。
みなし申告を適用するための3要件
- 各種法定帳簿をしっかりつけており、時間とおりに納税すること
- 年間売上と業外収入合わせて3,000万NTD以下であること
- 実際の利益率が国税が定めた事業別利益率を下回るが、それでも当該利益率で確定申告を行うこと
1点目はできて当たり前なので、簡単にクリアできる条件となります。2点目はまさに中小企業が対象にされる基準であり、マイクロ法人なら難なくクリアできるでしょう。一番気になるのは3点目で、実際の利益率が事業別利益率より低いから、そのまま申告するほうが税金が少なくなるはずで、何故わざわざ比較的高い利益率に合わせて申告・納税しなければならないのか、との疑問が自然に浮かび上がると思います。そこはまさにミソです。
一生懸命商売してもなかなか利益が出ない場合はあります。事業がうまくいかないことでただでさえ悔しいのに、そのとおりに申告することができず、あえて政府が定めた利益率に準じて比較的多めの税金を払いだす方法で申告する、というのはどう考えても理屈に合いません。それでもみなし申告が普通に利用されているのは、税務調査のリスクを回避したいからとの理由です。
国税が定めた事業別利益率は、毎年行われる法人税の確定申告のデータを参考に、〇〇事業を行う会社は大体〇%ぐらいの利益を出したのをチェックしまとめられたものであり、それなりの信憑性があります。それを上回る利益率を出せる会社は、同業他社のうちより優れた営業成績を残した形となり、比較的怪しまれずに済みますが、会社の利益率が当該事業別利益率を下回ったり、もしくは赤字であったりする場合、あえて利益を隠して不当に脱税するかも、と国税が考えたりして、税務調査を発動する可能性が濃厚となってきます。
もちろん、脱税の意図が全くなしで、利益が悪いというのは単に営業不振によるものであり、かつ会計帳簿も完璧につけているのであれば、たとえ税務調査にされてもひるむ必要はなく、そのとおりに申告しても問題ありません。にもかかわらず、台湾中小企業の会計帳簿は、税務調査にされたらほとんどの場合追徴課税が伴うクオリティなので、それを何とか避けようとみなし申告が採択されるわけです。
話し戻りますが、脱サラしたマイクロ法人のオーナーが行う事業は、サラリーパーソン時代で行った業務と何ら変わらないので、大した経費がかからないまま法人税の確定申告を行うと、税負担がかえって重くなったりする可能性が無きにしも非ずなので、一層国税が定めた事業別利益率に準拠し、税務調査のリスクが低いみなし申告を行おう、と考えるのも自然な流れでしょう。
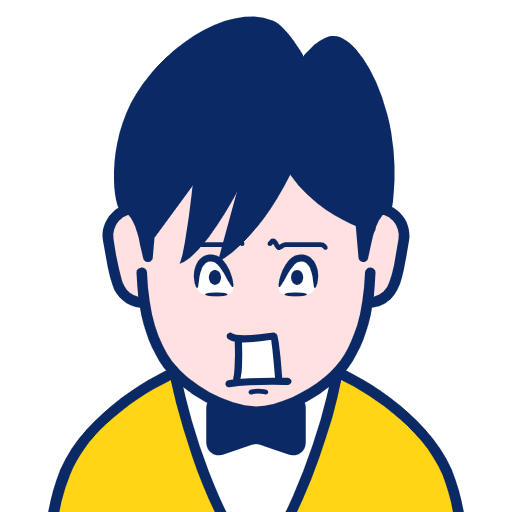
えっ、実際の利益率が国税のやつより低い場合のみ、みなし申告ができるはずなのに、経費があまり発生しない、脱サラしたマイクロ法人のオーナーは何故それを使えるのでしょうか?
この辺の話は、グレーゾーンの領域に踏み入る可能性が濃厚なので、興味のある方はマサヒロへ個別相談でお願いします。
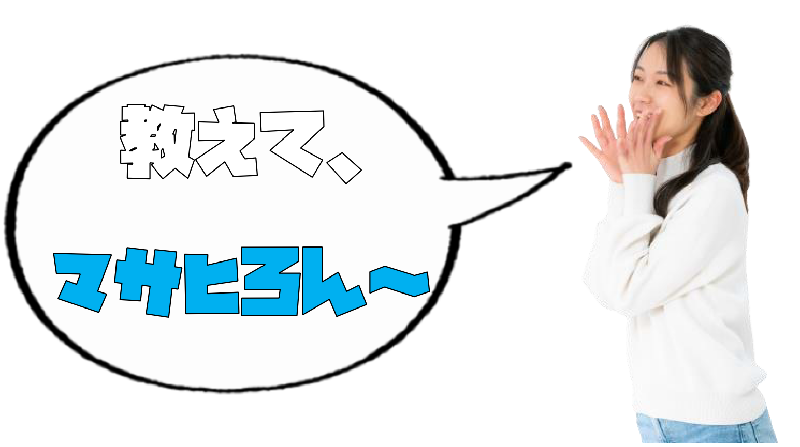
節税の代償
以上の考察で、マイクロ法人スキームはサラリーパーソンより節税効果に優れていることが、お分かりいただけるかと思います。かといって、手放してマイクロ法人スキームを無批判的に迎え入れることは少々危険です。理由は以下です。
マイクロ法人スキーム実施時の要注意点
- 「税務調査にされる可能性が低い」、というのは法人税みなし申告の特典の一つです。低いというのは「ゼロ%」を意味するわけではないので、会計帳簿をそれなりにまじめにつける必要があります。
- マイクロ法人の設置にかかる初期費用、及び記帳代行や確定申告など専門性の高い業務にかかる外注費といった、サラリーパーソン時代にないコストが発生しますので、経費負担の面においては要考慮。
- 勤め先に対して、サラリーパーソン時代でもらっている給料を業務委託費として払ってもらう相談を行うとき、内税方式か外税方式かあらかじめはっきりさせる必要があります。5%の営業税の負担先は税活において割と肝心な要素です。
- サラリーパーソンは勤め先とは雇用関係で結ばれているため、雇用関係の解消は台湾の労働法に準拠して行わなければならず、相当ハードルが高いものですが、節税の観点で自らの意志で脱サラして、外注先として元の勤め先と取引を行うビジネス関係となりましたら、このようなビジネス関係の解消に労働法の遵守は必要とされず、ぱさっと切れる関係なので、元の勤め先は定年まで業務委託料を払い続けてくれるかは未知数です。
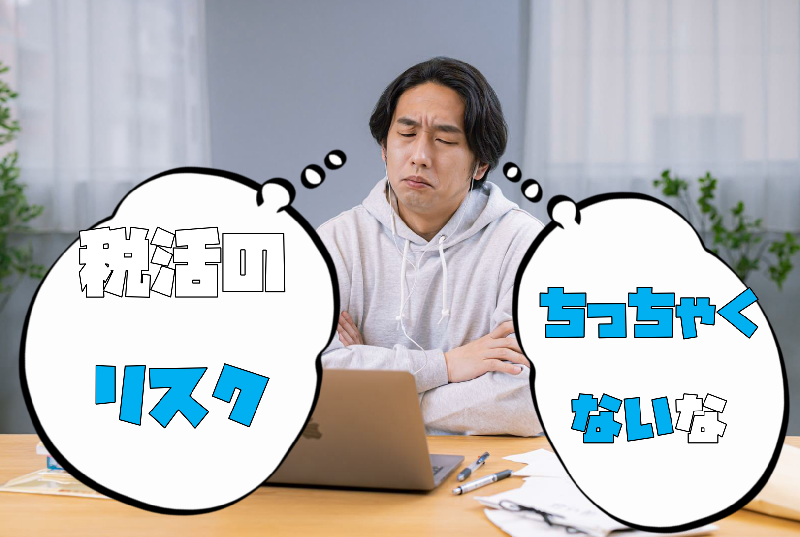
まとめ
「大いなる力には、大いなる責任が伴います」。所得を多く稼げる人は、金銭面においてそれに比例した社会貢献をできるだけ行うことは美徳であり、一種の責任でもあります。所得税の制度はまさにそのコンセプトに乗っかる形で作られたものです。ですから、多くの税金を支払っているというのは、それなりの所得を稼いだことを意味し、ちょっとしたステータスにもなるため、歓迎すべきことかもしれません。
にもかかわらず、節税活動はあちこちでごく普通に行われており、国税でさえたまに会社を訪問し、節税情報を紹介したりしています。それはつまり、「納税は台湾に住んでいる人々の共通の義務ですが、必要以上の税金を払う必要はない」との一言に尽きましょう。
過度な節税は脱税行為に該当する可能性があり、違法行為とされますので、合法的に賢く税活に取り組むことが望ましいのです。税に関して迷うときは、是非気軽にマサヒロへご相談してみてください。