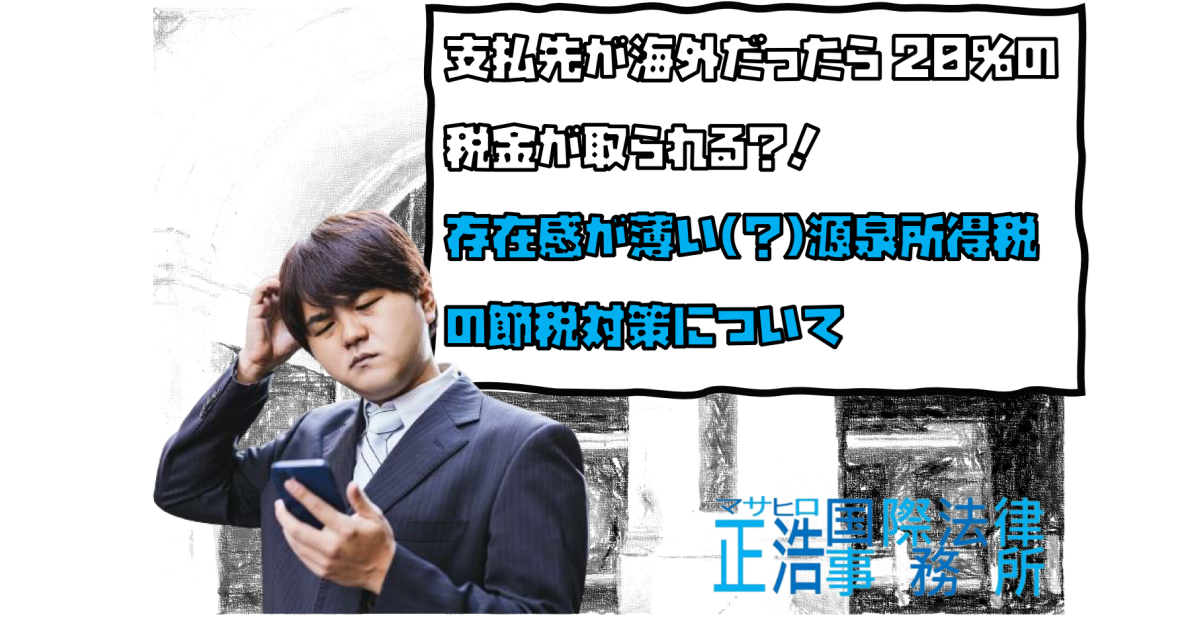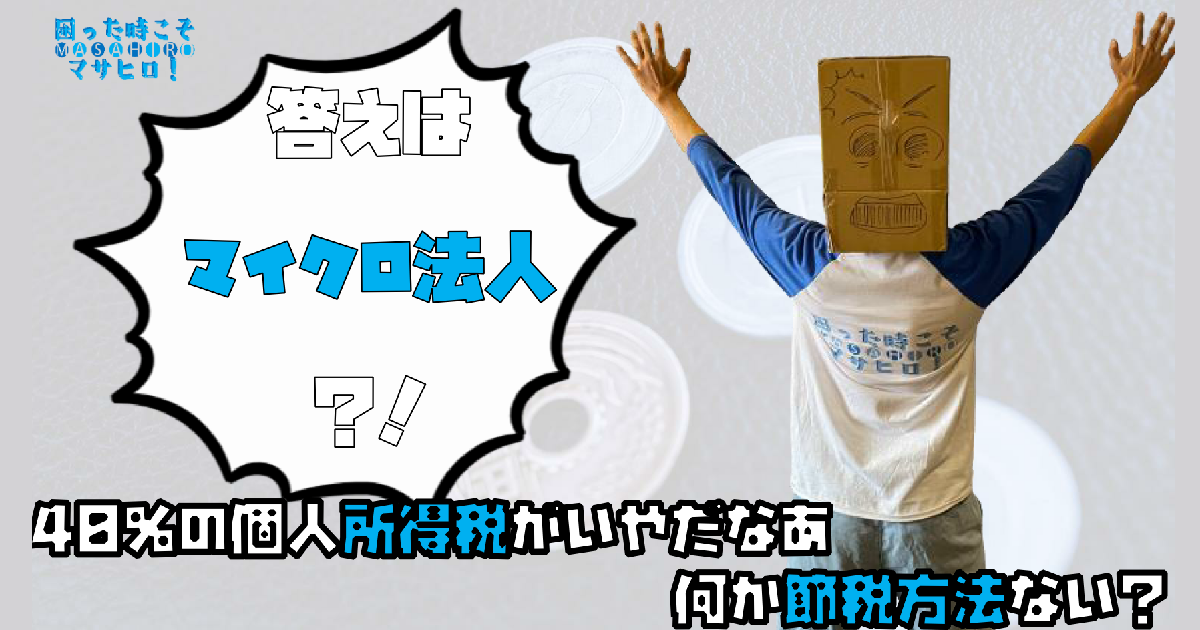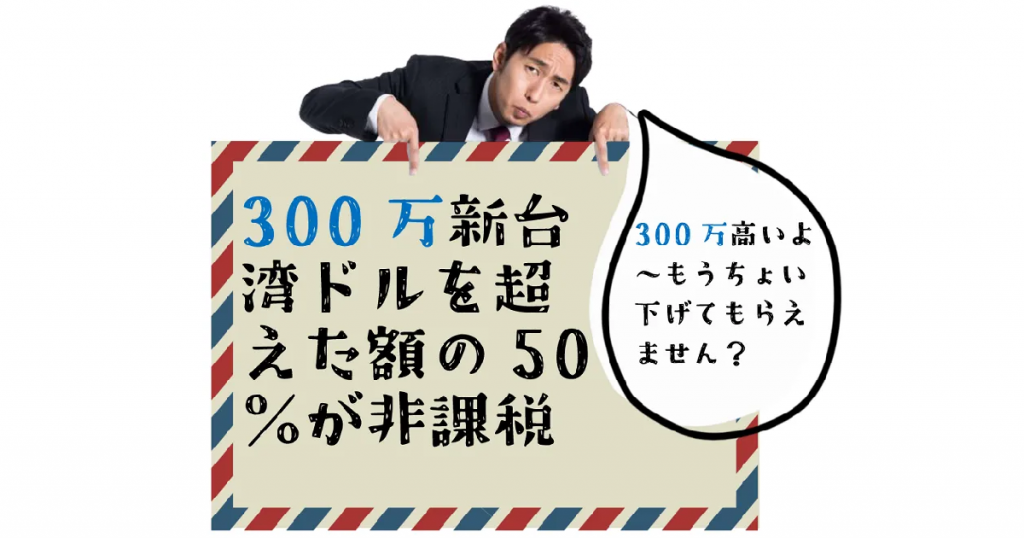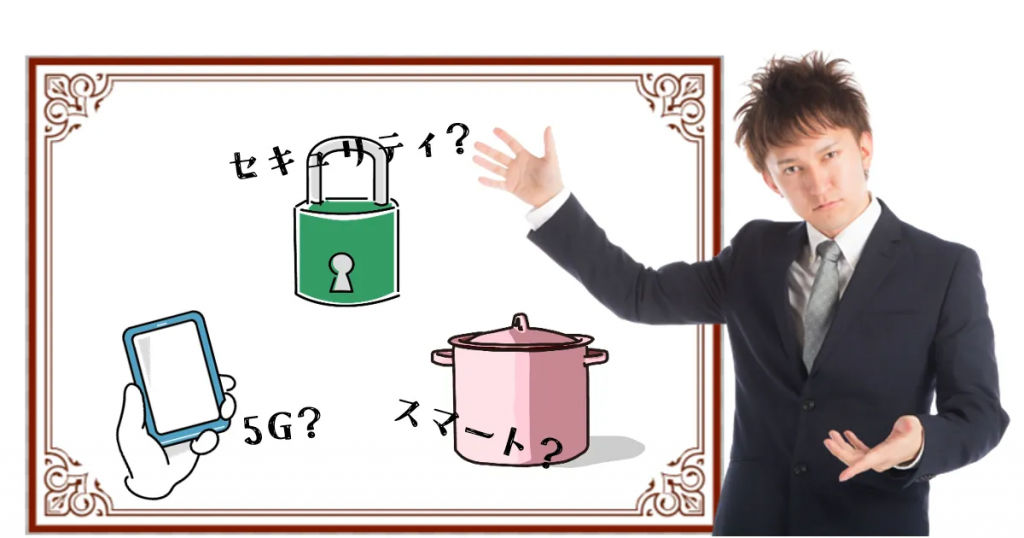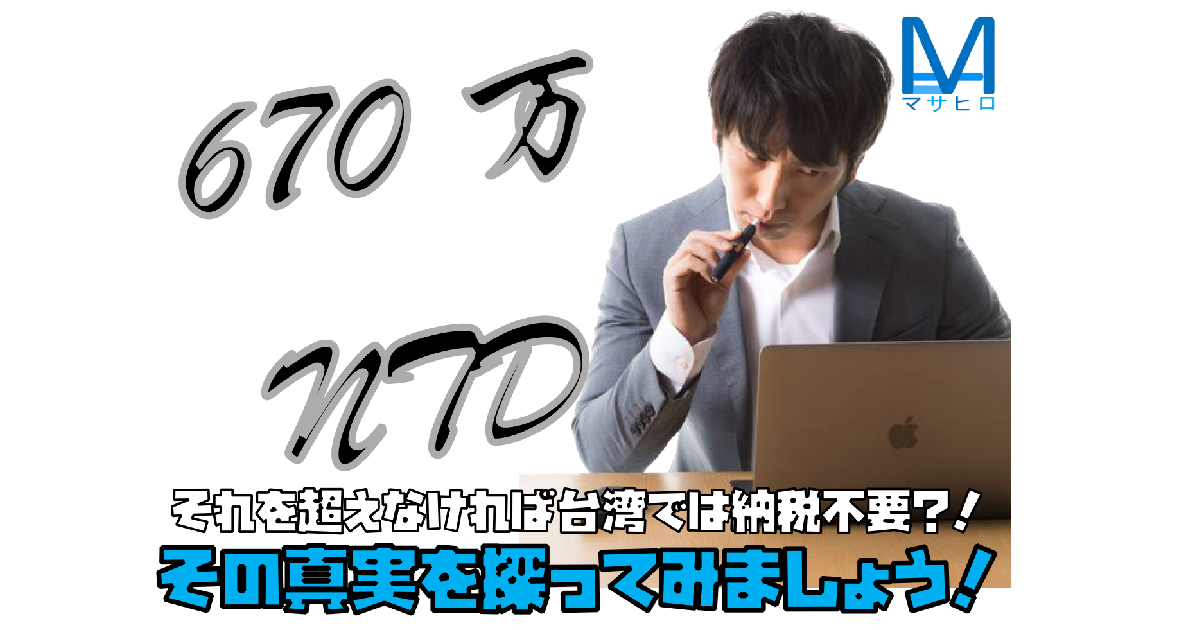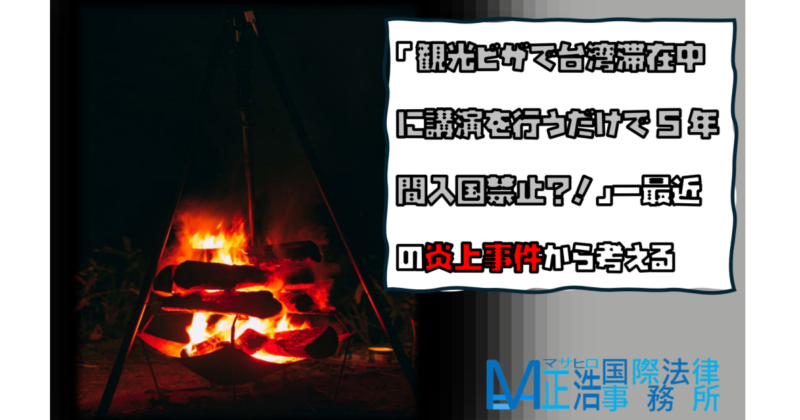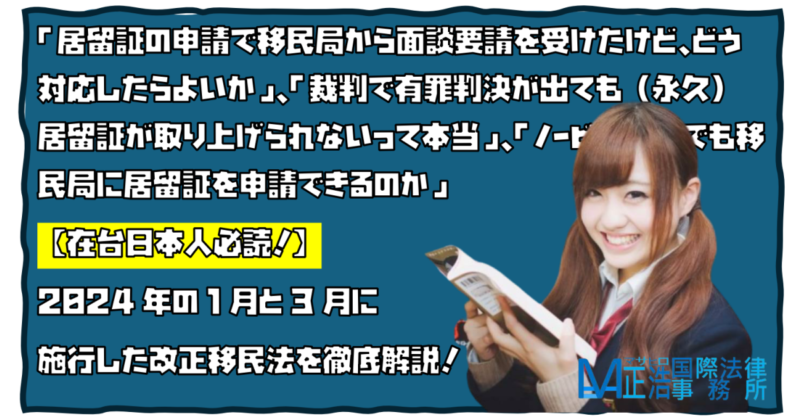社員数を増やしたり、増給したりすればするほど節税効果が高くなる?!労使WinWinな節税対策にチャレンジしてみませんか!
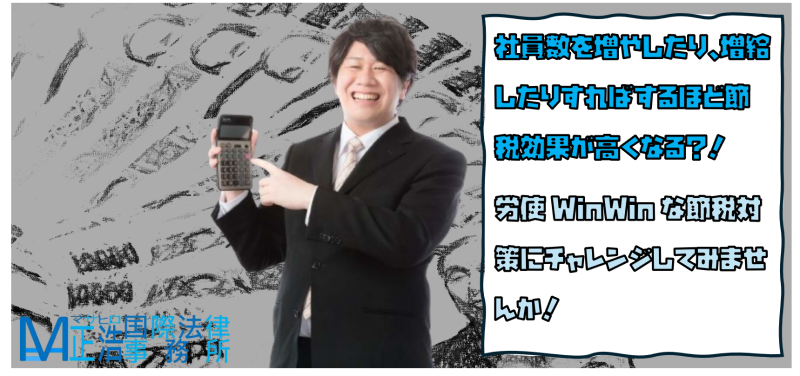
社員を2名雇用すると、1名のみ雇用する場合より人件費が高くなり、その分会社の利益が減るので、法人税が安くなります。ベースアップや昇給などを実施する場合においても、同じ理屈で支払うべき法人税が減ります。これはどの国でも通用する、至極当然な常識なので、紹介するまでもありません。ですから、今から説明するのは、上記のような自然の摂理ではなく、税金面においてプラスアルファ的な効果が得られるお話です。
10の売上があって、原価が5、人件費が3とすると、支払法人税が0.4(税率20%)との計算です。実際にかかった人件費は同じ3だけど、一定の要件を満たせば、計算上は1.5倍の4.5、または1.3倍の3.9にできれば、納付すべき税金が0.1か0.22となり、それぞれ0.3と0.18の節税効果が得られます。
いわゆる一定の要件というのは、まさに表題の「雇用拡大」と「昇給」です!
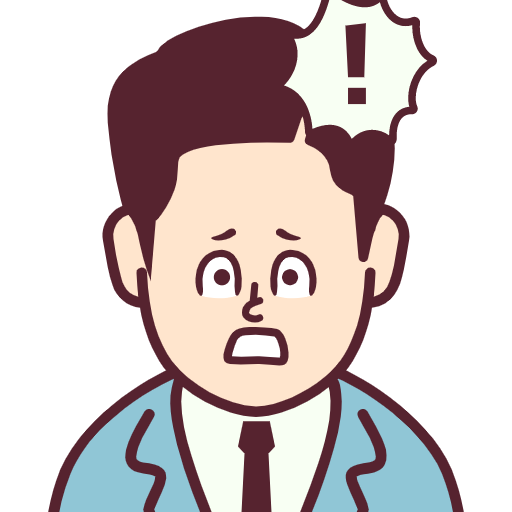
節税のためにあえて社員を増やし、もしくは昇給を実施するのは本末転倒なんじゃない?税率が20%だから、増加した人件費は節約した税金だけじゃ完全に回収できないよ!
その通りです!節税するための雇用拡大や昇給はありえないのです!ただ、節税とは関係なく、会社は最初から生産拡大のために作業員を増やす必要があったり、元々年次定期昇給の制度があったりして、そこでもし通常より少な目の税金を支払ったらよいのであればハッピーなのではありませんか?しかも、これから紹介する税金優遇政策はまもなくよい方向でパワーアップされるので、今のうちに関連情報を押さえればそれに越したことはありません。どうかついてきてください!
目次
節税に必要な要件
社員の雇用人数を増やしたら節税できます。社員の給料を引き上げたら税金が安くなります。ただ文字とおりに、社員を1名から2名、もしくは月給をNT$3万からNT$30,001に増額すれば、政府はすぐ税金をカットしてくれるかというと、話しはそれほどおいしくありません。増員または昇給という大前提があって、それからそれらに付随するいくつかの細かい条件も悉くクリアしないと、節税の果実を享受することはできません。以下、昇給の場合と雇用拡大の場合に分けて、それぞれの条件について紹介します。

昇給で節税の条件その①―タイミングが大事
台湾政府が提供する昇給で節税の優遇策は、

うち去年ぼろ儲けしていたから、10年ぶりにベースアップを実施しよう~
というように、会社が昇給の原資を十分に稼いだから、社員に還元するよう後押しするようなものではなく、台湾の失業率が6ヶ月連続して一定の数値を超え、かつ当局によって公告されてからの2年以内に昇給を実施しないと、一切優遇が受けられないとされます。そのため、本件節税措置を利用するにあたって、当局の公告情報を随時把握しておくことが大事です(中小企業の従業員への昇給に伴う給与手当割増控除弁法第2条、同法第3条)。
昇給で節税の条件その②―「中小」であること
本件節税措置は、適用対象は台湾の「中小企業」に限定されており、上場または店頭公開会社などの大会社は原則として適用しません(中小企業の従業員への昇給に伴う給与手当割増控除弁法第2条)。
では、どのような条件を有したら中小企業と認定されるのかというと、資本金がNT$1億以下、もしくは社員数が200人未満の会社または個人事業主に該当すれば、中小企業の定義に当てはまります(中小企業認定標準第2条)。留意が必要なのは、月次の平均売上高がNT$20万未満、統一発票を発行不要な小規模事業者は適用対象外です。
昇給で節税の条件その③―昇給する社員が「対象内」であるかどうか
本件節税措置が施行された趣旨は、不景気の中においても一般社員を昇給させる会社を奨励し、それによって高い給料をもらっていない一般社員の生活が少しでも改善できたらとの思いによるものです。従って、昇給の対象が役員や管理職のみの場合は税金の優遇対象から外されます。
一般社員の定義について、会社と無期雇用契約を結んで、年次賞与を含めない、月次で受領する給与や手当などの平均額がNT$5万以下の台湾籍社員とされます(中小企業の従業員への昇給に伴う給与手当割増控除弁法第2条)。従って、外国人労働者または日本の駐在員を昇給させても減税の対象にはなりません。
昇給で節税の条件その④―減税対象外の状況
条件その①~③をクリアして、失業率が6ヶ月連続して基準値を超えていたら、すぐ必要書類を主務機関に提出して減税効果を楽しもうと思いきや、結局不許可にされる場合もあります。
以下いずれかの状況に該当すれば、本件節税措置の適用が認められません。
- ダンスホール、スナック、キャバクラ、バーなどの事業を営む場合
- 労働者派遣事業に従事する場合
- 約束手形が不渡りになり、振出人が受けた銀行取引停止処分がまだ解除されていないか、直近3年間に税金を納めていない事実があった場合
- 直近3年間、労働法または環境保護もしくは食品安全衛生に関する法律に違反し、その程度が重大で、かつ主務機関もしくは司法機関によって違法事実が認められた場合
- 当年度または過去1年に減給、実質昇給していない事実があった場合
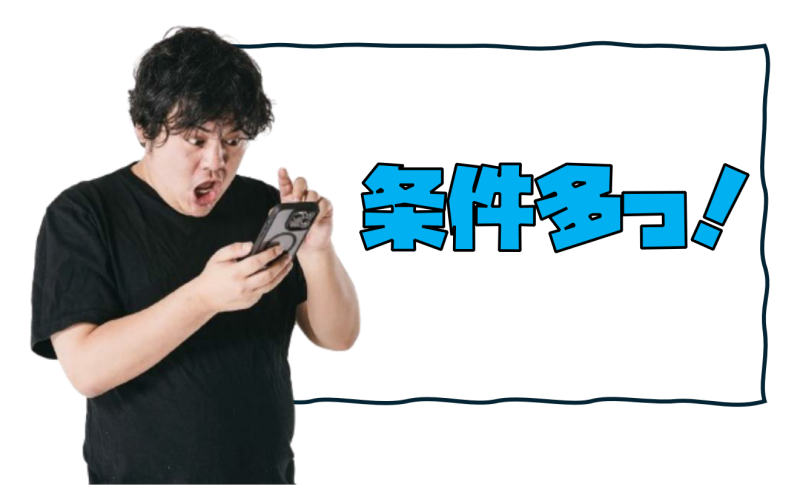
昇給で節税の効果
以上の所定要件を全て満たした会社は、法人税を計算するときに、昇給実施後の給与から昇給前の給与を差し引いた金額に1.3を乗じて算出した額を損金算入できます。例えば、A社員をNT$100昇給させるとした場合、税務上は昇給にかかる経費としてNT$130を計上可能となり、それによって課税所得が通常よりNT$30減り、税金が安くなる仕組みです(中小企業の従業員への昇給に伴う給与手当割増控除弁法第3条)。
昇給で節税を適用するときの留意点
以上は、昇給で節税を利用するための法的要件と節税効果についての説明です。それぞれの条件を逐一確認すれば、適用可能かどうかが分かると思うが、以下のような見落としやすい細かい設定も合わせてチェックできたらさらに確実です。
昇給で節税における要注意点
- 台湾政府が年1回実施する最低賃金の引上げに伴う昇給は対象外。
- 雇用拡大の税金優遇を既に受けた場合は、本件節税措置の適用が認められません。つまり、二重で控除を受けることはないということです
- 一人当たりの給与手当の平均支給額が過年度の金額を下回る場合、たとえ昇給を実施したとしても適用できません(つまり、一部昇給、一部減給でプラマイゼロの状況は排除されます)。
- 昇給を実施した年度に政府から補助金を受領した場合、1.3倍で損金算入できる昇給額から当該補助金を控除しなければなりません。
次は社員数を増やすことによる節税の方法をチェックしましょう。
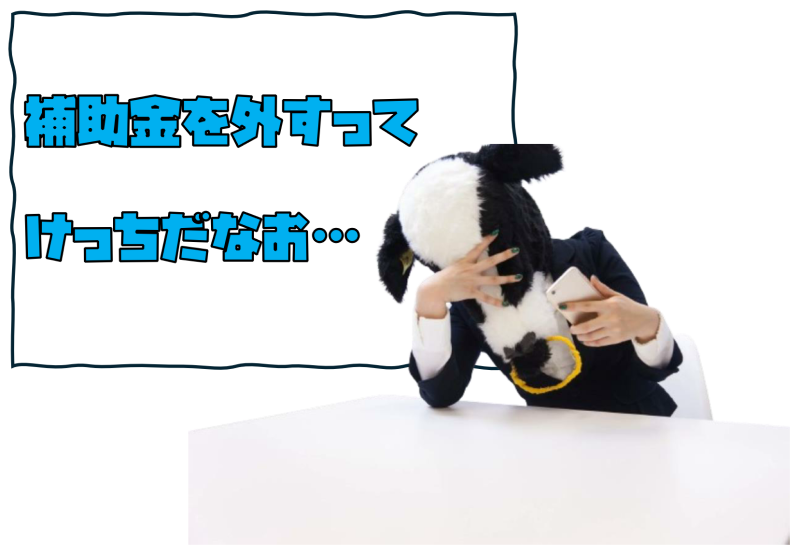
雇用拡大で節税の条件その③―最低消費額がN T$50万
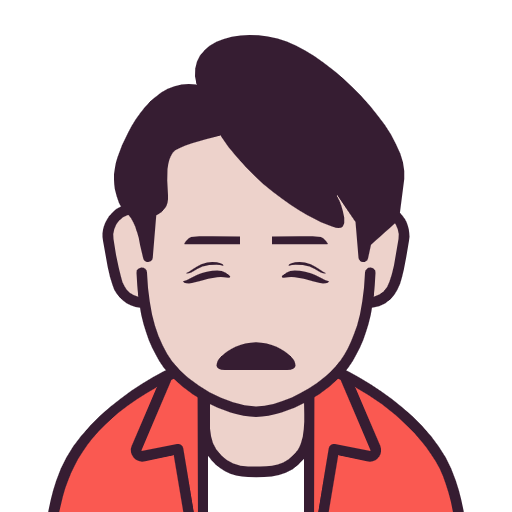
①と②は?何故いきなり③からスタート?
①と②を飛ばす理由は簡単です。雇用拡大で節税は昇給で節税と同じく、①―失業率要件と②―中小企業要件も要求されるからです。
そして、雇用拡大で節税に求められる最低消費額というのは、会社または個人事業を新たに作って、それに注ぎ込む資本金額がNT$50万以上、または既存会社もしくは個人事業にNT$50万以上の増資(累計も可)を行うことです。しかし、増資の目的はこれまでの累積損失を補填するのであれば、追加投資にならないので、会社の純資産がプラスであることも条件の一つとされます(中小企業従業員の雇用拡大に伴う給与手当割増控除弁法第4条)。
また、新規に資本金NT$50万以上の会社を作るパターンは、会社を設立する翌年に増資を実施しなくても、最長2年間本件の減税措置を享受可能という点も魅力的ですね(経企字第10404602510号通達)。
雇用拡大で節税の条件その④―減税対象外の状況

④は「昇給で節税」と同じ「減税対象外の状況」じゃないか、今度は飛ばさないのか?
はい、飛ばしません。何故なら、NGとなる条件が3個増えたほか、一部の条件も異なるからです。以下確認しましょう。
- 企業が提供するのは海外の雇用機会
- 企業が提供するのはパートタイムまたは定期雇用労働者の雇用機会
- ダンスホール、スナック、キャバクラ、バーなどの事業を営む場合
- 労働者派遣事業に従事する場合
- 約束手形が不渡りになり、振出人が受けた銀行取引停止処分がまだ解除されていないか、直近3年間に税金を納めていない事実があった場合
- 他社の事業または財産の買収による雇用拡大、もしくはただ単にグループ会社間で社員を出向させること
- 雇用拡大の実施に競争を阻害したり営業秘密を侵害する行為が伴い、かつ主務機関もしくは司法機関によって民法、公正取引法または営業秘密法に違反したと認められた場合
- 直近3年間、労働法または環境保護もしくは食品安全衛生に関する法律に違反し、その程度が重大で、かつ主務機関もしくは司法機関によって違法事実が認められた場合
雇用拡大で節税の条件その⑤―雇用増人数の最低ライン
社員を1名でも増やせば「雇用増」と言えます。ただし、それだけでは節税のメリットを享受するには至っていません。「雇用拡大で節税」はルール上、1年以内に少なくとも2名以上の台湾籍の正社員を雇用しないと適用できないとされます(中小企業従業員の雇用拡大に伴う給与手当割増控除弁法第4条)。
また、雇用増の人数にカウントされるのは「正社員」だけなので、パートタイマーや派遣社員、定期契約労働者などは対象外とされるが、前述の非正規雇用社員を正社員にすると、雇用増の人数にカウントされます。従って、改めて新入社員を募集するより、在籍する非正規雇用社員を正社員として迎え入れるほうが、本件節税を適用するためのショートカットとなりましょう。
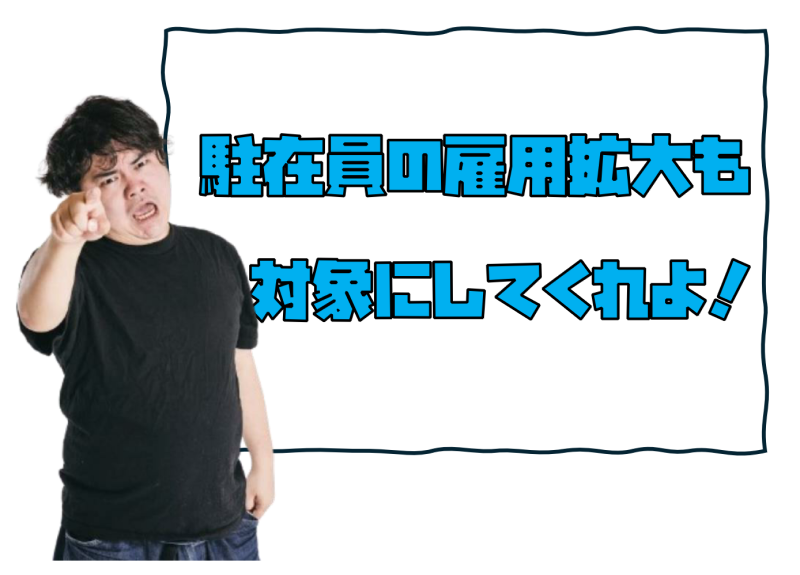
雇用拡大で節税の効果及び留意点
以上述べた所定要件をクリアした会社は、新規採用を実施した年の法人税を計算するとき、必要な疎明資料を主務機関に提出して、新規採用の社員に支給した給料×1.3で算出した額を損金算入できます。また、新規採用したのは24才以下の労働者であれば、損金算入できる倍率が1.3から1.5に引き上げられるので、会社さんの若者を採用するモチベーションが上がるのではないでしょうか(中小企業従業員の雇用拡大に伴う給与手当割増控除弁法第3条)。
申請時の留意点としては、政府からの補助金を予め差し引く必要があるほか、申請年度における給与手当の総支給額が過年度における給与手当の「総支給額+α」を上回るという前提条件を満たさなければならない点です。この気になる「α」の計算はいささかややこしいので、詳細は割愛するが、「全社員への給与手当が過年度より多く支給すること」、つまり雇用拡大が原因で一部の社員を減給させると優遇が受けられない設定は覚えておきましょう(中小企業従業員の雇用拡大に伴う給与手当割増控除弁法第4条)。
補足ですが、上記の総支給要件をチェックするとき、外国籍の社員、パートタイマー、及び定期契約労働者への給与手当を外す必要があります。
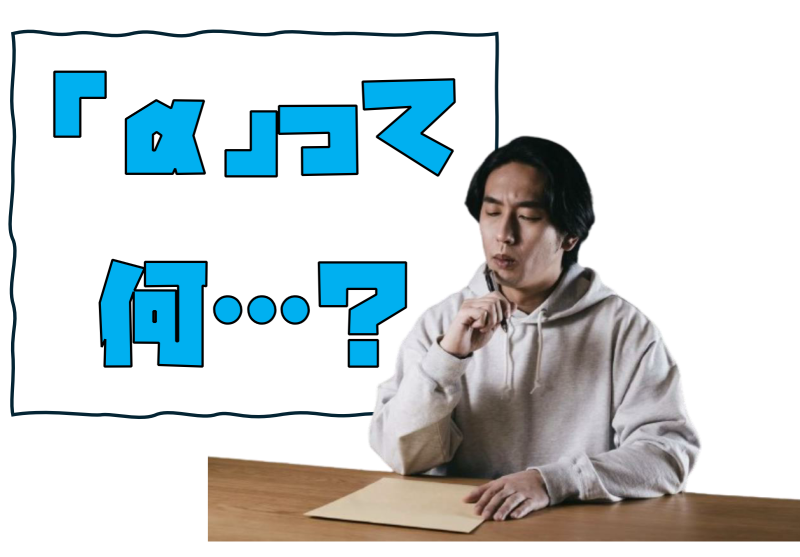
最新の法改正の動き
実は、昇給で節税といい、雇用拡大で節税といい、両方の優遇策は今年、2024年5月19日に退場する予定とされています。
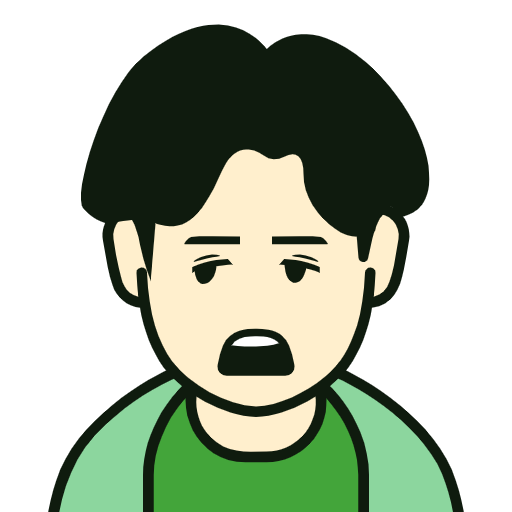
えっ、あと少しで退場すんじゃないか、ここまで読んできて損した~
と評価するのは早急です。
近年において失業率が上がらないから(望ましい状況ではあるだけど…)、ここ10年間1~2回軽く顔出ししただけで、それほど活用されないまま今年の5月にリタイアさせるのはまったいない、と考えたりする台湾政府は、それらの有効期限を今年からさらに10年伸ばして、会社さんにもっと活用してもらおうと、以下のようなカンフル剤をねじ込むつもりで法改正の手続きを進めています。
改正ポイント!
- 雇用拡大で節税においては、24才以下の若者社員を新規採用すると、同人に支払う給与手当を1.5倍で計算し損金として算入できるのに加えて、45才以上の中高齢者や高齢者を雇用する場合も1.5倍の恩恵が受けられる、というように改正する見込みです
- この2本の節税措置は過去10年間において、それぞれ2回、1回のみ発動され(1回の有効期間が2年)、その後は失業率がなかなか発動値に達さなかったため、「制度がちゃんとできてるけど、活用できるタイミングが来ない」という宝の持ち腐れ状態が長い間続いています。それを鑑みて、失業率基準を撤廃し、確実に昇給すれば減税、確かに雇用を拡大すれば減税、というように改正する見込みです。
- 本件節税措置は、原則として給与手当の支給額を1.3倍にして損金算入することで、課税所得を減らす仕組みを取ってきたが、これからは倍率が一律に1.5倍となる、というように改正する見込みです。
- 雇用拡大で節税を利用するには、資本金NT$50万の会社を新規設立するか、既存会社にNT$50万の増資をしなければなりません。これらのハードルを取り外し、新規で社員を採用したらすぐ適用できる、というように改正する見込みです。
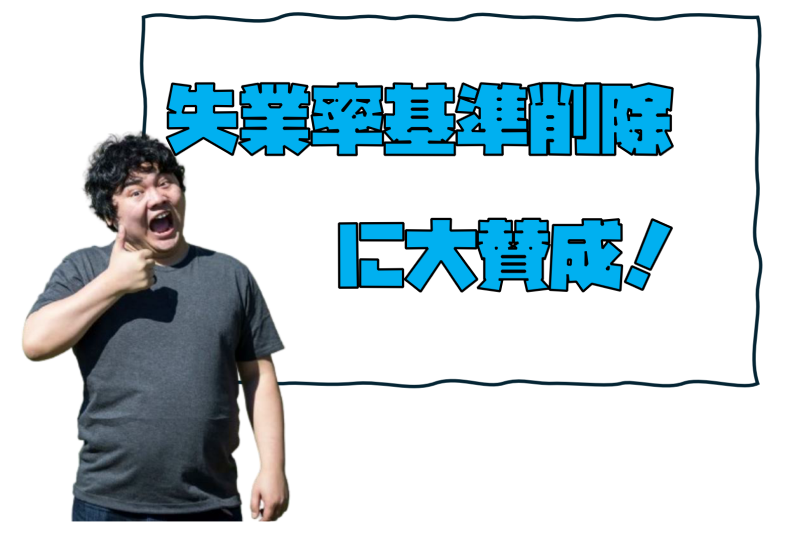
今週の学び

社員を昇給させれば節税できる、社員を新規採用すれば税金が安くなるという話しを今まで聞いたことがない。簡単にできそうなのにあまり成功事例を聞かないのは何故?
理由はシンプルです。この間、どこかしこも人手不足の問題を抱えており、失業率はここ数年間ずっと低い水準を保っているため、本件節税優遇策が発動されないまま、冬眠の状態に保っており、会社さんが昇給または雇用拡大を実施しても申請しようがないわけです。ただ、「最新の法改正の動き」にて共有したように、現在進行中の法改正では失業率基準を完全撤廃する方向で検討が進められており、それが確定したら、本件節税措置は今までよりずっと使いやすくなるので、これからの当局の発表を注目しながら、税活に取り組む日を迎える準備を前向きにしてください!