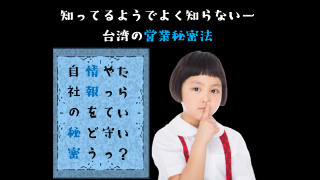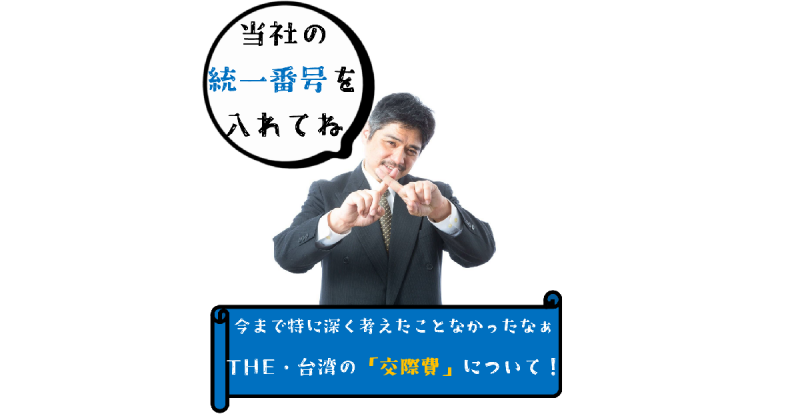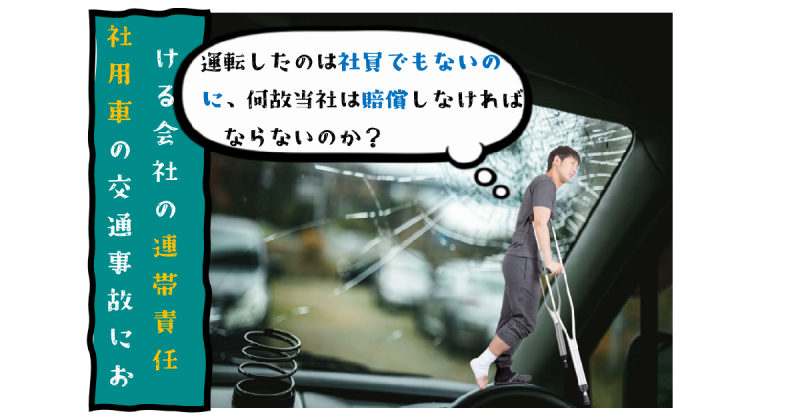自社の秘密情報をどうやって守ったらいい?知ってるようでよく知らないー台湾の営業秘密法
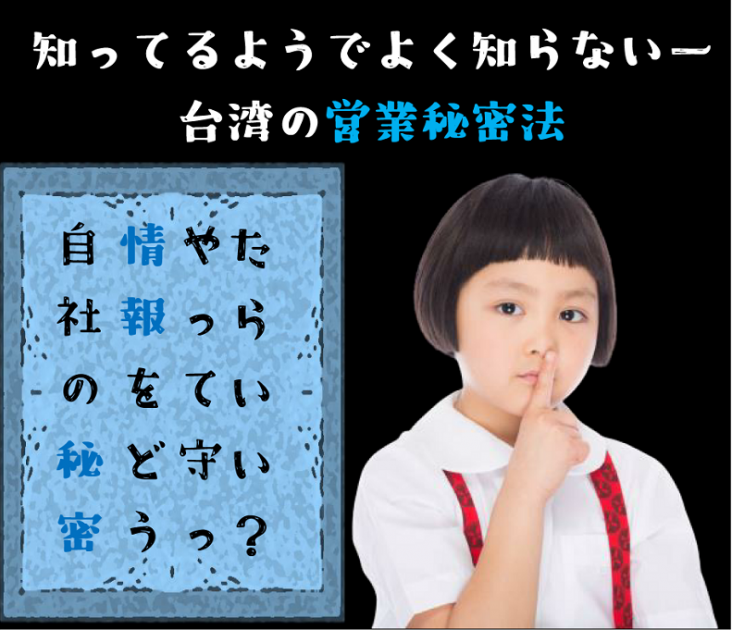
先日、Apple社のサプライヤーであった台湾金属筐体大手のC社は、自社の営業秘密が管理職クラスの従業員によって中国企業へ不当に流出される被害を受けた、とのニュースが報じられていました。
C社は台湾の上場企業であり、自社の秘密情報を徹底的に保護しようと、比較的厳しい管理措置が敷かれているはずなのにもかかわらず、今回のように、不当な輩から不正利用されてしまうぐらいですから、秘密管理措置をしっかりとっていなかったり、若しくは全く管理していなかった中小企業のほとんどは、常に自社の秘密情報が不正利用されるリスクに晒されているでしょう。
完璧を追い求めませんが、自社の秘密情報に対して最低限どんな管理体制を取ったら、不正利用のリスクをある程度抑えられ、いざ被害に遭ったら有効な法的手段をタイムリーに取れるのかについて、そもそも営業秘密とは何か、自社もC社と同じく台湾の営業秘密法に基づき犯罪者を取り締まれるのかといった点を含め、台湾における営業秘密の取り扱いに関する基礎知識を詳細解説させていただきたいと思います。
目次
法的に認められる「営業秘密」とは?
台湾の営業秘密法によると、以下3つの要件を満たせる方法、技術、製造工程、配合、プログラム、デザインその他生産や販売、会社経営に使用される秘密情報は、営業秘密に該当するとされています。(営業秘密法第2条)
営業秘密の3要件
- 同じ業界に従事する人であっても、通常はそれを知り得ることはできない、つまり「秘密性」を有すること
- 既に又は潜在的に経済的価値を有すること。
- 妥当な秘密管理措置が施されること
営業秘密の範囲は、上記に挙げた方法、技術、製造工程、配合、プログラム、デザインのほか、前述3つの特徴を有する秘密情報であれば、法的に有効は営業秘密として認められる傾向です。
営業秘密は、大まかに「商業性営業秘密」と「技術的営業秘密」に分けることができます。前者は顧客リストや代理店の一覧表、商品の販売価格、仕入原価、相手先との取引金額、人事管理、原価分析その他会社の運営に関する秘密情報であり、後者は方法、技術、製造工程、配合その他特定事業の推進や応用に関する秘密情報です。ただし、会社内で取り交わされる、経済的価値を有さない私的やり取り、法律に反するノーハウや配合等は対象外とされています。
以下、ある秘密情報が営業秘密に該当するかを判断するための3要件について、深堀っていきましょう。
秘密性の有無
通常の一般人が知らないだけでなく、同じ分野の専門家さえ知らないのであれば、当該秘密情報は、営業秘密になるための第一関門、「秘密性を有する」要件をクリアすることになります。
ただし、第三者は自ら行った研究開発の活動で、当該営業秘密に辿り着き、それをジャーナル等に発表することによって、一般的に知られていたら、当該営業秘密は「秘密性」がなくなり、法律における営業秘密の地位が失われてしまいます。
経済的価値の有無
ある秘密情報を利用することで、売上の成長につながり、若しくはコストの有効削減ができれば、「経済的価値を有する」、という営業秘密になるための第二関門がクリアされます。
製造工程やノーハウ等技術的営業秘密はもちろん、得意先の趣味嗜好や消費傾向が明記される顧客リスト等の「商業性営業秘密」も使いようによれば、独自のブルーオーシャンを作り出すことも可能なので、経済的価値を有する典型的な営業秘密となりましょう。
ある秘密情報が他社に知られ、若しくは一般公開されたら、当該秘密情報の元の持ち主はそれによって、当該業界における優位性が損なわれたり、経済的地位が低下したりするか、といった点は基本的な判断基準とされています。また、一部特殊な事例を除き、ビジネスへは直接的な影響が及ばない国家機密や選挙戦略等は営業秘密としてみなされない形となります。
妥当な秘密管理措置の有無
社内の秘密情報について、従業員と秘密保持契約を交わしたり、秘密情報が記載される文書に「社外秘」や「Confidential」等の注記を入れたりするという、それを守ろうとする意思表示があって、なおかつ、当該秘密情報の電子データにパスワードを掛けたり、秘密情報の文書を金庫に入れて鍵を掛けたりする等、積極的な管理措置も施された場合には、営業秘密にレベルアップする第三関門を突破する可能性があります。
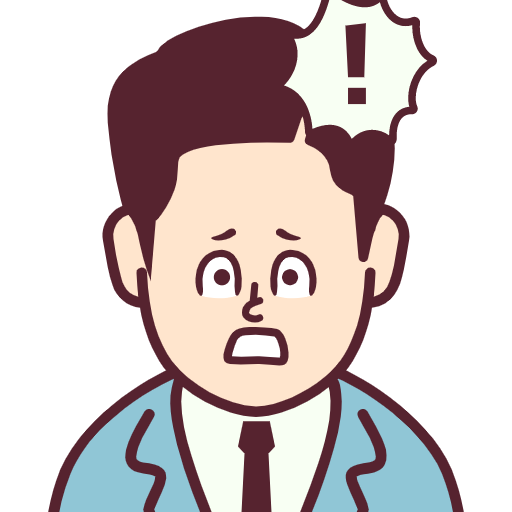
えっ?突破したのではなく、可能性だけですか?
企業秘密を営業秘密に仕上げるためには、ただ単に何らかの秘密管理措置を設けたらよいというわけではなく、当該管理措置は、企業秘密の重要性を考慮のうえ、社会通念上、それが「妥当」であるかどうかをもって、判断しなければなりません。
例えば、従業員と締結する秘密保持契約書において、「Confidential」と明記された書類に限定することなく、自社内一切の文書・資料全てが秘密情報であるという、実務的によく見かけるケースについては、本当に価値のある秘密情報は特別に慎重に扱われることなく、その他社内情報に埋もれているため、かえって漏えいされるリスクが生じてきます。
そのほか、技術情報に関する電子データにパスワードがかけられたのはよいが、何年たっても、それにアクセス可能な離職者が出てきても、パスワードは当初設定時のままで、一度も変更したことがないとのケースは、「妥当な」秘密管理措置が施されたとは到底言い難いでしょう。
営業秘密の漏えいに関する訴訟では、過半数の案件は検察段階で不起訴処分が下されたとの結果でした。それら処分書の内容をチェックしてみたら、大体は社内の秘密情報に妥当な秘密管理措置が施されておらず、営業秘密としての要件は十分に満たしていなかったため、営業秘密法に基づき起訴処分を下すことが難しい、との結論がほとんどであることが分かりました。
「秘密性」と「経済価値」に比べたら、比較的手間やコストがかかる秘密管理措置の整備は、自社の秘密情報は、営業秘密として取り扱われるかにおける一番重要な要素と言えましょう。
(「あなたは監視されている!会社がPCソフト等で実施する従業員のモリタニング・監視制度の合法性について」を合わせてご参考いただけます)

営業秘密法に抵触した法的責任
自社の秘密情報を営業秘密として成立させるためには、法律に定めた3つの関門を悉くクリアしなければならないことについて、前述した説明の通りです。そのなかで比較的手間ひまがかかり、ハードルが高いと思われるのは「妥当な秘密管理措置」を導入することです。

相当な経費をかけて、立派な秘密管理措置を導入するまで、自社の秘密情報を営業秘密に仕立てる意味ってある?なんかコスパ悪そうな感じが....
社内の秘密情報を法的に営業秘密として成立させることができたら、当該秘密情報の取り扱いに台湾の営業秘密法が適用され、不当利用を行った者に対して厳しく違法責任を問うことができるとされています。そのため、大事な無形資産である企業秘密を徹底的に守るためには、少々コストがかかっても仕方のない話しですね。
まず、営業秘密法に定めのあった比較的重たい刑事責任をチェックしてみましょう。
営業秘密法に違反する刑事責任
意図的に、自己又は如何なる第三者に不法利益をもたらしたり、営業秘密の所有者の権利を損なったりしようと、以下いずれかの行為を働いた、若しくは働こうとする(未遂犯も対象!)場合には、5年以下の懲役刑または禁錮刑、及び100万~1,000万NTD(犯罪所得がそれを上回った場合、当該所得の3倍を限度に罰金刑を重くすることは可能)の罰金に科せられる場合があります。(営業秘密法第13-1条)
また、上記違反事項のいずれかに該当し、かつ台湾の営業秘密を不当に海外に持ち出そうとする場合には、懲役刑として1~10年、罰金刑として300~5,000NTDが用意されるなど、もっと重たい刑が適用されます。(営業秘密法第13-2条)この辺は、国の利益を重視する法律設定となっています。
要留意なのは、営業秘密法を違反したら、窃盗罪や放火罪のように、警察は自動的に容疑者を取り調べてくれるわけではなく、被害者が被害届を出したり、提訴したりしない限り、容疑者は一切法的責任を問われません。(営業秘密法第13-3条)こういった「親告罪」の性質をしっかり把握し、タイミングよく、営業秘密法に基づき自社の秘密情報を不正利用した者に対して法的手段を講じる必要があります。
次、営業秘密を不当に取り扱う者に対しては、どういった民事責任を問うことができるか見てみましょう。
営業秘密法に違反する民事責任
自社が有する営業秘密が第三者によって、不当に取得されたり、不正に使用されたり、守秘義務があったにもかかわらず理由なく漏えいされたりする被害を受けたら、民事訴訟を提起することで、当該営業秘密を不当に取り扱う第三者に対して、不法行為を直ちにやめさせることができるとともに(営業秘密法第11条)、不法行為が行われて10年内、若しくは当該不法行為が行われたのを知って2年内であれば、損害賠償を請求可能です。(営業秘密法第12条)
ここでの要注目点はと言えば、営業秘密の実質的所有者(被害者)がもし自らの被害額を立証することが難しいのであれば、
- 営業秘密が悪用されない場合で得られる妥当な利益から、被害を受けた後で得られた実質的な利益を差し引いて算出した額を損害賠償額にする
- 加害者が営業秘密を不当利用したことで得られた利益を損害賠償額にする
以上2案から、自社にとって比較的有利な案を選択可能とされており、営業秘密犯罪の被害者に寄り添おうとする考えが伺えましょう。
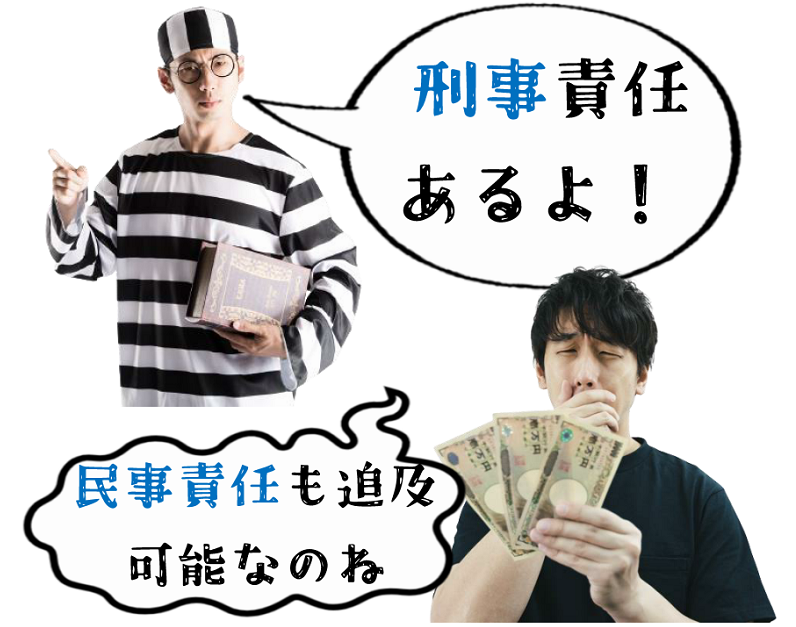
犯罪の取り調べにおける秘密漏洩リスクの防止
営業秘密法に違反する者に対しては、重たい刑事罰や損害賠償責任が用意されており、一定の抑止力を期待できますが、前述したように、法的に営業秘密と認められる3要件のうち、「妥当な秘密管理措置」が施されたかとの点において突っ込まれやすいので、告訴が成功するかどうかそもそも不安であり、検察側が行う取り調べで営業秘密の二次流出リスクも大変懸念されています。それによって、営業秘密不正利用の被害に遭ったにもかかわらず、提訴しなかったケースが多く存在しています。
こういった営業秘密の二次流出リスクを防止し、被害者にもっと積極的に法的アクションを取ってもらおうと、2019年末に営業秘密法に関する一部の法改正がなされ、取り調べ中の営業秘密を保護するための条項が追加されました。(施行日は2020年1月15日)
新たに導入された営業秘密の保護措置を以下要約します。
営業秘密二次流出被害の予防措置
- 営業秘密がらみの犯罪を調査する検察官は、必要に応じて秘密保持命令を関係者に発する権利が付与されること(営業秘密法第14-1条)
- 秘密保持命令を受けた者は、検察官が行う調査以外の目的に対象とされる営業秘密を使用したり、同命令を受けていない第三者に開示したりしてはならないこと(営業秘密法第14-1条)
- 秘密保持命令は書面又は口頭で発するものとし、営業秘密の所有者はそれについて意見を述べられること。(営業秘密法第14-2条)
- 秘密保持命令に違反した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮に科せられるほか、100万NTD以下の罰金刑も用意されていること。(営業秘密法第14-4条)
上記とは別に、外国法人が所有する営業秘密に対しての秘密保護措置を強化する規定も同法改正に盛り込まれています。
今まで、台湾政府から許認可を受けていない外国企業は、台湾の営業秘密法に則り、台湾における自社の営業秘密に関する不正利用を取り締まることができず、企業秘密を守る観点では不公平な取り扱いを受けていました。
2019年末の法改正以降、台湾政府から許認可を受けていない外国企業であっても、台湾の営業秘密法を活用し、自社の企業秘密が不当に流出され、不正利用されるリスクを回避しようと、台湾の司法機関に提訴することができるようになりました。(営業秘密法第13-5条)それによって、経済的価値の高い営業秘密を保有する外資系にとって、台湾は比較的安心・安全な国として、気軽に投資していただけるという、ちょっとしたアピールができたかもしれません。

終わりに
企業のサステナ経営には売上の追求は欠かせません。そして、売上の追求を支える原動力は企業の営業秘密になります。営業秘密を守ってくれる法的インフラが整備されず、誰でも簡単に他社の営業秘密を盗んだり、不正利用できたりする事業環境であれば、資本家は安心して投資したり、企業は積極的に社会に役立つ研究開発をしたりすることは望めません。
一方、営業秘密を保護するための法整備が既に整えているが、それをしっかり理解しておらず、若しくは不完全な認識しか持っていないとすれば、客観的に見てどれだけ事業主にとってフレンドリーな投資環境であっても、いざという時に、法的手段を使って貴重な営業秘密を守ることができません。
今回解説させていただきました「妥当な秘密管理措置」の有無については、例えば、とある会社は何かしらの管理措置を導入したが、コスパの問題もあって、それを定期的にアップデートしておらず、会社の管理職も如何に当該措置を活用するか完全に把握できなくて、無関心なままやり過ごしていました。事後になって、昔の離職者がフラッシュディスクで難なく社内の顧客リストや技術資料を一括持ち去ったことを発見したにもかかわらず、秘密管理措置が大変疎かであったことに気付き、かつ犯罪者の刑事責任を追及可能な時効も過ぎたため、自社の営業秘密が不当に利用された件によって被った損失を諦めるしかない等、非常に残念な経験を持つ中小企業が少なくありません。
営業秘密不正利用の犯罪者に対して、法的手段をもって対抗できる手立てが用意されているのに、その前提要件を知らない、若しくは形だけ前提要件をクリアしたことで、運悪く被害に遭ってしまったら、一切法的措置を講じることができない、という極めて悔しい状況を回避しようと、台湾の営業秘密に定めた3要件を悉く満足したのかを定期的にチェックすることがお勧めです。そのうち、特に失敗しやすい、妥当な秘密管理措置をうまく導入したか問題について、丁寧に確認することが必要でしょう。基礎的なチェックポイントは、例えば以下の管理措置10か条です。
秘密管理措置10か条
- 個別の従業員と法的に有効な秘密保持契約書を締結したか
- 個別の従業員と法的に有効な競業避止契約書を締結したか
- 従業員の退職手続きに合理的な秘密管理措置があったか
- 社内文書について、コピーを取る枚数に制限があって、かつコピーの使用先を追跡可能か?
- 社外秘の文書は適宜保存し、管理されているか
- 企業秘密の保管場所についての出入管理と監視がなされたか
- 秘密文書の廃棄処理が適切に行われているか。
- 取引先と秘密保持契約書を締結されているか
- 社内ネットワークのセキュリティ対策と管理がしっかりなされているか
- 入退室管理システムを実施されているか
日頃から自社の営業秘密を守る活動を実践しながら、法律的にはどのように営業秘密を取り扱うべきかとの観点を取り入れ、定期的に秘密管理措置のチェック・強化を行えたら、こういった貴重な無形資産が不正に利用されるリスクを相当な確率で抑えることができますので、必要に応じて、気軽にマサヒロとご相談ください。