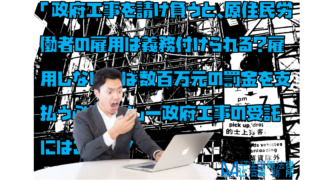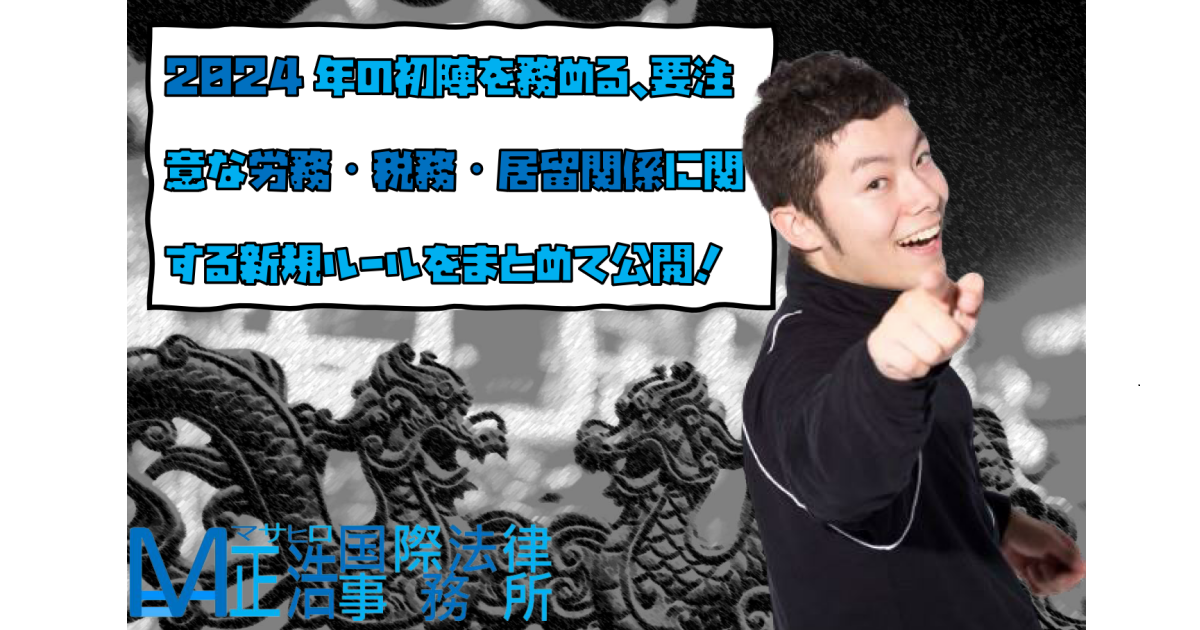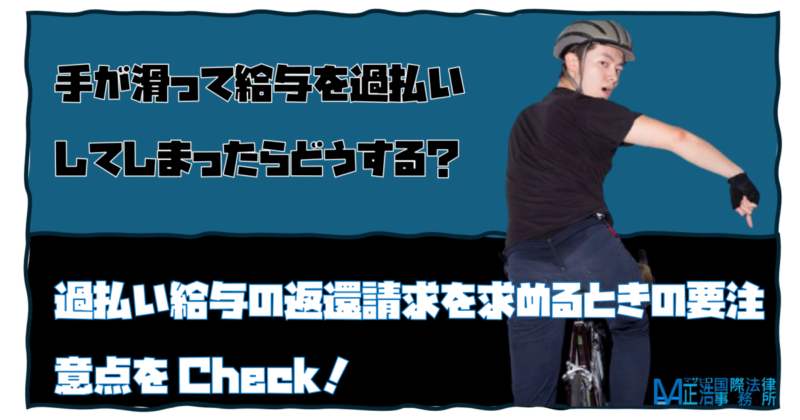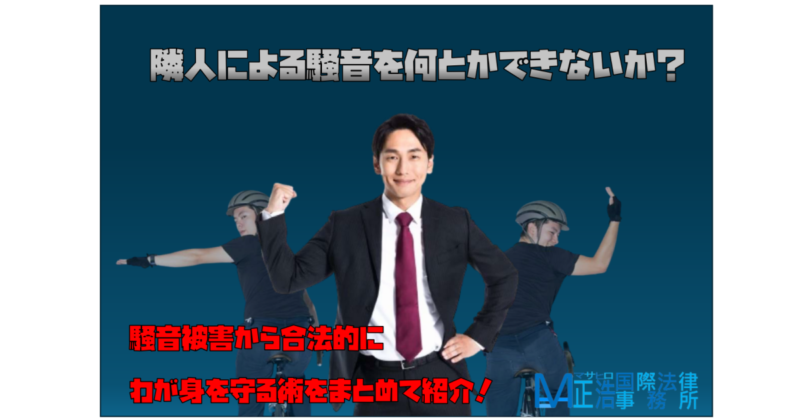「政府工事を請け負うと、原住民労働者の雇用は義務付けられる?雇用しなければ数百万元の罰金を支払う必要?!」―政府工事の受託にはご用心!
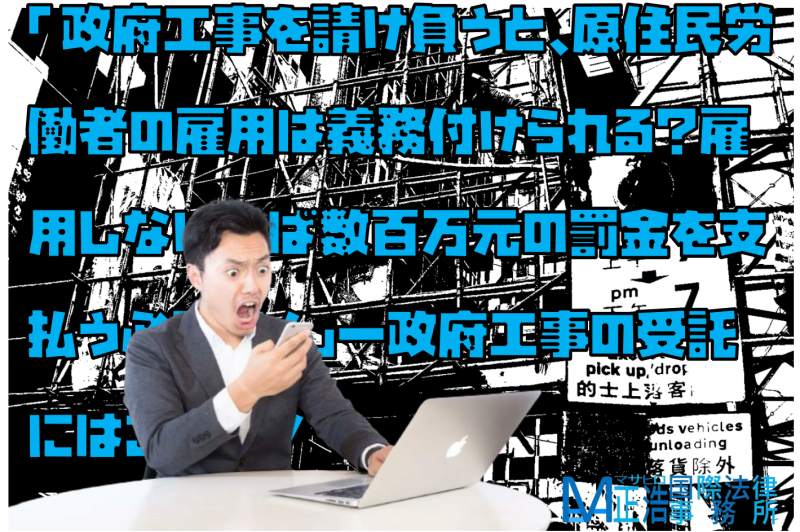
台湾において、法人対法人の取引は、善良風俗に違反しない限り、契約当事者は原則として契約書に記載されたそれぞれの権利と義務を守れば、取引を無事終わらせることができます。
それに対して、法人対公的機関の取引は、往々として目の遠くなるほどの内容がびっしり詰まった契約書が使用され、政府から案件を受託する会社は膨大な時間を費やしてそれを読み解いて、記載事項の通りに全ての義務を果たしたにもかかわらず、結局契約書に詳しく記載されていない法的義務を履行しないことで、思わぬ行政罰を食らってしまう事例が少なくないようです。
台湾電子機器受託製造大手のD社は、政府からいくつか工事を請け負って、問題なく完成できたものの、十分な原住民労働者を雇わらなかったことで、当局からNT$400万元超の就業支援金を追加で支払うよう命じられました。当該行政処分に不満を持つD社は、高額な支援金の支払い義務を何とか逃れようと訴訟で争いました。
以下、D社の裁判例を参考に、「政府工事を請け負うと、原住民労働者の雇用は義務付けられる?雇用しなければ数百万元の罰金を支払う必要?!」について解説したいと思います。
目次
原住民労働者の雇用を義務付ける法的根拠
台湾の公的機関から案件を受託した会社は、通常の法人間取引とは違い、契約書に可視化されている双方の権利と義務のみならず、関連法律に定められた、案件を受託する側が遵守すべき法的義務もしっかり果たさなければなりません。今回のマサレポに登場した主役であるD社は、まさに以下の法律によって、当局からNT$数百万元の就業支援金の支払いを命じられたわけです。
政府調達法に基づき公的機関から案件を受託し、かつ台湾国内での社員数が100人を超えた会社は、案件を施工する間に、全社員数×1%を下回らない原住民労働者を雇用する必要がある。当該会社が雇用する原住民労働者の人数が前述の比率を満たさなかった場合、原住民族に就業支援金を支払わなければならない。
政府調達法に基づき公的機関から案件を受託した会社が雇用すべき原住民労働者の人数を計算するとき(全社員数×1%)、小数点以下切り捨てて計算すること。
上記の法律を見れば、

大会社の雇用者数は大体変動が激しいから、全社員数×1%で計算するとき、「いつ」の社員数を基準にしたらよいか?
のような疑問が湧きましょう。これについてのルールも一応用意されています。
雇用すべき原住民労働者を計算するとき、政府から案件を受託した会社毎月1日の社会保険加入人数を全社員の人数とし、原住民労働者を十分に雇用しているかをチェックする際にも、当該会社の名義で「労工保険」に加入した原住民労働者のみ対象とする。
この法律を知っておらず最初から原住民労働者を雇用しなかったか、一生懸命募集をかけたが、結局十分な原住民労働者が集まらなかった場合には、D社と同じく支援金を支払う義務が生じてくるわけですね。問題は、支援金をいくら支払ったらよいのか、どのように計算したらD社のようにいきなりNT$数百万元規模の支援金を追徴されるのか、です。
政府から案件を受託した会社が十分な原住民労働者を雇用しなかったときに支払うべき就業支援金は、足りない人数×法定最低月給とする。
総社員数が200名の会社であれば、少なくとも2名(全社員数×1%)の原住民労働者を雇用必要で、1名のみ雇用した場合は、足りない1名×法定最低月給を原住民への支援金として支払うというロジックですね、なるほどです。次の疑問点は、法定最低月給をどうやって決めることです。
いわゆる「法定最低月給」とは、労働基準法に定めた「最低賃金」を指す。
労働基準法に定めた最低賃金について、今年2024年の金額はNT$27,470元です。前述の設例だと、政府から案件を受託した会社が支払うべき支援金はNT$27,470元との計算になります。この計算方法でいくと、台湾国内だけでも社員1万人以上を雇用するD社は、NT$400万超の支援金を追徴されるのも納得できるかもしれないが、こんな額をただ支払うより、原住民労働者を雇用して仕事を協力してもらうほうがよほどお得かなとも思います。
以上は、支援金を支払う法的根拠、及び支援金の計算方法についての説明です。しかしながら、原理原則こそ知っているが、当該「原理原則」の妥当性を疑問視しているD社は、手元にあるNT$400万元超の支援金追徴納付書を見て、とことん食い下がることを決定しました。次は、「原住民族に就業支援金を支払う」というルールが妥当かどうか、D社が原住民族委員会を相手取って行った行政訴訟における裁判官の判断をチェックしてみましょう(112年度訴字第731号行政判決)。
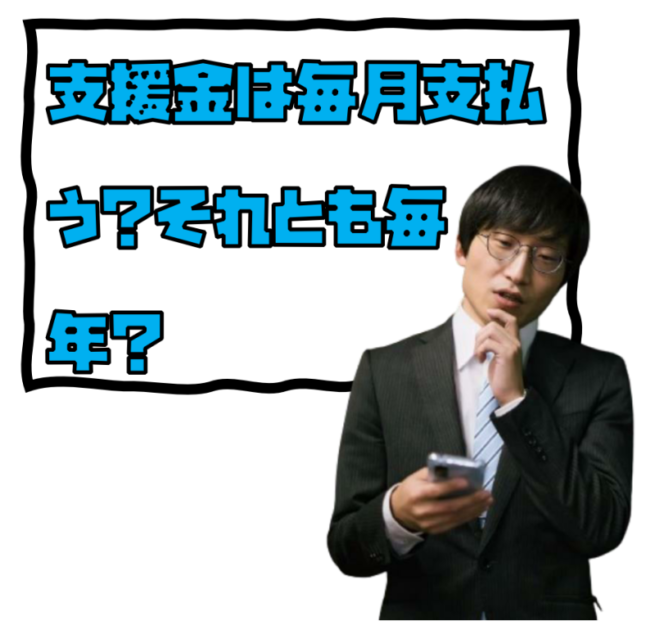
支援金制度の是非を問う―憲法の定め
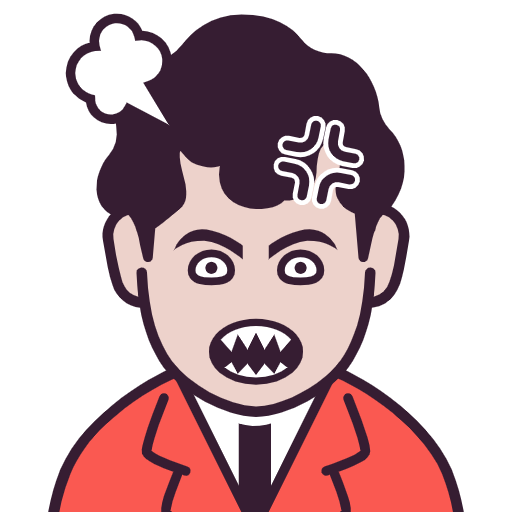
政府案件を実施する間に原住民労働者を雇用しなければならないという法律は、会社が労働者を雇用する自由が制限され、支援金の強制納付制度というのも財産権の侵害に該当するから、不適切だ!
というD社の主張に対して、裁判官はこう論破しました。
憲法に定めた民族平等の原則、及び原住民族への扶助義務に則り、原住民族の就業促進、社会的地位を改善しようと、政府から案件を受託した会社に原住民労働者を雇用することを義務付けたわけです。かつそれは国際的な流れにも沿ったものだし、重要な公共利益を守る観点で妥当性があったと認めます。
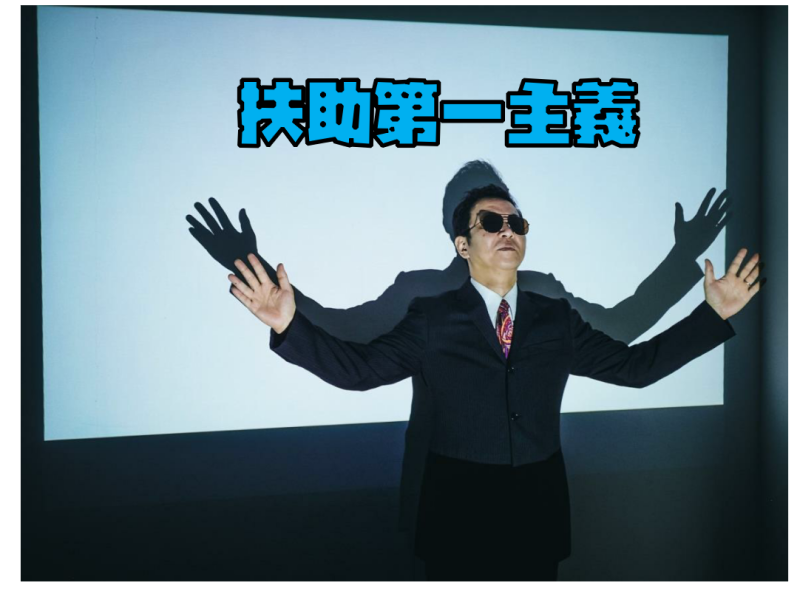
支援金制度の是非を問う―比例の原則

支援金の額があまりにも高すぎて、金額の設定方法は明らかに問題がある!
というD社の主張に対して、裁判官はこう論破しました。
総社員数の1%に相当する原住民労働者を雇用すればよいから、決してめちゃくちゃ高い比率設定ではありません。また、支援金が高すぎるか問題については、政府の案件を受託する前に検討すべき条件なのに、案件を受託してから「高いな」と文句を付けられてもしょうがありません。そして、原住民族への支援という公共利益を守ることと支援金の額を天平にかければ、比例の原則に反していないことが分かります。
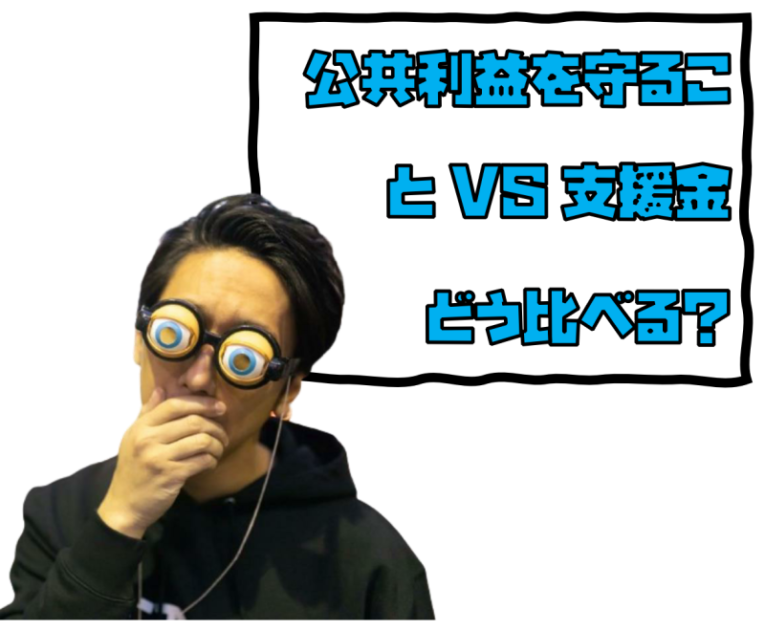
支援金制度の是非を問う―平等の原則

社員数が100人超の会社にだけ原住民労働者を雇用する義務を課すというのは不公平じゃない!政府から案件を受託する全ての会社に同じ義務を要求すべきだ!
というD社の主張に対して、裁判官はこう論破しました。
社員を100人超雇用する会社は規模が大きく、雇用する労働者数を比較的調整しやすいので、「大いなる力には、大いなる責任が伴う」という論点に基づき、社会に貢献する義務をより多く課すことは理にかなっています。
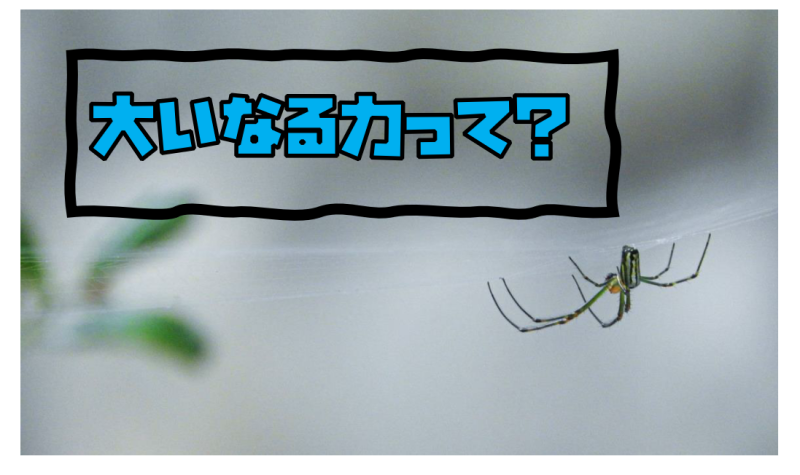
支援金制度の是非を問う―優遇しすぎる問題
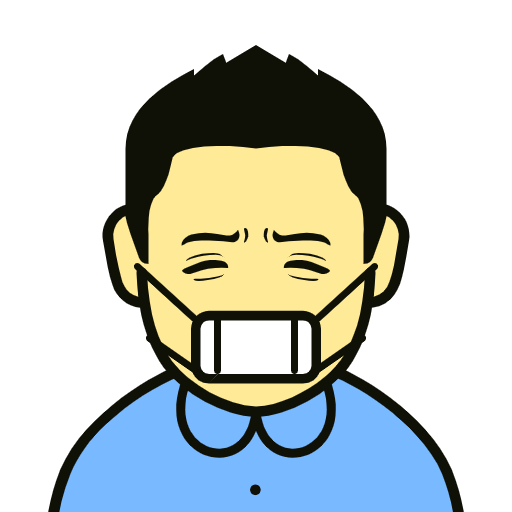
原住民労働者の失業率は台湾全体の失業率との差が微小であり、大卒労働者及び15~24才の若手労働者の失業率はむしろ原住民労働者の失業率より高い。何故大卒労働者または若手労働者の追加雇用を会社に要求せず、原住民労働者だけ優遇するのか?逆差別にならないのか?
というD社の主張に対して、裁判官はこう論破しました。
政府から案件を受託した会社に課す原住民労働者を雇用する義務は、いわゆる「アファーマティブアクション(積極的格差是正措置)」に該当します。その目的は、長年にわたり社会に内在している不平等を是正し、原住民労働者の就業機会を確保することで、実質的な平等関係を達成するためにあります。なお、雇用すべき原住民労働者の人数は、総社員数の1%という相当低いレベルに達せばよいので、逆差別の心配はありません。
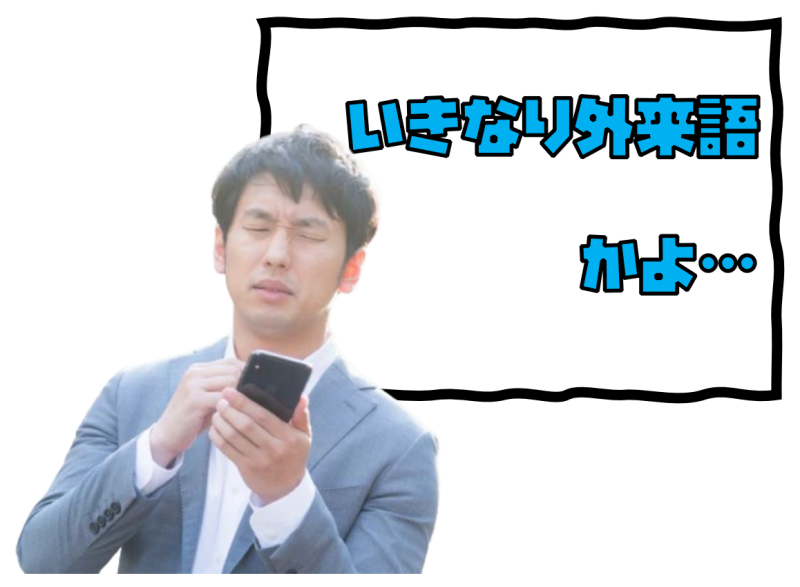
支援金制度の是非を問う―不当連結禁止の原則
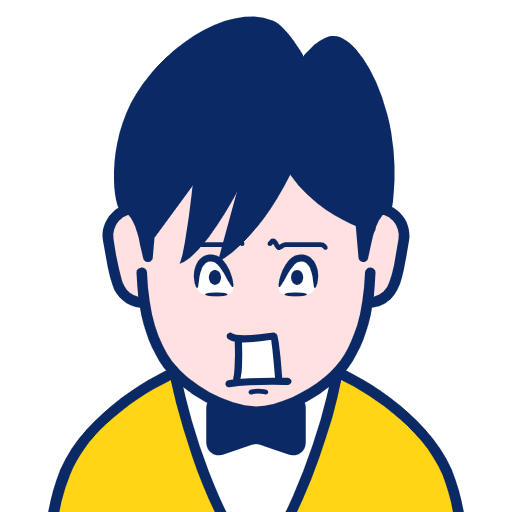
政府から案件を受託しようとするときに守るべき政府調達法は、原住民の失業問題を解決しようとする原住民族就労権保障法とは全く無関係な法律であり、それらを強引に結び付ける形で、「原住民労働者を雇用しろ」という政府側の義務を会社に押し付けるのはどうかなと。
というD社の主張に対して、裁判官はこう論破しました。
政府の案件をどの会社に任せるか、いくらで任せるかは、国の予算に関わる問題です。国の予算が関係する以上、「公共利益の向上」という要素を考えなくてはなりません。そのため、政府調達法に、原住民族の失業率を改善可能なルールを導入するのも至極当然な話しだし、不当連結禁止の原則に反するものには当たりません。
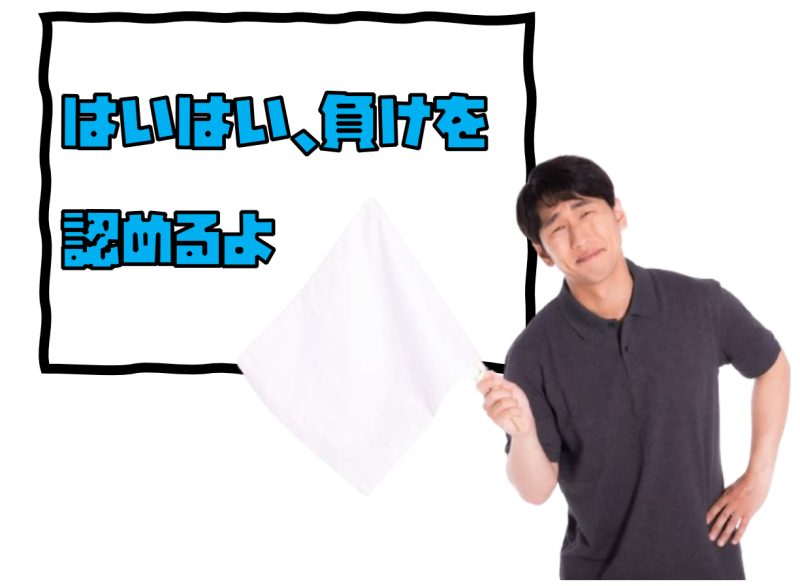
支援金制度の是非を問う―無い物ねだり
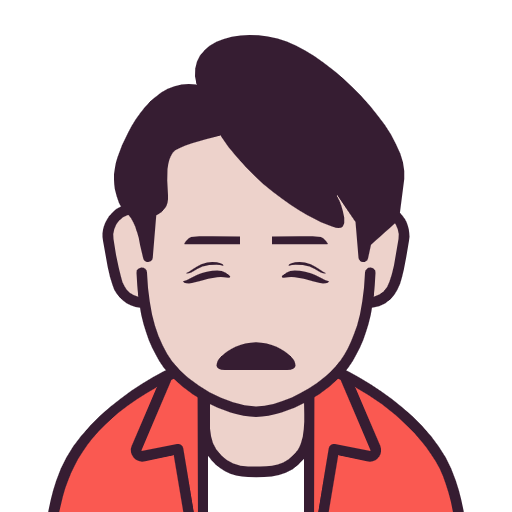
就職活動を行っている原住民労働者はそれほど多いわけではないから、政府の案件を受託してからいきなり大勢の原住民労働者を雇用しろと言われても、どれだけ一生懸命に雇用しても十分な原住民労働者が集まらないのだよ!
というD社の主張に対して、裁判官はこう論破しました。
D社は「一生懸命に雇用しても」という企業努力を証明できるエビデンスを提出しておらず、原住民労働者の雇用に取り組んだ、との姿勢が見当たりません。それに、比較的よい賃金条件や福利厚生で募集をかければ原住民労働者も雇用しやすくなるはずなのに、それをやらずして企業努力を果たしたと言えますか?
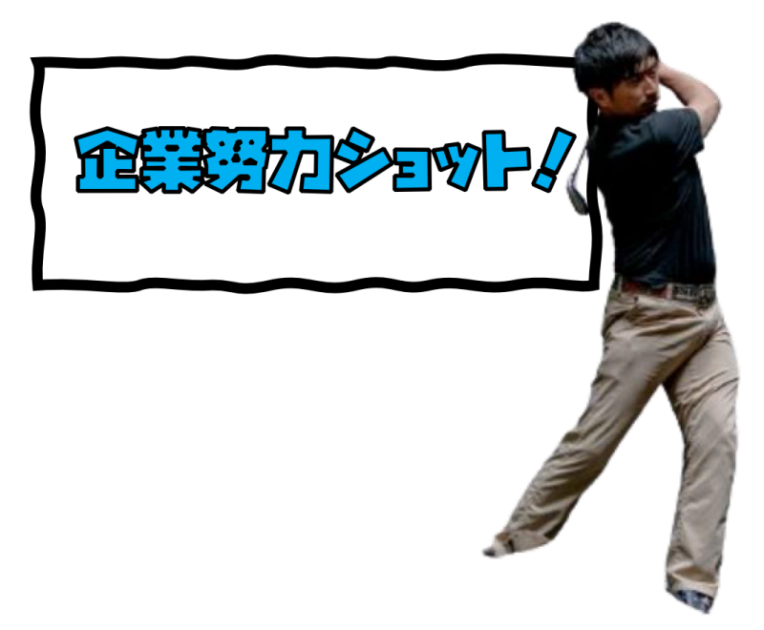
支援金支払い義務の例外
各種主張を繰り出したD社は、とうとう裁判官が展開したATフィールドを破ることができず、支援金制度の是非を問う訴訟にて華麗に玉砕してしまい、NT$400万超の支援金を追加で支払う結末を迎えることとなりました。一方、十分な原住民労働者を雇用していない政府案件の受託会社に課す支援金の支払い義務にも実は例外があります。
ある会社が政府から受託した案件の契約金額がNT$164万元であるにもかかわらず、支払うべき支援金の額はなんとNT$294万元との計算結果でした。当該会社が裁判所に対して不服申し立てを行った結果、「受託会社が契約金額以上の支援金を負担するのがおかしい、比例の原則に反するのである」、との見解が示されました(釈字第810号)。
上記の見解により、行政院が今年2月15日に可決した原住民族就労権保障法の改正草案に、「受託会社の負担する支援金の額が政府案件の契約金額を超過し、かつ超過した金額が一定の比率に達した場合は、負担すべき支援金を減額することができる」、という支援金の軽減措置が盛り込まれました。この草案が施行されると、「政府から案件を受託すればするほど損する」という違和感が持たれる現象が確実に減ると期待されています。

今週の学び
取引契約を締結するとき、双方が約定する準拠法によって互い守るべき法律が決まります。それに対して、台湾の公的機関と契約するとき、契約書の内容のみならず、「政府調達法」の内容も別途確認する必要があり、一つでもひっかかる条項があれば、自社の条件に照らし合わせて、課題をクリアできるか事前に、徹底的に検討してから、発注機関の入札に参加するかを決定することがおすすめです。政府調達法についてのご相談は気軽にマサヒロへお問い合わせください!