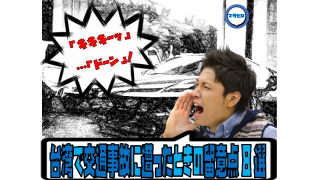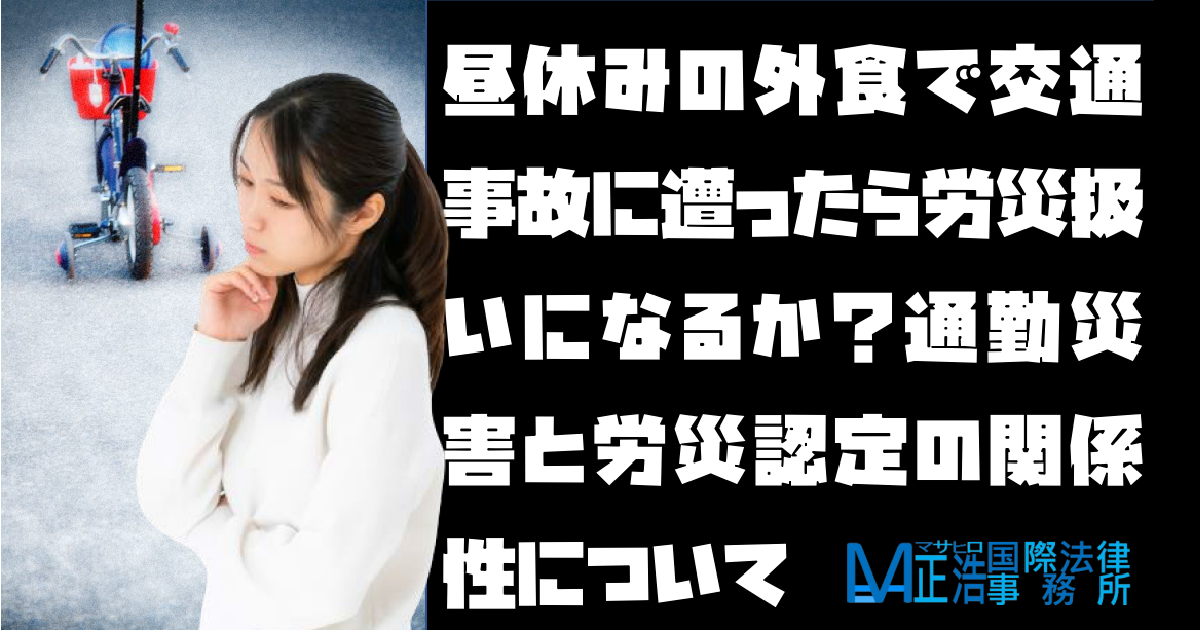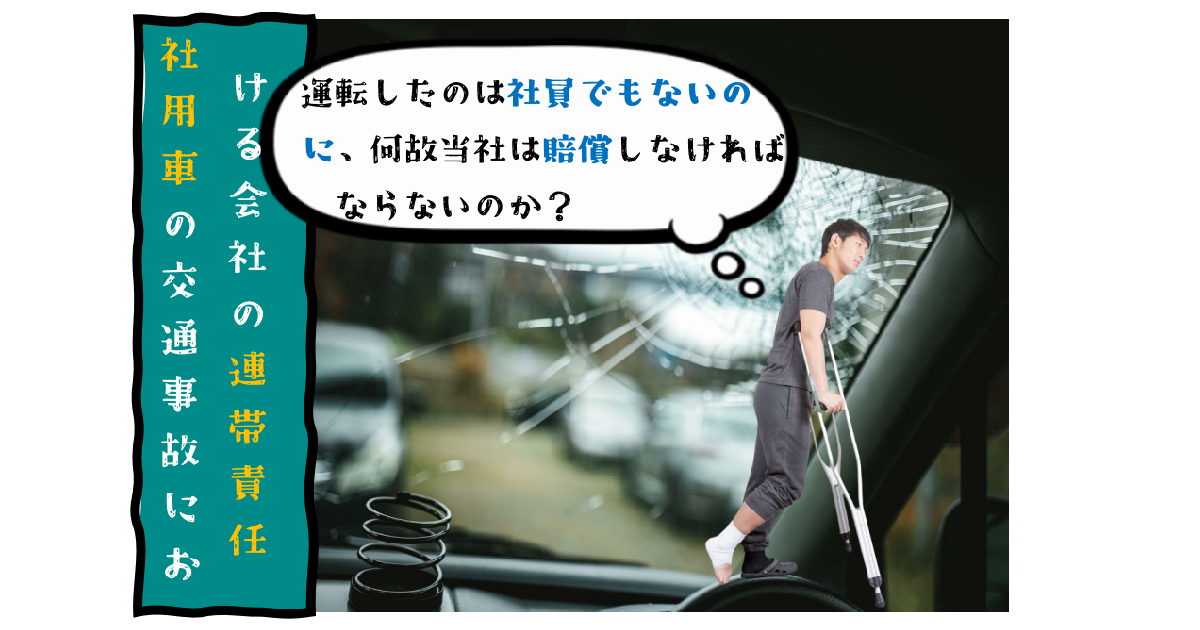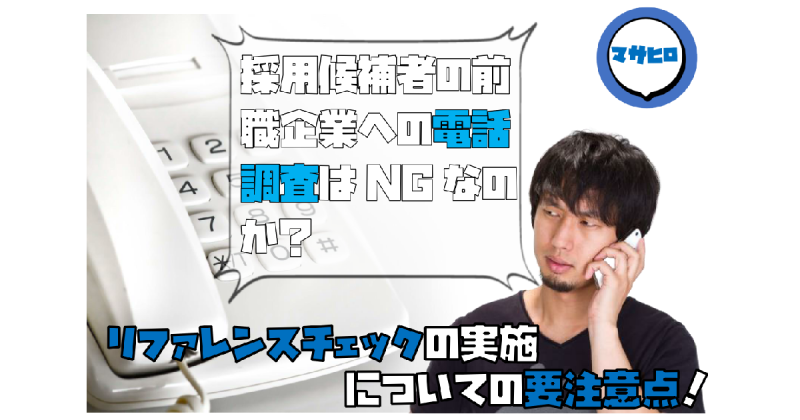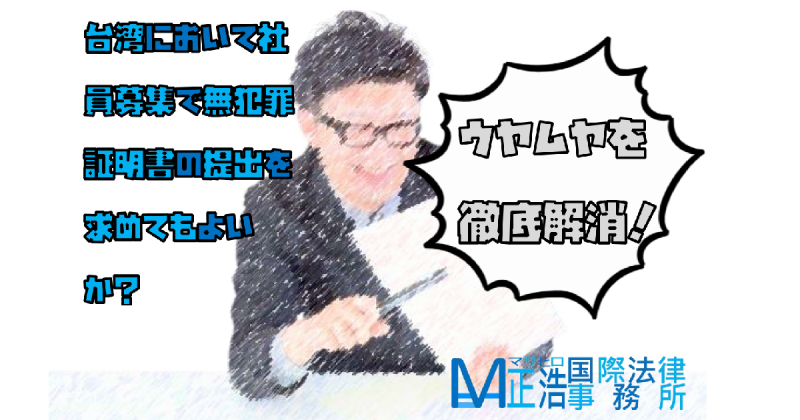「キキキーッ」…「ドーン」!台湾で交通事故に遭ったときの留意点8選
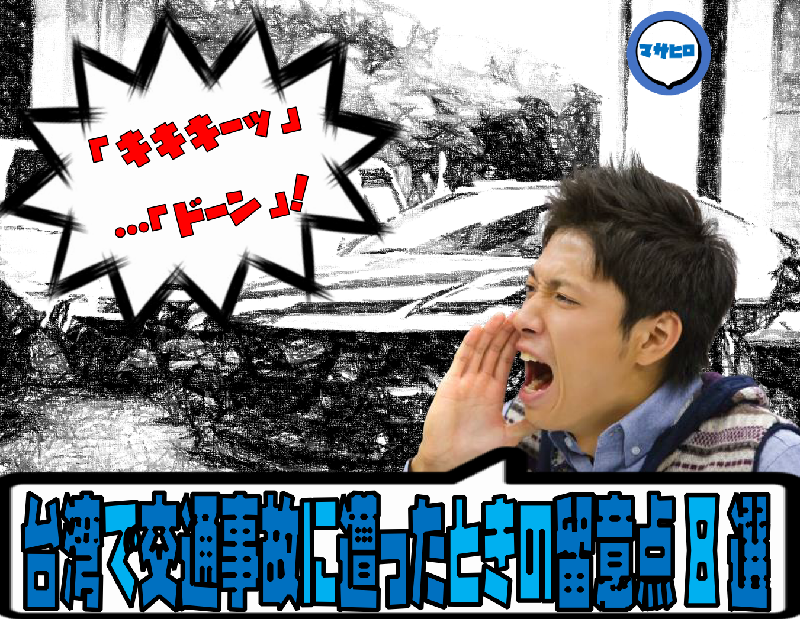

テレビを付けたら、交通事故のニュースが流れています。
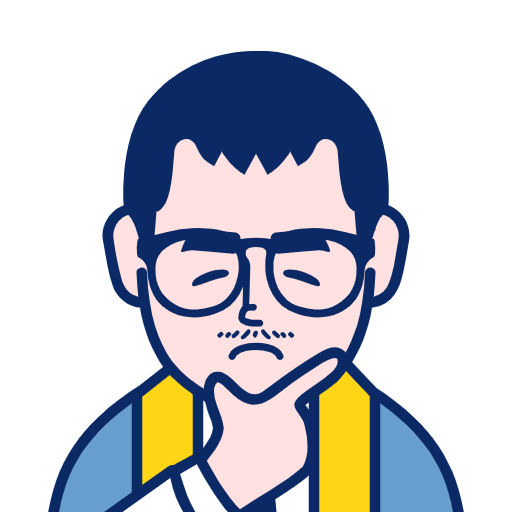
会社への通勤路で1~2日に少なくとも1回の頻度で交通事故を目撃しています。
昨年の暮れ、アメリカの大手メディア・CNNから「生き地獄」と評されたのをきっかけに、台湾の交通安全問題が以前にもまして議論されており、横断歩道で歩行者に道を譲らなかったり、高速道路で各種危険運転をしたりする行為への厳罰化に関する法改正もすごい勢いで進められています。にもかかわらず、厳罰化の効果はおそらく限定的で、道路の構造を根本から変えなければ、台湾の交通事情がよくならないのでは、とも囁かれています。
上記の話は、なにも歩行者だけ気にしそうなものではなく、台湾で車やバイク、自転車を運転する人にとっても、真剣に向き合うべき課題となりましょう。
交通事情がいきなり改善される可能性が低いである以上、安全運転に気を付けながら、いざという時にどういった対応を取ったらよいのかについて、関連法律をもとに、Q&A形式で留意していただきたい情報を以下展開致します!
目次
Q1:相手は怪我していないので、警察に通報しなくてもよいか?

ゆっくり運転で相手のバイクをかすっただけであり、見た目怪我もなさそうだから、警察に通報する面倒さを考え、バイクの修理代をカバーできる現金を相手に渡して解決としよう。
上記の考え方は大変危ないのです。
傷害の程度を問わず、交通事故で相手に怪我を負わせたにもかかわらず、警察に通報せず現場を離れた場合、当て逃げ罪に該当する可能性があり、6ヶ月~7年の懲役刑に処せられるとともに(刑法第185-4条)、1,000~9,000NTDの過料並びに運転免許の取り消し(道路交通管理処罰条例第62条)の行政罰が下され、相手からも損害賠償請求をされてしまいます。
ですから、たとえ全然大して被害が認められない交通事故に見えたとしても、警察への通報を強くおすすめします。
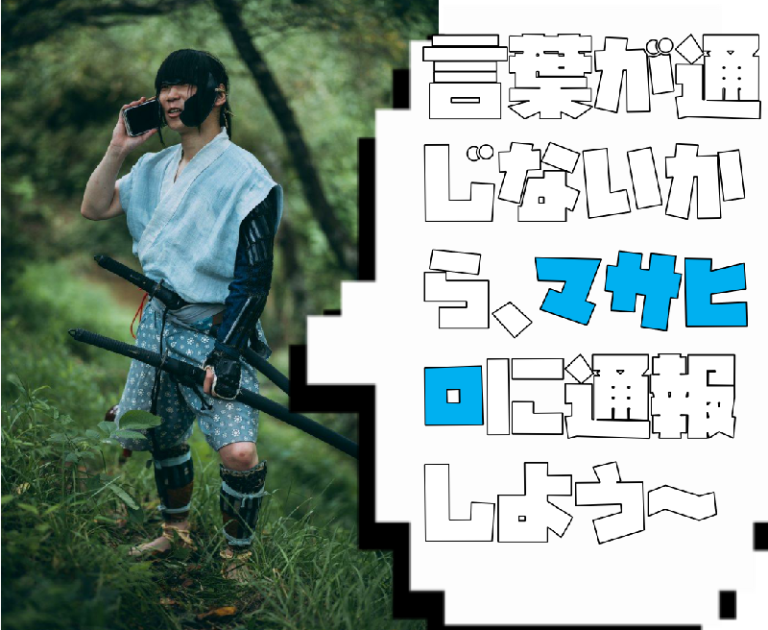
Q2:事故車両を移動してもよいか?
答えは、可も不可もなく、その場の状況によって個別判断が必要です。
交通事故の当事者に負傷者または死亡者がなく、事故車両も運転可能な状態であるにもかかわらず、当該車両をただちに移動せず、かつそれが交通の妨害となったら、600~1,800NTDの過料処分が下されます。
一方、負傷者または死亡者が出た場合、原則として事故車両を勝手に移動してはならず、違反したら3,000~9,000NTDの過料を払わされる形になりますが、当事者双方合意のうえ、チョークなどで車両の位置を書き記して、交通の妨害にならないよう車両を移動しなければならないともされています(道路交通管理処罰条例第62条)。
留意が必要なのは、相手が負傷しているかどうか見た目で判断しにくく、車両の位置を正しく記録できるかどうかの自信もなさそうな場合、現場の会話を録音したり、現場の様子を写真や動画で記録したりしておくことがよいでしょう。

Q3:停止表示器材の設置は義務なのか?
台湾のルールでは、交通事故が起きたら、後続の車両から見えやすい適当な場所に三角表示板などの停止表示器材を置かなければならず、違反した過料は1,500~3,000NTDです(道路交通管理処罰条例第59条)。
また、いわゆる「適当な場所」に関するルールも定められています。
- 高速自動車国道
- 事故現場の後方100メートルの地点
- 自動車専用道路または法定速度が時速60キロ超の道路
- 事故現場の後方80メートルの地点
- 法定速度が時速50~60キロの道路
- 事故現場の後方50メートルの地点
- 法定速度が時速50キロ以下の道路
- 事故現場の後方30メートルの地点
- 交通渋滞または時速10キロ以下の低速走行が続く道路
- 事故現場の後方5メートルの地点
停止表示器材の設置を怠ると、過料が発生するのみならず、それによって二次的交通事故をもたらしたら、刑事と民事責任も問われますので、停止表示器材を予め用意しておくことがおすすめです。

Q4:命の危険がないから病院に行かなくてもいい?

車事故で差し障りのないかすり傷をいくつか負ったが、病院で治療を受けるほどの負傷ではなく、時間がもったいないから、警察のヒアリングが終了したら帰宅しよう。
相手がいない物損事故であれば、時間を節約する観点で、病院で治療を受けなくても問題ないかもしれませんが、相手がいる交通事故なら、たとえ事故当日に自覚症状がほとんどなくても、病院で受診し、診断証明を発行してもらうことが望ましいです。
何故なら、事故当日に体に違和感を一切覚えていなくても、翌日または翌週、体調が急に悪くならない保証は何もないにもかかわらず、事故当日に診断証明を入手しなかったことで、体に起きた異変と交通事故との因果関係を立証することが難しくなり、最低限の損害賠償を求める権利も損なわれかねないからです。
交通事故の事後処理をスムーズに進めるためには、負傷が非常に軽微であっても、当日に診断証明書をゲットしておきましょう。
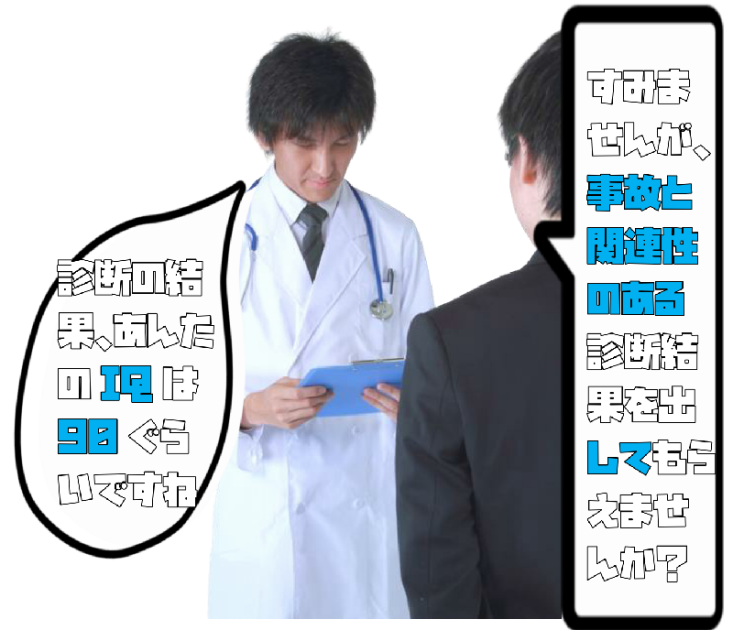
Q5:示談や保険関係に必要な書類とは?
警察に通報したら、担当する警察官が事故現場に出向き、現場を確認するとともに事故の当事者などへのヒアリングを行って作成した実況見分調書を事故当事者に渡します。こちらの書類を保険会社に提示すれば、その後の示談や賠償手続きを協力してもらえます。
事故から7日目以降、警察局に対して事故現場の写真と見取り図を取得できるようになり、当事者が負傷した場合は、オンライン申請で同資料を入手可能です。
示談や賠償手続きに関しては、以上の資料はあくまでも補助的な役割しかならず、事故から30日目以降に申請できる交通事故簡易判定表は重要性が比較的高いです。事故現場の状況をありのままに表す実況見分調書と事後現場見取図とは違い、簡易判定表は当事者それぞれが負うべき事故責任に関する言及がなされているため、賠償金額を決定する判断材料になりえます。
ただし、交通事故に関しては、簡易判定表のみで当事者間の過失割合がはっきりしない場合が少なくありません。その場合、3,000NTDの手数料を負担のうえ、専門家委員会に対して交通事故の鑑定作業を依頼する必要性が生じてきます。専門家ではない警察機関が作成する簡易判定表より、専門家委員会が作成した鑑定意見書のほうが最終的な判断基準とされる傾向なので、示談でなかなか決着がつかなければ、鑑定作業の依頼が有効です。
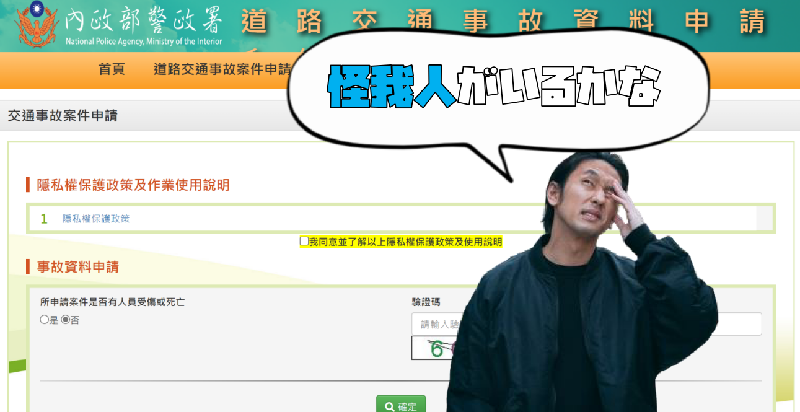
Q6:鑑定意見書の内容に不満があったら?
交通事故専門家委員会が出した結果に納得がいかなければ、訴訟を起こし裁判官に直訴して、鑑定意見書の見解を覆すことにチャレンジする手段がある一方、同意見書を受領して30日内にさらに2,000NTDを支払い、1回限定の不服申し立てを行うことも可能です。
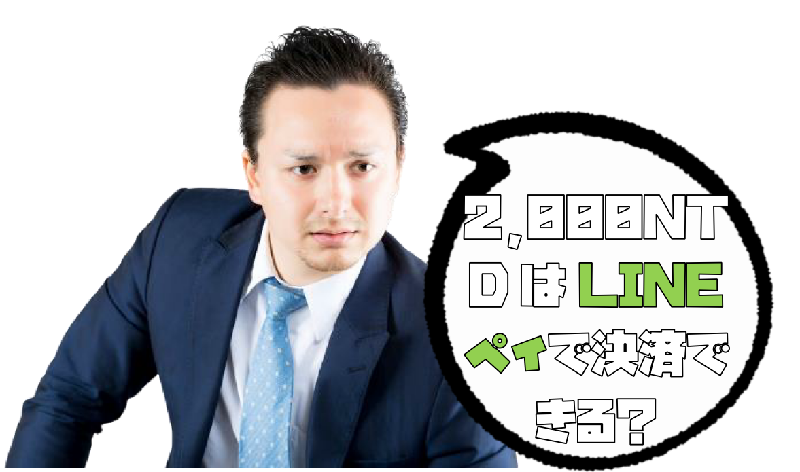
Q7:交通事故の訴訟って時効あるか?
交通事故で負傷者または死亡者が出て、かつ示談も成立しなかったら、裁判で決着をつける形になります。
示談で一番もめやすいのは、「妥当な賠償金をいくらにするか」との点です。それをはっきりさせるには、民事訴訟を提起して損害賠償を求める手段が有効です(民法第184条)。提訴可能な期間は、被害事実を知ってから2年以内とされているため(民法第197条)、余裕をもって裁判を起こすかどうか検討できます。
それに対して、損害賠償のみならず、相手の刑事責任も問おうとする場合は、相手が故意に交通事故を引き起こすという極端なケースを除き、過失傷害罪(刑法第284条)または過失致死罪(刑法第276条)で刑事訴訟を提起可能となります。留意が必要なのは、過失傷害罪は親告罪に該当し、被害者が提訴しなければ検察機関は能動的に調査手続きを開始しません。なお、提訴可能な期間は加害者を特定できてから6ヶ月以内、という比較的短い消滅時効のルールが適用されるため(刑事訴訟法第237条)、民事訴訟を提起するかより、こちらの告訴を申し立てるかの検討を先に行わなければなりません。
一方、実務的には、裁判所に支払う政府手数料を節約する方策として、先に政府手数料がかからない刑事告訴を行い、起訴が決まったら、刑事付帯民事訴訟を追加で提起する方法が取られています。

Q8:示談に期限あるか?
交通事故の当事者双方が行う示談にはこれといった期限はありませんので、原則としていつでも実施可能ですが、刑事裁判で有罪判決が出てからの示談は意味が薄いので、それまでに示談を行うことが望ましいのです。
保険会社の担当者に、相手との示談を任せたら時間の節約にはなりますが、相手が相場を超える賠償金を提示してきたら、保険会社任せの示談が成立する確率がだいぶ下がるので、必要に応じて、自ら示談に臨んだりするのもよいでしょう。
示談のポイントは、当事者双方が納得する賠償金をいくらにするかを別として、示談書にどういった内容を書くかも大事です。例えば、示談書においては、保険金や慰謝料などを含めた賠償金を完璧に定めましたが、加害者への法的責任を追及する権限に関する言及が一切触れていなかったら、たとえ加害者が賠償金を全額払ったとしても、結局被害者から訴えられ、有罪判決を言い渡された可能性も無きにしも非ずです。示談書の作成に関して、予め法律専門家の意見を聞いたりすることがベストです。
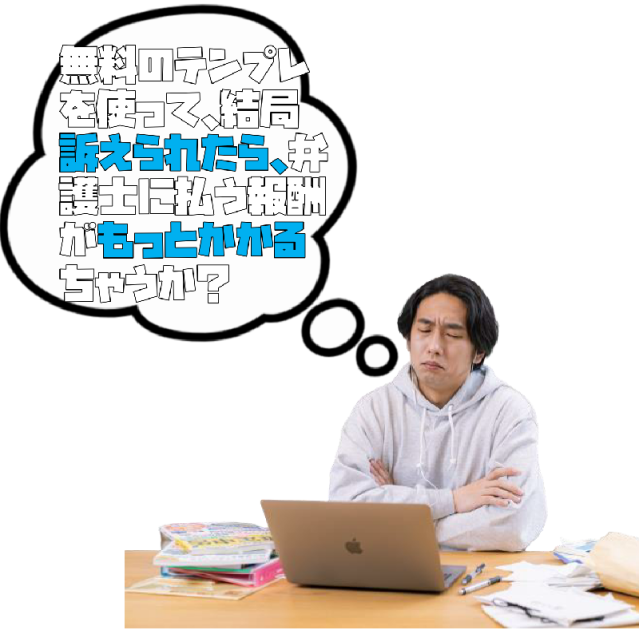
今週の学び
どれだけ一生懸命気を付け、安全運転に努めたとしても、道路設計の問題や相手の不注意など、こちら側でコントロールしようがない要因で交通事故が起きたりします。ですので、交通ルールと運転マナーは勿論大事なんですが、いざという時に備え、事後処理に役立つ法律知識もしっかり身に着けておきましょう。