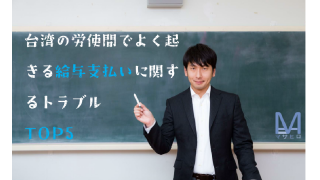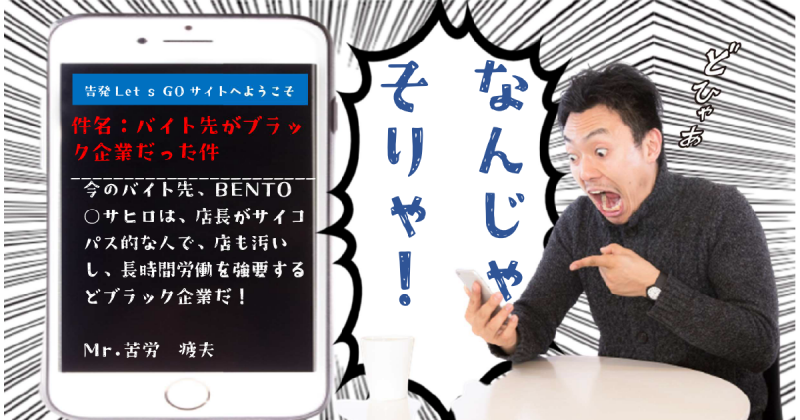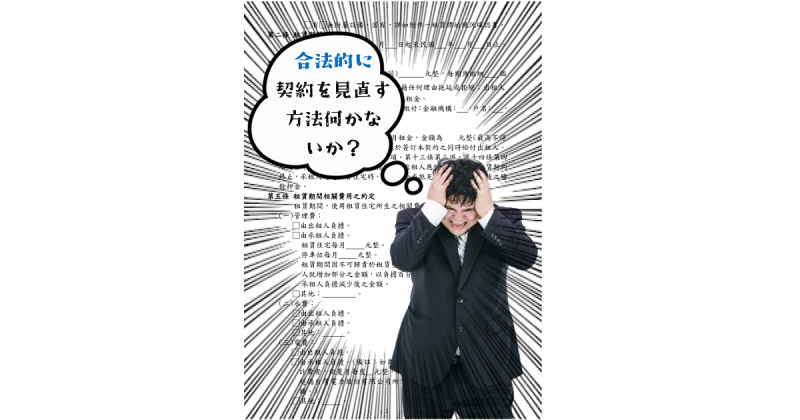台湾の労使間でよく起きる給与支払いに関するトラブルTOP5
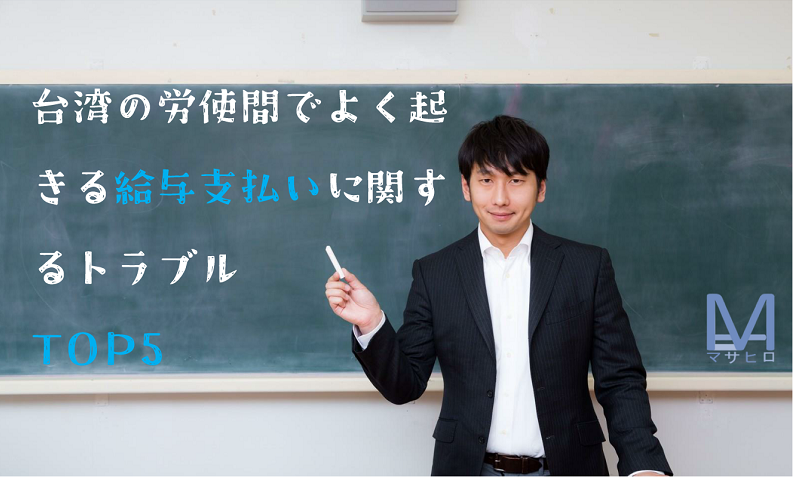
従業員が事業主の命令に従って労働を提供し、事業主が従業員から受領する労働に基づき対価を支払う、これが至極当然のやり取りです。にもかかわらず、台湾の労使間のトラブルにつながる火種として、給与支払いにまつわる問題は、幾度となく取り上げられています。
給与を全く支払わなければ、それが紛れもなく違法なので、そのようなリスクをあえて冒してまで給与を未払いにする事業主はそれほど多くありません。実務上よくトラブるになっているのは、約束した給与が、完全な状態で、正しいタイミングで支払われるのか、いわゆる「賃金全額払いの原則」に関する法令遵守の問題です。
社会保険の自己負担や源泉所得税、従業員が月次ベースで拠出する退職積立金等は、会社が関連法律に基づき給与の天引きを行っており、かつ天引きされた分は公的機関に納付されるので、賃金全額払いの原則が適用されません。それとは別に、会社が実施する社内罰金制度や減俸処分は、賃金全額払いの原則に照らし合わせたら、どこまでがセーフラインで、どこからがアウトになってしまうのか、うやむやを感じる事業主が少なくないでしょう。
台湾の労働部が近日、労働者から相談を受けた給与支払いに関する問題を整理し、よくトラブるにつながる5つのパターンを公表しました。今週のマサレポは、当該5つトラブルの類型を分かりやすく紹介しながら、それに関する対応方法や留意点について解説させていただきたいと思います。こちらの内容を、自社の労務ヘルスチェックの参考にしていただけたら幸いです。
目次
給与支払いに関するトラブルその❶―タイムカードの打刻
労働部への電話相談のうち、相談事案ランキングTop10に食い込めるのではと思われるほどの高頻度を維持し続けているトラブルとして、「タイムカードの打刻を忘れたら、会社は勝手に給与を引けるか」との質問です。
台湾労働基準法の定めによっては、事業主は、従業員の勤怠記録を作成し、5年間保存必要であるとされています。(労基法第30条第5項)そのため、従業員の出勤・退勤時間を記録する義務は会社側にあって、従業員が毎日行っているタイムカードの打刻は、あくまでも会社が負わなければならない法的義務に協力するに過ぎないとの位置づけであることが分かります。
従って、従業員が実際時間通りに出退勤していたにもかかわらず、タイムカードの打刻がなされていないのみを理由に、遅刻や早退、欠勤扱いにして、その分給与を差し引いたら、労基法違反となってしまいます。
一方、社内に設置された監視カメラで、とある従業員が明らかに遅れて出社するのが分かって、若しくはその他の従業員からの証言で、当該従業員が遅刻又は早退が有ったと証明できた場合には、給与の減額処分が可能となります。
実務的によくあるのは、タイムカードの打刻を忘れたら、1回に付き有給休暇又は自己都合休暇を○分(又は○時間)を取得しなければならない、という風に作られた社内規則です。法律的には、有給休暇又は自己都合休暇は、原則として従業員が自らの意志で取得するものとされており、タイムカードの打刻忘れを理由に、従業員に休暇の取得を強制するルール作りは労基法に反するものであり、労使間のトラブルにつながる恐れがありますので、留意が必要です。(労基法第38条第2項)
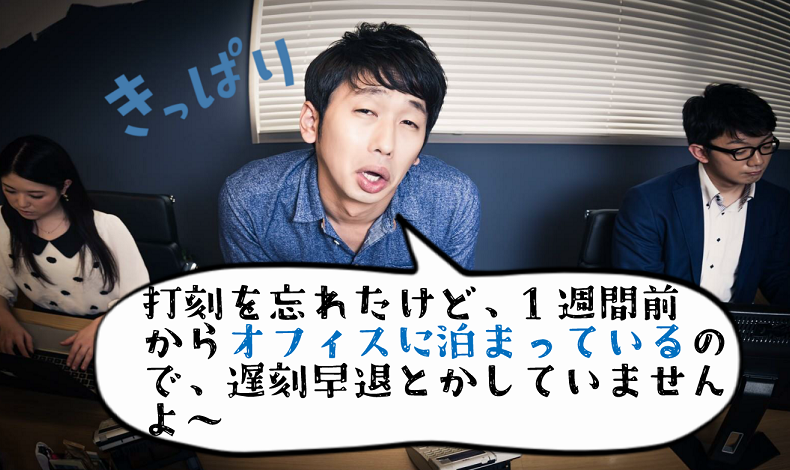
給与支払いに関するトラブルその❷―社内罰金制度

デパートが行う覆面調査で、接客態度が不合格と評価され、給与の一部が罰金として差し引かれました。
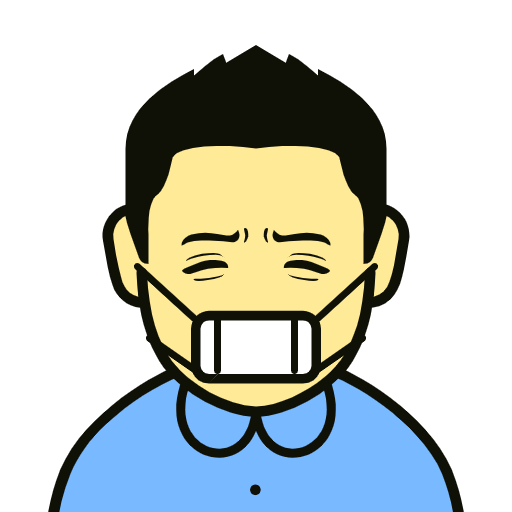
料理の盛り付けや配膳の手順が少しだけSOPと異なるだけで、ひどく叱られた挙句、給与明細書をもらったら罰金を食らいました。
以下マサレポを合わせてご参考いただけます↓

ビラ配りの最中、ちょっと息が苦しくなって、マスクをしばらくの間ずらし呼吸していたら、それが監視カメラに映ったようで、上司から罰金処分を言い渡されました。
以上の事例は、労働部がよく労働者から受ける労基法違反の告発案件だそうです。
従業員が会社の就業規則に定めた懲戒事由を違反したら、会社は、比例原則に基づき従業員に処分を下すことは、原則として台湾の労働法に禁じられていません。ただし、処分の内容は、会社が一方的に定めた罰金額を従業員の月次給与を一部ないし全部差し引く社内罰金制度の実施は、賃金全額払いの原則に違反する事項として、ペナルティを科される可能性が非常に大きいです。
従業員に作業ミスがあって、その結果会社に何かしらの損失をもたらし、会社への金銭的損害賠償として当該従業員に処分を下そうとする場合には、法律に触れないやり方としては、一方的に給与を差し引くのではなく、従業員の同意をしっかり取得してから、支払いを求めることが望ましいです。
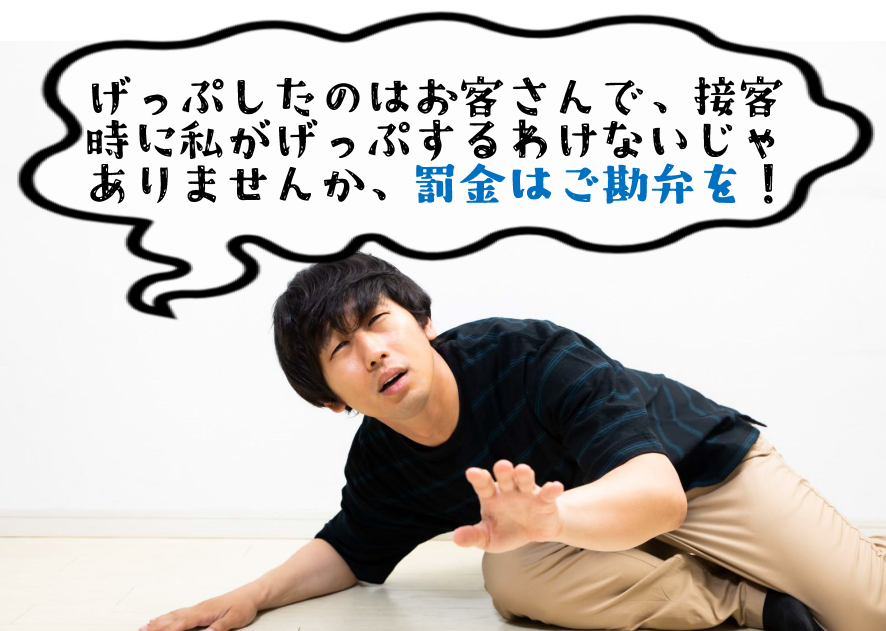
給与支払いに関するトラブルその❸―減俸処分
従業員は会社が定めた就業規則に違反し、かつその程度が重大であったりする場合には、降格又は減俸、解雇等がよく採られる懲戒処分です。
解雇については、従業員から労働を提供する権利を取り上げる処置なので、法律上、一番厳しく見られるのは言うまでもありません。そのため、会社は解雇という最後の手段を回避し、比較的寛大な処分として減俸を実施しようとしたら、地方労工局が行う立ち入り検査で、当該減俸処分が「賃金全額払いの原則に反する」と指摘され、ペナルティを受けてしまう事例が決して少なくありません。
従業員に重大な規則違反があったにもかかわらず、減俸ぐらいの処分もできないのか、それともストレートに懲戒解雇するほうが無難なのかと、台湾の中小企業の間ではよくこういった疑問が湧くようです。最大の問題点は、減俸処分の実施そのものではなく、従業員の同意を得られることなく会社が一方的に減俸を決定する点にあるのです。
従業員が受領する月次給与の額は、労働契約に記載すべき事項で(労働基準法施行細則第7条第3号)、それを変更するためには、労使間の合意が必要とされ、会社又は従業員のどちらか一方的にそれを変更することができないとされています。(行政院労工委員会労働2字第0980130120号通達)
従って、懲戒処分としての減俸の実施を会社が決定したら、対象従業員とそれについて協議を行いかつ了承を得てから、正式的に減俸を実施する、というのが比較的正しい対応方法と考えられます。
一方、減俸処分について協議を行う際に、対象従業員はただ黙りこくって、人事担当からの一方的なおしゃべりを聞いているだけでは、従業員の同意が得られることにはならない、つまり「黙示的同意」との考え方は本件には通用しないわけです。(行政院労工委員会労働2字第0980130120号通達)そのため、こういった同意を取得するプロセスにおいては、労使間の署名・捺印がなされる書面を残すことが望ましいです。
ちなみに、業績賞与制度を導入する会社は、従業員の理解を得られることなく、業績を達成するハードルを一方的に引き上げたら、実務的に、賃金全額払いの原則に反すると行政側が判断する事例もありますので、業績賞与制度の運用に気を付けておきましょう。
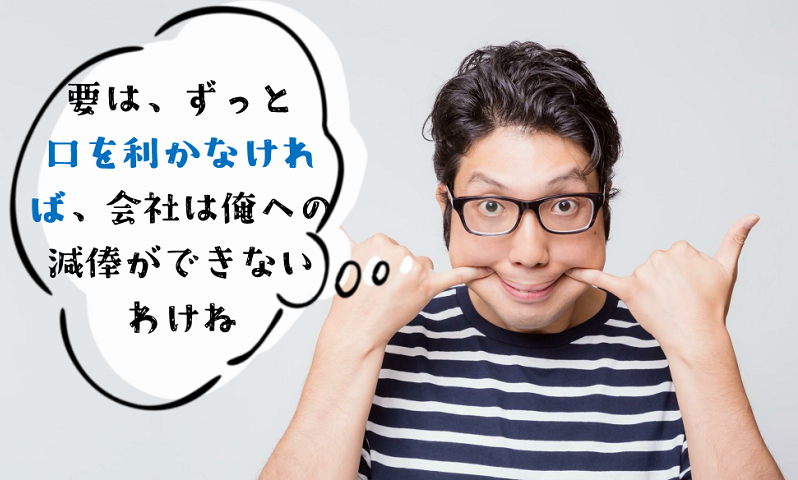
給与支払いに関するトラブルその❹―退職時の給与支払い
台湾の労働部は、台湾の中小企業にある賃金全額払いの原則に反する行いとして、従業員によく相談を受けているNO.4は、退職月の給与支払い問題です。
労使間のトラブルにつながる事例として、会社は、退職時の引継ぎが不完全であったり、退職月の実働日数が少なかったり等の理由をもって、従業員の給与を一部減額したり、約束した日時に支払いを行わなかったり、或いは嫌がらせっぽく、最終回の給与のみ現金払いにし、雇用関係が終了したにもかかわらず、あえて従業員に出社させて受領させたりする場合です。
給与額が労働契約に記載すべき事項であると言及したが、それとは別に、給与が毎月支払われるタイミングも記載必須事項とされています。
従って、たとえそれが最終回の給与支払いであったとしても、会社は従業員と締結した労働契約に定めた日時通りに支払いを行わなければ、賃金全額払いの原則に反するのみならず、労働契約の違約責任も同時に負わなければならない形となってしまいます。
よく聞く話しとして、会社に退職願を提出した従業員は、担当の仕事をほったらかすだけでなく、後任者への引継ぎもろくにしないことがあります。そんな無責任な退職者に、少なくとも最低限な引き継ぎをきちんとしてもらわなくてはと、せめて最終回の給与支払いをけん制手段として活用したい、との事業主の気持ちは重々理解していますが、行政に入られたら、ペナルティの基本料金が2万新台湾ドルなので、背に腹は代えられない、その辺は時間通りに給与支払いを行いましょう。
退職者が引継ぎを怠ることで、明かに会社に損失をもたらした場合には、別途民事訴訟を起こして、当該退職者に損害賠償請求を行う、という比較的ややこしい法的手段も必要に応じて検討できましょう。

給与支払いに関するトラブルその❺―寄付金の給与天引き
賃金全額払いの原則に反するNO.5の事例は、一般事業者はあまり馴染まず、台湾の社会福祉施設等の団体にたまに起きる「寄付金の給与天引き制度」です。
一部の社会福祉施設は、社会貢献という大義名分をもって、従業員に精神的なプレッシャーをかけたりして、給与から数千新台湾ドル程度の額を月次ベースで寄付してもらい、支払い給与からそれを毎月天引きすることで、従業員がそれによって生活苦に陥ってしまう問題が、近年においてよくマスメディアに取り上げられています。
もし従業員は経済的に余裕があって、その分社会に還元しようと、労使間で寄付金に関する取り決めも確実に結ばれていたら、法律的には全く問題ありませんが、従業員が入社早々、右も左も分からない段階で、事業主が寄付金の件を持ちだして、半ば強制的に了承を取得しようと働きかけたりすれば、賃金全額払いの原則に反する行為として、行政からペナルティを受けてしまいうリスクがあります。
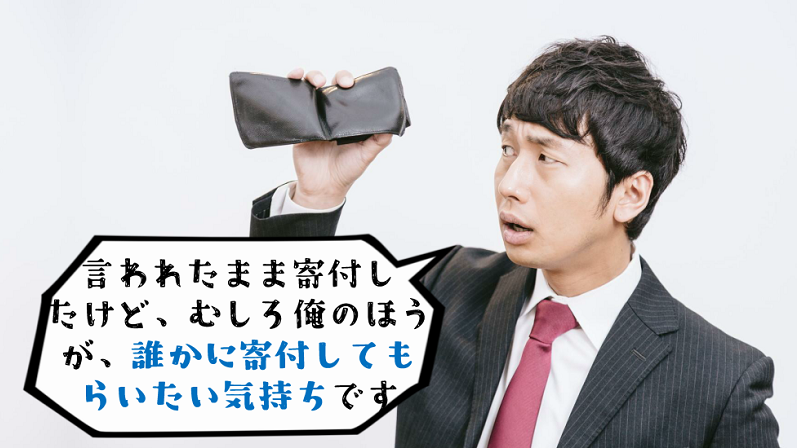
終わりに
賃金全額払いの原則に反する罰則として、2万~100万新台湾ドルの過料と社名公表がなされます。
電話一本又は労働部のHPにワンクリックしたら、すぐ労基法違反した事業主を告発できる時代なので、日ごろの労務管理、特に従業員への給与支払いに関して、アンテナを張って、よく従業員の声に耳を傾けながら、必要に応じて専門家にセカンドオピニオンを出してもらったりすることで対応していくことが望ましいと思われます。