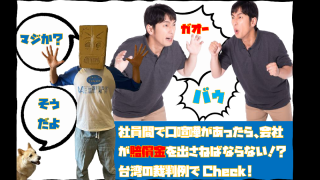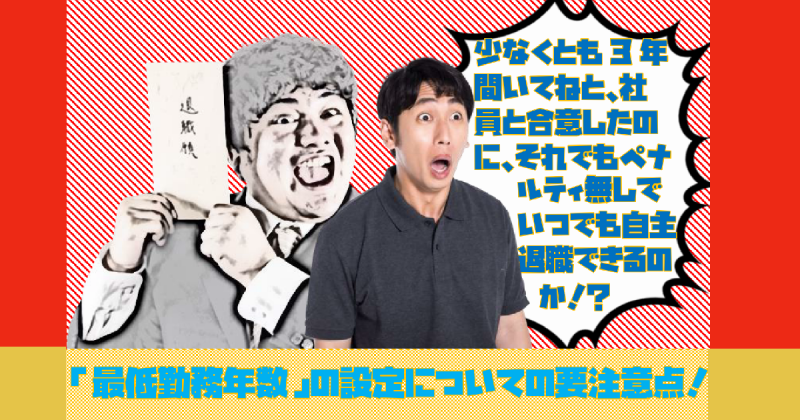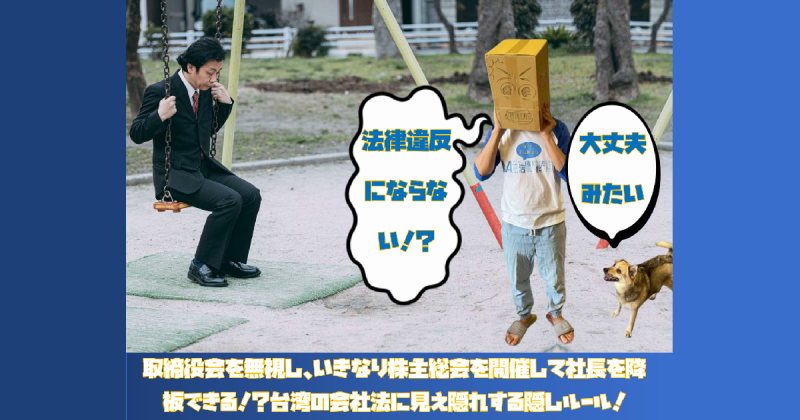社員間で口喧嘩があったら、会社が賠償金を出さねばならない!?台湾の裁判例でCheck!
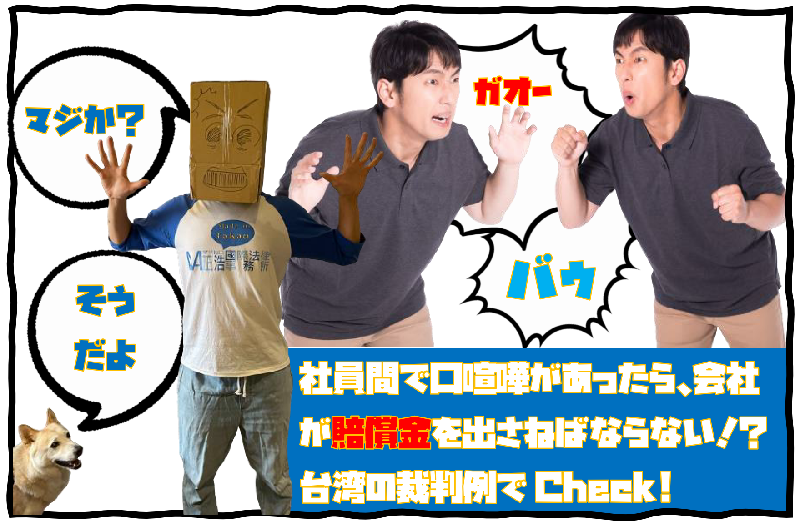
社内の機械装置に訳の分からない不具合が発生し、それによって、製造現場に居た社員が怪我を負ってしまいました。同社員は任された仕事をこなすために怪我を受けたわけなので、このような労災事件は、会社が責任を持たなければなりません。
また、社員その他第三者が社用車で交通事故を起こし、他人に怪我させた場合にも、会社は、事前に相当な予防措置を講じない限り、交通事項を起こした社員その他第三者と連帯して、被害者に対する損害賠償の義務を負うことを、以前のマサレポで紹介させていただきました。
上記2つのパターンは、会社とはそれなりの因果関係が認められるので、会社側に損害賠償の責任が発生することを想像し難くないかもしれません。では、社内で社員同士の口喧嘩が起こり、その後誹謗中傷又は侮辱行為があったことで訴訟沙汰に発展してしまったら、会社もそれに関する損害賠償の責任を追及されるものなんでしょうか。
口喧嘩の当事者が社員で、事件の現場は会社、いざこざが起きたのは勤務時間内、かつ喧嘩の火種も仕事の内容にかかわっている、という会社にとって、いかにもTPO的に言い逃れが難しい状態においては、「社員個人間の問題」とだけ主張したら、すんなり通るとも考えにくいものです。
台湾の裁判の現場においては、こういったケースは果たしてどのように見られているのかについて、最近の裁判例を取り上げて、考察を進めていきたいと思います。
最初は原告目線でCheck!
私、L氏は、半年ぐらいマーケティング顧問として台湾にある香港系企業のK社に勤めていました。パフォーマンスと業績がよい、業界でのキャリアが長い、かつ給与もその他従業員より高いため、それを面白く思わない同僚からは頻繁に嫌がらせをされていましたが、波風が立ったらK社によからぬ影響が生じかねないと思い、ずっとやせ我慢をしていました。
ある日、私は同僚のJ氏から、「卑しいボケ」、「お前なんざ尊重に値しない」、「お前勉強してる?」、「KYでしつけが足りない」等で貶され、私のことを殴りかかろうとされており、ひどいパワハラを受けました。
私は自分の権利を守ろうと、前述のパワハラ被害をK社に伝えたら、翌日会議に呼ばれ、人事マネージャーをはじめとする人事部門の面々が揃うなかで、「貴方は同僚とうまくやっていないから、職場の秩序を維持するために、貴方を解雇せざるを得ない状況なんだが、解雇された経歴があったら、これからの就職活動に何かしらの支障を来す可能性が大きいから、自主退職をしろ!」と恐喝されました。
K社から前述の屈辱を強いられた私は、緊張と恐怖で震えが止まらない状態で、否応なしにK社が予め用意した退職証明書にサインさせられた後、即日退職を告げられました。それがきっかけで、私はPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症してしまいました。
元同僚のJ氏は、仕事の関係上という大義名分を利用し、私に対する名誉毀損を行ったりする等のパワハラ行為を働いており、それによって、私がK社から退職を強要され、そしてPTSDを患うことになったため、J氏に、損害賠償金として私に約110万NTDを支払うとともに、台湾の大手新聞紙で私へのお詫び記事を掲載することを要求します。
他方のK社は、職業安全衛生施設規則第324条の3の定めに従い、従業員の身体と精神の健康を守るための措置と計画を一切用意していないため、私がパワハラの被害を受け、PTSDを発症してしまいました。だからK社もJ氏と同罪で、J氏と連帯して私に対する110万NTDの賠償金支払義務を果たさなければなりません。
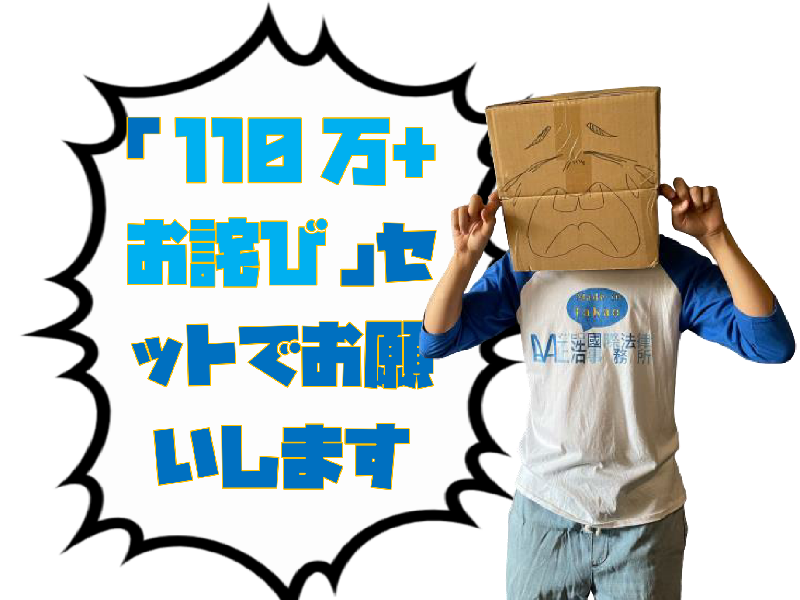
次はJ氏目線でCheck!
L氏は自分が受けた、いわゆる「パワハラ」をもって、検察署に僕を訴えました。結果、L氏が主張した公然侮辱罪や恐喝罪、加重誹謗罪はいずれも成立しておらず、最終的に不起訴処分が下りました。
L氏は、僕が彼女に殴りかかろうと主張したが、社内カメラの映像では、私はただ単にL氏を指さして議論しており、互いも一定の距離を保っていたから、僕はL氏を殴る意図はみじんもありません。
僕もL氏もK社での担当がマーケティング顧問でして、役職が一緒のため上下関係がありませんでした。だからL氏が主張した、「立場が高い人からパワハラを受けた」説は成立しません。なお、K社においては、個人の給与情報は秘密保持の一環とされているため、L氏の基本給情報を把握し、それを理由にパワハラを働いたことはあり得ません。
L氏から提出された病院の領収書で、一部はPTSDの疑似症状で通院したことの証明にはなり得るが、ほとんどの領収書はL氏の主張とはどういった関係性があるかが見えず、損害賠償金である110万NTDのうち、100万NTDが慰謝料である、との要求も怪しくて、何をもってそんな金額を算出したのかを証明可能な資料が未見です。
ついでにK社目線もCheck!
当社社員のJ氏と元社員のL氏との間で起きた口論は、互いに不快な気持ちを与えこそすれ、社会通念上常軌を逸した評価がなされたわけではなく、L氏に対する名誉毀損には至っていません。百歩を譲って、J氏がL氏への行為がパワハラに当たると仮定しても、J氏は職務を果たすために、もしくは職場での地位を利用して、L氏にこういった行為を働いたわけでもないから、当社は連帯責任を負う必要がありません。
当社は就業規則において内部通報制度を導入しており、パワハラその他悩みを抱える社員は何時でも利用可能となっています。当社は当初、L氏からJ氏とのトラブルに関する相談を受けた後、両氏に対し個別で面談を行い、事実関係についての情報収集を可及的速やかに実施しました。ですから、当社は本件に関してはタイミングよく適切な処置を行ったため、民法第188条第1項の但し書きに基づき、J氏と連帯してL氏に対する損害賠償の責任を負わなくてよいと主張します。
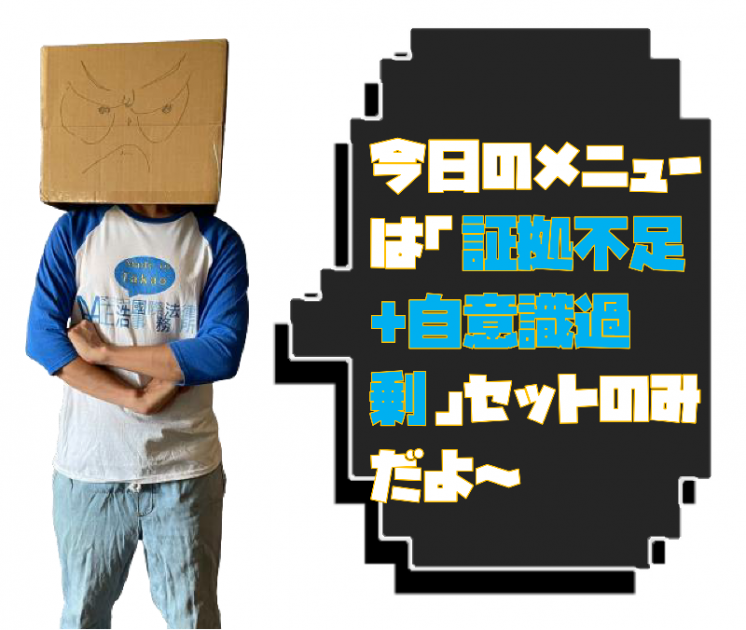
裁判官目線でCheck!
J氏はL氏との口論においては、個人の主観的評価に関する発言はあったものの、他人を侮辱する言葉を使ったとは認めない。たとえJ氏がでかい声でL氏の気持ちを害する発言をし、L氏にとって快く受け入れられない動作を行ったが、それらがL氏の名誉又は健康にどういった害を及ぼしたかがはっきりしない。そのため、L氏がJ氏からパワハラに該当する行為を受けたとは認めがたいし、パワハラが存在しないためK社の連帯責任も成立しない。
L氏は以前、自分がセクハラの被害者であったにもかかわらず、K社はそれを正しく対応していなかったことで、地方の労工局に通報したことがあった。同局が行った調査で、K社は、L氏が入社する前に、既に自社の就業規則にセクハラの防止に関する条項を追加し、事業所での掲示、周知を行っており、L氏から被害相談を受け、直ちに適切な対応も取っていたから、性別就業平等法等の法律に違反していない、との結論が下された。L氏はそれに不服申し立てを行ったが、結論は覆らなかった。ましてや、L氏が今回の訴訟で主張したパワハラによる被害では、ほとんどは証拠力が低い一方的な主張であり、事実上パワハラに該当するかは極めて疑わしい。
以上の説明によって、L氏の主張は理由がないものとして、その損害賠償請求を認めない。(111年度労訴字第59号)
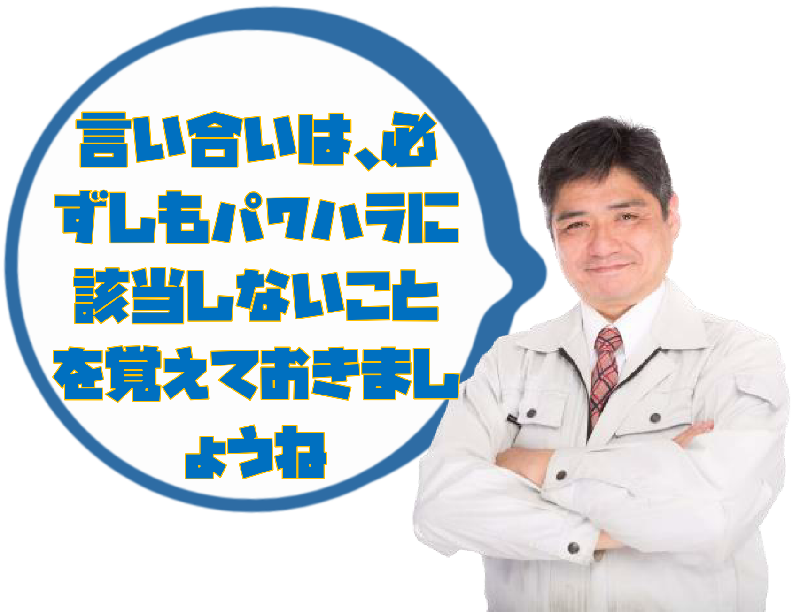
今週の学びをCheck!
今回の事例においては、原告である元社員の主張が裁判官に受け入れてもらえず、被告である会社と元同僚に軍配が上がりました。ここで留意が必要なのは、本件はたまたまパワハラ被害が成立せず、会社は連帯して損害賠償金を払わずに済むだけであって、もし社員間でパワハラ又はセクハラと思わしき事件が起きたら、時と場合によっては、直接関わっていない会社も責任を追及される可能性がある点です。
以下、台湾の民法第188条第1項前半の内容を見てみましょう。
使用人は、職務を遂行する関係で、他人の権利を不当に侵害したときは、使用者は使用人と連帯して当該他人に対する損害賠償責任を負う。
もしJ氏がL氏にかけた言葉は、L氏が裁判で主張したパワハラに該当し、かつそのきっかけが両氏の仕事と何らかの因果関係があったと認められれば、K社にJ氏に対する損害賠償の義務が発生してまいります。
既存の裁判例に照らし合わせたら、前述の件はどちらかと言えば、情状が比較的軽微なケースになります。その他事例、例えば顧客の自宅へ電器の修理に行った社員が強盗や窃盗を働いたり、社員同士が工場内でハンマーで殴り合ったり、社員が顧客の個人情報又は写真をネット掲示板に投稿し笑いものにしたり、社用車で外出する途中、通行人に大けがを負わせたりするなどのケースも数多く実在しており、こういった事例は、いきなり数百万ないし千万NTD規模の損害賠償金の支払いを、会社側に連帯責任を追及されてしまっています。
一方、法律的には会社が取りうる救済措置も一応用意されています。
使用者は、使用人の選定、及び使用人の職務遂行に対する監督へは既に相当な注意を払い、若しくは相当な注意を払っても回避しようがない損害が起こったときは、損害賠償責任を負わない。
(民法第188条第1項後半)
つまり、会社は、社員のパフォーマンスを一定期間モニターし、得手不得手を見極めてから適時適切な配転を行いながら、日々の社員教育を怠らず、かつそれらを書面による記録をこまめに取っているようであれば、社員の行いで他人から損害賠償請求をされたとしても、会社は免責の主張ができる、ということです。
この辺で終了したら会社も一安心できますが、残念ながら、同法はまだ続きがあります。
被害者は前項の但し書き(会社が取りうる救済措置)によって損害賠償の請求ができなかったときは、裁判所は、被害者が行う申し立てに基づき、使用者と被害者の経済的事情を考慮し、被害者に対する損害賠償義務の全部又は一部を果たすよう、使用者に命じることができる。
(民法第188条第2項)
もし法律を違反した社員は、稼いだ分だけ散財するタイプのような人で、かつ被害者もそれほど裕福なほうではなかったら、たとえ社員教育をしっかり行っている会社であっても、社員とともに賠償責任を負わされる運命からは逃れられない可能性があります。
そして、同法第3項において、会社は、連帯責任により被害者に賠償した分を、違法行為のあった社員に請求できるとも定められているので、同社員に引き続き働いてもらいながら、会社に賠償金の返済を要求したりする対策も考えられるが、同社員が10~20年の有期懲役又は無期懲役に処せられた場合には、こういった社員に対する請求可能な賠償金を貸し倒れとして処理せざるを得なくなりましょう。
マサレポ、今週の学び
- 社内の就業規則その他規程に、各種ハラスメントに関する防止措置を早期に導入し、定期的にマサヒロのようなところに頼んで、法律に関する社員の講習会を開催することで、社員が起こしたトラブルによって発生する会社の損害賠償責任の可能性を最小限に抑えておくことが推奨されます。