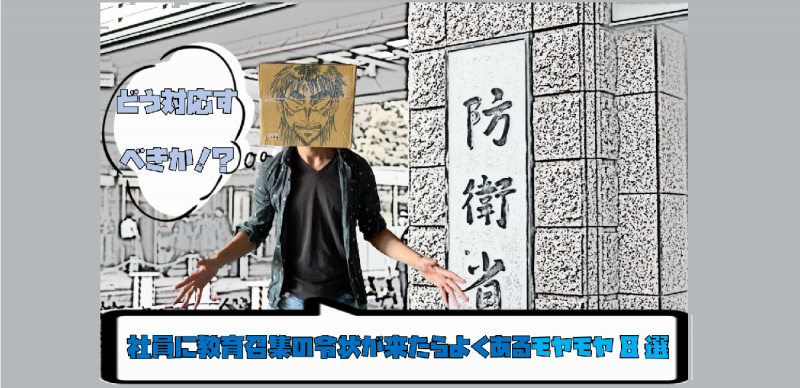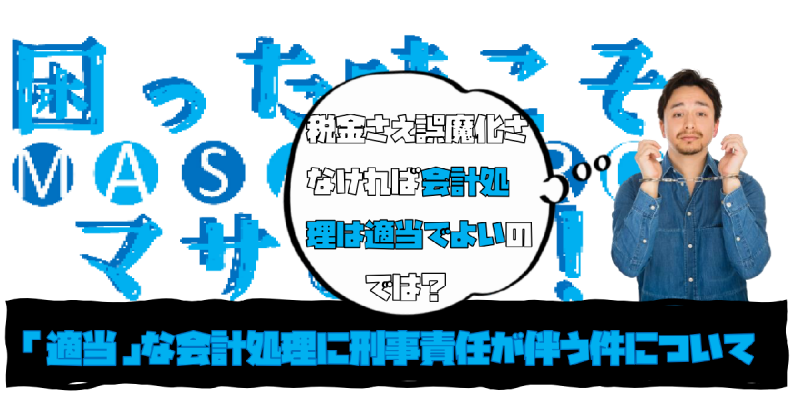解雇事由のファミリア・ストレンジャー⁉能力不足を理由とする解雇に関するトラブル事例
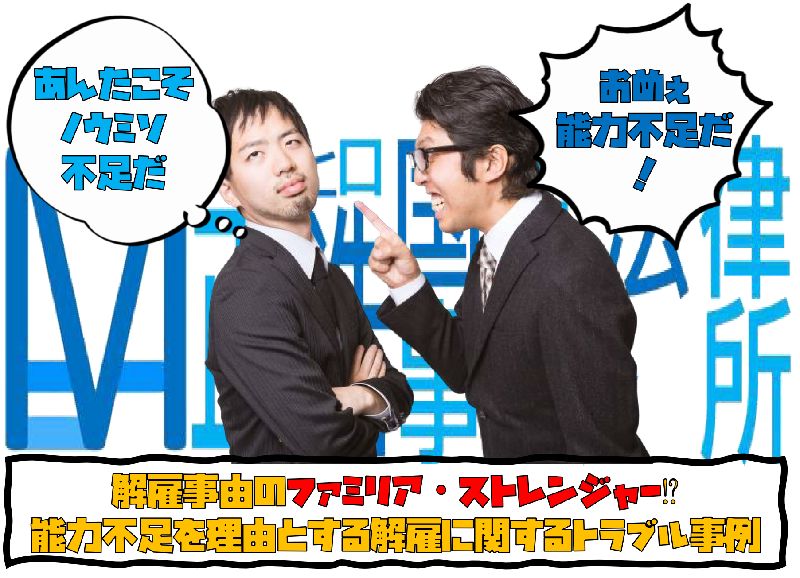
解雇は台湾において、大きく懲戒解雇と予告解雇に分けることができます。従業員に明らかに看過できない問題がある場合なら前者、会社側に不可抗力的な要素が生じたら後者、という分かりやすい構図で、解雇の実施がなされているようです。
会社から解雇手当の支払いが受けられない、政府からも失業補助金が出ない懲戒解雇と比べたら、会社都合による予告解雇は、対象となる従業員は退職後しばらくの間では最低生活保障的な給付を受けられるので、トラブルにつながる事例は少ないはず、と考えられており、実際もその通りです。
にもかかわらず、台湾の労基法に定められた予告解雇の要件のうち、利用される頻度がNO.1だが、法律条項の書き方がなんだかはっきりしない、「労働者は確かに担当業務をこなせない」という事由は、実務の世界において結構トラブル事例が発生しています。解雇の理由としては、ハードルを低く感じるのに、なぜ?と思われるかもしれませんが、そう考えることに別におかしくはありません。何故なら、裁判官でさえ、その取扱いについて見解が分かれるケースが多いですから。
今週のマサレポは、一つの事件に対して、地裁から最高裁まで異なる心証が示された裁判例を紹介させていただくことで、「労働者は確かに担当業務をこなせない」、という労務上のファミリア・ストレンジャーについて理解を深めていけたらと思います。
能力不足?それともやる気がない?
W氏は2017年に、香港系人材派遣会社のC社に一般事務アシスタントとして雇用され、派遣先であるネットワーク機器販売大手のS社でオフィス環境整備業務及び郵便物仕分け発送業務の担当を命じられました。
2019年11月、S社からクレームが届いたから、事実関係についての調査結果が分かるまでしばらく自宅で待機しろ、とC社に言われたW氏は、数日間家で大人しく待っていたら、調査会議への出席要請を受けたため、それに応じました。しかし、会議の進行を録画又は録音で記録を取りたいというW氏の申し出があり、それが社内ポリシーに反するとC社が判断したため、同会議が中止となって、それ以降も進捗なしでした。
C社は同年12月13日に、求人サイトでその他興味のある派遣先を31日までに探し出して申請してください、そうでなければ解雇する、との旨を記載したEメールをW氏に送信したが、30日になってもW氏からの申請がなかったため、C社は解雇合意書の締結を要求し、W氏はそれを断りました。
翌日の12月31日、C社はEメールで、「担当業務をこなせない」を理由に、W氏を解雇する旨を同氏に通知しました。

C社から一方的に解雇を言い渡されたことを不満に思うW氏は、裁判所にこう直訴しました。
- 私が今になっても、派遣先のクレーム内容が何なのか分からず、私がどういう風にルール違反したかの証拠をC社からも提出されていないから、「担当業務をこなせない」を理由に自分を解雇したことに正当性がなく、解雇が不成立です。
- 派遣先から、勤務時間中に特定の女性社員に仕事以外の話しを頻繁に持ちかけたりして、同女性社員を困らせ、パフォーマンスに支障を来した、とのクレームを受けたことが「担当業務をこなせない」の理由だと、C社がいまさらながら主張してきたが、派遣先はセクハラ防止法に基づき本件について調査を行っていない、C社も事実関係の調査を取りやめた理由は何なのか?派遣先のクレームが事実であるかどうかをはっきりさせないのに、私を解雇したのはおかしくありませんか?
- 新しい派遣先を見つけろと言われても、賃金条件は今まで通りとの保障は一切してくれなかったから、こんな一方的に社員の労働条件を不利にする行為は既に法律違反です。
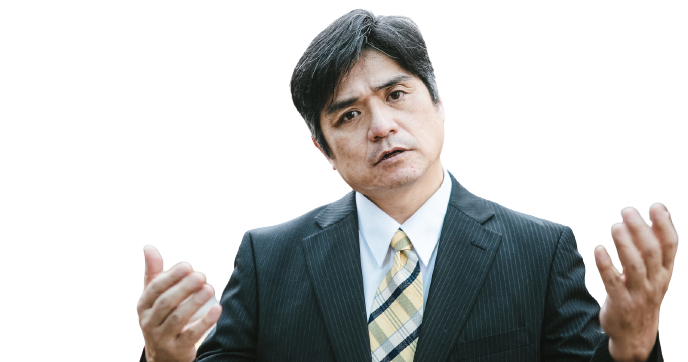
C社もそれに負けじと、以下のように反論しました。
- 当社と派遣先のS社との契約では、S社が理由さえ伝えれば、何時でも当社からの派遣社員を交代できると定められています。なお、派遣社員が何かしら報復活動を行ったら面倒なので、W氏にクレームの内容を伝えることなく、なるはやで交代してほしい、とS社からの要望を聞いて、当社はW氏にマイクロソフト社の郵便物仕分け発送業務を協力してもらおうと打診したが、同氏に断られました。
- W氏がS社の某社員へのハラスメントがエスカレートしていたようで、同社はEメールで、W氏をすかさず担当から外し、そして3日後同氏は立ち入り禁止にする、との告知を行いました。当社はS社との契約を遵守し、W氏を配転したわけだから、労基法の違反にはなりません。
- 当社は12月中旬前後で2回ぐらいW氏にその他派遣先の情報を提供し、W氏の配転を積極的にサポートしてあげたが、同氏はこれといった理由を提出しないままその他派遣先を拒み続けました。ですから、W氏には「できるのにあえてしない」、「やってもよいのにその気にならない」、という「担当業務をこなせない」の成立に要求される主観的要素を有しています。
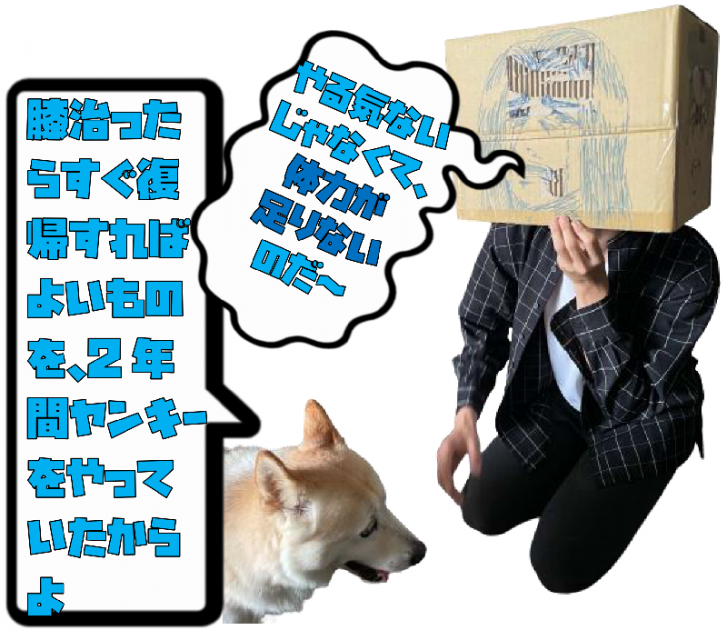
第1ラウンド:やはりやる気ないんだ

第1ラウンドの審判を務める地裁の見解は以下です。
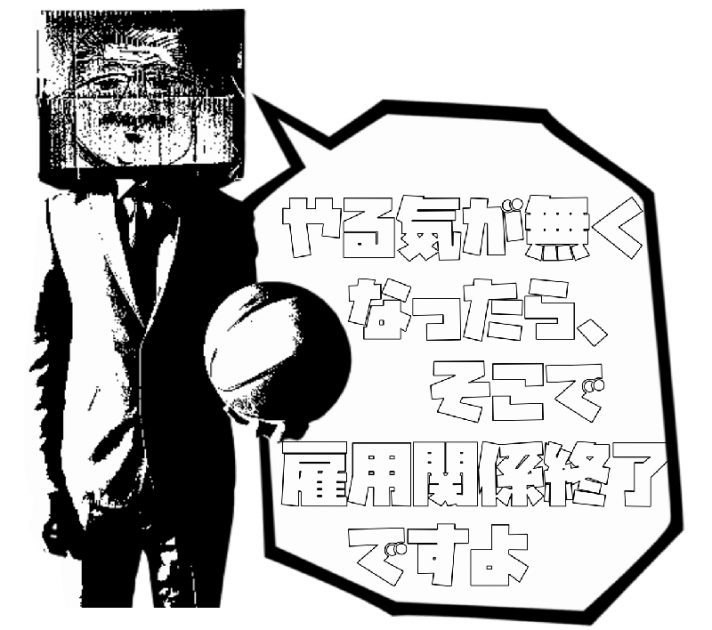
第2ラウンド:次の仕事を指定しないほうが悪い!
仕事的にはやる気がないかもしれませんが、訴訟を続ける気満々なW氏は高裁でゲームを再開しました。

高裁からのフィードバックはこうです。
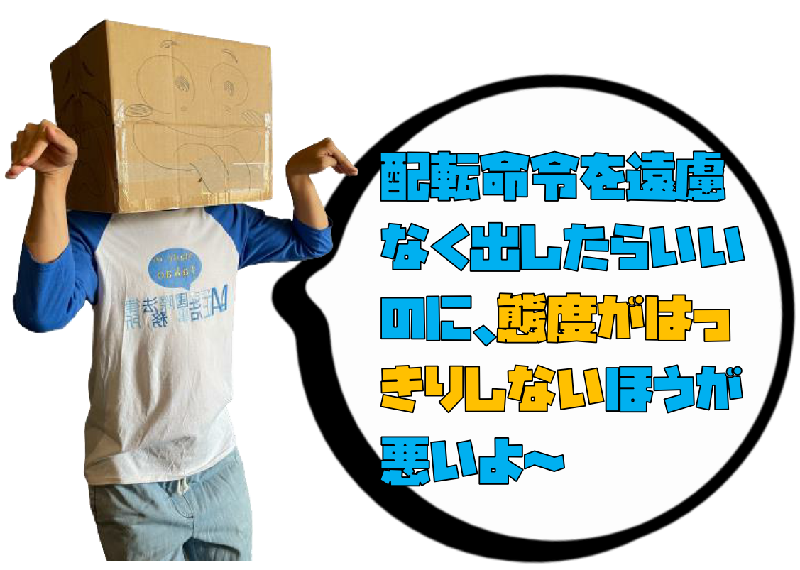
第3ラウンド:会社が果たした努力義務と従業員の対応を天平にかけて
さすがW氏、ダブルV(ビクトリー)は伊達じゃないじゃなさそうだ、と感心しつつ、上告する道をC社は選びました。

最高裁の答えはこうです。
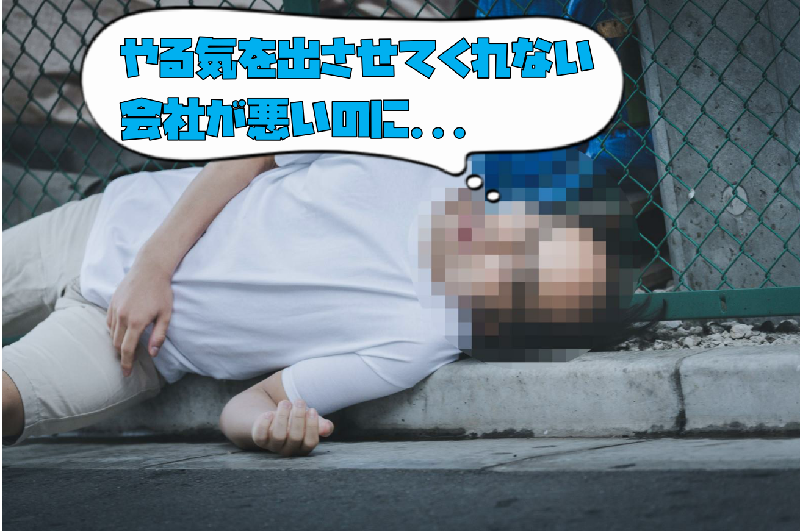
今週の学び
台湾の労基法に定めた予告解雇の要件としてよく利用されるのは、「労働者は確かに担当業務をこなせない」という理由です。
Aさんは担当の仕事をよくミスしており、何回か手本を見せて改善を要求していたものの、一向に進歩しておらず、「確かに担当業務をこなせない」から、仕方なく解雇を言い渡した、といったケースは実務的に多く存在しています。言葉通りに解釈すれば、「社員が会社に任された仕事をうまくやっていない」場合、会社側に解雇権が発生する、という風な内容として一般に認知されているかもしれません。しかしながら、労働者保護の観点で、法的に有効な解雇を実施するためには、前述ストレートな方程式だけでは物足りず、従業員が初犯か累犯、故意にミスしたのかそれとも過失によるものか、会社にもたらす損失、労使関係、在籍年数などの要因を総合的に評価のうえ、解雇の妥当性を考える必要がある(109年度労訴字第133号)という司法見解が持たれているため、法律的に完全ノーリスクな「確かに担当業務をこなせない」を理由とする解雇はありえないかもしれません。「確かに担当業務をこなせない」というコンセプトの取り扱いについては、常に「要チェックや!」の意識を持つことが大事かと思います。
一方、今回裁判にかけられた「確かに担当業務をこなせない」は、対象従業員に担当業務の遂行能力に問題があるでもなく、重大なミスを犯したわけでもありません。争点となっているのは、「従業員にその気さえあればうまくできるかもしれないのに、やろうとしない」問題です。ある意味、一生懸命努力してもやはり「能力不足」の従業員より扱いにくいと考えられなくもありません。何故なら、裁判官の間でも真逆な見解が示されていたぐらいですからね。