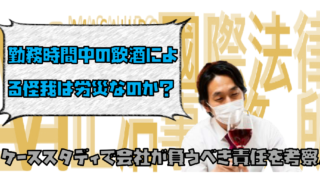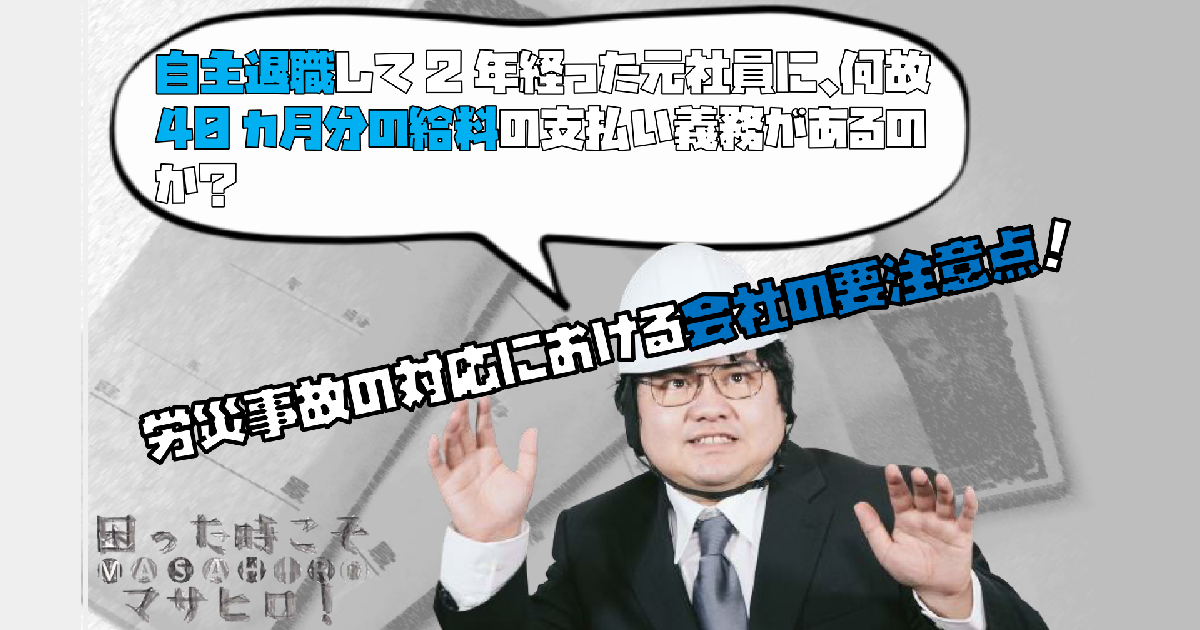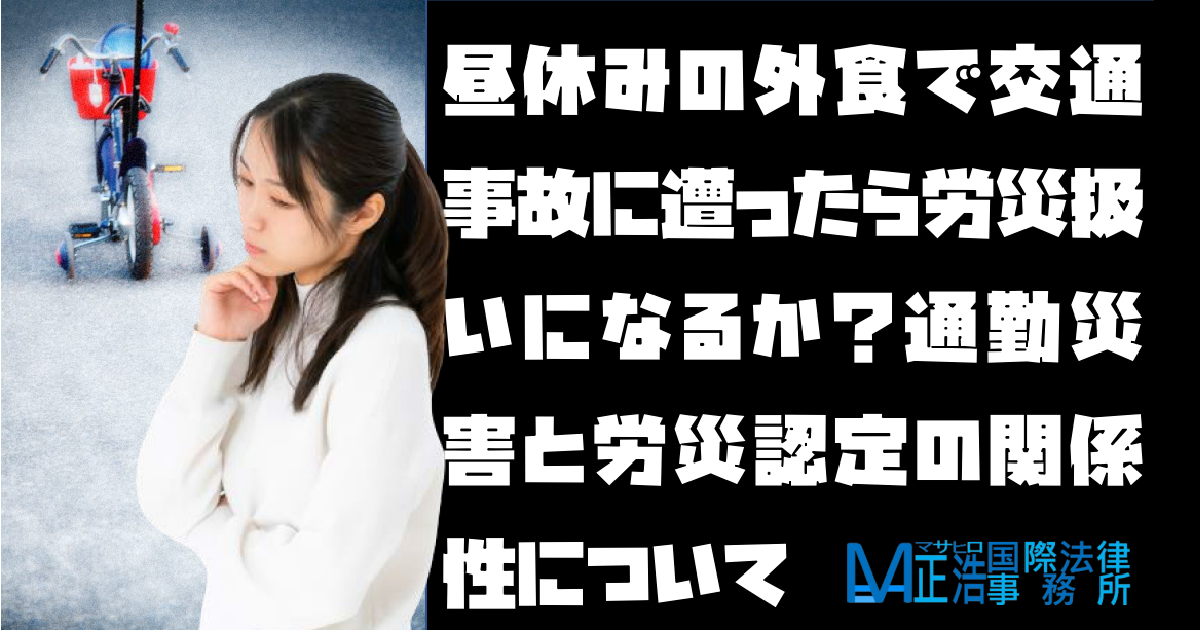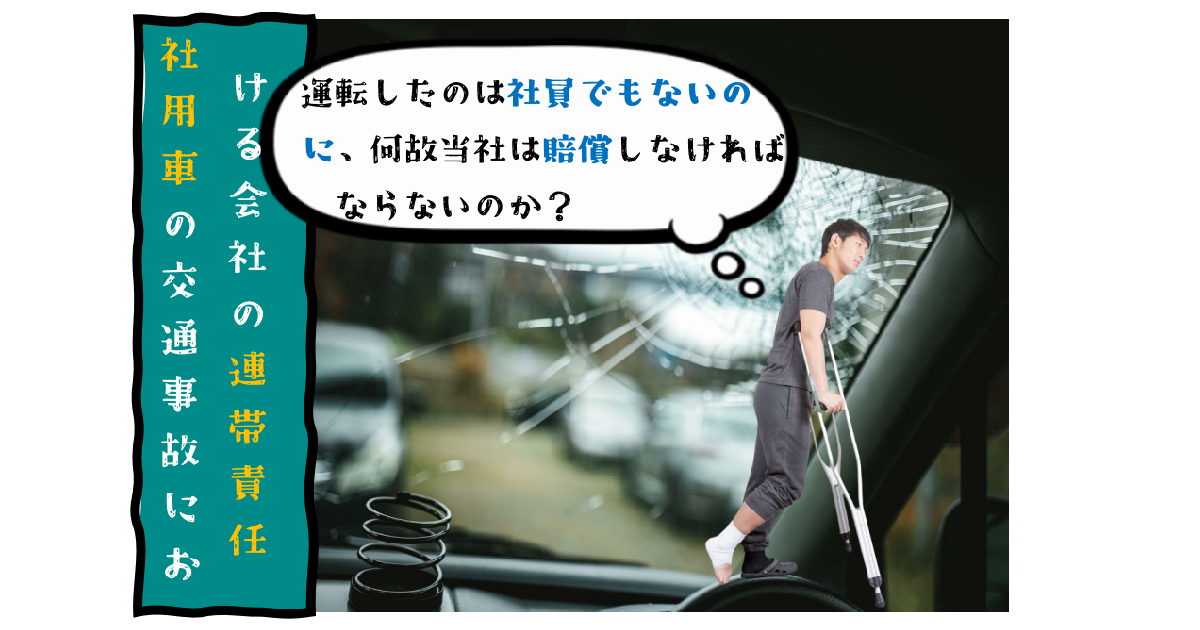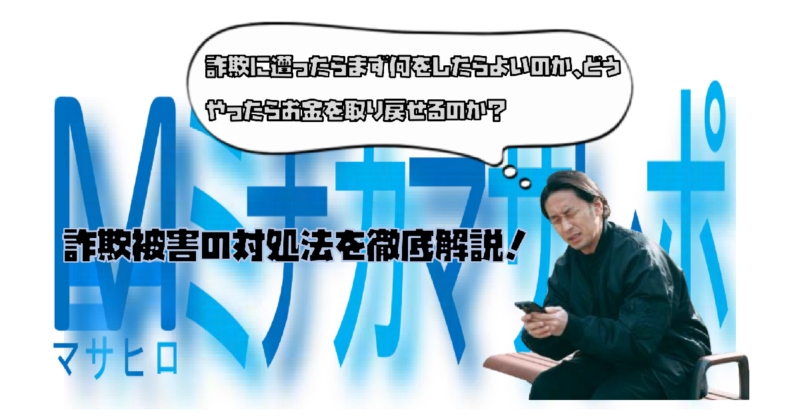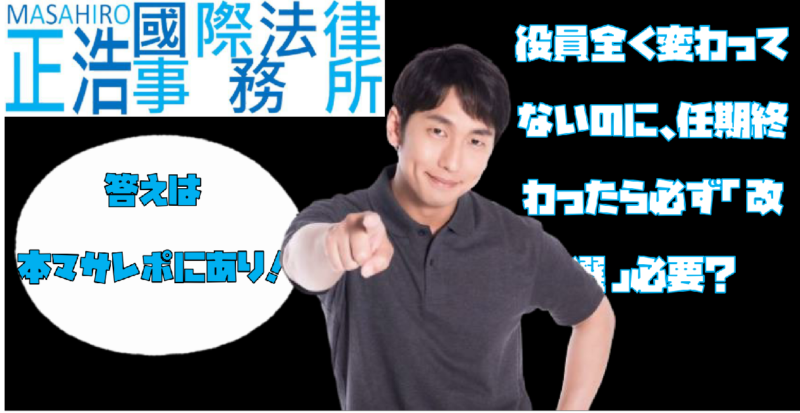【勤務時間中の飲酒による怪我は労災なのか?】―ケーススタディで会社が負うべき責任を考察!
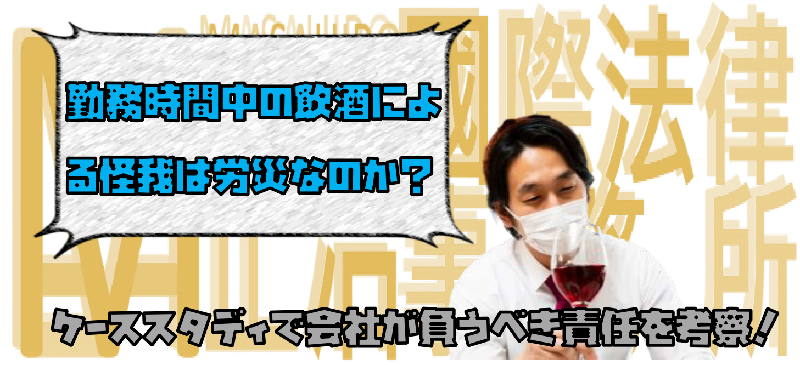
仕事中に酒を飲むことは法律に違反するわけではありません。しかし、一部極レアなケースを除き、アルコールを摂取すると大体業務遂行能力が低下するので、労働者が守るべき職務専念義務や誠実労働義務を考え、「勤務時間中の飲酒」は、一般的に会社のルールによって禁じられています。
一方、会社では禁じられているものの、職場で隠れ酒をして、それが原因で勤務時間中に怪我などをした労働者がいた場合、当該労働者は会社に対し労災補償を求める権利が生じるのか、そのような権利があったとしても、会社は100%の責任を負うべきなのか、といった質問に対して、台湾の裁判例でケーススタディを通して考察を進めながら、役立つ要注意点を洗い出してみたいと思います。
考察例その①
A氏は、防護・安全装置が用意されず、安全衛生教育も施されないまま会社から装置の操作を命じられたせいで、ひどい怪我を負ったため、会社に労災請求を求めたが、会社側ではA氏が事故当日に飲酒した事実があり、自ら負った怪我にある程度責任を負わなければならないため、会社に補償責任はないと主張。
裁判で以下の事実が明らかとなりました。
高裁109年度労上字第200号判決
- 会社はA氏に対象装置の操作を命じる前に、安全衛生責任者を現場に置いていなければ、妥当な安全衛生教育も施していなかった。
- 会社は安全基準に従い、対象装置に対する適切な防護・安全装置をつけていなかった。
- 会社はA氏に飲酒の事実があったと主張したが、それを証明できる証拠を有しておらず、A氏を受け入れた病院にも飲酒に関する記録がなかった。
結果:A氏が負った怪我が労災に該当し、会社は労災責任を負わなければなりません。
考察例その②
B氏は会社の命を受け、墜落制止用器具が用意されず、現場責任者も不在の状態で足場の解体作業を実施している間に、建物の3階から墜落しひどい怪我を負ったため、会社に労災請求を求めたが、会社側ではB氏は事故前に飲酒したことを理由に、3割の賠償金しか出せないと主張。
裁判所の判断はこうです。
高裁109年度重労上更一字第18号判決
- 事故現場で墜落制止用器具が用意されていなかったことは、目撃者の証言でわかった。
- B氏は飲酒により注意力を低下させた過失があったものの、会社はしっかりした保護具を用意しておけば事故は起こらなかった。
- 作業現場で労働者を監督する責任を果たしていなかった現場責任者も会社と連帯賠償責任を負うべし。
- 受け入れ病院の検査報告では、事故当日のB氏にアルコールが検出されたため、1/3の損害賠償責任を負うことが妥当。残り2/3の損害賠償責任は、墜落制止用器具を用意していなかった会社が負わなければならない。
結果:B氏は損害賠償金の2/3を会社に請求できます。
考察例その③
工事現場にガードフェンスや安全帯などが設けられていなかったため、高所で作業をしていたF氏が墜落し、下半身麻痺を宣告された。F氏から労災請求を求められた会社は、F氏は以前から勤務時間中にお酒を飲む癖があって、何回注意しても是正せず、今回の墜落事故も同氏の飲酒によるものなので、だから賠償義務はないと主張。
裁判所の判断はこうです。
高裁台中支局105年度重労上字第2号判決
会社には墜落防止装置を用意していなかった過失があるが、病院で行ったアルコールチェックで飲酒した事実が確認されたE氏にもそれなりの責任がある。
結果:痛み分けという形で、会社とE氏はそれぞれ50%の賠償責任を負担します。
考察例その④
H氏は勤務時間中に、うつ伏せの状態で作業現場で倒れているのが見つかり、一切救急措置も施されず、数時間経過してからようやくタクシーで病院に搬送されたせいで、数か月後に病院で死亡しました。H氏の親族は会社に労災の責任を追及したが、会社側ではH氏の死亡はアルコール中毒によるもので、賠償を拒みました。
裁判所の判断はこうです。
高裁高雄支局106年度労上字第13号判決
- H氏は事故前、会社から過重労働を要求されたことはなかったため、職業病による死亡の可能性は排除できる。
- 証人の話では、H氏が泥酔状態で倒れたのを発見したとき、体からお酒の匂いがプンプンしているし、近くにビールの缶と同氏の吐瀉物もあって、何回声をかけても返事しなかったから、寝かせておいたが、退勤時間になっても起きようとしなかったため、タクシーで病院まで搬送したという。大の酒好きなH氏のことだから、医療専門家でもないその他従業員は、その場でH氏の異様に気付き、適切な救急措置を施すうえ、救急車を直ちに要請する、といった判断を出すことはどう考えてもあり得ない。
結果:H氏の死亡は労災に該当せず、事故当日の対応に過失のない会社にも責任がありません。
考察例その⑤
K氏は作業現場で指が機器に挟まれ怪我をしました。会社がしかるべき安全装置を付けておらず、妥当な教育訓練もしてくれなかったことによる労災事故と主張するK氏は、会社に対して労災請求を求めたところ、K氏の怪我は、勤務時間中の飲酒による注意力低下が主な原因であり、賠償義務はないと会社が主張。
裁判所の判断はこうです。
高裁台中支局106年度労上易字第6号判決
- K氏が会社に求めたのは損害賠償ではなく、労災補償であるため、たとえ本件事故の要因が「飲酒による注意力低下」であり、K氏にも過失が認められたからといって、K氏の過失を根拠に、会社が負担すべき労災に対する補償責任をチャラにすることはできない(会社が無過失責任を負担すべき)。
- にもかかわらず、K氏は15~16年の作業経験を理由に、会社が行った安全講習を8回もさぼっていた。K氏自身も労災に対して責任を負わなければならない。
- K氏が操作した機器は自動式ではなく、マニュアルで動かす仕組みとなっているため、会社は別に安全装置を付ける必要はない。
結果:無過失責任を負う会社は、K氏に対する労災補償の義務はあったが、損害賠償の義務を負わずに済みます。

考察例その⑥
退勤後の帰宅途中で交通事故に遭ったE氏は、会社に労災請求を求めたが、当該交通事故はE氏の飲酒運転によるものなので、労災に該当しないと会社が反論。
裁判で以下事実が明らかとなりました。
高裁90年度労上字第22号判決
- 病院がカルテに記載した「飲酒運転によるバイク転倒事故」という内容は、E氏の付添人の話しをそのまま記録として取ったものであり、アルコールチェックを行った結果ではない。
- 事故現場の目撃者(会社の従業員ではないその他第三者)の証言によると、当日のE氏には酒の匂いが一切しておらず、意識もしっかりしていたという。会社からも、その他飲酒運転に関する証拠が提出されていない。
結果:本件交通事故が労災に該当し、会社は賠償責任を負わなければなりません。
考察例その⑦
車で客先からの帰社途中に交通事故に遭ったG氏は会社に労災請求を求めたが、G氏の仕事は客先を訪問する必要性がなく、事故も自らの飲酒運転によるものであり、労災に該当しないと会社が主張。
裁判所の判断はこうです。
高雄地裁99年度労訴字第4号民事判決
- 事故当日、G氏と行動を共にした上司の話によると、G氏は製品のメンテなどでほぼ毎日外出する必要があるという。従って、本件客先からの帰社途中に起きた交通事故は明らかに業務遂行性がある。
- G氏は、顧客とはより良い関係を築くため、顧客から勧められてお酒を飲んだわけなので、それによって起きた交通事故はやはり労災であると主張したが、G氏は営業職ではなく、かつ同行した上司からも止められたにもかかわらず、自らの判断で飲酒運転を行い事故に遭った。従って、本件交通事故には業務起因性がない。
結果:業務遂行性と業務起因性、ひとつでも欠いたら労災に該当しないため、会社にはG氏に対する労災補償の責任がありません。
「勤務時間中の飲酒」ではないが、労災が起きた後の飲酒行為と会社が負担すべき労災補償との関係性を垣間見る事例もチェックしてみましょう。

考察例その⑧
C氏は手術して約5カ月の休養を経て職場復帰。それから社内で繰り返しパワハラを受け続け、重度のうつ病を患いました。それで労災補償を会社に求めたが、会社側では、うつ病は労働当局が指定した職業病に該当せず、かつCはもともとアルコール依存症を患っていたから、会社には労災補償をしてあげる義務はないと抗弁。
裁判所の判断はこうです。
高裁110年度労上字第153号判決
病院が発行した診断報告では、C氏にはうつ病のほか、重度のアルコール依存症も認められたことが分かった。うつ病の発生はアルコール依存症との因果関係は完全に排除できないし、それのみでパワハラ被害を受けた事実があったとも推測できない。
結果:うつ病はC氏の日常的な飲酒習慣との因果関係が不明であり、パワハラを受けた事実を証明できる証拠もないため、労災認定ならず。
考察例その⑨
会社の責任者は、従業員のD氏が運転するトラックに乗せたショベルカーを操縦しトラックから降りたところ、操作のミスによりトラックの運転席にあるD氏に怪我を負わせました。D氏はそれを根拠に労災請求を責任者に求めたが、D氏には操縦ミスがあったのみならず、怪我した後においても酒を飲み続けて、容態を悪化させた責任があると会社が主張。
裁判所の判断はこうです。
最高裁111年度台上字第1837号判決
- 「D氏に操縦ミスがあった」ことを証明可能な証拠品が未見であるため、第三者が出した報告書に則り、責任者の操縦ミスが事故の主な原因と認定。
- 「D氏が怪我した後においても酒を飲み続ける」ことに関する立証はなされておらず、証拠として提出されたのは、「飲みに行かないか」、という責任者が一方的に誘う会話履歴のみ。
結果:会社の責任者は100%の労災責任を負う必要。
労災こそ起きないが、勤務時間中の飲酒を繰り返す労働者を合法的に解雇できるかの事例も確認しておきましょう。
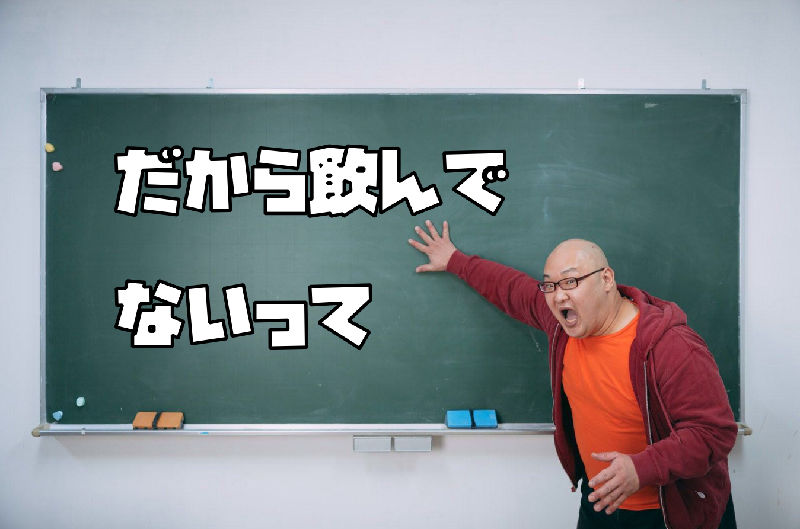
考察例その⑩
営業マネージャーを担当するF氏は、客先との付き合いで勤務時間中に飲酒したことで会社から懲戒解雇され、それが不当解雇に該当し、会社に対して150万NTD超の解雇手当を請求しました。
裁判所の判断はこうです。
高裁99年度労上字第15号民事判決
- F氏は大体週1~2回、勤務時間中に部下2~3人を連れて客先と飲んでいた事実があり、目的が業績の向上とはいえ、管理職として部下を指揮監督する本分を果たしたとは言えない。
- 部下の誕生日祝いで、F氏は月1回ぐらい社内でワインパーティをやっていた。お酒を飲んだのは退勤時間後ではあるが、F氏に任されたのはセキュリティが大事な銀行業務という点から考えると、F氏の行いはやはり不適切である。
結果:F氏を懲戒解雇することは法に反しておらず、解雇手当の請求は認められていませんでした。
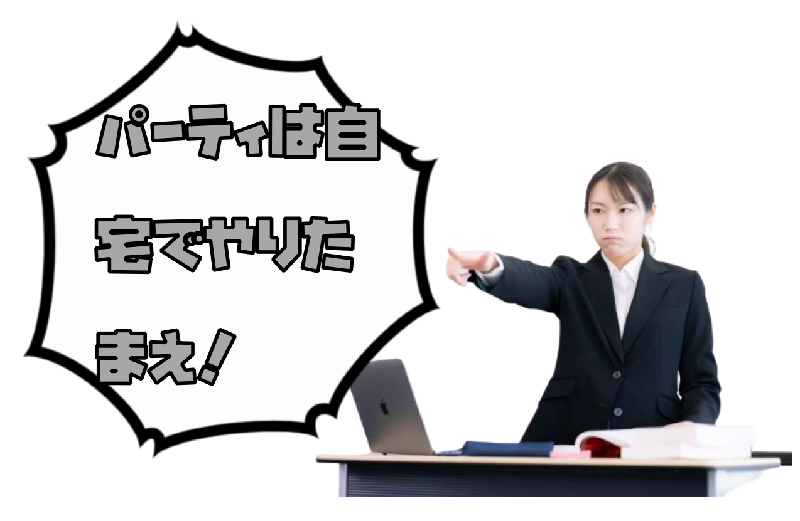
今週の学び
以上、「勤務時間中の飲酒」などに関するトラブル事例を10件ほど考察してきたが、いかがだったでしょうか。集中力が非常に大切な製造業や工事業の現場は勿論だが、会社の管理が行き届かないリモートワーク中の労働者がもし軽くお酒を飲んで、自宅で転んだり、椅子から転び落ちたりして怪我してしまったら、無過失責任を負う会社はそれによって労災補償を行う必要がどうか問題も新たに生じてきます。ですので、あらゆる「勤務時間中の飲酒」に関する場面を想定し、事前に予防策を検討し、確実に導入することがおすすめです。