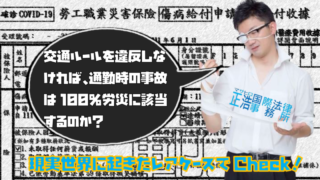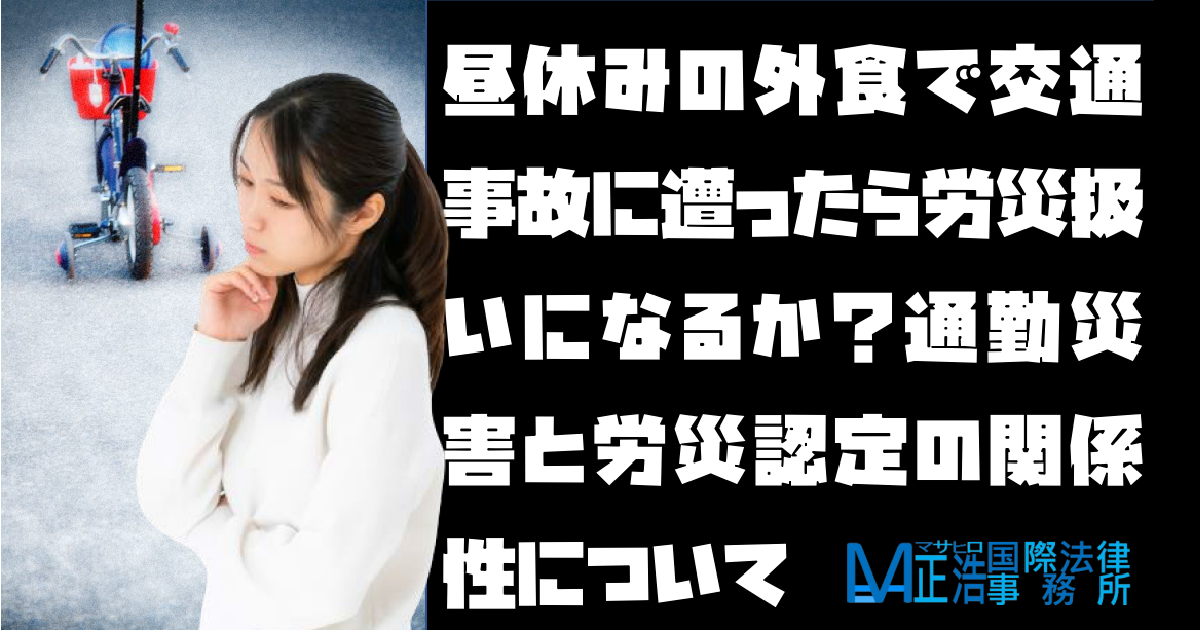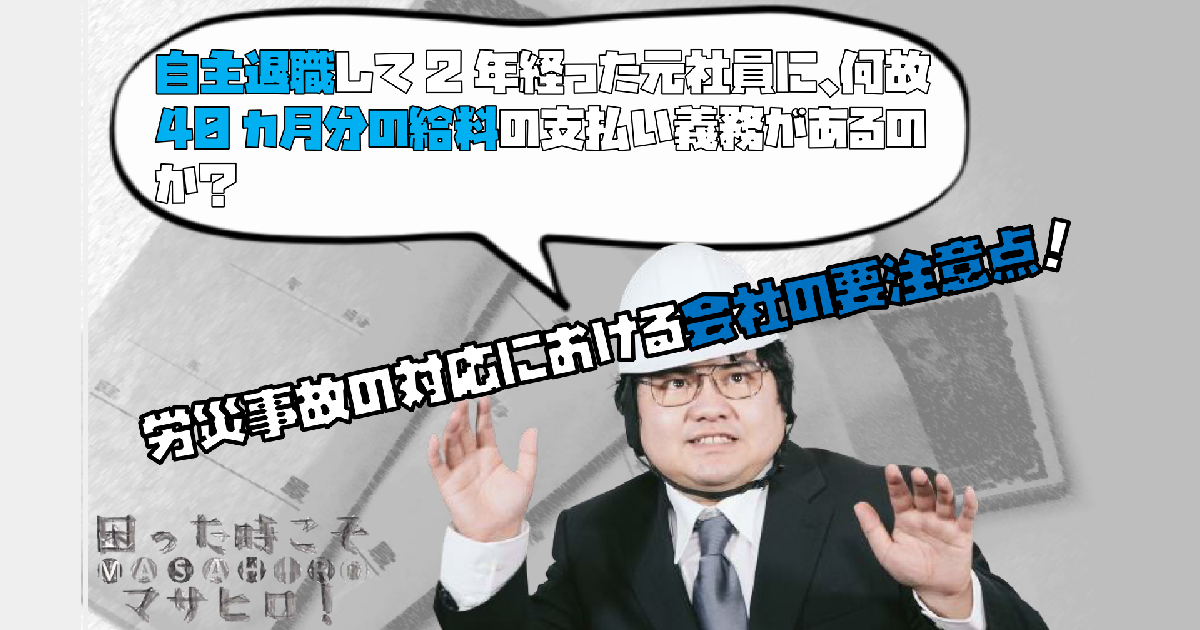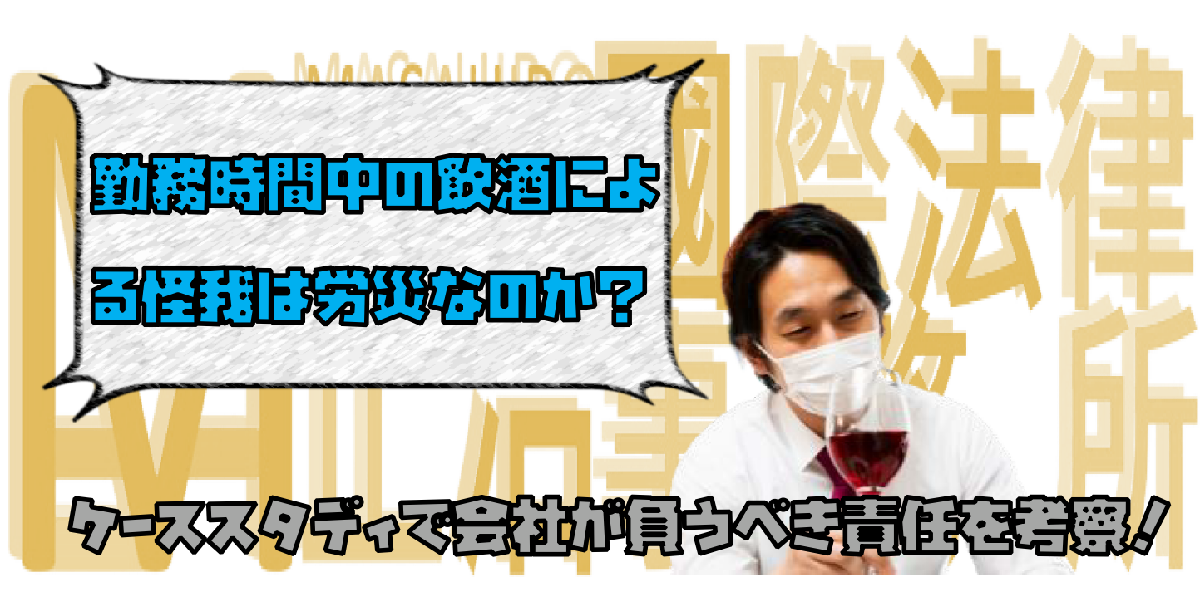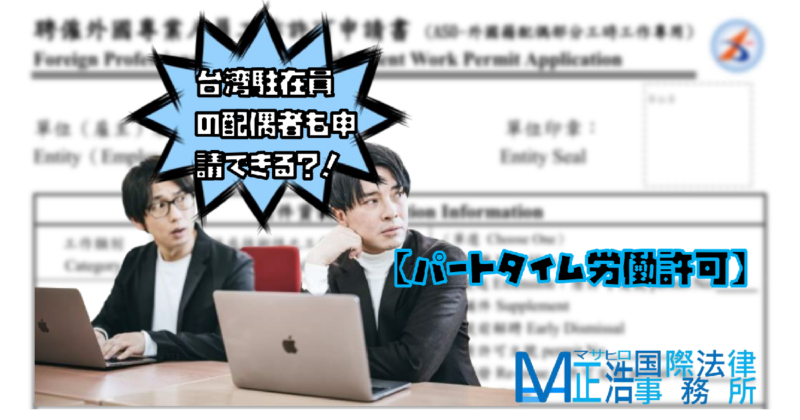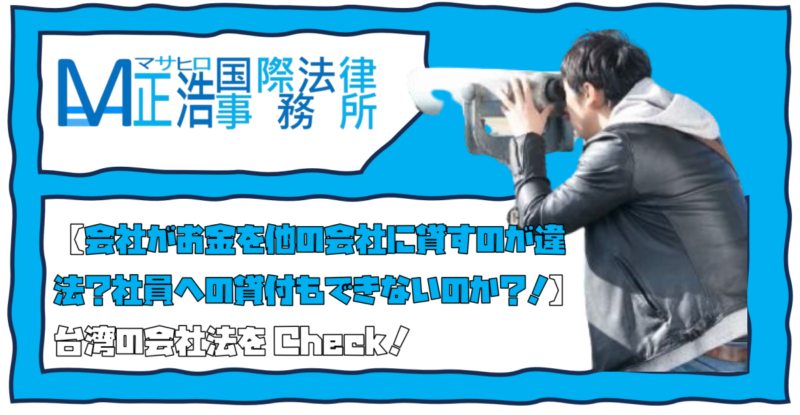【交通ルールを違反しなければ、通勤時の事故は100%労災に該当するのか?】―現実世界に起きたレアケースでCheck!
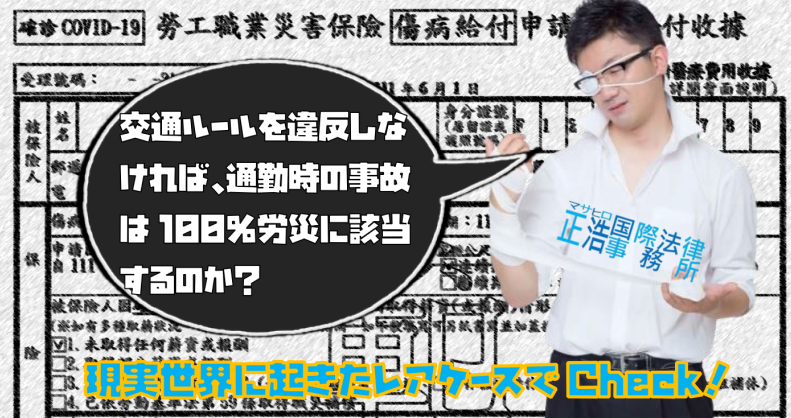
「日々の営みに該当しない私用」及び交通ルールの違反などの状況を除き、労働者が通勤中で怪我したら、原則として労災と認定されます。
また、いわゆる「日々の営みに該当しない私用」というのは、配偶者や子供の送迎や金融機関での現金引き出しなど以外の私用がそれに該当し、そして労働者が昼休み時間の外食で交通事故に遭っても労災に認定される可能性があると、以下のマサレポで紹介させていただきました。
つまり、判断に迷いやすい「日々の営みに該当しない私用」を一切行わず、かつ交通ルールも違反していない前提で起きた労働者の通勤災害は、ほぼほぼ台湾労働法が定義した「労災」に該当し、会社はそれに対しての補償義務が生じるわけです。
では、某キャプテンのように、ある労働者がサッカーボールを蹴りながら通勤し、会社に到着する一歩手前にバイクとぶつかって怪我した場合はどうでしょうか?

このサッカーマニア労働者は途中でどっかへ寄ったりするわけでもないから、「日々の営みに該当しない私用」は関係ない、「通勤経路でドリブルしていた」からといって、労災認定の例外として定められた交通ルールの違反例にも該当なさそうなので、もう労災決定だろう!
上記いささか常軌を逸した事例を別として、今回のマサレポは、ちょっとレアかもしれないが、正真正銘現実世界に起きた、示唆に富んだ労災認定トラブルについて紹介したいと思います。どうかついてきてください!
事件の経緯
- 起
- キックスケーターで通勤するM氏は、ある日、H社での仕事を終えて帰宅する途中で、通勤経路の下り坂で転び怪我を負い、病院で手術を受けました。

- 承
- 3ヶ月後退院したM氏は、自宅で6ヶ月間の休養を経て、翌年初に職場復帰。M氏はこの間には一切出勤していなかったが、H社からは通常通り給料の支払いを受けていたほか、当局から労災給付金の支給も受けました。

- 転
- 職場復帰したM氏は、それからの2ヶ月の間にさらに14日間の休暇を取って、そしてH社には給料の遅配問題、及び労災による治療費の未払い問題があったと指摘したうえ、雇用関係を解消し解雇手当の支払いを請求しました。

- 結
- 一方的に雇用関係を解消したM氏からの請求にH社が応じず、M氏は労働当局に対して労使争議の調停を申請したが、不成立となったため、M氏は弁護士を付けてH社を相手取って訴訟を起こしました。

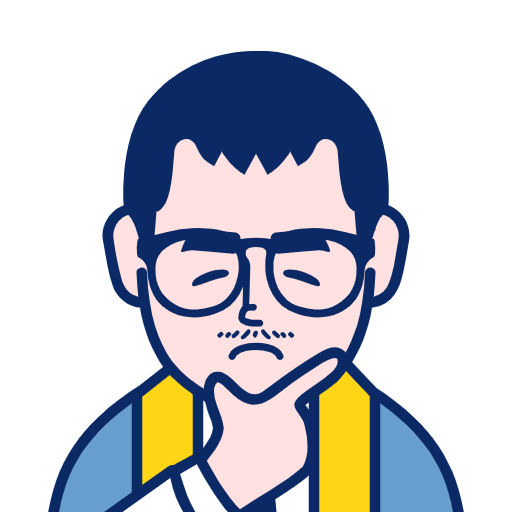
M氏の怪我は通勤途中で負ったものだし、当局もそれを労災だと認定し給付金を支給したから、治療費の支払いを拒否したH社に落ち度があり、裁判には負ける気がする…
結局どちらが正しいのかを、裁判官の見解を以下追っていきましょう。
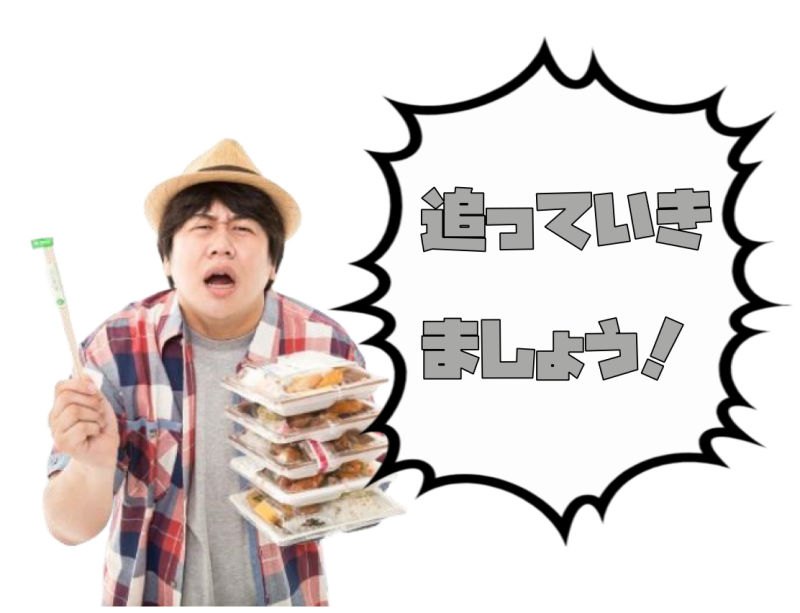
キックスケーターの転倒事故は果たして労災なのか?
キックスケーターは、インラインスケートやスケートボードなどと一緒で、運動とレジャー活動の遊具に該当し、それらの遊具を道路で使用し、かつ交通の邪魔になると認められたら、500NTDの過料に処せられます(道路交通管理処罰条例第78条)。
この規定から考えると、キックスケーターはバイクや車などとは違い、道路を走ることができず、一般人もキックスケーターを通勤手段として考えたりしません。従って、キックスケーターの利用は、労災対象外になる「日々の営みに該当しない私用」であり、それによる転倒事故は労災ではない、と裁判官がまず説明しました。
補足ですが、台湾においては電動キックスケーターはまだ道路で使用することができません。違反した場合1,200~3,600NTDの過料に処せられ(道路交通管理処罰条例第69条)、飲酒した状態でキックスケーターを使用したら、さらに刑事責任を問われる可能性もあるため(刑法第185-3条)、留意が必要です。

H社にはM氏に治療費や解雇手当を支払う義務あるか?
上記の説明で、M氏の転倒事故は労災に該当しないことが分かりました。労災が起きていないため、H社にも労災補償としての治療費をM氏に支払う義務が発生してこないわけです。
なお、M氏は事故が起きた日から長い間休暇を取っており、労災の事実がないということで、それらの休暇を病気休暇として取り扱う必要があります。台湾においては、通院のみの病気休暇は年間30日を超えなかった場合、休暇期間の給料は半分が差し引かれ、年間30日を超えた通院のみの病気休暇は、私用休暇と一緒で休暇期間は無給扱いになるルールが取られています。
当初、M氏の転倒事故が労災に該当するかどうか定かではないため、遅刻や欠勤した分こそ控除したが、H社はM氏に給料を支払い続けていました。それに当局から支給を受けた労災給付金を加算すれば、M氏が転倒事故の後に受領した総額は、法に基づき計算したH社から支払いを受けられる額を上回ったことが分かります。従って、給料の遅配問題など労基法に違反した事実があったとして、一方的にH社との雇用関係を解消し、H社から解雇手当を受領する権利がある、というM氏の主張は、裁判官に認められませんでした。
ちなみに、能力不足を理由に会社が一方的に労働者を解雇した場合、会社は労働法に定められた解雇手当を当該労働者に支払う義務があることは一般的に知られるルールだが(労働基準法第11条、労働者退職金条例第12条)、実は、もし会社に給料の遅配があったり、労働者の権利が損なわれる恐れが生じるほど会社が労働法に違反したりすれば、労働者は一方的に会社との雇用関係を解消のうえ、労働法に定められた解雇手当を請求できる、という逆パターンのルールも存在しています(労働基準法第14条、労働者退職金条例第12条)。
雇用関係を解消し、解雇手当を請求できる法的事由
- 事業主が従業員と契約時に不誠実な行いがあった場合
- 事業主等が従業員に暴行を加え若しくは重大な侮辱行為を行った場合
- 契約した職務は従業員の健康を害する心配があったにもかかわらず、事業主に改善をお願いしたが対応が不十分であった場合
- 事業主等が従業員に伝染する恐れがある法定伝染病を発症し、かつ従業員の健康に重大な被害を及ぼした場合
- 事業主が労働契約に基づき賃金を支払わない、もしくは出来高制の従業員に割り振る仕事が明らかに不十分であった場合
- 事業主が労働契約又は労働法に違反し、それによって従業員の権利が損なわれた場合
M氏はまさにこの下克上ルールを利用し、H社に解雇手当を請求しようとするものだが、H社側には給料の遅配または労働法違反のいずれも認められなかったため、M氏の野望は不発で終わってしまったわけですね。
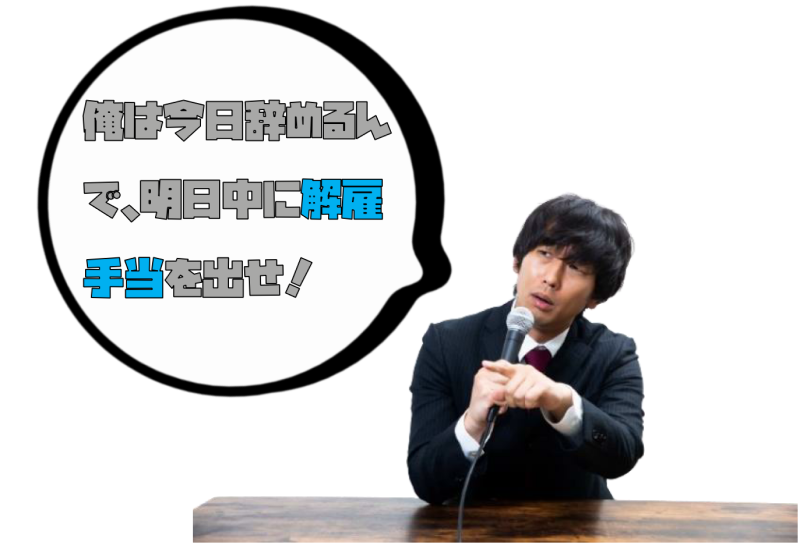
H社はM氏に離職票を交付する義務あるか?
会社に給料の遅配または労働法違反の問題があって、かつそれが原因で労働者から雇用関係の解消を申し込まれたら、会社は当該労働者に離職票を交付しなければならないとされます。
ただし、H社は給料も遅配しなければ、労働法に違反するわけでもないので、M氏から雇用関係を解消されても、離職票を発行して交付する義務がない、と裁判官が判断しました(112年度労上更一字第2号判決)。
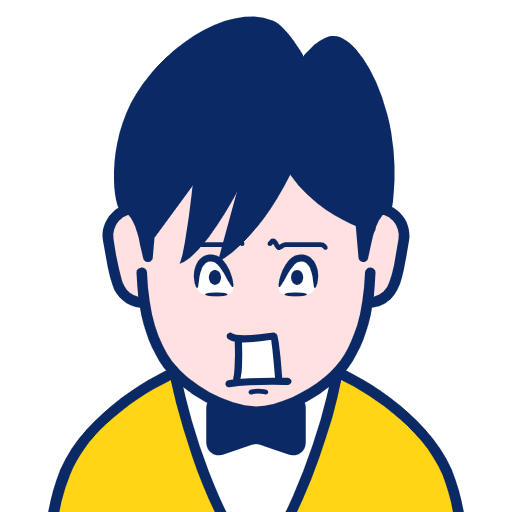
離職票ぐらいで、わざわざ訴訟で請求する必要あるのか?
離職票をゲットできたら、会社から退職後、保険当局からはMax的に月給の80%×9ヶ月相当額、合わせて30万NTD以上の失業給付金をもらえる権利があります。金額的には決して低くないことから、「一端の退職者は離職票を取ってなんぼ」、という都市伝説が流れています。

労働当局が労災認定したのに、労災じゃない?!
M氏の転倒事故は、保険当局から労働災害として認定され、かつ労災給付金も出ました。

同事故が労災であるかどうかは既に公的機関の判断がなされていたから、裁判所はその判断を覆すことができるわけ?
M氏とH社との労使トラブルを見て、上記のような質問が生じたりするかもしれません。それについては、地裁の裁判官はこう述べました。
保険当局は労働災害審査準則という行政命令を根拠に、M氏の転倒事故を労働災害と認定し、給付金を支払いました(労働者職業災害保険職業傷病審査準則第4条)。にもかかわらず、同準則は「保険関係」に基づき労災の定義を定めたのに対して、労働基準法は「会社の被災労働者への補償義務」を踏まえて労災を定義づけました(労働基準法第59条)。両者の目的がはっきりと異なるわけなので、「労災給付金が出たから、会社からも労災補償金を出さなければならない」という理屈が通りません。
台北地裁109年度労訴字第295号判決
つまり、保険当局が認める「労災」は、必ずしも労基法が定義づけた労災と一致するとも限らないのです。両者の違いをしっかりと見極めるうえ、会社にも補償金を対象者に支払う義務が生じるかを検討しておきましょう。

今週の学び
個人レベルでサステナ活動を行おうと、昔ながらの車・バイクをやめて、環境にやさしいキックスケーターやインラインスケートなどで通勤することは、時代の流れ的には考えられなくもありません。ただし、現在の法律では、電動かどうかを問わず、道路でキックスケーターを使用したらペナルティが伴うほか、事故したら労災に認定されないなどから、「キックスケーターで通勤」することは、やはり時代が早すぎると言わざるをえませんね。