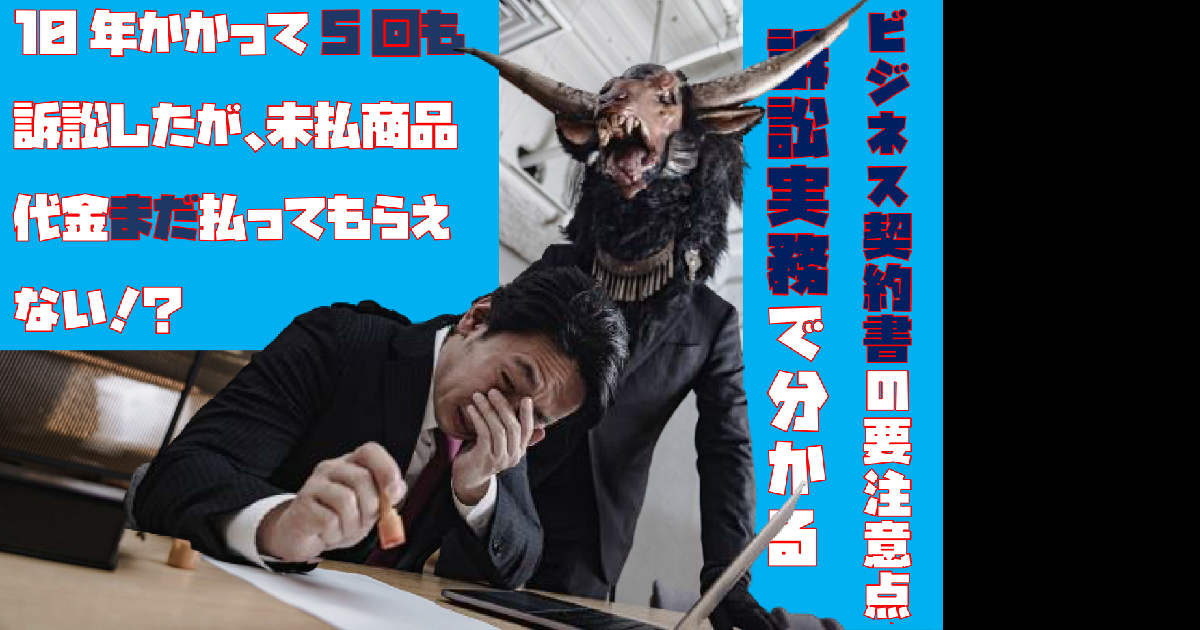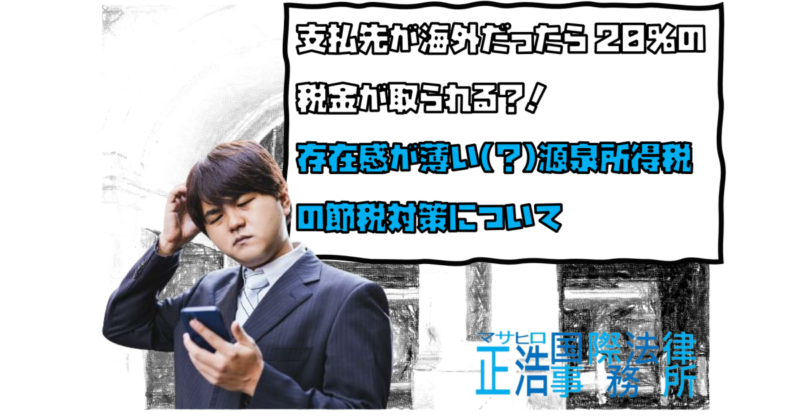取引条件をガチガチに固めても、「あれ」に気をつけなければ「大どんでん返し」が起きかねない?!―「契約書の準拠法について」

商品の単価をいくらぐらい、納期をいつ頃まで、そして支払い条件をどうすればなどが合意に至れば、甲乙が契約書を締結し取引を開始します。
もしその後取引の一方が契約に違反し、代金の支払いを渋ったり、もしくは約束した納期が到来してもなかなか商品を出荷しようとしなかったりすれば、他方は当該違約責任を追及し賠償を求めることで、損失を発生させない救済措置を行使することはできます。
上記の救済措置を問題なく実施するためには、それを規定する「法律」を知ることが大前提となっています。取引の両サイドはいずれも台湾の現地企業、取引自体も台湾国内で行われるのであれば、普段慣れ親しんだ台湾法をもとに取引相手の違約責任を追及したらよいが、違約した一方が海外企業である場合、同じく台湾法に基づいて同海外企業に責任を負担してもらっても問題ないか、という疑問点が生じてまいります。
今週のマサレポは、国際取引の契約書によく登場する「準拠法」について軽くお話させていただこうと思います。
侮るべからず、準拠法!

お客さんがこの値段で一度にこの量を買ってくれようするから、その他細々な条項を気にして機嫌を損なうより、稼げるうちにすぐ契約書をサインしよう~
確かに、競争が激しいビジネスの世界においては、儲かるチャンスが目の前へ来たにもかかわらず、細かい検討をしすぎて、結局商機を失ってしまうリスクが大きいので、利益につながる最重要条件さえ押さえれば、その他決まった文言は取引相手の要求をそのまま呑む、というのはよくある話です。純然たる国内取引であれば、何かしらトラブルが生じても、今までの商売経験と知識で何とか乗り越えられるかもしれないが、もし取引相手が海外企業で、かつ当該海外企業と合意した準拠法は台湾以外の国の法律であれば、トラブルの対応時に、今まで重ねてきた経験が役に立たず、どんでん返し的な結末を迎える恐れがあります。
例えば、米国企業との取引においては、準拠法を台湾法にした場合、たとえ契約書ではめちゃくちゃ高い違約金が設定されたとしても、裁判官は通常の類似ケースを引き合いに出して、違約した一方が賠償すべき金額を下げたりする傾向があるだが、通常の損害賠償より上回る「懲罰的違約金」の請求権を法的に認める米国法を準拠法にした場合、もし破天荒な違約金が契約書に書かれたら、違約した一方は結局そのとおりに賠償しなければならない形になる可能性が大きいという、準拠法の違いによって賠償責任についての考え方がだいぶ変わります。
なお、台湾においては、代金の請求権は15年で時効が成立し(民法第125条)、利息その他1年や1年未満の債権は5年(民法第126条)、商品の対価などはたったの2年で時効が成立します(民法第127条)。これらの時効ルールを考慮し、取引先に対する未収債権を管理すればよいと思って、準拠法が他国の法律にされたのを特に意識しなかった場合、結局当該他国の消滅時効が台湾の年数設定と異なることで、うまくいっていると思い込んだ債権管理が一気に崩れ、請求できて当たり前の商品代金はそれによって取れなくなるリスクが一気に膨らんできました。
そして、一部の契約書でこれから起きうる全てのトラブルに関する事項を網羅するはずがないので、そうすると、ビジネス行為を規定する法律を引っ張ってきて是非を判断するしかありません。もし準拠法が全く理解が及ばない他国の法律にされたら、契約書がカバーしきれない事項は全て取引相手の国の法律に委ねられ、一寸先が闇的な展開に陥ったりします。
ですから、契約書をチェックするときに、ビジネス条件は勿論重要だが、契約書の内容を如何に解釈するかについて支配的地位を有する準拠法もしっかり押さえておくべきです。

準拠法条項を設けないときは?
一方はA国の法律を準拠法にしたい、他方はB国の法律を準拠法にしたい、双方とも相手の国の法律を準拠法にしたくない場合があります。そうすると、ビジネスに関する法整備がより進んでいる第三国の法律を準拠法にしようとする妥協案が考えられます。準拠法を取引双方所在国以外の国の法律にしても構わないので(渉外民事法律適用法第6条)、その辺の設定は自由です。
ただし、第三国の法律を知らないし、かといって、取引相手の国の法律にもしたくないといった状況においては、いっそ準拠法を書かない、という選択肢も浮かんできます。
準拠法の定めがない場合、台湾のルール上、対象取引からしては最も密接な関係のある国の法律が適用されます。では、「密接な関係のある国の法律」とは何なのかというと、取引の実施によって生じる債務には、当該取引を特徴づける点があったと認められれば、債務を負担する当事者の居住地の法律は「密接な関係のある国の法律」になります(渉外民事法律適用法第20条)。例を取り上げて説明しましょう。
台湾に経営拠点を置く、ドラ〇ンボールを販売するナメック星人がいて、ある日台湾にいるフリーザ氏に半額セールの情報をメールで送信したが、翌日に値段の表示が一桁足りないことに気付いたナメック星人はフリーザ氏にメールを再送しようとしたとき、「では7つを頂戴」というフリーザ氏の返信がきて、ナメック星人は当該返信を無視して半額セールの件を白紙に戻す旨を伝えたました。にもかかわらず、フリーザ氏は当日の午後にお代を1通目のメールに書いてあった銀行口座に送金しました。ナメック星の法律によると、送信のタイミングを問わずキャンセルのメールさえ送ったら、取引を何時でも取り消せるとの主張を持ち出して、ドラ〇ンボールを出荷しようとしないナメック星人に対しては、フリーザ氏は台湾で訴訟を提起し、ナメック星人に出荷請求を行いました。
設例
果たして、上記の設例における準拠法はナメック星法にすべきか、それとも台湾法にすべきかというと、当該取引においては、ナメック星人はドラ〇ンボールをフリーザ氏に出荷する義務がある、つまり債務者の立場にあるため、準拠法はナメック星人の居住地の法律になります。なお、ナメック星人はビジネスを展開するために「台湾に経営拠点を置いた」事実があり、本件取引に限っては経営拠点の所在地国をナメック星人の居住地とみなすことが可能なため、準拠法は台湾法である、との結論にたどり着きます。
つまり、準拠法の定めがない場合、原則として取引において債務を負う一方が取引行為を行う際の居住地国の法律は準拠法と推定される考え方です。ちなみに、準拠法の定めがない不動産関連取引のケースは上記の考え方とは違って、債務者ではなく、不動産の所在地国の法律が準拠法と推定されることを留意しておきましょう。

準拠法の例外
取引双方は準拠法についての定めがあれば、当該準拠法がトラブルの解決において無効とされる場合を除き、当事者が合意した準拠法が取引の実施を支配する法律とされ、もし準拠法に関する取り決めがなされなかったら、債務を負う一方の当事者が契約を履行するときの居住地国の法律が準拠法とされます。
以上の原則が設けられたにもかかわらず、準拠法の定めがあっても、裁判となったら、取引双方が合意したのと異なる法律が準拠法にされたケースもあります。
日本のA社は台湾のB社にソフトの使用許諾を行ったが、B社はその後許諾外利用があったと認められ、A社は当初双方が取り交わした契約書に従い、日本法に基づいて契約を解除したものの、B社は契約解除後においても対象ソフトを利用し続けたため、A社は台湾の裁判所に提訴してB社に対する差し止め請求を行いました。
準拠法が日本法、管轄裁判所が日本の地方裁判所であると契約書に定めがあった原因で、台湾の地裁と高裁から門前払いを食らったA社は最高裁に不服を申し立てました。最高裁は以下の判断を下しました。
最高裁94年度台抗字第164号民事裁定
準拠法及び管轄裁判所に関する合意は、「ソフトの使用許諾」についてなされたものであり、B社が契約解除以降に行った権利侵害行為、及びそれによって不当利得を得たなどの違法行為へは効力が及ばない、つまり、契約書に定めたソフトの使用許諾、及び契約外におけるソフトの無断利用は別々の事件であり、前者にあった縛りは後者が受けない。なお、外国人が不当利得や権利侵害についての案件で提訴したとき、適用する準拠法をどのように認定したらよいか定めがないため、被告人の住所地国、及び権利侵害行為がなされた地域の裁判所にはそれを審理する権利がある、という民事訴訟法の定めが適用される。
取引の当事者が行うビジネス行為は、原則として契約書に定めた準拠法の縛りを受けなければならないが、当事者間は契約書に定めのない権利侵害行為によってトラブルが生じた場合、当初合意した準拠法とは異なる法律が適用される可能性があることは注意に値します。

今週の学び
ただでさえ協議すべき契約書の内容が多いから、いちいち準拠法などの設定に気が回らない、のようなコメントはたまに聞きます。ただし、準拠法に気をつけなければ、どれほど丁寧に契約書の内容をチェックしたとしても、とどのつまりで大どんでん返しが起きるリスクが終始伴うので、準拠法に関するリスクマネジメントをしっかり行ったうえ、契約内容の協議に臨むことがおすすめです。